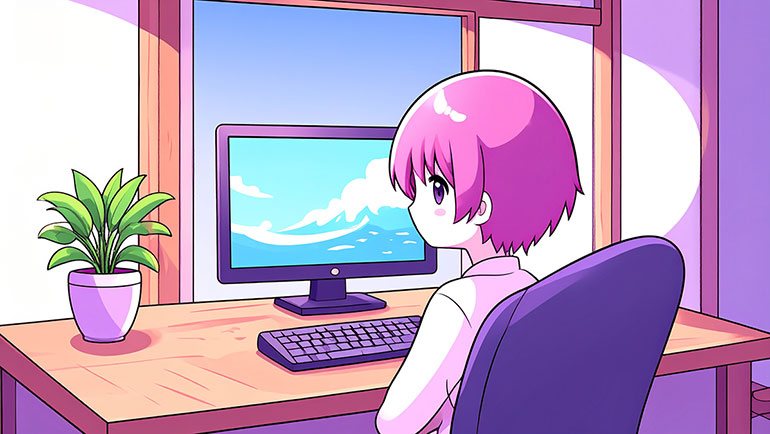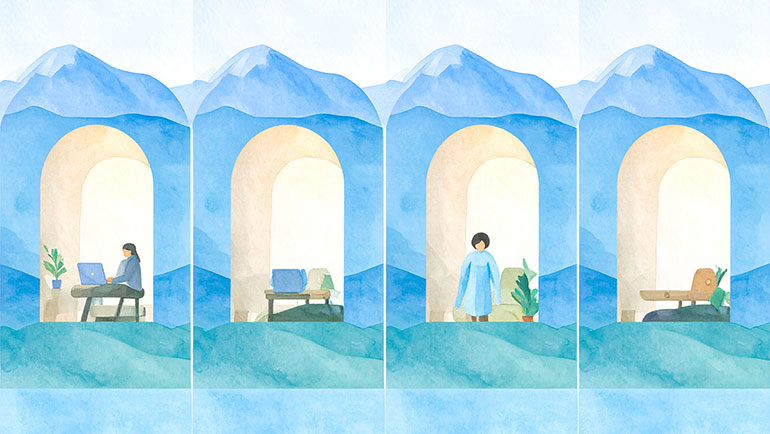ミスのたびに「誰が悪いのか」と責任を探す――そんな職場では、雰囲気が重くなり、成長のチャンスを逃してしまう。心理学でいう「帰属のエラー」は、人の行動を性格のせいにしてしまう思考のクセ。この記事では、そのメカニズムと、チームを前向きに変える3つの防止習慣を紹介する。
「どうしてこんなミスが起きたんだ?」「またあの人か……」仕事をしていれば、そんなふうに誰かにイラっとする場面は誰にでもあります。ビジネスの現場では、ミスのたびに「誰が悪いのか?」という空気が流れがちです。
しかし、その問いにこだわりすぎると、チームの空気は重くなり、ミスも減りません。心理学には、他人のミスをその人の性格や能力のせいにしてしまう「帰属のエラー」という思考のクセがあります。
この記事では、職場でよくある「帰属のエラー」のパターンと、それを防ぐ3つの習慣をご紹介します。「誰かのせい」ではなく「何が起きていたか」を見直せたとき、チームも仕事も、前に進みはじめます。
帰属のエラーとは? 「人のせい」にしてしまう心理のしくみ
私たちは、誰かの行動を見たとき「性格の問題だ」と思い込みがちです。なぜそのような錯覚が起こるのでしょうか。
たとえば、同僚が締め切りに遅れたとき、「だらしない人だな」と思うことがあります。けれど、実際には他の案件に追われていたり、システムの不具合があったかもしれません。
人の行動を、背景の状況ではなく、その人の性格や能力のせいにしてしまう。これが「帰属のエラー」と呼ばれる思考のクセです。
一方で、自分自身の出来事でも、同じようなゆがみが起こります。うまくいったときは「自分の努力のおかげ」と考え、失敗したときは「運が悪かった」「環境が悪かった」と思う。こうした都合のよい原因の解釈も、帰属のエラーの一種です。
つまり、私たちは他人にも自分にも、正確に原因を見られなくなることがあるのです。だからこそ、目の前の「人」ではなく、起きた「状況」や「仕組み」に目を向ける視点が大切なのです。
職場で起きやすい「帰属のエラー」のパターン
職場では、気づかないうちに帰属のエラーが起きています。どんな場面で生まれやすいのか見ていきましょう。
■パターン1:部下のミスを性格や能力のせいにする
「確認不足だ」「集中力が足りない」と決めつけてしまうのは、帰属のエラーの典型です。
実際には、指示があいまいだったり、担当範囲が広すぎるなど、環境面の問題が隠れていることもあります。原因を人だけに求めてしまうと、仕組みを見直すチャンスを逃してしまいます。
■パターン2:チームの不調を誰かのせいで片づける
成果が出ないとき、「あの人のやる気がない」「協力的じゃない」と特定の人を責めてしまうことがありますよね。けれど実際には、目標の共有不足や役割分担の偏り、情報の行き違いなど、チーム全体の仕組みに原因があることも多いのです。人を責めるよりも、「どんな状況でうまくいかなかったのか?」を一緒に考えるほうが、再発を防ぐ近道になります。
■パターン3:上司の厳しさを性格で片づけてしまう
「短気な人だ」「怖い人だ」と感じるのも、帰属のエラーの一種です。上司もまた、上層部からのプレッシャーや納期の制約を抱えていることがあります。「なぜその言い方をしたのか」という背景を想像することで、感情的に反応せず、冷静に向き合いやすくなります。
「帰属のエラー」を防ぐ3つの習慣
人を責めずに建設的に考えるためには、日常の中で、ものの見方を少しずつ変えていくことが大切です。ここでは3つの習慣を紹介します。
■習慣1:まず「どんな状況だった?」と聞いてみる
ミスが起きたとき、「なんで?」と問い詰めるよりも、「どんな状況だったの?」と聞いてみることから始めてみましょう。どんなタスクを抱えていたのか、どのタイミングで何が起きたのか。そうした背景に目を向けるだけでも、相手への見方が少し変わります。
状況を一緒に確認しようとする姿勢は、報告や相談のしやすい空気をつくります。相手を責めるより、落ち着いて事実を共有できたほうが、その後の対応もしやすくなります。
■習慣2:仕組みで防ぐ発想を持つ
同じミスが何度も起きるときは、個人の注意不足ではなく、仕組みの問題を疑ってみましょう。チェックリストを作る、報告ルールを明確にする、情報共有を簡単にするなど、環境を整えることでミスは減ります。
「人はミスをするもの」という前提に立ち、仕組みで支える視点があるだけで、働く側もずいぶん気持ちがラクになります。ミスをしても「自分のせいだ」と抱え込みすぎずに済みますし、対策があるという安心感は、気持ちにゆとりをもたらしてくれます。
■習慣3:自分に対しても帰属のエラーをしない
「なんで私ばっかりダメなんだろう」そんなふうに、自分のミスや不調をすべて自分のせいにしてしまう人も多いのではないでしょうか。実はこれも、「帰属のエラー」のひとつ。
もちろん、自分を省みることは大切です。
しかし、常に「私が悪い」と結論づけると、視野が狭くなり、本当の改善点を見失ってしまいます。「どんな状況だったのか?」「他に要因はなかったか?」と一歩引いて考えることで、より建設的に考えることができます。
まとめ:背景や状況を見直すことから始めてみよう
私たちはつい、他人のミスをその人の性格や能力のせいにしてしまうことがあります。「帰属のエラー」という言葉があるように、無意識のうちに偏った見方をしてしまいがちなのです。
だからこそ、「どんな状況や背景があった?」「ほかに要因は?」と問い直してみることで、見えるものが変わってくることがあります。「人はミスをするもの」という前提に立ち、仕組みで支える意識があるだけで、気持ちに少し余裕が生まれます。それが、結果としてチームにとっても、自分にとっても、前向きな変化につながっていくはずです。
構成/高見 綾
意味づけ理論が教えてくれる〝つらい出来事〟との向き合い方とは?心が折れそうな時に立ち直るヒント
目の前の仕事に、意味を感じられない。あの出来事には、どんな意味があったのか。仕事も人生も頑張ってきたけれど、「このままでいいのかな」と心がざわつくことはありませ…
最近、何をしても心が動かない人へ。誰にでも起こりうる「感情鈍麻」のメカニズムと対処法
前は好きだったことも、今は「まあ、そんなもんかな」で終わってしまう。そんなふうに、気づかないうちに心の動きが鈍っていることはありませんか? もしかすると、それは…
問題は〝あなた〟じゃない!人生の物語を書き換える「ナラティブセラピー」とは?
皆さんの人生がうまくいかないと感じたとき、そのうまくいかない原因だと感じていることは、本当にあなた自身が関係していることなのでしょうか? ナラティブセラピーとは…















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE