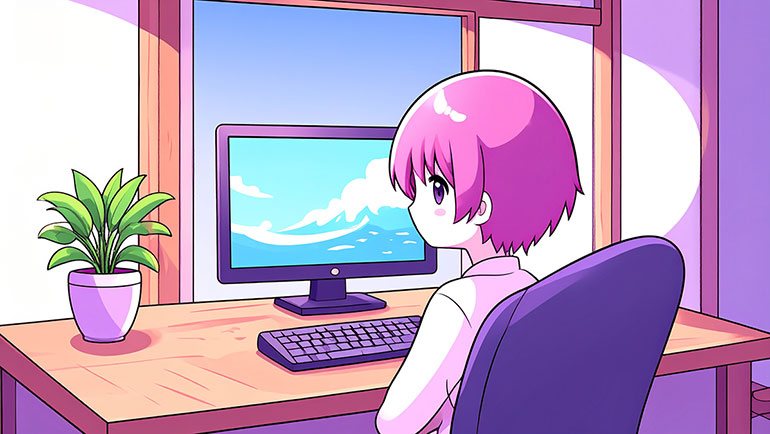「前は楽しかったのに、今は何も感じない」――そんな心の鈍りを感じていませんか? 感情鈍麻(かんじょうどんま)は、ストレスや過労の中で誰にでも起こりうる心の防衛反応です。 心が動かないのは「冷たくなった」からではなく、傷つかないよう守っているサイン。 この記事では、その原因と回復のヒントを紹介します。
前は好きだったことも、今は「まあ、そんなもんかな」で終わってしまう。そんなふうに、気づかないうちに心の動きが鈍っていることはありませんか? もしかすると、それは「感情鈍麻(かんじょうどんま)」のサインかもしれません。
感情鈍麻は、うつ病や統合失調症などの精神疾患の症状としても見られますが、実は、仕事や人間関係のストレスの中で誰にでも起こりうる心の状態です。ここでは、そうした日常の中での感情の鈍りについて、その背景と回復のステップをお伝えします。
感情鈍麻ってなに?
「最近、心が動かない気がする」「何をしてもピンとこない」そんな実感がある人はいませんか? それは、心からのサインかもしれません。まずは、感情鈍麻とは何かを見ていきましょう。
感情鈍麻とは、気持ちの起伏が弱くなり、心が動きづらくなる状態のことです。医学的には、うつ病や統合失調症、PTSDなどの症状として扱われることがあります。一方で、日常生活の中でも同じような感情の鈍りが起こることがあります。
たとえば――
・喜びや悲しみを感じにくくなった
・楽しい出来事があっても心がついてこない
・人に共感しようとしてもピンとこない
・疲れているのに、その感覚すらわからない
こうした状態は、「心が冷たい」わけではありません。心が自分を守るために、感じることを抑えているサインなのです。
なぜ感情が鈍くなるのか?
誰だって、もともとは感じる力を持っています。それなのに、どうして心の動きが鈍くなってしまうのでしょうか。その背景には、心が自分を守ろうとする働きがあります。
感情が鈍くなる背景には、強いストレスやプレッシャー、そして「感情を出すと嫌われるかも」という無意識のブレーキがあることが多いです。
特に、怒りや悲しみなどのネガティブな感情を「出してはいけない」と抑え続けていると、喜びやワクワクといったポジティブな感情まで一緒に感じにくくなることがあります。これは、感じることで心が傷つかないようにする、無意識の「防衛反応」として知られています。
たとえば――
・仕事で感情を抑えて働くことが当たり前になっている
・感情を出すと「扱いにくい」と思われそうで我慢してきた
・共感疲労で、他人の気持ちに触れること自体がしんどくなった
こうした日々が続くと、心は「感じないことで自分を守ろう」とします。その結果、「何も感じない自分」に戸惑い、さらに自分を責めてしまう……そんな悪循環に入ってしまう人も少なくありません。
私自身、20代の頃に感情の鈍りを経験しました。喜びも怒りも薄れ、人の涙を見ても「ふーん」としか思えず、「私って冷たい人間なのかも」と悩んだ時期がありました。
でも今振り返ると、それは性格ではなく、「感じたらしんどいから、感じないようにしていた」だけだったのだと分かります。心が無理を重ねた結果、感情の回路がいったん閉じていたのです。
感情を取り戻すための4つのステップ
感情は「戻そう」と意識することで、少しずつ感じられるようになります。自分を取り戻すために今日からできる、4つのステップをご紹介します。
(1)感じない自分を責めない
感情が鈍くなるのは、心の防衛反応です。ストレスやプレッシャーが続くと、人は感じないようにして自分を守ろうとします。「感じない=冷たい人間」ではありません。それだけ頑張ってきたサインなのです。まずは、自分を責めるのをやめるところから、回復は始まります。
(2)安心して感情を出せる環境を用意する
感情は、「安全」だと感じられる環境があると、少しずつ動き出します。信頼できる人との対話や、安心できるカウンセリングなど、否定されずに受け止めてもらえる場を持つことが大切です。
一人では難しいと感じるときには、専門家に相談してみるのも良い方法です。私も、感情が動かなくなっていた時期に、グループセラピーやカウンセリングに参加したことで、「どんな気持ちも否定されず、受け止めてもらえる」という安心感に触れ、少しずつ感情の回路が開いていきました。
(3)五感を通して小さな感覚を拾う練習をする
まずは、身体を通して感じる練習から始めてみましょう。たとえば、「おいしい」と思った味をしっかり味わう、好きな音楽や香りを取り入れる、空を見上げる、風を感じる、こうしたささやかな体験を重ねることが、感情を少しずつ動かす練習になります。
(4)感じたことをノートに書く習慣をつける
感情は、言葉にすることで少しずつ整理されていきます。「今日の気分」や「印象に残った感覚」を短く書くだけでも十分です。「今日は何も感じなかった」と思った日も、そのまま書いてみましょう。それも立派な感情です。
また、怒りや不満、嫉妬など、「こんなこと書いていいのかな?」と思うような感情も遠慮なく書いてOKです。ノートに書くだけなら誰にも迷惑はかかりませんし、正直な気持ちに触れることが、感じる力を取り戻す第一歩になります。
感じる力は、いつからでも取り戻せる
感情が鈍くなるのは、心が傷つかないようにと働く「防衛反応」のひとつです。感じることがつらすぎると、心はその感覚にフタをして、何も感じないように自分を守ろうとします。
それは性格ではなく、ストレスの中で生き抜くために身についた心の仕組みなのです。感情は、安心できる関係や、ほっとできる時間の中で少しずつ動き出します。焦らず、自分に合ったペースで向き合っていきましょう。
構成/高見 綾
意味づけ理論が教えてくれる〝つらい出来事〟との向き合い方とは?心が折れそうな時に立ち直るヒント
目の前の仕事に、意味を感じられない。あの出来事には、どんな意味があったのか。仕事も人生も頑張ってきたけれど、「このままでいいのかな」と心がざわつくことはありませ…
「コミュ力おばけ」がまぶしいあなたへ、職場で疲れない距離感のつくり方
職場にひとりはいますよね。どこに行ってもすぐに誰かと仲良くなって、会議や雑談でも自然と場の中心になる人。SNSでは、そんな人たちを「コミュ力おばけ」と呼ぶようで…















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE