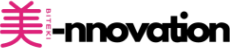世の中を変えるポテンシャルを秘めたプロダクトと、その誕生秘話を紹介する不定期連載「イノベーションの旗」。原料は食品廃棄物100%、にもかかわらずコンクリートと匹敵するほどの強度を持つ。今回はそんな夢のような新素材の物語だ。大阪・関西万博の展示施設の資材としても採用された。
fabula(ファーブラ)株式会社は東京大学生産技術研究所に籍を置く町田紘太CEO(32)が、2021年10月、小学校時代の同級生とともに設立したスタートアップ企業である。社会問題化する食品廃棄物だが、その量は国内で年間約472万トン(2022年 出典:https://www.env.go.jp/press/press_03332.html)、これを原料にコンクリート並みの強度を持つ新素材を開発、起業に至った町田紘太の足跡をたどる――。
当たり前でない世界があると知った幼年期
横浜市郊外の住宅街で育った町田は、父親の仕事の関係で、小3~小5までオランダのアムステルダムで暮らした幼年期の経験が、印象に残っている。通学したインターナショナルスクールでは体験学習のような授業が多く組まれていた。町田紘太は言う。「例えば『ブラインド・チャーチ』という課外授業では、真っ暗にした教会の中をみんなで手をつないで歩く。視覚障害のある人の世界を実際に体験する。当たり前じゃない世界があるのだなと、子供ながらに実感した記憶があります」
オランダは国土の約4分の1が海抜0メートル地域。地盤が軟弱なため学校の敷地にあった遊具が沈み、遊べなくなっていのを目のあたりにしたことは、大学時代の学びが机上の空論にならなかったことに繋がっていく。
オプティミスティックと社会課題
進学校から東京大学文科一類へ。将来は官僚か、一流企業への道を考えたのか。
「いや、何も考えていませんでした。僕はオプティミスティック、楽観的な人間で“どうにかなるでしょう”というノリで生きてきて」
一方で、「社会課題には興味があったんですよ」と言うのは、幼少期のオランダでの体験が影響しているのか。レポート選考をパスし、ニューヨークの国連本部を見学し、地球規模の社会課題を生業にしている国連の職員を目の当たりにした経験は、社会課題に取り組む思いを強くした。彼は仲間と学生団体を立ち上げる。SDGsが世の中に浸透していく2016年頃だ。町田紘太は言う。
「ヘルプマークやマタニティーマークとか、“属性を表明”しなくても、“助け”へのニーズは目に見えないことが多い。例えばメンタルに障害がある人とかは、外見ではわからないわけで」
SDGsを言葉にしなくても、身障者やハンデキャップを持つ人たちを自然な形で社会的に包括する、そんな発想がビジネスに結びつけばいい。学生団体の活動を通して、町田は漠然とそんな志向を抱いていた。
彼は大学3年のときに理系に転部。SDGsの精神やハンデキャップを持つ弱者を自然な形で包括する、そんなシステムやプロダクトを思考して、将来的な起業が胸中にあったのか。
食べられるコンクリート
当初は都市計画系を志望していたが、第一志望はゼミ選考で定員から漏れた。同時期に今も研究員として籍を置く、コンクリートの研究室の酒井雄也准教授の話を聞く機会を得た。
町田紘太は言う。「『企業がやらない研究をやっていきたい』という酒井先生の言葉に、『面白いなー』と。逆を言えば『企業ができない研究をやる』という意味でしょう」
コンクリート工学の授業で、“コンクリートは世界のCO2排出量の約8%を占める、最も環境負荷の高い工業材料の一つ”と教わり、驚かされた。
当時、研究室では間伐材等、使い道のない木材とコンクリートの瓦礫を組み合わせて、新素材を作る研究等が進んでいたが、「食べられるコンクリートって面白くない?」。これも雑談の中での酒井准教授の言葉だった。町田は言う。
「僕は料理が好きで、当時は実家で家族4人でしたが、白菜に付いた土が気になって表面の2枚ぐらいを捨てたり、ネギのはしは使わなかったり、ほかにもみかんの皮などシンクの三角コーナーに、山のように野菜くずが溜まっていました」
めちゃくちゃ捨てているな、もったいない…。
かねてより気になっていたことと、“食べられるコンクリート”という言葉が、彼の脳裏で結びついた。それが食品廃棄物を原材料にした新素材――。
食品廃棄物という社会課題の解決、そんな硬派なイメージとは異なる着目点が町田らしい。
社会実装=起業
さてどうするか。原材料を乾燥させ、ミキサーで粉砕、粉末状のものを金型に入れ、機械で熱圧縮し成形する。この工程は木材とコンクリートを混ぜ合わせ、新素材を研究・開発する、研究室で用いられる工程を踏襲した。コロナ禍の最中だったが、町田はオレンジや白菜やホウレン草や身近なもので、次々と”食べられるコンクリート“の試作に取り組んだ。
研究室での作業だった。機械で熱圧縮しても固まらなかったり。失敗を繰り返した末に、最初に成功したのはコストコで購入したオレンジから出た皮だった。完成したオレンジ色の固い板状の試作品に鼻を近づけると、しっかりとオレンジの香りがした。
“食べられるコンクリート”は当初、卒論のテーマだったが――。
大企業に入社しても、この研究が続けられるかわからない。大学に残って研究を続けても、創り出したプロダクトをキャンペーン的にバラまいて終わる気がする。ちゃんと世の中のためになるものにしたほうがいいのではないか。
得られた研究成果を社会問題解決のために応用、展開する――。そんな社会実装の視点に立ったとき、町田の中で起業が現実味を帯びた。
新たな物語を創造する
後に設立のメンバーとなる小学校からの友人たちとは当時、こんな話をしたに違いない。
「夕飯で食べたおでんの汁で翌日、カレーを作るとか」「夕飯で鍋をしたときの汁を翌日、ラーメンの汁にしたり」「でも誰もそれをサステナブルとは言わないよね」町田にはSDGsとかリサイクルとか、硬派な言葉が性に合わない。
残り汁はいろんなエキスが溶け込んでいる。味があっておいしい。本来の役割を終えた汁だが、再び違う形で人に愛されている。それは食品廃棄物を新素材に生まれ変わらせるという、町田のやろうとしていることと重なる。
社名の「fabula(ファーブラ)」はラテン語で「物語」を意味する。役割を終えた食品廃棄物で新たな物語を創造する、“ゴミから感動を作る”、社名にはそんな思いが込められている。
会社設立は2021年10月。町田紘太の新素材に対して各業界や企業の反応は素早かった。インパクトがあったのだ。その詳細は明日配信する後編で。
取材・文/根岸康雄














 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE