
「静かな退職」という言葉が、日本でトレンドワードになりつつある。
これは、もとはアメリカのキャリアコーチが発信した「Quiet Quitting」の和訳。海外で大きな共感を呼んで、SNSを通じて爆発的に広まり、日本でも1年ほど前に上陸した新語だ。
その意味は、「退職はしないが、働く意欲はあまりなく、最低限やるべき業務をやるだけの状態」といったもの。「社内失業者」や「働かないおじさん」を思い出すが、それとはまったく異なる概念だ。
「静かな退職」をトピックとした国内ニュースを拾うと、新たな社会問題とみなす論調が主体。たしかに、やる気のない社員がいれば、業績は下がり、社内での軋轢も増えるなど、ろくなことにならないと予想される。
一方、「静かな退職」を別の視点から捉え、むしろ日本人の働き方に一石を投じるものだとするのは、大正大学表現学部客員教授の海老原嗣生さんだ。
先般『静かな退職という働き方』(PHP研究所)を上梓された海老原さんに、詳しい話をうかがった。
欧米はほとんどの人が『静かな退職者』
――調査会社「ギャラップ」の調べでは、世界では「静かな退職者」の割合が約6割に及ぶとあり、ちょっと驚きました。
「実態はもっと多いと思います。欧米では7~8割の従業員が『静かな退職者』に当たると思います。
海外では、仕事をしない人たちは、本当に仕事をしていません。少し古い本になりますが『イギリスの工場・日本の工場』の中で、「遅刻者は1600人を下らないし、さらに、従業員の10%が何等かの理由で欠勤している」と、リバプールの工場の実情が記されています。ヨーロッパでは、今もそれほど変わりません。手抜きはするし、欠勤や遅刻の常習者もざらにいます。
トップのエリート層を除けば、だいたいが「静かな退職者」なのです」
不良品やミスを過剰に忌避する日本企業
――では、日本でも「静かな退職者」が増えたら、大変なことになるのでしょうか?
「いえ、むしろ日本の労働環境の異様さがあぶりだされると思います。
日本の「働かないおじさん」ですら、海外基準から見たら平均以上に働いています。日本の企業社会全体が頑張り過ぎていて、逆に悪い効果を生んでいます。
例えば、日本の製造業は、不良品を出さないことにすごく熱心です。1%の不良品率を0.1%にまで減らそうとかですね。
欧米だと、作る側も買う側も、1%くらいの不良品があることは気にしません。不良品があれば「返品すればいい」というスタンスですから。イケアやGAPのような一流企業でも、不良品率は日本より高い。返品率も高いのですが、売り手も買い手もそれでOKという風土です。
良く考えると、1%の不良品率を0.1%にまで減らしても、歩留まりはたった0.9%しか伸びないわけです。対して、そのために要する労働量は一気に2割とか3割も伸びるわけです。
日本は、ミスについても不寛容ですよね。それが、企業活動の足を引っ張っています。中国の企業などは、開発でもなんでも、間違ってもいいから早くやるという方針。最初から完璧な計画なんて無理という前提で、とにかく早く進める、ミスはしてもいいけれど、気づいたらすぐ直して、同じミスは繰り返さない。
そうして日本の企業は、中国の企業に出し抜かれたわけです。
日本の「静かな退職者」は、露骨な遅刻や欠勤はしません。やるべきことはやるけど、不良品率を極限まで減らすといった、それ以上の過剰な仕事はしないので、かえって生産性は上がるのではとみています」
「静かな退職者」が変える日本人の働き方
――では、「静かな退職者」の増加は、日本にとって好ましい流れということでしょうか?
「日本の企業が駄目になっている理由の一つに、日本的な働き方もあると思います。無駄に頑張りすぎて、忙しすぎて、かえって生産性を下げています。
それに、正社員である限り、年齢とともに役職が上がって、業務も難しくなるのは日本の企業社会だけです。海外では、少数のエリートを除き、平社員のままずっと同じ仕事をまっとうするのが当たり前。
ところが日本には、年功序列がまだあって、途中で役職や給料を下げるわけにはいかないとなる。そこで、ひずみが生まれてしまいます。『一生懸命働かなくては』と、ずっと駆り立てられ続けるわけですが、課長以上になれる人は一握りです。
そうした問題が『静かな退職』で、かなり解決できると考えています。
そもそも、『静かな退職』をする日本人は、上司から言われた仕事しかしない、もうひと頑張りが足りないといったレベルです。海外のノンエリート社員と比べれば、まっとうすぎるくらいのレベルです。
下手に出世を目指すより、言われた仕事を黙々とやって、定時に帰るというワークスタイルを定年までしたらいいのではというのが、私の提言です」
「静かな退職者」になると決めたら……
――なんだか「静かな退職者」が素晴らしい働き方に見えてきました。でも、あえて「静かな退職者になるぞ」と決断しても、実践には困難が伴うようにも思います。なにかコツなどありますか?
「一番大事なのは、言われた仕事はしっかりこなすことです。怠けたらクビになるわけですから、求められていることはする。職場内でのパフォーマンスが、下位2割に入らないよう注意してください。
そして、上司の心証を良くするため、言葉遣いには気をつけることです。自分の業務が増やされるときを除いて、上司に反論をしないことはとても重要です。
それから、ある年齢で給与は頭打ちになることは覚悟します。出世したくないという若手は多いですが、出世しなくても最終的には年収1000万円になると思っている人が多い。
でも、出世しない限り給与は、650万円までしか上がらないというキャリア設計に変更することになるでしょう。もちろん、出世できる人たちはバリバリ働き今以上もらえるようになります。
あくまでも出世を望んで頑張り続けるか、出世も昇給もない代わり定時で帰れるほうを選ぶか。そういう選択なのです。
雇用する側も、そういう選択肢を最初に与えた方がいいわけです。最大で650万円しか払わないで済むから、経営サイドとしても都合がいいでしょう。
日本社会の問題はもう1つあって、いまだに専業主婦モデルを理想としていることです。夫が1人で家計を支えるという前提なら、給与が上がらなかったらもう大変だと。でも、夫婦で働けば、世帯収入は1000万円をクリアできるわけです。
おまけに2人とも早く帰れるから、家事・育児も万全でワークライフバランスもはかれます」
欧州のやり方をまねてはいけない
――しばしば、「ドイツや北欧の人の働き方を学べ」といった記事を見かけます。「静かな退職」についても、ヨーロッパの先行事例から学べることはあるでしょうか?
「『静か退職』というコンセプトは海外から来ましたが、海外と同じことやっては、日本の良さが全くなくなります。
欧州の多くの国は、学歴で全てが決まってしまう世界です。基礎教育の段階で落第する人が2割から3割いて、そういう人たちが就ける職業は低所得です。
職業高校に進んだ人も同様です。普通高校の成績上位のわずかな生徒だけが、一生エリートとして生きられます。そうでない人たちは、給料は上がっても500万円台までしか上がりません。若いうちに全部が決まってしまう社会なのです。
日本が、そんな欧州をまねるのは、良くないでしょう。『静かな退職』をしても年収600万円ぐらいまでいけるようにしつつ、学歴に関係なく上を目指すことも可能という選択肢のある社会がいいのではないでしょうか。
ただし、ポストの数が限られている以上、上を目指しても、叶わない人がほとんどとなります。一生懸命に働いたけれど、50歳になっても課長にもなれなかったという人は、ふつうに出るはずです。
であれば、「自分は出世コースから外れた」と気づいたら、ゆるい働き方にシフトした方がいいはずです。
とにかく、全員一律で同じ仕組みのなかで、ひたすら頑張って働くのは、早急に止めるべき。日本人は、ものすごく頑張ってはいて、なのに先進国の中では生産性が低く、給料も安いというのは、まともではないと思ってください。まず、そのことを実感して最初の一歩を踏み出してほしいですね。
■お話を伺った方:海老原嗣生さん
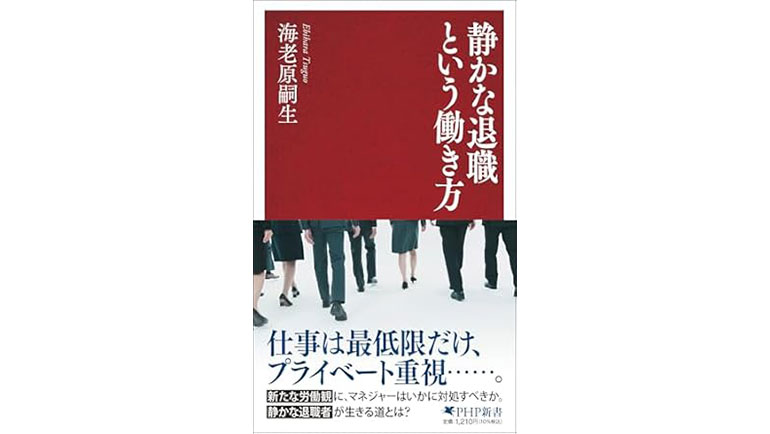 サッチモ代表社員。大正大学表現学部客員教授。1964年東京生まれ。 大手メーカーを経て、リクルートエイブリック(現リクルートエージェント)入社。新規事業の企画・推進、 人事制度設計などに携わる。その後、リクルートワークス研究所にて雑誌「Works」編集長を務め、2008年にHRコンサルティング会社サッチモを立ち上げる。『エンゼルバンク――ドラゴン桜外伝』(「モーニング」連載、テレビ朝日系でドラマ化)の主人公、海老沢康生のモデルでもある。人材・経営誌「HRmics」編集長、リクルートキャリアェロー(特別研究員)。著書も30冊余り出しており、『静かな退職という働き方』(PHP研究所)は最新の著書。
サッチモ代表社員。大正大学表現学部客員教授。1964年東京生まれ。 大手メーカーを経て、リクルートエイブリック(現リクルートエージェント)入社。新規事業の企画・推進、 人事制度設計などに携わる。その後、リクルートワークス研究所にて雑誌「Works」編集長を務め、2008年にHRコンサルティング会社サッチモを立ち上げる。『エンゼルバンク――ドラゴン桜外伝』(「モーニング」連載、テレビ朝日系でドラマ化)の主人公、海老沢康生のモデルでもある。人材・経営誌「HRmics」編集長、リクルートキャリアェロー(特別研究員)。著書も30冊余り出しており、『静かな退職という働き方』(PHP研究所)は最新の著書。
取材・文/鈴木拓也
「35歳転職限界説」は過去のもの?40代、50代の転職は10年で約6倍まで伸長
かつて転職市場で唱えられていた「35歳転職限界説」。35歳を過ぎると転職の成功率が著しく低下することを指す言葉だが、少子高齢化に伴う慢性的な人手不足が叫ばれる今...
従業員を守るために大切な「機能する内部統制」の仕組みづくりとは?
読者の皆様、日々こんなニュースが日常茶飯事となっていませんでしょうか? 不正会計、粉飾決算、データ改ざん、各種ハラスメント、経費の不正利用、個人情報流出etc。...















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE















