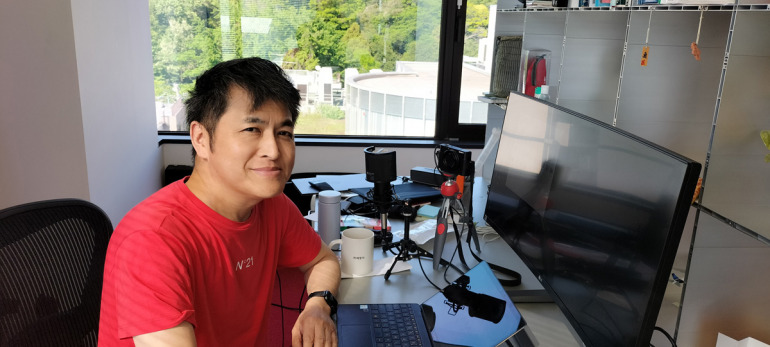世の中に刺さる、イノベーションの矢を放つ会社のお話である。ロボット、自動運転、自動運搬、自動配達――益々、働き手が不足する日本にとって、必要とされる製品を開発している会社である。
株式会社ZMP、谷口恒代表取締役社長(58)。設立は2001年、谷口社長が創業者である。自動運転のロボットの開発、販売、IT、AIによるロボットシステムの構築が主な事業内容だ。運搬を担う物流支援ロボ「CarriRo(キャリロ)」、無人宅配ロボ「DeliRo(デリロ)」、歩行速モビリティ「RakuRo(ラクロ)」、無人警備・消毒ロボットPATORO(パトロ)」等、ロボットの製品ラインナップは20種類以上。運送業界を直撃する2024年問題、深刻な人手不足、自動運転への熱い視線――。「創業30年の2031年には売上高で数千億円を目指す」現在の100倍以上の大成長を語る谷口社長の言葉も、大風呂敷を広げたとは思えない響きがある。
二足歩行ロボ、ピノ(PINO)との出会い
兵庫県姫路市内の天台宗の寺の家に生まれた谷口恒は、中学時代に比叡山で得度、群馬大工学部高分子化学科卒後は僧侶との兼務を考え、実家から通えるにエアブレーキの会社に技術者として就職。そこで得た自動車関連の技術は、後に自動運転車の開発に生かされることになる。ほどなく横須賀市に転勤、3年後には商社に転職。画像処理や計測器の精度を高める緑のレーザーの技術営業に携わる。
90年代、インターネットのビッグウェーブを谷口恒も感じとっていた。彼は言う。「レーザーは自分で作れませんが、コードを書けばホームページでも作れる時代がきた。自分で作れるところが魅力でした」当時、洋書で機械語を独学。7年間の商社勤めを辞め、知り合いと、音楽や画像データのコンテンツ販売を手掛ける会社を立ち上げ、中央区にオフィスを構える。98年頃のことだ。
2000年の初頭にITバブルが崩壊。さてどうしようかと模索しているときに、知人を介して、科学技術振興事業団の後押しで開発された「ピノ(PINO)」という人型二足歩行ロボットと出会う。ピノの身長70㎝、パソコンで操作し、ヨチヨチ20歩ほど歩く。エンジニアの手作りだった。谷口は言う。「二足歩行のロボットに可能性を感じましたね。僕が本腰を入れたら、売れるようなものができるんじゃないかと思いました」
“楽しい”、そして“便利”な製品とは何か
谷口は2001年、ロボットに特化したZMPを一人で起業した。ピノの半分ほどの身長にして、モータもピノより10個ほど減らし15個程度にした。ラジコン操作の二足歩行ロボット「ヌーボー(nuvo)」の発売開始は2004年、スタスタとピノより滑らかに歩く二足歩行のロボットだった。価格は58万8000円。
ソニーの犬型ロボット『AIBO』がヒットした。谷口は人型ロボットのヒット商品第一号を目指した。ヌーボーは評判となり、一人で2台購入するユーザーもいたが……
――手ごたえはイマイチでしたか。
そんな問いに谷口が応える。
「二足でしっかり歩くロボットは珍しいし、楽しんでもらえたのですが結局、楽しさだけだと飽きちゃうんです。楽しさプラス、便利さがないとお客さんに刺さるものにはならない。その便利さが見つけられませんでした」
そもそも“楽しく便利な社会を作る”それが会社の理念だ。”楽しく“”便利な“製品で重要なのは日常的に使われることである。そう考えると移動性能の面で、二足歩行は逆に足かせとなってしまう。試行錯誤の末、谷口恒は2本足を2輪に替えて、音楽ロボットを開発し、「ミューロ(miuro)」と名付け2007年に発表した。価格は10万円ほどだった。
ミューロは使う人の足元に付いて移動し、ステレオに向き合わなくても音楽を聴くことができる。例えば夜10時に、お気に入りのジャズナンバーを足元でリスニングできるよう、セットすることもできる。当時としては画期的なミュージックライフの提案だった。
図らずもコアな自動運転技術の開発
谷口は言う。「”認知“”判断“”操作“自動運転は3つのプロセスに分かれていますが、ミューロの開発の過程で、それらの技術開発を手掛けたことが大きかったです」
音楽ロボの開発を通して、谷口たちは二つのコア技術に取り組んだ。RoboVison(ロボビジョン)はカメラとセンサーを使った障害物等の認識機能である。もう一つのIZAC(アイザック)は認識したものを判断し、障害物を避ける等の信号をモータに送る機能である。この技術が次の製品へとつながっていく。
ミューロは初回生産500台を完売し健闘したが、音楽ロボは会社にとって重要なテーマである“便利さ”を十分に満たしたのだろうか。そんな暗中模索の中で、谷口はリーマンショックの激動を迎える。2008年だ。
ベンチャーキャピタルが次々と資金を引き上げ、資金調達が困難になった。谷口は奔走したが資金を手当てすることは難しかった。社員も減り会社の貯金の残高が1000万円ほどになって、谷口恒は最後の勝負を決断する。
――それが自動運転の自動車の開発だったわけですね。
「新卒で就職したのが自動車の分野の会社で、車の構造がわかっていた。それが“車もロボットになるに違いない”という発想につながったんです」
自動運転車、ロボカー1/10
音楽ロボットの開発で培ったロボビジョンと、アイザックの技術を実際の10分の1のサイズの車に搭載したRoboCar(ロボカー)1/10の発表は2009年。外苑前の貸しオフィスの床に道路を模して障害物を配置し、ロボカーの自動運転のデモンストレーションを行った。
特に日本は大企業を含め専門分野に特化して、既存のものをより高性能にする研究・開発が最優先される。時代を先取りする新しいアイテムの研究は、ほとんど手付かずの状態である。だが、ひな形さえあれば別だ。ひな形を参考により優れたものを形にしていく、日本人の得意なパターンを彼は熟知していた。
自動運転が近未来、飛躍的に進歩するに違いないことは知れ渡っている。発表したロボカーは白線の外側を逸脱せず、障害物があると止まる、レベル2相当の自動運転車だが、企業はこれを踏み台にして、自動運転の技術開発を加速させるに違いない。
ターゲットは自動車関連企業の研究者だ。
うちは自動車開発がメインではない。ロボット開発の会社じゃないか
谷口のそんな見立ては的中した。自動運転に特化したロボカーに注文が相次いだのだ。会社はロボカーでV字回復を果たした。
でも所詮、おもちゃじゃないか。実際の車の10分の1のサイズのロボカーへそんな声もあった。そこでロボビジョンとアイザックという二つのコア技術を市販の一人乗りの車に搭載。人が乗れることで、車の自動運転化に近づいたと、周囲の視線が熱を帯びてきた。さらに試行錯誤の末、ハイブリット(HV)車にコア技術を搭載して、HVの自動運転車、RoboCarHVを2012年に発表。だが、
ちょっと待てよ…
谷口恒は言う。
「うちは本来、自動運転の自動車を開発する会社ではない。ロボットの開発を手掛ける会社ですから」
消費者をターゲットにしたB to Cの会社だったはずが、企業を意識したB to Bの業態に変化したことも気にかかる。“楽しさ”と”便利さ“二つの会社の理念を満たす製品の開発も道半ばだ。
これらの課題を谷口恒は劇的にブレイクスルーしていく。その物語は明日公開の後編で詳しく語る。
取材・文/根岸康雄















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE