■連載/あるあるビジネス処方箋
前回は、管理職になるまでの仕組みについて私の考えを紹介した。今回は、役員になる仕組みを取り上げたい。
明治大学大学院グローバル・ビジネス研究科の客員教授であり、人事コンサルタントの林明文氏に取材をした際に、ひとりでも多くの会社員が知っておくべきと私が思った部分をまとめてみた。林氏は30年以上にわたり、多くの中堅、ベンチャー、大企業、外資系企業などのコンサルティングに関わってきた。
なぜ日本企業では内部昇格が多いのか
Q.役員になる場合、日本では内部昇格(管理職から役員になる)が、外部から招くケースよりも多いですね。管理職から役員になるためには、特に何が必要なのでしょうか?
林:役員ならば、少なくとも自社のビジネスの価値を語ることができないといけない。例えば、次のようなものです。
「我々のビジネスはこういうところで、これほどに優れている。こんな顧客に、こういう価値をこのようにして提供できる。それで、利潤を得る」
さらに言えば、ビジネスの根幹をなす商品やサービスの市場、今後の動向、それらに対しての効果的な戦略、例えば、価格やそのあり方を次々と語ることができて当然なのです。そのいずれにも説得力があり、ビジネスとして実現をさせることができないといけない。
ところが、このようなことを語る役員は少ない。日本企業では役員は、社員の昇格の「上がり」(ゴール)になっている傾向があります。部長や本部長から役員を選ぶときに、経営を心得ているかどうか、という目で選んでいないのでしょう。たとえば、「本部長のときに、こういう業績があった……」として選んでいることが多い。経営をする人を選ぶ、という意識が社長、役員に希薄なのです。
言い換えると「役員とは何か」と深く議論をしていない。役員の定義、評価、報酬があいまいで、明確なルールが今なお浸透していない。役員の数を減らす企業は増えていますが、一方で執行役員を設け、その数を増やしている場合があります。しかし、双方の位置づけや役割があいまいで、経営と執行機能がきちんと分離されていない。結果として、たとえば、「役員会に誰を残すか、誰を専務にするか、執行役員から誰を役員会に入れるか」といった社内バランスで判断していることが多いのです。
事業部制の厳しい環境、競争が経営力を磨く
Q.それでは、国際競争に負けてしまいかねませんね。では、どのような人が役員になるのにふさわしいのでしょうか?
林:たとえば事業部制の会社に勤務し、配置転換のローテーションのもと、様々な上司に仕え、幅広い分野の仕事をして、高い実績を残してきた人は相対的に優秀な人が多い。その場合の「優秀」とは経営やビジネスについて深く考え、深く語ることができることを意味します。考える力があるのです。
事業部制では、1つの事業部が1つの会社のようなものです。特に本部長や部長などの管理職は損益を真剣に考え、責任をもちます。マネジメント能力を磨かざるを得ない。中小企業の社長のような、ある意味での厳しさを持つのです。
市場などの環境変化が激しいと、商品やサービス、価格、コスト、ヒトなどについて常に深く考え、結論を素早く導かないといけない。グローバル化が進めば、なおさらのことでしょう。
こういう厳しい中、管理職どうしで激しい競争をします。おのずと優秀な人が生まれる可能性が高くなります。少なくとも、製造、営業、管理などと機能別組織の会社に長くいる本部長や部長よりは、経営やビジネスについて鋭い議論ができます。
一方で機能別組織では、横の部署への人事異動が少ない。製造、営業、管理などからそれぞれのエースが役員会に入ります。彼らは「機能の専門家」であったとしても、「経営ができる人」とは言い難い。大企業で、環境の変化があまりない会社では、今なお、こういうことが行われています。
Q.事業部制は総合商社やメーカー、一部のメガベンチャー企業でよく見かけます。確かに、30代半ばで経営を語る社員は多いような気がします。役員を育成する点においては、事業部制のほうが職能別制度よりも優れているのでしょうか?
林:事業部制のほうが、複数の機能を束ねられる経験や能力を身につけた管理職が生まれてくる傾向があります。役員になるならば、複数の機能を束ねられる経験や能力があり、経営やビジネスを語り、道筋をつけることができないといけない。
たとえば総合商社の子会社で役員をしている男性がいます。彼は親会社である商社の事業部でエースに近い存在となり、大きな成果を出します。その後、人事部長になり、大改革をします。人事部プロパーの部長よりは、はるかに優秀でした。出向し、子会社で役員になっています。いずれは、親会社に戻り、社長になるかもしれない人です。
今後、役員になりたい人はこのような人から学ぶべきです。例えば、なぜ、エースになったのか。なぜ、人事部長になり、らつわんを振るうことができたのか、という視点で観察し、深く考えるのです。
Q.なるほど、私なりに理解しました。一方で多くの企業では、管理職が降格や減給になることがありません。それでもようやく、バブル世代(現在の50代前半から60歳前後まで)のリストラを本格化させた企業もあります。この動きをどう捉えますか?
林:実際は、その世代のリストラは10年以上前から静かなブームです。2030年までくらいは、「リストラバブル」として止まらないはずです。それにしても、この世代のリストラのタイミングは極端に遅い。彼らが50代になるまで待つ必要があったのだろうか、と思います。
バブル世代の扱いに苦慮する大企業の姿は、多くの中堅、中小、ベンチャー企業も抱えています。実は、バブル世代の下の20~40代にも能力、成果、実績と賃金が見合わっていない社員は少なからずいます。しかも、そのまま放置されています。
日本企業の人件費の管理がいかにどんぶり勘定で、杜撰で、いい加減であるのかが今後、はっきりとわかるはずです。
Q 大企業がリストラをするとき、退職金に割増金をつけることがあります。額が5000万円~8000万円になるケースもあるようです。あの額は「それぞれの社員の成果や実績からすると高すぎる」といった批判も一部ではあります。
林:その思いはわからないでもないのですが、仕方がない面もあるのです。大企業に現在50歳で、年収1000万円の社員がいるとします。60歳定年まで働くと、会社は少なくとも1億円を払わないといけない。退職金を払うと、1億数千万円を超えます。今は65歳定年が増えていますから、さらに支払う額が増えるかもしれません。
50歳のとき、仮に退職金2000万円に割増金を5000万円にして、計7000万円で辞めてもらえるならば、ざっと5000万円以上の人件費を削減することができるのです。これが数十人~数百人になると、相当な額の人件費を減らすことができます。ここまで考えるならば、大企業の人事部は「1人につき、5000万円を上乗せすることは高くない」と思うでしょう。
もっとリアルに言えば、5000万円という額を支給する場合、暗に「あなたの市場価値は年収500万円です」と言っているようなものです。60歳の定年まで10年とすると、500万円×10年で、5000万円となります。ここまで踏み込んで、本人たちに伝える大企業は少ないでしょう。しかし、人事部は「年収500万円相当の人材」としか見ていない可能性が高いのです。
大企業では依然としてこのレベルの人にも50歳で1000万円を支給している場合が少なくない。その大きな理由が、職能資格制度にもとづく年功給によるものです。役職にふさわしい実績を残している本部長や執行役員クラスならば、年収1000万円で何ら問題はありません。働きや成果・実績に応じて、もっともらってもいいでしょう。
しかし、実績がさほどない課長や非管理職にまで1000万円に近い額を支給しているところがあります。この人たちに「5000万円前後を上乗せするから辞めてほしい」と言う会社は、労働市場の価値といかにかけ離れた額を支給してきたか、を立証しているようなものです。能力、成果、実績などと賃金が見合わっていないことこそが、問題なのです。
大企業でも、一部の情報産業や小売業界では退職金の割増金は基本給の半年~1年分くらいの会社が少なくありません。労働市場の価値に近い額を支給してきた会社ととらえることもできます。今後、10年ほどでこのカテゴリーに入る大企業が増えるでしょう。管理職に限らず、役員のあり方は、必ず変わっていきます。
取材を終えて
数回前にこの連載の記事「大企業からベンチャーへの転職で「若手が会社に抱く不満」は解消されるのか?」で、人事コンサルタントに取材した記事を掲載した。その中で、このコンサルタントがメガベンチャー企業に勤務する30代の男性が現在、グループ会社を経営していると話していた。事業部制の企業では、確かに30代で経営の中核を担う立場になるケースはある。
新卒や中途採用試験を受ける際にいずれは役員になりたいと思う人はその会社が事業部制であるか、職能別組織であるかを確認するとよい。ホームページで組織図が載っているケースがある。企業内労組が加盟する産業別労組の機関紙を見て、調べることもできる。労組の役員に聞いてもいい。
これまで長い間、賃上げがなかなか進まなかった理由の1つは今回、林氏が後半部分で語っているところにあると私は思う。つまり、人件費の管理がどんぶり勘定で、杜撰であることだ。しかも、管理職の減給や降格が難しい。なぜか、マスメディアが報じない点ではあるが、大事なところではないだろうか。
文/吉田典史
















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE










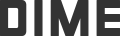 最新号
最新号







