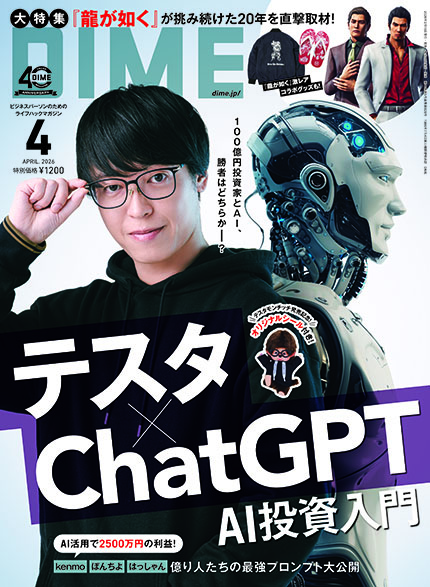2020年代後半、エンタメはビジネスでもカルチャーでも不可欠なキーワードになった。非常に身近なワードでありながら、「エンタメとは何か?」という問いに明確な答えを持つ人は多くない。
今回は、広告・メディアの最前線でエンタメ領域を担当する電通の有元氏と、社会学の視点から現代文化を読み解くエンタメ社会学者・中山氏による対談をお届けする。
テーマは「愛されるコンテンツとは何か、そしてエンタメの未来はどこへ向かうのか」。
クリエイターが人々を熱中させるもの、それが「エンタメ」
ーー本日はよろしくお願いいたします。それでは、お二人の自己紹介からお願いします。
中山:私は「エンタメ社会学者」という少し変わった肩書で活動しています。今ではアカデミックな領域でも活動をしていますが、過去にはDeNA、バンダイナムコ、ブシロードなどに勤めていた経歴もあり、主にアニメ、ゲーム、カードゲームなどを海外に展開する仕事をしていました。
「エンタメ」とは非常に曖昧な言葉ですが、私は「クリエイター」が「メディア」を通して「ユーザー」に届けるものをエンタメと定義しています。舞台、映画、テレビ番組、音楽、アニメ、ゲーム、SNS、VTuber──人が「熱中して楽しむもの」と感じる行為すべてがエンタメになります。2022年時点の国内コンテンツ産業の市場規模は13兆円程度ですが、世界規模で大小含めたクリエイターが生み出すエンタメ産業全体では200兆円を超える規模になります。その規模や影響力は計り知れません。
本日は「エンタメ」の届け手である電通の方とお話できること楽しみにしております。よろしくお願いいたします。

中山惇雄さん
エンタメ社会学者
1980年生まれ、東京大学大学院修了。リクルートスタッフィング、DeNAなどを経てRe entertainmentを創業。コンテンツビジネスに精通し、教員、行政(経産省コンテンツPjt主査、内閣府知財委員)を兼任する。
有元:よろしくお願いいたします。
私は電通のクリエイティブディレクターとして、エンタメ領域の仕事に関わることが多いです。広告会社の仕事はクリエイターやコンテンツの魅力をメディアに通す際に、その魅力を最大化させることだと考えています。中山先生の言葉を借りるなら「クリエイター」が「メディア」を通す際に、クリエイターを支援する役割だと考えています。
「エンタメ=コンテンツ産業」というイメージが強いですが、もうそれだけでは語れません。今は個人そのものがエンタメにもなる時代となりました。かつてはテレビ番組や映画など「完成されたコンテンツ」を届けていたのが、今では制作過程も含めて、SNSで誰もが発信者としてエンタメをつくれる。そういう意味で、私たちが支援する「エンタメ」もどんどん多様化しており、それぞれに愛され方も違うので、お手伝いする難しさを感じています。
本日は中山先生とのお話の中で答えやヒントが見つけられれば嬉しいです。本日はよろしくお願いいたします。

有元沙矢香さん
株式会社電通
クリエイティブディレクター・コピーライター
1985年生まれ。電通zero所属。朝日放送テレビ『M-1グランプリ』『熱闘甲子園』『探偵!ナイトスクープ』、テレビ朝日・東宝『君の名は。』地上波放送、Netflix、藤子プロなどのプロモーションを担当。
「愛されるコンテンツ」の第一条件は”クリエイターの熱量”
ーーいま、有元さんが口にした「愛されるコンテンツ」について、有元さん自身はどのように感じていますか?
有元:一言で言うなら“熱量”です。どんなに仕組みやアルゴリズムを整えても、心が動かないものは広がらない。最近は「効率的にウケるフォーマット」も多くありますが、それだけでは共感は生まれない。熱を持った作り手の“好き”が伝わるものこそが愛されるコンテンツの条件だと思います。
中山:すごく共感しますね。
今では個人のクリエイターが直接ファンと繋がることが当たり前になって、クリエイターの熱が伝わりやすくもなってますが、「熱量」はファンが支持する最初の起点です。
私もゲーム会社時代は「コンテンツに面白さは必要ない」と考えていた時代がありました。当時、ソーシャルゲームの全盛期でもあり、売れるフォーマットに合わせて時間つぶしになるコンテンツを作れば売れると考えていたんです。確かに、初期はフォーマットに沿ってスピード重視なものが当たりました。しかし、それも2~3年たってみるとクリエイターの熱量がないものは重力に負けて落ちていく。あのときに売れる売れないのフォーマットよりも、クリエイターとファンの熱量で残った息長いゲームが10年以上残っていて、それは以降のプロデューサーへの学びになりました。
有元:そうなんですよね。クリエイターの熱量があってこそ、アルゴリズムやフォーマットも生きると思います。
「熱量」と「共創」の両輪で愛されるコンテンツは生まれる
ーー2025年の現在地において、「愛されるコンテンツ」は具体的にどのようなものがありますか?
有元:今年よくXで盛り上がりを見かけたのは、 ABEMAで配信されていた『BOYS PLANET2』などのオーディション番組、映画『国宝』、『鬼滅の刃』や『チェンソーマン』といったアニメ映画、アーティストの「Mrs. GREEN APPLE」などでしょうか。
中山:いいですね。「クリエイターの熱量」とは別の視点で言うと、「ファンの共創意識」は日本で愛されるコンテンツの重要なポイントなんですよね。まさにオーディション番組なんかは顕著ですが、日本では古来より「ファン」は支持して消費するだけではなく、「推し」のようにコンテンツに関与していく存在でした。

ーー『ちいかわ』をはじめとして、近年ではSNS初のコンテンツも注目されています。SNSの距離感も「共創」を手助けしているのではないでしょうか?
中山:はい。SNSの登場でエンタメの構造が大きく変わりました。昔は企業が大きなメディアを通じてコンテンツを発信していましたが、今は個々人が直接ファン同士で届けあうことができます。SNSの拡散の構造は「共創」のひとつかもしれません。その起点になるのももちろん、ナガノさんがささやかな生活や食、人間関係を愛でることへの強い熱量がファンを触発しているからにほかなりません。
有元:とても興味深いです。私は『M-1グランプリ』と言う番組を吉本興業さん、朝日放送テレビさんと共に盛り上げる仕事をしています。M-1は年々、参加者が増加していて今年は1万1000組以上が参加してくださっています。漫才師一人ひとりの熱量もさることながら、M-1が愛されるコンテンツとして支持されているのは、お笑いファンの存在も欠かせません。近年では、視聴者という立場ではなく、M-1グランプリにエントリーをして一緒に盛り上げてくれる方もいらっしゃいます。熱量を受け取ったファンがクリエイターにもなるという循環は、まさにコンテンツの共創であり、愛されるコンテンツとして理想的な姿だと感じています。
時代は変わっても「エンタメ」の本質は変わらない
ーーこれから先、愛されるコンテンツはどのような変化を遂げていくのでしょうか?
中山: 時代の流れとともに、映画、テレビ、配信、SNSとメディアは多様化・複合化し続けていますが、メディアが変わってもエンタメの本質は変わらない。すなわちクリエイターの熱量とファンの共創環境をどう引き入れるかがカギになると思いますが、この点について、有元さんはどう思われますか?
有元:私も同感です。「クリエイターの熱量」や「ファンとの共創」は変わらず愛されるコンテンツの本質だと思います。熱がなければ、誰かを惹きつけることはできない。熱があれば、小さな火花がムーブメントにもなる。これから先、どのようなエンタメが誕生するのか楽しみですね。本日はありがとうございました。

中山:こちらこそ、ありがとうございました。
ーーお二人とも、本日はありがとうございました
取材・文/峯亮佑 撮影/干川修















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE