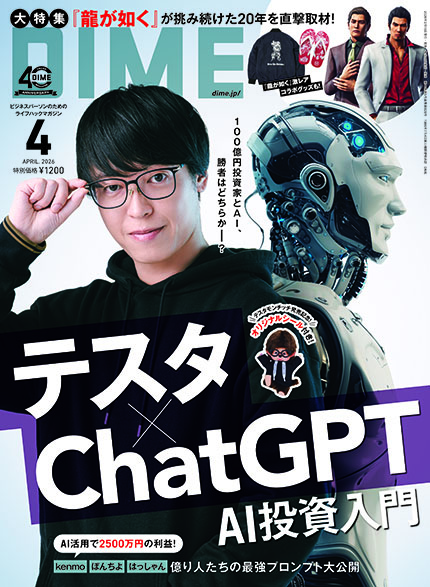B.LEAGUEは今年、開幕10年目を迎えた。
B.LEAGUEはプロスポーツの枠を超え、国内のバスケットボールファンに「エンターテインメント」としての熱狂を届けている。音楽や照明を駆使した演出、地域密着型のイベント、SNSを通じたファンとの双方向コミュニケーションなど、10年に渡り観戦体験を常にアップデートしてきた。選手たちのプレーはもちろん、チームと地域、そしてファンが一体となってつくり上げる“ライブエンタメ”への挑戦はスポーツ事業という言葉だけでは語れない。スポーツとエンタメの境界を越える存在となったB.LEAGUE。その取り組みの足跡をB.LEAGUEとB.LEAGUE GROWTH PARTNERとして支援する 広告会社・電通のキーパーソンに話を聞いた。

2026年から「B.革新」でリーグの昇降格制度が撤廃
ーーB.LEAGUEは2016年の開幕以後、順調に右肩上がりの成長を続けています。リーグやクラブの事業規模はもちろん、ファン数や認知度も大きく向上し、そして日本のバスケットボールの実力も世界レベルへと引き上げられました。この10年を振り返りどのように感じていますか?
佐野:日本のバスケットボール人気は90年代の『SLAM DUNK』であったりマイケル・ジョーダン選手の世界的ブームで人気に火がつきました。しかし、それ以後、20年近く日本のバスケ界はなかなか成長軌道に乗ることができませんでした。日本代表の実力は徐々に世界に遅れをとりはじめ、プロリーグへの発足にも紆余曲折がありました。
そうした時代を経て、2016年、ついに国内バスケファンの念願であった統一プロリーグ「B.LEAGUE」が開幕しました。
2025年にはB1に26クラブ、B2に14クラブの合計40のクラブがあり、選手数は540人(2025年10月17日時点)の規模にまで成長し、昨シーズンの来場者数は480万人を超えました。47都道府県のうち33の都道府県にクラブがあり、日本全国でバスケットボールと地域が接点を持っています。年俸1億円を超えるプレイヤーも誕生するなどB.LEAGUEの成長はさまざまな角度から語ることができるようになりました。
ようやく日本でバスケットボールがスポーツエンターテインメントとして根付いてきたと感じている所です。

佐野正昭さん
公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ
専務理事
2005年にアーサーDリトルジャパン入社。戦略コンサルタントとして様々な業界での経営支援の経験を経て、2016年より公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグに参画。マーケティング、クラブ経営支援、B.Hope(B.LEAGUEの社会的責任活動)、経営企画など様々な部署を歴任し、現在は、同リーグの専務理事として、リーグの事業成長を牽引。
ーー2026年からは「B.革新」という新たな取り組みが始まります。B.LEAGUEはどのように変化するのでしょうか?
佐野:「B.革新」はクラブが地域とともに成長するための新たな制度設計です。リーグやクラブ、そして競技が長期で成長していくためには地域社会の成長は欠かすことができません。地域と一体となったクラブ運営を続けていくための改革です。具体的に、我々はリーグの「昇降格制度の撤廃」を行ないます。
現在、クラブは競技成績に基づいて昇格・降格が行われていますが、この制度を廃止します。クラブの経営規模に応じたリーグに改革します。2026-27シーズンからは基準(※)をクリアしたクラブはトップリーグに当たる「B.LEAGUE PREMIER」に参加できるようになります。これはB.LEAGUEが地域創生や地域活性化に資するリーグであるために選手への投資だけでなく、地域社会への投資を促す目的があります。これによりB.LEAGUEは新たなエコシステムを生み出し、これまで以上に持続可能な団体を目指します。
※入場者:4,000名、売上基準:12億円、アリーナ基準:新設アリーナ基準充足 / 5,000席 など
ーーB.LEAGUEのファンにとって、この改革はどのようなメリットを享受できるのでしょうか?
佐野:「B.LEAGUE PREMIER」の参加基準の一つにアリーナの存在があります。先日開業した「TOYOTA ARENA TOKYO」(東京・江東区)のような大規模アリーナが全国各地で誕生しています。その結果、これまで日本に存在しなかったライブエンターテインメントを実現し、ファンはこれまで以上にバスケの観戦体験を味わえることになります。

「TOYOTA ARENA TOKYO」/©B.LEAGUE
マーケティング支援から事業支援へ
ーーB.LEAGUEの歩みの中で電通は広告会社としてどのような支援をしてきたのでしょうか?
安渕:2016年から電通はスポーツマーケティングの分野でご支援してきました。
発足当時はまだまだB.LEAGUEの価値に多くの企業やファンは気づいておらず、世の中にB.LEAGUEの魅力を届けるところからはじめました。

安渕 哲平さん
株式会社 電通
チーフソリューションダイレクター
2005年に電通入社。デジタル・営業・インキュベーション部門での経験を経て、2011年よりスポーツ事業に従事。スポーツの国際連盟や国内競技団体・リーグ等における放送・配信権事業やプラットフォーム開発、デジタル・SNS戦略等の推進に加え、当該領域での投資・協業等を推進。2024年より、同スポーツ領域におけるソリューション全般をリード。
ーーNPB(プロ野球)やJリーグ(サッカー)にないB.LEAGUEならではの魅力をどのように考えていますか?
安渕:やはり一つはファンの年齢層が若いことです。また、ファンの男女比は男性より女性ファンの方が多くプロスポーツとしてはめずらしく、特別な価値になっています。B.LEAGUEでは選手やクラブを「推し活」する文化もありますが、その背景には若年の女性ファンが多いことが寄与しています。こうした客層の傾向やアリーナならではのエンターテインメント性は他のスポーツにはない魅力となっており、こうした側面を強調することで、B.LEAGUEは多くのファンを獲得し、多くのスポンサー企業にも興味を持ってもらうことができています。
ーー「B.革新」をはじめとするB.LEAGUEの事業の中長期計画ビジョンにおいて電通はどのような役割を担っているのでしょうか?
安渕:電通はいま、マーケティング支援から事業支援へと支援の幅を広げています。B.LEAGUEにおいても「感動立国」をテーマに2050年のビジョンを掲げています。スポーツの感動を通じて地域や国を元気にしたいというビジョンです。そのためにいまB.LEAGUEではさまざまな新規事業を始めています。それに伴い電通もマーケティングだけではなく企画提案から事業策定まで、これまで以上にB.LEAGUEに寄り添った支援を始めています。
クラブが長期的に経営を続けるためには地域の活性化は不可欠
ーー直近のB.LEAGUEの取り組み「B.LEAGUE Hope PLANET VISION」においても電通の協力があったと聞きます。どのような取り組みか教えてください。
竹嶋:B.LEAGUEは発足当時からB.Hopeとして「PEOPLE・PEACE・PLANET」の3つの分野で社会活動に取り組まれています。特にSDGsは世の中が注目するよりも早くから意識されており、NBAなど世界の団体と同じく社会貢献への感度が非常に高いです。B.LEAGUEは2050年に向けて「感動立国」のビジョンを掲げていますが、クラブがある地域が元気でなければ人々に感動を届けることはできません。環境対策である「PLANET」は地域の環境や活性化の持続に貢献することを意味します。
「PLANET」を具体的に推進していくために、何のために、どのように進めていくのかの方針を制定したのが「B.LEAGUE Hope PLANET VISION」です。電通にはサステナビリティの専門チームがあり、この新規事業プロジェクトでも支援をさせていただくことになりました。

竹嶋 理恵さん
株式会社電通
サステナビリティコンサルティング室 エグゼクティブ・プラニング・ディレクター
ストラテジーからキャンペーン構築、ウェブやイベント、店舗開発等まで様々なジャンルの商品やサービスのプランニングに携わる。SDGsコンサルタントとして様々なステークホルダーに対してサステナビリティ起点の戦略策定、コミュニケーション、事業変革支援を手掛ける。電通グループサステナビリティオフィスとともに、広告とメディア業界の脱炭素化の推進に取り組む。
ーー具体的に「B.LEAGUE Hope PLANET VISION」はどのような内容なのでしょうか?
竹嶋:「B.LEAGUE Hope PLANET VISION」は地域が元気であり続けるために、バスケットボールを通じて、環境問題についてできることから取り組んでいこうというリーグやクラブの宣言であり、ファンや地域の方に向け、一緒に動いていくために呼びかけています。次に、 リーグと各クラブの道標となるようなハンドブックを開発しました。「PLANET」では、「気候変動対策(CO2の削減)」、「循環型社会の実現」「生物多様性への取り組み」のテーマのもと、クラブ経営、会場運営、移動・宿泊、飲食、グッズ、地域課題解決の6つのカテゴリーで具体的なアクションの事例を提案しています。例えば、飲食の販売過程により発生するCO2やゴミを削減するために「リユースカップを利用する」等です。当たり前のことかもしれませんが、こうした小さなアクションを一つずつ取り組むことで変えていきたいと考えています。
ーー環境負荷に関して言えば、アリーナの建設から運営、さらにはスポーツ興行を実施すること自体が多くのエネルギーを消費し、CO2も発生させています。その点に関してはどのように考えているのでしょうか?
竹嶋: CO2の削減や環境問題への対応についてはできることからしっかりと取り組みながら、そのためにスポーツやエンタテインメントの活動を制限したり、質を下げることはしないというのが大前提です。スポーツには人々の関心を高め、巻き込み、心や行動の変革を促すパワーがありますので、クラブや選手そして応援してくれるファンや地域の方々と一緒に大きなうねりを作っていける可能性があると信じています。
***
日本でバスケは流行らないーー。こうした過去の日本人の常識はB.LEAGUEの成長とともに消え去った。次にB.LEAGUEが目指すイノベーションは何か。
「B.LEAGUEはスポーツの枠を超えて”ライブエンターテインメント”だと思っています。選手同士の熱い闘いをファンが一緒に盛り上げる。そこに大きな感動が生まれ、その力を社会を変える新たな原動力にしていきたいです」(佐野さん)
スポーツから事業に、そして社会的インフラに。B.LEAGUEが起こす次のイノベーションに期待したい。
取材・文/峯亮佑 撮影/干川修















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE