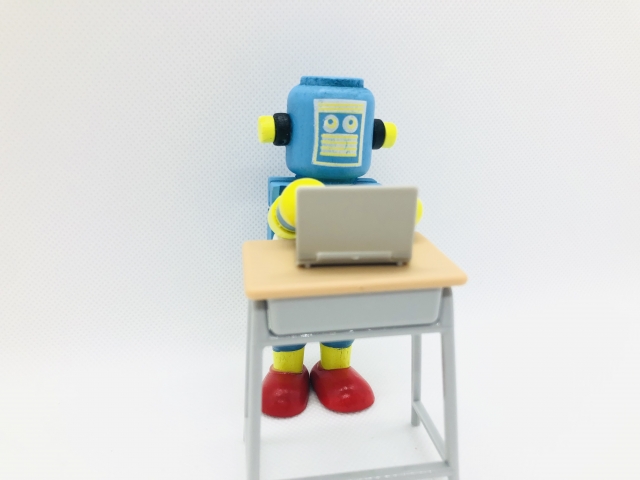生成AIなどのビジネス活用が進む中、採用領域にも浸透しつつある。AI活用は業務効率化につながる一方で、選考シーンにおける完全なる感情理解は不得手だ。2社の事例を通じて、AIと人の落としどころを探った。
1.「AIタレントリクエスト」機能
日本のキャリアSNS 「YOUTRUST(ユートラスト)」は個人向けだけでなく、法人向けとして転職潜在層へアプローチできるサービスを提供している。
2025年4月には、気になるタレント(スキルを持った人材)をAIがリストアップしてくれる機能「AIタレントリクエスト」をリリースした。
募集ポジション・求めるスキル・人物像を入力するだけで、YOUTRUST上のタレントからAIが条件にマッチした人材をリストアップする。
同サービスの特徴は「AI完全代替」ではなく、「人間とAIの協働」を目指している点にある。
株式会社YOUTRUST 技術基盤室長 山田昌弘氏は次のように解説する。
「採用活動は“人の人生を左右する意思決定”を求職者に求める行為であり、その責任をAIに負わせるべきではないと考えています。
AIの力の源はインターネット上の膨大なデータであり、候補者が自社にマッチするかを判断するための情報がすべてデータ化されているわけではありません。
例えば、会話のテンポや受け答えの誠実さ、同僚からのリファレンス、対面で感じる覇気や雰囲気など、履歴書や公開プロフィールには現れにくく、対面でしか得られない情報がたくさんあります」
一方で、AI活用はメリットが多い。
「採用要件のシステムへの入力や、候補者の一次リストアップ、スケジュール調整などの定型作業はAIの得意分野です。人間がすべきこととAIに任せるべきことを見極め、人間は求職者と向き合うような仕事に集中するべきだと考えています」
●導入事例
MOSH株式会社は当初、多くの採用候補者の中から条件に合う人材を探し出すのに時間がかかっていたが、同機能によって求める要件にフィットする方のリストアップ工数が大幅に削減できた。
またakippa株式会社も、候補者のピックアップに時間を要していたが、大幅に工数を削減でき「ストライクゾーンに入る候補者が多くなった」とのこと。
さらに「スカウトに対する返信からのカジュアル面談移行率は約80%」などの効率化だけでなく、マッチ率の精度向上の効果も出ている。
「これらの事例では、AIは『大量データの中から条件に合致する候補者を抽出する役割』、人は『候補者との接点作りやコミュニケーションの質を高める役割』を担いました。AIと人の補完関係がうまく機能していると思います」(山田氏)
●AI機能における今後の展望
同サービスは今後もAI機能を拡充させていくという。
「既存のスカウト文章作成支援機能や候補者検索機能のアップデート、スケジュール調整支援機能などを予定しています。AIの力を借りて、スムーズで満足度の高い採用活動と転職活動の体験を実現し日本の人材流動性を高め、ひいては日本のモメンタム(※勢い・推進力)を上げていきたいです」
2.対話型AI選考システム「harutaka AI面接」
株式会社ZENKIGEN「harutaka AI面接」は、AI面接官が応募者の特性や強みを瞬時に分析し、最も能力を発揮できる質問や場面設定を動的に生成し、応募者の真の魅力を引き出すサービスだ。
AIは人間の業務を完全に代替するのではなく、あくまで採用担当者の「アシスタント」として機能するという。
株式会社ZENKIGEN 人事広報部 マネージャー 清水邑氏は次のように解説する。
「AIが担う領域は、『データに基づく個別最適化』と『生産性向上』です。応募者の回答内容や話し方、表情などをAIが分析することで、面接時の効果的な質問や応募者の評価サポートを客観的なデータに基づいて行うことができます。
一方、人が対応する領域は、『対話と評価の最終判断』です。AIはあくまでデータをもとに評価のサポートを行うものであり、応募者の個性、熱意、企業文化へのフィット感など、言葉の裏にある機微や文脈の解釈は人が担う領域です。
さらに、人の人生を大きく左右する合否の最終的な判断は、応募者との対話を通じて、人間の感性や洞察力をもって行うべきものと考えています」
●導入事例
先日は、長野県塩尻市がトライアル導入した。従来のエントリーシートの記述内容をAI面接で代替することで応募者の負担を軽減する目的だ。受験生は何度でも面接のやり直しが可能で、面接練習の機会として活用できるのも魅力だ。また受験生一人ひとりとの対面面接の時間は限られているため、よくある質問はAI面接で事前に聞くことで対面面接ではより深い話ができるという。
応募者向けには面接練習サービスの提供も行っており、AIアバター面接官との模擬面接を通じて自身の強み・弱み・自己PRの表現方法などのフィードバックを得られる。
「当社では、採用活動におけるAIと人との関係性を『代替』ではなく『共存・共栄』と考えています」と清水氏。
「AIはあくまで人間がよりクリエイティブな業務に集中するためのツールであり、採用活動の核心である『人と人とのコミュニケーション』を豊かにするための技術であるべきです」
企業側の選考効率化に主眼を置くのではなく、応募者側の自己理解を促進し、自身の魅力を最大限に発揮できる選考の実現を目的とする。
●AI機能における今後の展望
今後、「harutaka AI面接」はどんな進化を予定しているのだろうか。
「企業向けの機能としては、各社の採用方針や求める人材像に合わせた面接体験の実現を目指してまいります。ビジョンの思考性を問う深掘り設問やカルチャーに沿った行動特性を問う設問機能の強化により、企業にマッチする応募者の早期検出を支援します。
応募者に向けては、単なる選考を超えた企業理解促進の機会として、対話形式による企業情報の提供機能を拡充してまいります。これにより、応募者が企業の魅力や働く環境をより深く理解し、納得感のあるキャリア選択を行えるよう支援します」
採用領域は、人間らしい感情や判断が採用後のマッチング度に大きな影響を及ぼす。両社は丁寧なAIと人とのすみわけを行い、開発していることがわかった。他分野でも応用できそうだ。
取材・文/石原亜香利















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE