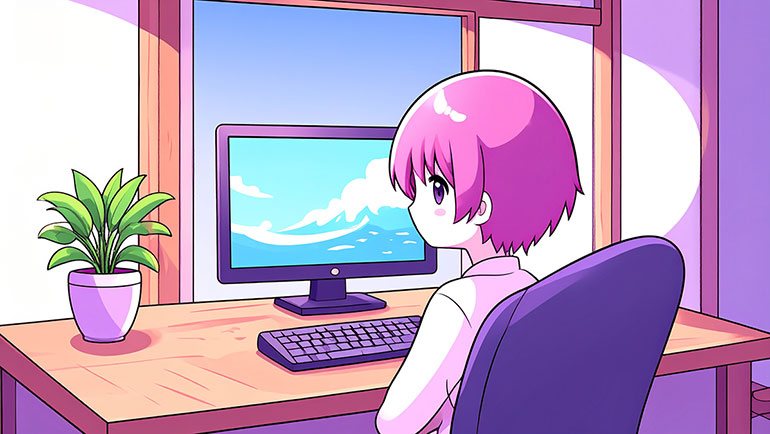
目の前の仕事に、意味を感じられない。あの出来事には、どんな意味があったのか。仕事も人生も頑張ってきたけれど、「このままでいいのかな」と心がざわつくことはありませんか?
思うようにいかない日々や、心が折れそうになる瞬間は、誰にでもあります。そんなとき支えになるのが「意味づけ」という視点です。心理学の「意味づけ理論」に基づき、心が迷ったときのヒントを紹介します。
意味づけ理論とは?
私たちは、出来事そのものより「どう受け取るか」で、感じ方も行動も変わっていきます。
では、「意味づけ理論」とはどういう考え方なのか、具体的に見ていきましょう。
「意味づけ理論」とは、起こった出来事に“どんな意味を持たせるか”という心の働きを扱う心理学の考え方です。たとえば、同じ失敗でも「自分には向いていない」と思う人もいれば、「次につながる」と受け止める人もいます。出来事の「解釈」次第で、気持ちや行動の方向は大きく変わります。
心理学では、「出来事そのもの」よりも「それをどう意味づけるか」が、心の回復や行動のモチベーションを左右すると考えます。 つまり、現実を変えられなくても、意味の見方を変えることで、気持ちは少しずつ立て直していけるのです。
意味づけが問われるのは、どんな時?
意味づけは、日常のあらゆる場面で私たちの心に自然と働いています。では、どのような場面で、意味づけの力がより強く問われるのでしょうか?
意味づけは、どんな出来事に対しても自然に働く、心の働きです。たとえば、嬉しいことがあったときにも、「うまくいってよかった」「誰かの役に立てた」と感じることで、その出来事に前向きな意味が生まれます。一方で、つらい経験や心が揺れ動く出来事では、その意味づけの力が、より強く問われることがあります。
たとえば、
・仕事で大きな失敗をしたとき
・努力が報われなかったとき
・人間関係の誤解や衝突で、自分を責めてしまうとき
・大切な人との別れや喪失を経験したとき
こうした出来事では、「なぜこんなことが起きたのか」と考え込んでしまいますよね。「自分が悪かったのでは」と自責に傾いたり、「何を信じればいいのか」と無力感に包まれることもあるでしょう。こうした苦しい場面では、「どんな意味があるのか」という視点を持つことが、心の回復の助けになります。
たとえすぐに答えが出なかったとしても、あとから「自分にとっての意味」が少しずつ見えてくることもあるのです。その小さな気づきが、次の一歩を踏み出すきっかけになるはずです。
意味を探す前にできる、心の整理ステップ
つらい出来事の直後は、意味づけをしようとしてもなかなかうまくいかないものです。まずは「いまの気持ちをそのまま受け止めること」から始めてみましょう。ここでは、意味を見つける前にできる3つの心の整理ステップをご紹介します。
■STEP1|前向きになれない自分を受け入れる
「こんな気持ちのままじゃダメだ」と自分を責めていませんか? 落ち込んでいるときは、無理に元気を出そうとするよりも、「今はつらい」とそのままの気持ちを認めてあげることが大切です。
■STEP2|感じた気持ちを外に出す
心の中にある思いを、言葉にして外に出してみましょう。ノートやスマホに、思いつくまま今感じていることを書き出します。「悲しい」「悔しい」「怒っている」など、どんな言葉でも構いません。出してみることで、少しずつ気持ちが整理されていきます。
■STEP3|焦らず、心を休ませる
次は、「何もしない時間」をつくってみましょう。散歩をしたり、好きな香りをかいだり、温かい飲み物を味わったり。何かを解決しようとせず、ただ静かに過ごすことがポイントです。気持ちが落ち着くと、自然と物事を少し客観的に見られるようになります。
意味づけを“いま”に生かす3つのヒント
意味づけ理論は、「いまを生きやすくする」ために活用できる心理学的な視点です。ここでは、日常の中で気持ちを立て直すための3つのヒントをご紹介します。
(1)自分の「受け取り方」に注目する
同じ出来事でも、「どう受け取るか」で気持ちは変わります。たとえば、上司に注意されたとき、「責められた」と感じるのと「期待されている」と感じるのとでは、次の行動がまったく違います。出来事は変えられなくても、「どう受け取るか」は変えられます。小さな場面で「私はどう感じたんだろう?」と立ち止まることが、意味づけの第一歩です。
(2)自分の本音を探してみる
落ち込みや怒りの裏には、たいてい“叶えたかった思い”が隠れています。 たとえば、プレゼンがうまくいかず、ひどく落ち込んだとします。 その奥には「認められたかった」という気持ちだけでなく、 「誰かの役に立ちたかった」「自分の仕事で人の助けになりたかった」という、貢献したい気持ちがあったのかもしれません。
失敗したことで「自分には価値がない」と受け取ってしまうと苦しくなりますが、 そこに、「本当は何を大切にしていたのか」という視点を向けてみると、 同じ出来事でも、「自分の大切な願いを教えてくれた時間」へと変わっていきます。
(3)違う角度から見直してみる
少し落ち着いてきたら、出来事を別の視点から見直してみましょう。たとえば、親しい人とのすれ違いで深く傷ついたとします。当時は「どうしてあんなことを言われたんだろう」と苦しかった気持ちも、時間が経つと「相手も不安だったのかもしれない」「自分も余裕がなかった」と気づけることがあります。
見方が変わると、「次に同じことが起きたら、少し違う関わり方ができるかもしれない」、あるいは「同じパターンを繰り返さなくてもいいかもしれない」と、新しい選択肢が見えてきます。その出来事から何を学び、どう次にいかすかを考えていくこと。その小さな変化が、立ち直る力(レジリエンス)を育てていくのです。
意味づけは「心を整理する」ための視点
意味づけとは、無理に前向きな意味を見出すことではありません。出来事の中にある「自分の気持ち」や「大切にしていた思い」に目を向けながら、少しずつ心を整えていくプロセスです。つらい出来事も、そこから何を学び、どう次にいかすか。意味を見つけようとするその時間も、あなたの心が回復していく大切なプロセスの一部なのです。
構成/高見 綾
「言えない」「怖い」問題社員への指導法について悩んだ時のヒント
「注意したいのに、言葉が出てこない」「叱ったら、“それ、パワハラです”って言われたらどうしよう」そんなふうに、伝えるべき場面で足が止まってしまうことは、ありませ…
「コミュ力おばけ」がまぶしいあなたへ、職場で疲れない距離感のつくり方
職場にひとりはいますよね。どこに行ってもすぐに誰かと仲良くなって、会議や雑談でも自然と場の中心になる人。SNSでは、そんな人たちを「コミュ力おばけ」と呼ぶようで…















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE
















