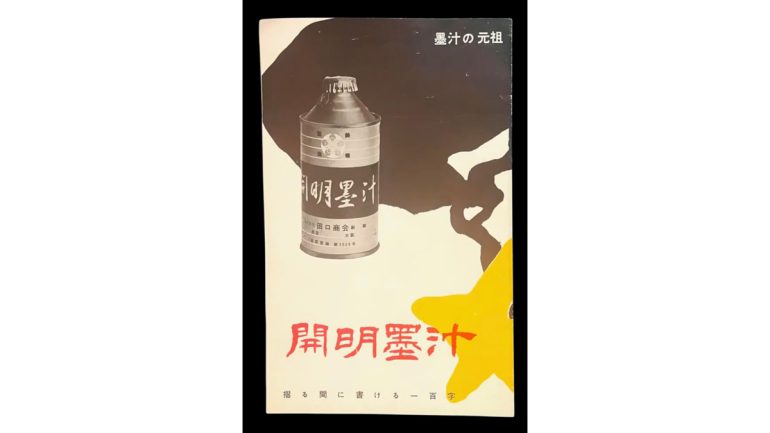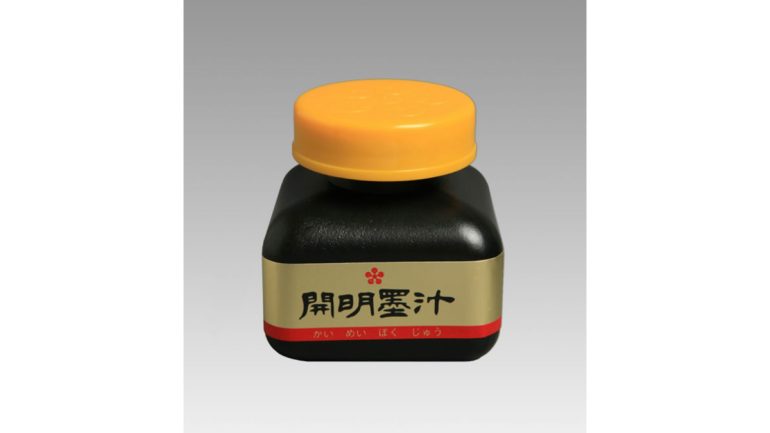
「鉄腕アトム」「ブラック・ジャック」など数々の名作を生んだ手塚治虫先生や、「ゲゲゲの鬼太郎」でおなじみの水木しげる先生など、日本を代表する天才漫画家が愛用したのが開明株式会社の『開明墨汁』だ。
老舗がだいぶふざけているのは、なぜ?
なぜ今この墨汁を取り上げるかと言うと、開明株式会社のSNSがバズっているからに他ならない。
創業127年の老舗企業であり、この世に墨汁を生み出した一流企業がSNSでダジャレを連発したりネタツイを頻繁に繰り出したり変わった商品も販売している。
老舗なのに少しだけ変だ。しかもひたすらバズりたい!という熱意もポストから漂っている。老舗がだいぶふざけている。
いくつか紹介すると、
日本が誇るロングセラーを生み出した真面目で実直な老舗企業はなぜSNSでハジけているのか?そこに企業としてのメリットはあるのか?
そして、水木しげる先生や手塚治虫先生が愛用した墨汁の未来をどう考えているのか?
今回、開明株式会社の「中の人」に話を聞いた。
――公式Xでのダジャレやネタがかなり印象的ですが…老舗がナゼ?
「当社は属している業界が非常に小さく、またアナログな面も多いため、新製品や情報が発信されても埋もれてしまうもどかしさがございました。そこでSNS、特にX(旧Twitter)の世界に強い可能性を感じ、積極的に適応するべく挑戦を続けております」
――ちなみに「中の人」はどんな方なんでしょうか?
「はい、営業マンが対応しております。かつては社内でグループを作り投稿案を持ち寄っていましたが、責任が分散し惰性になりがちだったため、約1年前にその体制を解散し、いまのスタイルに切り替えました」
「堅く真面目な会社というイメージはそのままに、ほんの少しだけ親しみを添えて伝えられるよう工夫しています。外見はユーモアでも、内側は真剣勝負の投稿です(笑)」
そんな開明株式会社、かつては創業120周年を記念して、墨汁の香りがする金色の消しゴム「墨汁屋さんの金の消しごむ」を販売。
これがホントの「キン消しだ!」と話題になった。
墨汁屋さんが消しゴムを売り出すというのもなかなか趣深いが、その理由はまた後ほど。
――SNSの投稿でこだわっていることは?
「旬な話題や投稿タイミング、反応の数値を意識しつつ、最も大切にしているのは「誰も傷つけないこと」です。読んでくださる方が少しでも幸せな気持ちになれるよう、常に前向きで温かみのある発信を心がけております」
「書道というと少し敷居が高い世界ですが、できる限り入りやすく親しみやすい形で文化に触れていただければと考えています」
そんな開明株式会社は、墨汁のパイオニア。伝説の漫画家たちも愛用した墨汁秘話があるという。
手塚治虫は「開明墨汁」じゃなければ漫画が描けなかった!?
時は明治半ばの1890年代。開明株式会社の創業者・初代社長の田口精爾氏は「子供たちがわざわざ墨を擦ることなく気軽に習字ができるようにしたい」との思いから、固形墨の研究に没頭。
たゆまぬ努力の結果、明治31年、1898年に理想の液体墨を完成させた。
稀代の発明品となった開明墨汁は以来、書道教育に欠かせないアイテムになるとともに、漫画界でも愛される存在に。
「今日の開明があるのは、手塚治虫先生の存在に負うところが大きいと感じています。トキワ荘の先生方をはじめ、先日はSNSを通じて水木しげる先生のご家族ともご縁をいただき、水木先生にもご愛用くださっていたことを改めて知りました」
「私たちは販売店を通じて製品をお届けしていたため、直接先生方と交流することは少なかったのですが、机上の写真や展示会での再現机に弊社製品を見つけたとき、その歴史と重みを強く感じました」
開明墨汁を愛していた漫画の神様・手塚治虫先生にまつわる、こんなエピソードがある。
「ある夜、「墨汁がないので漫画が描けない」と仰った手塚先生。編集スタッフが夜中に文具店を探し回ったものの「開明墨汁でなければ駄目だ」と譲らなかったそうです」
「作画に没頭される漫画家の方々にとって、描線の伸びやかさやインクの乾き具合はまさに生命線であり、そこに弊社の製品が寄り添えたことは誇りに思っております」
そして、@DIME読者も小中学校時代にお世話になったであろう「開明書液」が、1969年(昭和44年)に販売された。
筆運びが軽く乾きも速いこの逸品は、今も数多くの小学校で使われており、開明株式会社を代表するベストセラー商品だ。
ちなみに、手塚先生らが使っていた「開明墨汁」と、我々が学校で使っていた「開明書液」の違いはこうだ。
そんな「開明書液」は昭和44年(1969年)の発売以来57年目を迎え、その売上は累計でおよそ5千万本。昭和40~50年代に学校教育での需要や手書き文化の隆盛を背景に最盛期を迎え、近年も絶えることなく幅広いジャンルで愛されている。
「ただ、平成後期から令和にかけてはデジタル化や生活様式の変化により手書きの必携性が低下し、近年の売上は緩やかに減少しつつ横ばいの推移をたどっています」
それは想像に難くない。学生時代とは違い、大人になって墨汁や筆を手にする場面は明らかに減った。自らの手書きの文字さえもご無沙汰の状況。
そんなデジタル時代の今、墨汁を絶やすことなく更に魅力を伝えるために必要なことはなんなのか?
「墨」を少しずつ日常に浸食させていく
文化庁が調査した「令和2年度 生活文化調査研究事業(書道)」の報告書がある。
書道経験者の現在の書道活動について、全体の88.8%が「これまではしていたが、現在はしていない」と回答。また、書道未経験者は20代から30代が最も割合が多いという結果に。
参考:https://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/tokeichosa/seikatsubunka_chosa/pdf/93014801_05.pdf
学校の授業や書道教室以外で「墨汁」と触れ合う機会はかなり減ってきているが…
「芸術文化の領域を超えて日常生活に取り入れられる新たな習慣や楽しみ方を提案していくことが重要だと考えています」
「デジタルでは味わえない手書きの魅力を再発見できるよう工夫を重ねる一方、最大の懸念である「手や周囲が汚れる」という課題を解消するため、「墨ックバリア」などの汚れ防止クリームを企画し、より気軽に安心して墨汁に親しんでいただけるよう取り組んでいます」
さらに開明株式会社は、時代に即した商品、そしてSNSのようにぶっ飛んだ逸品も積極的に開発している。
【墨汁の香りがする 墨汁屋さんの消しごむ】
「墨の香りには心を落ち着かせる作用があり、懐かしさをまとった墨汁の香りと消しごむを組み合わせることで、ストレス社会の現代において幅広い世代に最適な商品となりました」
「墨そのものは消せないため、えんぴつ用の消しごむを黒くして香りを加えたのですが、当初は「墨汁が消える」と誤解されやすかったため、パッケージにも「墨は消えません!墨ません。」とユーモアを添えて訴求しています」
さらにこんなものも。
「現在では「墨のかおりシリーズ」として、入浴剤、ハンドソープ・ねりけし・開明墨糊などへと展開し、少しずつ生活の中に“浸食”を広げています。」
100年以上にわたり、ニッポンの書道や漫画、手書きの文化を支えてきた開明株式会社。老舗企業と墨汁が長年愛されている理由はなんなのか?そして墨汁のこれからの未来は?
「開明が続いてこられた理由は、決して「愛されてきたから」だけではありません。墨(ぼく)たち自身が墨汁、そしてお客様を深く愛しすぎてしまったから――その想いこそが支えとなり、今日まで歩ませてくれたのだと思います」
「グローバルな世界になってきたからこそ、私達は書道を通して日本人の心にふれ、自筆の文字だけが持つ温かみ、書いた人の心の動きが鏡のように表れる深い味わいを大切にしていきたいと思っています」
取材協力
開明株式会社
元祖墨汁王 開明墨汁公式X @kaimei1898
文/太田ポーシャ















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE