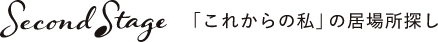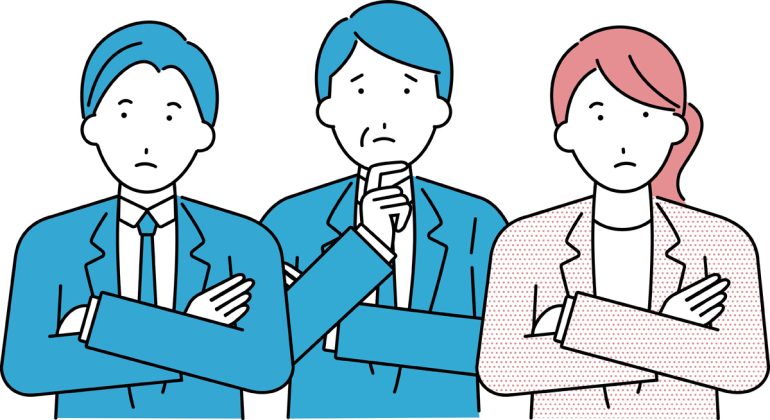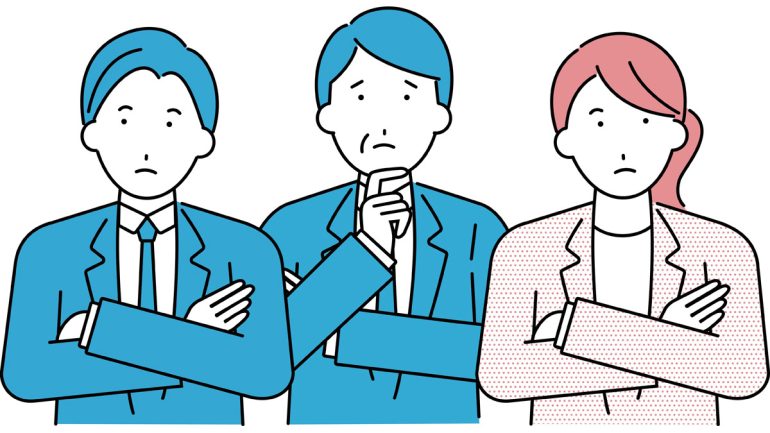
高齢者雇用安定法の改正に伴い、2025年4月からは、すべての企業に65歳までの雇用確保が義務付けられました。
若いころと変わらず、自己成長への意欲や、自身のスキルや経験を活かしたいというミドル・シニアは多く、日本の社会としても、年齢を問わず、長く働き続けられる環境がより整備されていくことは大切です。一方、外部環境が大きく変化し年齢を経るなかで、ミドル・シニア個人としては、今後のキャリアに対して悩みを抱えている人が少なくありません。
「転職や副業・兼業等、社外に活躍の道を見つけるにしても、現在の会社の中でも活躍し続ける道のいずれを選択しても、実は本質的に求められるミドル・シニア人材は大きく変わらない」と語るのは、日本総合研究所の研究員として、ミドル・シニアのキャリアに関する調査・研究をおこなうスペシャリスト・小島明子さん。
今後も活躍し続けたいと願うミドル・シニア自身の気づきにつながるよう、どのような人材が求められるか、また、そうした人材像に近づくために意識すべき・取り組むべき5つのポイントを紹介していただきます。
*本稿は、『定年がなくなる時代のシニア雇用の設計図』(日経BP 日本経済新聞社/宮島忠文・小島明子)を一部改編しました。
Point1 年齢を重ねて蓄積した経験値をプレイヤーとして活かす
誰でも年齢とともに体力は低下しますが、年齢を経ることが強みとなる経験値などの蓄積できる能力や特性があります。求められるミドル・シニアとはこの能力や特性をうまく活用し、年齢にとらわれない活躍ができるようになっている人です。
その特性の一例として、企業内での存在感が挙げられます。高齢になり、長く組織にいれば、その組織での影響力は大きくなります。役職にかかわらず、また、役職者が役職を離れたとしても容易に消えるものではありません。
長く働き続けているが一度も管理職になったことがない方でも、コミュニケーションに長け、キーパーソンをはじめ職場の人のことを熟知している方を見かけたことはないでしょうか。このような特性を活かし、若い後輩たちのために、社内で適切なキーパーソンをうまくつなぎ、サポートすることで、組織的には大きなメリットが生まれることがあります。
役職についていた方でもその多くは、いずれ役職を離れ、活躍し続けるためにはプレイヤーとして活動が求められます。体力を考えると、再び若い時のように働くことは難しいかもしれません。しかし、そもそも若者と同じ仕事の仕方をするという発想ではなく、まずは年齢を経る強みを活用して、より付加価値の高い仕事ができるよう意識してみることが重要だと考えます。
Point2 大事なのは経験を「活かす」こと
ミドル・シニアの価値は「経験」です。その経験と言うのは実践の場面で培った体験的な知見であり、どういう場合にはどうなるのか先読みができる、実体験からもたらされる実践的な知見です。身につけるためには時間がかかるため、ミドル・シニアの大きな魅力だといえます。
その魅力である価値ある「経験」は活かせなければ意味がありません。活かすためには、前提として自分の経験を「きちんと理解」をすることが求められます。キャリア研修等でよく棚卸しが行われますが、「単に○○という仕事を経験してきました」だけでは、異なる仕事で十分に活用することはできません。どのように組織や顧客等に貢献してきたのかを具体的に語れることが必要です。
そして、学び続けながら、そのスキルを使い続けることによって、その経験を活かし続けることができます。学んでいないうちに環境は変化をしてしまうため、環境に合わせてどんどんインプットし、常にアップデートをしていかなければなりません。たとえ、現場から少し遠いところにいたとしても、少しでも良いので現場のメンバーと話し、最新の知見を入れることを意識しておくことが大切です。
自身のスキルを今までと異なる仕事のなかでも活かせるよう、再現可能性を意識しつつスキルを整理することで、「年齢に見合った経験値」が「きちんと活用」できることにもつながるのです。
Point3 課題“解決”だけではなく、課題“発見”能力を高める
多くの方々は高い課題“解決”能力を保有し、改善することが得意だと感じます。新しいことを自ら発案し、進めていくことよりも、会社や上司から指示を受けた内容以上の業務量をこなし、成果を出すことに慣れている人は多いのではないでしょうか。
ミドル・シニアに限った話ではありませんが、今後は、付加価値の高い仕事をしていくために、企業、あるいは顧客が抱えている課題“発見”能力を高めていくことが求められています。現場においても、課題“発見”能力が弱ければ、何か手伝いますとは言えても、自ら主体的に仕事を分担するための行動にまではなかなかつながりません。
相手の困り事を発見することもできなければ、受け身的な仕事の仕方が続くことになりますので、結果として、代替可能な人材に陥り、今後のキャリアを歩む上でのリスクとなる可能性があります。そのため、このことは、働き続けてほしいか否かを分ける、大きな差と捉えてもよいと考えます。
しかし、ミドル・シニアには、先に述べた通り、年齢を経ることによるプラスの能力や特性、長年の経験値があります。そのような能力が活かしやすい、ミドル・シニアこそ、課題発見能力を高めやすいのではないかと感じます。また、そのことは、閉塞感のある組織、広くは社会を活性化させるきっかけになると期待しています。
Point4 いくつになっても手を動かすことを厭わない
ミドル・シニアになると若手を教育する立場につきたい、あるいは、現場から少し離れてサポートする側にまわりたいという方が増える印象があります。適性を踏まえて、周囲からそのようなことが求められているということであれば話は別ですが、そうでないのであれば、現場で積極的に手を動かしながら仕事をして成果を出す仕事の姿勢を見せることが重要です。
手を動かさず指摘ばかりをするミドル・シニアの存在の話を耳にされたことがあるかもしれません。歳を取ればとるほど仕事で手が動かしづらくなるため、結果として口を動かすことが目立ってしまうのだと思いますが、そのようにならないよう意識することは大切だと感じます。
特に職場内であれば、一メンバーではあっても、チームのリーダーの目線で全体を俯瞰し、どこの役割が手薄であり、チームメンバーが如何に楽になるかを普段から観察し、そして行動に出ることが必要です。チームメンバーがどんな問題点を抱えているのか、そこを観察して足りない部分を補うことが、チームの生産性向上にもつながり、必要な人と認識されるようになります。
Point5 困難な場面に直面したときに柔軟に発想を転換できること
年齢を経れば、若いころに比べると、キャリアの転換のハードルが高くなります。そのため、職場内でのキャリアの行き詰まり感や不満がより強くなるミドル・シニアの方は少なくありませんが、環境に不満をもったとしても、(経営者でない限り)自分の力では変えられることはほとんどありません。
しかし、そのような場面でも柔軟に発想を転換することができれば、自分自身も成長し、仕事の環境や周囲の人間関係も変わることがあります。その切り替えができるかどうかが求められるミドル・シニアになれるかどうかの大きな分かれ目だといえます。諦めて落ち込むのではなく、まずは発想を切り替え、色々なアクションを行うことができれば、外部の人脈の構築や、新しい仕事のチャンスを得るきっかけにもつながります。
困難な場面に遭遇したときに、職場の身近な人間に期待をし、解決の糸口を探ったり、あるいは新しいチャンスを得ようとする人は多いと感じます。筆者の経験則からも、困ったときに助けてくれたり、あるいは、将来につながる新たなチャンスとなることは、近い人ではなく、遠い関係の人が持ってきてくることは少なくないと感じます。
困難をストレスとしてもうダメだとあきらめるか、あるいは、何かのチャンスと捉えて外に意識を向けて行動できるかどうかで、その人自身の成長はもちろん、人生も大きく変わっていくはずです。
* * *
本稿では、求められるミドル・シニア人材になるための「5つのポイント」をテーマに取り上げました。少しでも参考になりそうなものを自分なりにカスタマイズして取り入れていただき、意識や行動を少し変えるだけでも、後々大きな変化につながるのではないでしょうか。
小島明子さん
1976年生まれ。民間金融機関を経て、2001年に株式会社日本総合研究所に入社。多様な働き方に関する調査研究に従事。東京都公益認定等審議会委員。主な著書に、『「わたし」のための金融リテラシー』(共著・金融財政事情研究会)、『中高年男性の働き方の未来』(金融財政事情研究会)、『女性と定年』(金融財政事情研究会)、『協同労働入門』(共著・経営書院)、『定年がなくなる時代のシニア雇用の設計図』(共著・日経BP 日本経済新聞出版)。