
2025年の年末調整では、基礎控除と給与所得控除が引き上げられ、特定親族特別控除が導入されます。扶養や配偶者、勤労学生控除の要件も緩和され、住宅ローン控除の拡充措置も続きます。申告書の記入ミスを防ぐことが大切です。
目次
2025年の年末調整が変更になると知り、自分の申告対応にどのような影響があるのか、気になっている方もいるのではないでしょうか。2025年度に実施された税制改正に伴い、12月に行う年末調整でも変更が生じます。2025年の年末調整における変更点や、注意点を解説します。
2025年の年末調整の変更に至った経緯

2025年の年末調整の変更は、税制改正に伴って行われます。
今回の税制改正では、所得税における「基礎控除」や「給与所得控除」の見直しに加え、新たに「特定親族特別控除」が創設されました。これにより、課税の公平性を高めつつ、納税者の実態に即した制度運用を目指しています。
改正内容は原則として2025年12月1日から施行され、同年分以後の所得税に適用されるため、2025年12月の年末調整以降、源泉徴収事務の手続きに変更が生じます。
一方で、同年11月までの源泉徴収事務には影響が及ばないため、改正の適用開始時期を正しく理解しておくことが重要です。
■物価高騰から家計を守る控除の拡充
2025年の年末調整における大きな変更点として、物価上昇に対応するための控除額の引き上げが挙げられます。
物価の上昇に応じて、インフレによる生活費上昇への対応や、人材確保のための競争力維持を目的に賃上げを行う企業もみられます。ただし、賃上げによって給料の金額そのものが上がったとしても生活コスト上昇に対応したものであるため、実質的に余裕が増えるわけではありません。
しかし税制上は「収入が増えた」として扱われるため、基礎控除が一定額のままだと課税対象となる所得が増え、結果として税負担が重くなる問題が生じます。
そこで、基礎控除を58万円に、給与所得控除の最低保障額を65万円に引き上げる見直しが行われました。これにより、従来「103万円の壁」と呼ばれていた非課税枠は「123万円の壁」へと拡大されます。
■「年収の壁」緩和による就業促進
2025年の年末調整に関する改正の背景には、労働力不足の課題もあります。
少子高齢化や人口減少が進むなか、誰もが働きやすい環境を整えることが急務となっています。そこで注目されたのが「年収の壁」の緩和です。
従来は、基礎控除と給与所得控除を合わせた103万円が課税ラインとされていたため、この額を超えると税負担が急増することから、働く時間を調整する人が少なくありませんでした。
今回の改正では基礎控除と給与所得控除の引き上げに伴い、非課税枠が123万円まで拡大されました。これにより、働き手は収入を増やしてもすぐに大きな税負担が生じにくくなり、安心して就業時間を延ばすことが可能になります。結果として、労働参加の拡大や多様な働き方の実現につながると期待されています。
そもそも「年収の壁」とは
「年収の壁」とは、一定の収入を超えることで税負担や社会保険料の負担が急増し、結果的に働く時間や収入を抑えざるを得なくなる状況のことです。
なお、年収の壁といっても、「税」と「収入」では、対象とする収入は以下のように異なります。
・「税」が対象とする収入:課税所得(個人が1年間で得たすべての所得金額から、各種所得控除を差し引いた残りの金額。通勤手当などの非課税所得は含まれない)
・「社会保険」が対象とする収入(会社員の場合):控除前の給与・手当・賞与(通勤手当や各種給付金も収入として扱われる)
例えば、収入の内訳が「給与収入103万円(課税所得)」と「通勤手当30万円(非課税所得)」の場合を考えてみましょう。
現行ルールでは、税法上は非課税分を除いた103万円が判定基準となるため、所得48万円以下となり「税」では扶養の対象になります。
一方、社会保険では通勤手当も含めて判断されるため、合計収入は133万円となり、扶養から外れる可能性があります。こうした「税」と「社会保険」での扱いの違いが、誤解や手続きミスを生む要因です。2025年改正後は、この「税」の基準が123万円に引き上げられるため、混同しないよう注意が必要です。
年末調整変更に関連するのは「税の年収の壁」
2025年の年末調整における大きな変更は、「税」の年収の壁に直結しています。
今回の改正では、基礎控除と給与所得控除が引き上げられ、さらに特定親族特別控除が新設されたためです。その結果、従来「103万円の壁」と呼ばれていた課税ラインが実質的に「123万円の壁」へと移行し、一定の収入までであれば税負担を抑えやすくなりました。
とくに大学生の年代の子どもがいる家庭では、親の税額が軽減されるケースが増えると考えられます。つまり今回の改正は、就業調整を強いられてきた層にとって働きやすさを広げる効果があるといえるでしょう。
2025年の年末調整の変更点
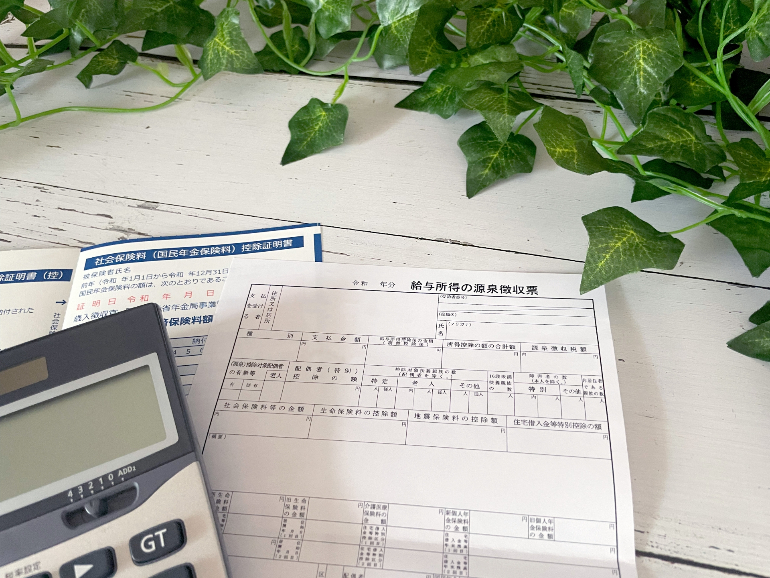
税制改正の内容とそれに伴う年末調整の変更点を正しく理解しておくことで、スムーズな対応につなげられます。ここでは、年末調整に影響を及ぼす税制改正の、各項目の変更の背景や具体的な変更ポイント、年末調整に与える影響を解説します。
■基礎控除の引き上げ
基礎控除は、すべての納税者が利用できる最も基本的な所得控除であり、生活を守るための重要な制度です。2025年の税制改正では、この基礎控除額が大幅に見直されました。
基礎控除引き上げの背景と具体的な変更内容、そして年末調整に及ぶ影響について解説します。
変更の背景
基礎控除の見直しが行われたのは、物価上昇や生活コストの増大から納税者の生活を守る必要性があったためです。
基礎控除は、納税者の最低限の生活を守るために設けられた制度で、すべての納税者が所得に対して一定額を控除できる仕組みです。
過去には令和2年に控除額が38万円から48万円へ引き上げられましたが、近年の物価高によって、その効果が薄れているとの指摘がありました。
そこで、令和7年度税制改正ではさらなる引き上げが決定され、2025年の年末調整から適用されます。この変更によって所得税の負担が軽くなり、家計への支援効果が一層高まることが期待されています。
変更のポイント
2025年の年末調整では、基礎控除額が大幅に見直されることがポイントです。具体的には、従来48万円であった基礎控除が、令和7年度以降は恒久措置として引き上げられ、さらに2025〜2026年の2年間は時限的に上乗せされる仕組みが導入されました。
その結果、控除額は最大で95万円まで拡大します。
【基礎控除額(改正された範囲)】
合計所得金額(収入が給与だけの場合の収入金額) | 基礎控除額 | ||
| 令和7・8年分 | 令和9年以降 | 改正前 | |
| 132万円以下(200万3,999円以下) | 95万円 | 58万円 | 48万円 |
| 132万円超 ~ 336万円以下(200万3,999円超 ~ 475万1,999円以下) | 88万円 | ||
| 336万円超 ~ 489万円以下(475万1,999円超 ~ 665万5,556円以下) | 68万円 | ||
| 489万円超 ~ 655万円以下(665万5,556円超 ~ 850万円以下) | 63万円 | ||
| 655万円超 ~ 2,350万円以下(850万円超 ~ 2,545万円以下) | 58万円 | ||
1 改正後の所得税法第86条の規定による基礎控除額58万円に、改正後の租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算額を加算した額となります。
2 58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した金額となります。なお、この加算は、居住者についてのみ適用があります。
3 特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
4 合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。
出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」
年末調整に与える影響
年末調整で基礎控除を受けるには、基礎控除申告書の提出が欠かせません。令和7年以降は、所得の区分がこれまで以上に細かく設定されるため、自分の合計所得金額に合わせて正しく申告することが求められるでしょう。
■給与所得控除の引き上げ
給与所得控除は、給与所得者にとって大きな役割を果たす制度であり、年末調整の計算にも関わる控除です。2025年の改正では、この控除額が引き上げられました。
とくに最低保障額が引き上げられることで、これまでの「103万円の壁」が緩和され、働き方の選択肢が広がる点がメリットです。給与所得控除を変更する背景やポイント、年末調整への影響を解説します。
変更の背景
給与所得控除は、会社員などの給与所得者が実際に負担する経費を考慮し、所得税の計算上、収入から一定額を差し引く仕組みです。これまでも給与収入に応じて控除額が段階的に決められていましたが、最低保障額が固定されているため、物価上昇により収入が増えても控除額が変わらない課題がありました。
そこで生活コストの増加や就業調整への対応として、給与所得控除の引き上げが実施されたのが、今回の変更の経緯です。
変更のポイント
今回の改正で、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。この変更により、基礎控除と合算した非課税ラインは160万円に拡大し、従来「103万円の壁」と呼ばれていた水準も大きく引き上げられます。
結果として、パートやアルバイトで働く人が収入増を目指しやすくなり、就業意欲の促進につながると期待されています。
【給与所得控除額(改正された範囲)】
給与の収入金額 | 給与所得控除額 | |
| 改正後 | 改正前 | |
| 162万5,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5,000円超 180万円以下 | 65万円 | その収入金額×40%-10万円 |
| 180万円超 190万円以下 | 65万円 | その収入金額×30%+8万円 |
(注)給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」
年末調整に与える影響
給与所得控除の引き上げにより、年末調整の実務でも正確な記入がより重要になるでしょう。
基礎控除と同様に、申告書の給与所得欄にある「所得金額」を記載する際は、最新の控除額を反映した正しい数値になっているかを確認しなければなりません。誤りがあると控除が適用されず、結果的に余分な税負担が生じる恐れがあります。
■特定親族特別控除の新設
2025年の年末調整では、新たに「特定親族特別控除」が導入されます。大学生年代にあたる19歳以上23歳未満の子どもなどを持つ世帯の税負担を軽減し、若年層の就業を後押しするための制度です。
従来、大学生年代にあたる子どもは扶養控除の対象から外れてしまうケースが多くありました。しかし、この新制度により一定の所得範囲内であれば控除が認められるようになり、家計の負担の軽減につながると考えられています。
変更の背景
特定扶養親族に対する従来の控除額は63万円でしたが、対象となる子ども(19歳以上23歳未満)の収入が103万円を超えると、親が控除を受けられなくなる点が課題でした。その結果、学生世代を中心に「年収の壁」を意識した就業調整が行われ、働きたい若者が収入を抑える傾向が生じていました。
こうした問題を解消し、若年層の就労意欲を促進するために「特定親族特別控除」が新設されました。
変更のポイント
今回の改正で新たに導入された「特定親族特別控除」は、特定親族を扶養に持つ場合に適用される仕組みです。対象となるのは、居住者と生計を共にする19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が58万円超123万円以下の方です。
控除額は合計所得金額に応じて段階的に設定されており、親の税負担を軽減すると同時に、大学生世代の就業継続を後押しする狙いがあります。
なお、大学生年代の方が、他の親族からみて「配偶者」と「特定親族」の両方に当てはまるケースについては、「配偶者」か「特定親族」のいずれかのみで扶養対象となります。
【特定親族の特別控除額】
| 特定扶養の合計所得金額(収入が給与だけの場合の収入金額(※)) | 特定扶養特別控除額 |
| 58万円超 85万円以下(123万円超 150万円以下) | 63万円 |
| 85万円超 90万円以下(150万円超 155万円以下) | 61万円 |
| 90万円超 95万円以下(155万円超 160万円以下) | 51万円 |
| 95万円超 100万円以下(160万円超 165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下(165万円超 170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下(170万円超 175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下(175万円超 180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下(180万円超 185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下(185万円超 188万円以下) | 3万円 |
(注) 特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」
年末調整に与える影響
特定親族特別控除を受けるためには、年末調整時に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出することが求められます。
この申告書には、対象となる親族の年齢や所得状況を正確に記載しなければなりません。記入内容に誤りがあると控除が適用されず、結果として税負担が大きくなる可能性があるため、提出前の確認が欠かせません。
■扶養控除・配偶者控除などの所得要件緩和
2025年の年末調整では、扶養控除や配偶者控除などの所得要件が緩和され、適用範囲が拡大されます。これにより、従来は対象外だった年収103万円を超える家族が新たに控除対象となる可能性があります。
また、勤労学生控除の要件も見直され、学生がアルバイト収入を得ながらも控除を受けやすい環境が整えられました。今回の改正は、家計の負担軽減と就業意欲の促進を両立させる狙いがあります。
変更の背景
扶養控除や配偶者控除の所得要件が緩和された背景には、基礎控除や給与所得控除の引き上げがあります。
従来の要件のままでは控除との整合性が取れなくなるため、制度全体のバランスを保つ目的で扶養親族や配偶者に関する基準も見直されることになりました。
変更のポイント
今回の見直しにより、扶養控除や配偶者控除の適用範囲が広がりました。具体的には、従来は対象外だった「年収103万円〜130万円未満の家族」が控除の対象となる可能性があります。
さらに、勤労学生控除の合計所得金額要件も「75万円以下」から「85万円以下」へ引き上げられました。これにより、アルバイト収入のある学生でも控除を受けやすくなり、家計や学業との両立を支援する効果が期待されます。
年末調整に与える影響
扶養控除や配偶者控除などの所得要件緩和は、年末調整の手続きにも直接影響します。
2025年12月1日以降に支払われる給与から適用されるため、新たに扶養控除の対象となる親族がいる従業員は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に追記して提出しなければなりません。
また、従業員のうち公的年金等を受給している方が新たに扶養控除を受ける場合、年末調整ではなく、原則として確定申告での手続きが必要となる点にも注意が必要です。
■その他の所得金額要件の引き上げ
基礎控除の見直しに伴い、扶養控除や配偶者控除などの所得要件も引き上げられました。主な変更点は以下のとおりです。
・控除対象扶養親族・ひとり親の子ども:所得要件が「48万円以下(収入103万円以下)」から「58万円以下(収入123万円以下)」に緩和された
・配偶者関連:同一生計配偶者の要件は「58万円以下」に変更。配偶者特別控除の対象範囲は「58万円超~133万円以下」となり、上限133万円は据え置かれた
・勤労学生控除:所得要件が「75万円以下(収入130万円以下)」から「85万円以下(収入150万円以下)」に引き上げられた
これにより、多くの家庭や学生が控除を受けやすくなり、家計支援や就業促進の効果が期待されます。
■住宅ローン控除の拡充措置継続
住宅ローン控除は、年末調整で申告することで税額から直接差し引かれる制度の1つです。今回、令和6年から導入されていた拡充措置が令和7年も継続されることになりました。主な改正点は以下のとおりです。
【控除対象借入限度額の拡大が継続】
特例対象個人(夫婦のいずれかが40歳未満、または19歳未満の扶養親族がいる世帯)が2025年中に認定住宅等を取得・入居した場合、借入限度額の上限は以下の水準が適用されます。
・認定住宅:4,500万円 →5,000万円
・ZEH水準省エネ住宅:3,500万円 → 4,500万円
・省エネ基準適用住宅:3,000万円 → 4,000万円
なお、認定住宅とは、国が定めた基準をクリアした住宅を指します。構造や設備、性能、維持管理といった多方面で一定の水準を満たしていることが特徴です。
ZEH水準省エネ住宅は省エネ性能が高く、最高ランクの断熱性能と高水準の省エネ性能により、快適で経済的な暮らしを実現できます。
また、省エネ基準適用住宅は、2025年4月以降に建てられる新築住宅に義務付けられた、国が定めた最低限の省エネ基準を満たした住宅のことです。
【床面積要件の緩和措置の延長】
合計所得金額が1,000万円以下であれば、40平方メートル以上50平方メートル未満の新築住宅も対象となる特例が、2025年12月31日までに建築確認を受けた住宅まで引き続き適用されます。
これにより、年末調整で住宅ローン控除を申告する際の対象範囲が広がり、若年層や子育て世帯を中心に節税効果が期待できるようになるでしょう。
2025年の年末調整における注意点
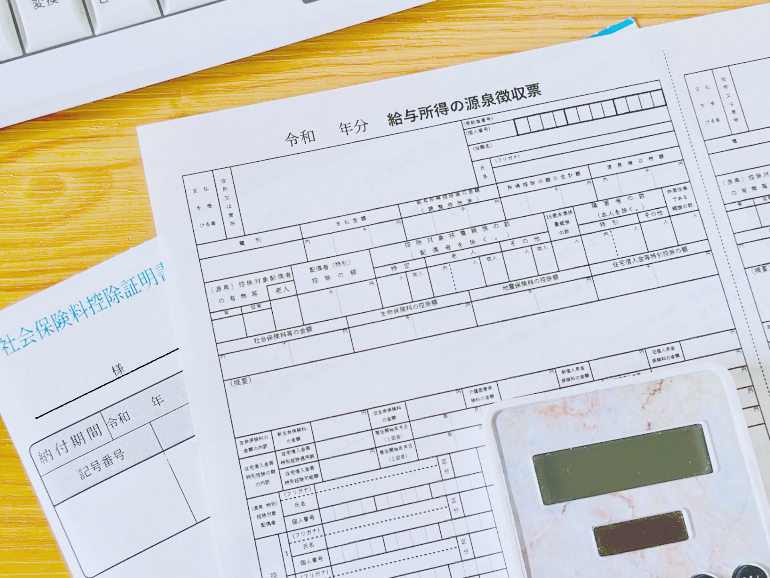
2025年の年末調整では、控除額や申告書の改訂により、計算や記入に誤りが生じやすいと考えられます。したがって、提出前に内容をしっかり確認し、ミスを防ぐ姿勢が求められます。
ここからは、2025年の年末調整で注意すべきポイントをみていきましょう。
■計算ミスや記入ミスに注意する
2025年の年末調整では、申告書の様式や控除制度が大きく見直されるため、例年以上に誤記や計算ミスのリスクが高まります。
とくに、基礎控除や給与所得控除の引き上げ、特定親族特別控除の新設などにより、適用条件が複雑化している点に注意が必要です。
誤った記載は控除額の算定ミスにつながり、結果として余分な税負担を招く恐れがあります。従業員は記入内容を丁寧に確認し、人事担当者も二重チェックでミスを防ぐことが大切です。
■11月30日までは従来の形式で対応する
2025年の年末調整に関する改正は、12月1日以降に適用される点に注意しましょう。つまり、11月30日までに実施される年末調整は従来のルールに基づいて行われます。
例えば、海外転勤で非居住者となる従業員が11月末までに出国する場合、その年末調整は改正前の税制で処理されます。改正内容を適用できるのは12月以降の調整のみであるため、12月1日以後に、出国した本人が税務署に更生の請求をしなければなりません。
2025年の年末調整の変更点を理解しよう

2025年の年末調整では、基礎控除と給与所得控除が引き上げられ、「103万円の壁」は実質「123万円の壁」に変更になります。あわせて19〜22歳を対象とする特定親族特別控除が新設され、さらに扶養控除や配偶者控除の所得要件緩和、住宅ローン控除の拡充措置継続など、多方面で改正が及ぶ点も特徴です。
その結果、従来対象外だった層も控除を受けやすくなり、家計への支援が広がることが期待されています。
これらの変更に伴い、年末調整における計算や記入内容は複雑化します。そのため、従業員は申告内容を丁寧に確認し、誤りを未然に防ぐことが重要です。
人事・総務部門も記載漏れや判定ミスをチェックする体制を整え、記入例を示すなどのサポートを行うことで、全体の正確な処理につなげることが求められます。2025年の年末調整の変更点を理解し、適切な対応を心がけましょう。
文/編集部















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE













