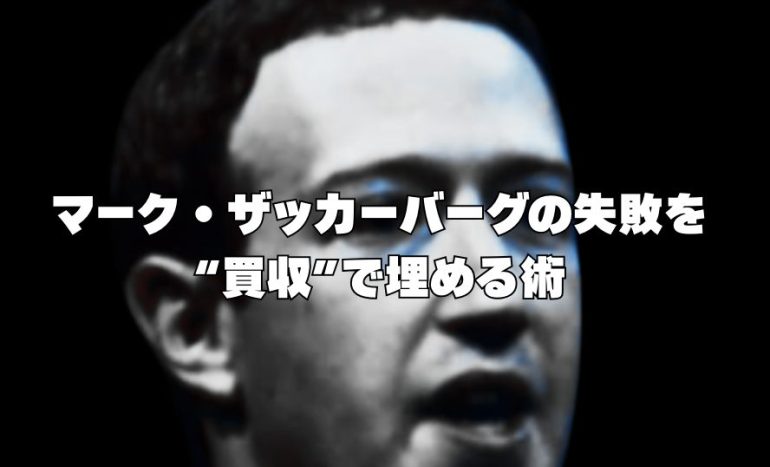
ザッカーバーグの歩みを一言でいえば、事業を「当て続けた人」ではなく「失敗しながらも諦めずに挑戦を続けた人」といえるでしょう。Meta(旧Facebook)の事業は世界規模のプラットフォームになりましたが、その過程では数え切れないほどの試作と撤退が積み重なっています。

たとえばAndroidを“Facebook化”するはずだった「Facebook Home」はユーザーの生活動線を奪いすぎて定着せず、ニュース体験を再設計した「Paper」は熱心な一部に刺さりながら大衆には広がらず、Snapchat対抗の実験アプリ群(Slingshot、Rooms、Riff)は各々が小粒なまま消えていきました。もっと古くは広告・トラッキングの「Beacon」がプライバシー反発で撤回に追い込まれ、のちの世論と規制の逆風を受けました。
こうした“失敗の山”をどう処理するか――ここでザッカーバーグは、買収というカードで「時間」を買うことを選び続けます。
モバイル写真の覇権はInstagramを、メッセージングの既定路線はWhatsAppを、巨大な波が立ち上がる“いま”のうちに自分の側へ引き寄せる。外れの損失は学びとして内部化し、足りないピースは外部から最短距離で連結する。これが、ザッカーバーグの勝ち筋となっていったのです。
なぜ“作る”ではなく“買う”のか
ザッカーバーグは創業当初から「配布(ディストリビューション)の戦い方」を追求していました。SNSの本質は機能の多寡ではなく“誰とつながって、どれだけ速く広がるか”。ネットワーク効果が強い領域では、良いプロダクトを作ることと同じくらい、拡張の速度を上げることが重要です。ここで行われる「買収」の目的は、(1)すでにプロダクト/マーケットフィットを得ているサービスを、(2)自社の配布網と広告基盤に載せ、(3)オペレーションの学習曲線をショートカットする手段になります。Facebook HomeやPaperのように“自社の文脈”から発想した新機能は、思い切ったUI変更や新しい行儀作法をユーザーに強いるぶん大衆化に時間がかかります。
対してInstagramやWhatsAppのようにユーザーが既に愛用している体験は、買収すれば導線を壊さずに広告スタックやクリエイター経済と自然に接続できます。買収は「機能のコピー」ではなく、「時間の圧縮」です。成長のボトルネックが“つくる難しさ”より“広げる難しさ”にある局面では、買収の費用は、逃す機会損失に比べればむしろ安い投資になるのです。
Instagram:モバイル写真という“弱点”を、最短ルートで主力に
2012年、FacebookはInstagramを約10億ドルで買収します。当時のInstagramは社員十数名・ユーザー約3,000万人の“小さな巨人”は、当時すでにモバイル写真=自己表現の最短手段というカルチャーを作りつつありました。一方でFacebook本体はテキストとリンク中心の「情報の場」へ進化し、写真の“瞬発力”が落ちていました。
ここでザッカーバーグは、自前で写真アプリを磨き上げて“いつか追いつく”より、既に愛されているUIとコミュニティを取り込む方が早いと判断します。
こうして、Instagram買収後もプロダクトの自律性は尊重し(Instagramブランドは存続)、一方で広告基盤はMetaの共通資産に載せる戦略を採用します。
具体的には、Stories/Explore/Reels への広告面拡張と測定基盤の共通化によって、広告在庫(面)と単価の双方を底上げする効果が生まれました。
これにより発見(Explore)の強化、広告商品の拡充、そして短尺動画「リール」でTikTok的な視聴体験も取り込み、滞在時間と広告在庫を同時に積み上げました。重要なのは、Instagramが“Facebookの延長”ではなくInstagramとして進化を続けたことです。もし「Facebook的」であることを優先していたら、若年層の審美眼と速度感に置いていかれてかもしれません。買収の成功は、過度に既存サービスのカルチャーに過度に干渉しない戦略に支えられているともいえるでしょう。
WhatsApp:広告を拒む哲学を抱えたまま、“世界の連絡先”を押さえる
2014年、FacebookはWhatsAppを約190億ドルで買収します(現金+株式、RSUを含む構成)。当時から「個人チャットに広告を入れない」という哲学と、驚異的な日次アクティブ率を併せ持つコミュニティでした。
そして2025年6月、Metaは受信箱や個別会話とは分離された「アップデート(Updates)」タブに限って広告を導入すると発表しました。Updates内の「ステータス(Stories型の短期投稿)」にも広告枠を設け、さらにチャンネルの有料露出(プロモーション)と、チャンネル運営者によるサブスクリプション(定額課金)を解禁しました。Updatesタブは1日あたり約15億人が利用しており、まずはここを収益化の表玄関に据える設計です。サブスクのアプリ内決済について、将来的に売上の10%を徴収する方針のようです。
一方で、個人チャットには引き続き広告を表示せず、エンドツーエンド暗号化の方針も維持します。広告のターゲティングは位置情報や端末の既定言語など限定的なシグナルにとどめ、メッセージ本文や誰と会話しているかといった個人チャットの内容は使わないと説明しています。
「買えない」相手には“機能で追い越す”――Snapchatの教訓
買収がいつでも通るわけではありません。2013年当時、FacebookはSnapchatに買収提案を持ちかけたと報じられましたが、交渉は不成立。ここでザッカーバーグは二本目の矢を放ちます。Instagramに「Stories」を実装し、“消える投稿”の体験をより大きなグラフに接続してしまう。これは単なるコピー論争ではなく、動線デザインの設計の勝負でした。Instagramはすでに“発見の場”として定着していたため、クリエイターと広告主が新しい表現様式に滑らかに乗れる土台がありました。「買えなければ、動線で勝つ」。買収がダメなら内製、内製が難航すれば買収――ではなく、どちらの回路も常に開けておく。この柔らかさが、ザッカーバーグの実務的な強さです。
失敗は“手数料”であり、“規制”は裏コスト――BeaconからDiemまで
成功物語の陰には、常に“手数料”のように支払われ続けた失敗があります。Facebook Homeは「人のスマホは人のもの」という当たり前の感覚を見誤りました。Paperはプロトタイピングとしては美しかったが、大衆の摩擦を取り切れなかった。Creative Labsは「たくさん撃って、当たりを拾う」思想でしたが、当たりを本体とどう重ねるかの統合設計が難しかった。
そして何より、規範と制度の壁です。Beaconはプライバシーの感覚を過小評価したがゆえの撤回でしたし、デジタル通貨Libra(のちにDiem)は、金融インフラという中核にテック企業が踏み込むことの難しさを露呈しました。ユーザー体験として「便利」でも、外部性とリスクが大きい領域では、民間の速度だけでは押し切れないのです。ザッカーバーグの強みは“速度”ですが、制度の壁は速度で突破できない――この現実は、買収万能論の限界も示しています。
2025年のMeta:AIは“買って”近道、“作って”深掘り
現在のMetaは、生成AIとデバイス(Ray-Ban Metaのグラスなど)を“表の顔”にしつつ、裏側では巨大な学習/推論インフラを敷設しています。ただし、AIはSNSよりも内部結合が強い分野です。モデル、データ、評価、プロダクトのループが一気通貫で回らないと、表の体験に跳ね返りません。InstagramやWhatsAppのように“既に完成した体験”を買って載せるのとは違い、AIは作る力の地力が問われます。買収はループの一部を加速しますが、全体の設計が甘いと、シナジーは立ち上がりません。ここは、ザッカーバーグがこれから越えようとしている領域です。
投資家視点の要点整理:何を見るべきか
(1)Instagramの粘度と収益密度――短尺動画の視聴時間が伸びるほど、広告の単価や配置の妙で“密度”を上げられるかが勝負です。発見(Explore)とリールの相互送客、ショッピングやクリエイター経済の連動がカギになります。
(2)WhatsAppの“行為の収益化”――広告にほとんど頼らず、企業メッセージ課金、API、決済、予約/顧客対応のB2B/B2Cフローでどれだけ積み上げられるか。新興国での決済と、先進国でのカスタマーケアDXが両輪です。
(3)規制の地図――買収は“競争の無力化”として常に疑われます。個別案件の可否だけでなく、事前規制(事前届出・分離の圧力)がどこまで強まるかを見ます。
(4)AIの統合度――LLMや生成機能が広告作成、広告配信最適化、クリエイター支援、検索/発見にどれだけ“実運用の改善”をもたらすか。ストーリーやリールの制作支援AIの質を底上げできれば、バリュープロップ(企業価値)が一段上がります。
この4点のうち、InstagramとWhatsAppは見通しの筋道が比較的描きやすく、AIと規制はボラティリティが高い。つまり、ザッカーバーグの成否は、“読める二本柱をブラッシュアップする”一方で、“読みにくい二本柱へ賭ける胆力”を維持できるかにかかっていますが、資金力でも問題がないため、次の覇権をハッキリと狙っているといえるでしょう。
おわりに
ザッカーバーグは、事業の成長曲線を途切れさせていない創業経営者として君臨し続けています。もちろん買収は魔法ではありません。規制の矢面に立ち、統合の労苦が伴い、文化的摩擦も起こります。それでも彼は、「いま必要なピースは何か」を貫いてきました。
現在、AIという未踏の荒野で、ザッカーバーグはまた同じ問いに向き合っています。“当て続ける天才”ではなく、“外しても勝ち筋を失わない経営者”。それが、2025年のいま見える、ザッカーバーグという経営者の才能といえるでしょう。
著者名/suzuki
肩書き/テックライター
経歴/企業史・起業家のストーリー、ビジネス文化の変遷を横断的に取材・執筆。教育・地域DXや情報リテラシーのテーマを発信。生成AIやテック全般の実務検証が得意。「難しいテクノロジーを生活のことばで伝える」がモットー。休日は山登りをしている。















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE













