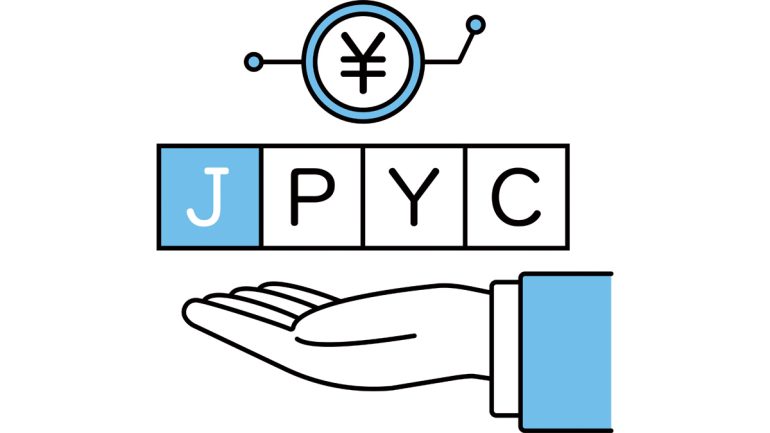
企業の請求・支払い、ECの返金、海外との小口送金は、時間・手数料・手続きの重さが常につきまといます。こうした“日々の面倒”を円のまま軽くする手段として注目されているのが、1円=1JPYCで扱える円建てステーブルコイン「JPYC」です。ブロックチェーンの即時性と自動化を取り込みつつ、日本の制度の枠内で安心して使えるのが特長で、越境ECや地域通貨のアップデートにも直結する実用性が見えてきました。本記事では、なぜ今JPYCなのかを、基本の仕組み・活用シーン・リスクと注意点・3年後の見取り図まで一気に解説します。
JPYCとは?最短でわかる“デジタル円”
JPYCは、ブロックチェーン上で発行される日本円に連動する電子決済手段(ステーブルコイン)。1JPYCは常に1円相当で、ブロックチェーンの速さ・自動化(スマートコントラクト)を活用して、送金・決済・プログラム可能な支払いを実現します。日本ではこれを法的に電子決済手段と位置づけ、発行体に厳格なルールを課すことで「常に1円に戻せる」安心感を担保しています。
なぜ今、注目?
法整備が揃った
2023年施行の改正資金決済法で、円建てステーブルコインの道筋が明確化。発行できる主体も限定され、利用者保護とAML/CFT(マネロン対策)を徹底。
発行体が登場
2025年8月、JPYC株式会社が資金移動業(関東財務局長 第00099号)に登録。これで“1円に償還できる”円建てステーブルコインの国内発行が具体化。
実需がある
法人間の決済・精算、Web3サービス内の支払い、越境ECの多通貨リスク回避など、フィーと遅延が重い既存の国際送金に代わる手段として期待が高まっています。発行後の裏付けは預金やJGB(日本国債)が中心になる見通し。
JPYCが解決する“面倒”——お金の流れがこう変わることが期待される
1)法人決済:締め日・振込の“待ち時間”を短縮
・受発注と同時に自動でエスクロー→検収→支払いまで進める“コード化された決済”が可能。
・銀行営業時間や国際送金のカットオフに縛られず、年中無休で即時性・確定性を持つ
2)越境EC:円のまま“世界と直結”
・たとえば海外のマーケットプレイスに出店した日本のD2Cブランドが、為替変動の瞬間リスクを抑えつつ、円建てでスムーズに受け取る/支払うことが可能に。
・中間コスト(多段の決済手数料・為替手数料・着金遅延)を圧縮。カゴ落ちの一因だった決済摩擦の低減が期待できます。
3)地域通貨の“アップデート”
・紙のプレミアム商品券やアプリ型のローカルマネーが抱えがちな、流通管理・不正対策・換金事務の負担をブロックチェーンで軽量化。
・予算執行やプレミアム付与を条件付きトークン(スマートコントラクト)で可視化・自動化。監査もしやすい。
・域内回遊のデータが残るため、商店会の販促・再投資設計に活用可能。(法的には発行主体・運営設計の整理が前提)
JPYCの“使いどころ”を具体化(業界別シナリオ)
製造・卸:受発注から支払いまで“ひとつのワークフロー”
・受注確定→自動で部分前払い、納品確認で残額決済。手形・約束手形的な運用のデジタル代替
・海外工場への小口多頻度送金も迅速化。為替ヘッジコストの平準化に寄与
EC・D2C:即時返金でCX改善、決済手数料の総額を圧縮
・返品受付と同時にプログラム返金。カードチャージバック対応の代替に
・アフィリエイトやマーケットプレイスのレベニューシェア配分も自動化
クリエイター・ゲーム/Web3:ロイヤリティ分配を“リアルタイム”
・複数人への同時自動分配(スプリット)で、マイクロペイメントも現実的に
・オンチェーンの透明性が新しい信用をつくる(監査・レポーティング容易)
よくある誤解Q&A
Q. JPYCは“仮想通貨(暗号資産)”ですか?
A. いいえ。円に連動し、1円に償還できる「電子決済手段(ステーブルコイン)」です。暗号資産(価格変動型トークン)とは法的な位置づけが異なります。
Q. 価格は本当に1円に固定?
A. 発行体は常に1円での償還を約束し、裏付け資産を保有します。市場板では微妙な乖離が出る場合もありますが、制度上は1円に戻す権利が利用者にあります。
Q. 旧JPYC(Prepaid)を持っているけど?
A. 2025年6月以降、新規発行は停止。既存分は前払式として引き続き決済や交換に利用できます。現金償還は原則対象外です(=新しい“規制版JPYC”とは別物)。
Q. どのチェーンで使える?
A. 初期は主要EVMチェーン(例:Ethereumなど)を想定。法人向けの使いやすさ・手数料・相互運用性を見ながら広がる見込みです(詳細は発行体の続報に依存)。
リスクと注意点(ここはシビアに)
1. 発行体リスク:規制準拠とはいえ、運営・システムのガバナンスが要。定期的な証憑開示(準備資産のレポート)をチェック。
2. チェーンリスク:手数料高騰や混雑、ブリッジの脆弱性などオンチェーン特有のリスクに留意。
3. 法改正の影響:今後の制度アップデート(例:運用可能資産の範囲調整)で裏付けや利便性が変化する可能性。
4. UXの壁:ウォレット・秘密鍵・KYCなど、最初のハードルは依然として高い。法人はカストディやAPIベースの決済基盤の導入が近道。
3年後の“お金のOS”を予測
・2025年:創世記
JPYCが国内初の“規制下の円建てステーブルコイン”としてローンチ。B2B決済・法人間精算・Web3サービスの決済レイヤから浸透。
・2026年:拡張期
主要ECプラットフォームや決済代行がJPYC対応を進め、越境ECの受払いで“円のまま世界と繋がる”体験が一般化。地方自治体・商店会の地域通貨アップデートにも採用。
・2027年:標準化
複数の円建てステーブルコイン(信託型・銀行型)が並立し、相互運用が進展。給与の一部をトークンで受け取る「ペイロールの可分化」、B2B請求管理の完全自動化が当たり前に。
インパクト:米国ではUSDCやUSDTの裏付けで米国債需要が増えたと言われます。日本でも、円建てステーブルコインの拡大はJGBの新たな需要を生む可能性があります。
さいごに(編集後記)
JPYCは、円をそのまま“ソフトウェア化”する道具です。派手な投資商品ではなく、現場の「待ち時間」と「事務の手間」を静かに減らすための仕組みだと考えてください。評価の物差しはシンプルに、安い・速い・自動の3つで十分です。
まずは小さく始めましょう。返品時の即時返金、売上の自動分配、検収と同時の支払いなど、社内で一つだけ使いどころを選んで試すのがコツです。その際は、経理・法務と連携して、仕訳の落とし方と監査ログの残し方だけ先に決めておけば安心です。
注意点は3つだけ覚えておいてください。
1. 権限管理とバックアップをきちんとすること。
2. 障害が起きたときの手順を紙1枚で用意しておくこと。
3. 発行体の準備資産やレポートの公開状況をときどき確認すること。
JPYCは、越境ECでも地域の取り組みでも、円のまま「早く・安く・自動」で回すための実用品です。今日の小さな実験が、3年後には“当たり前の使い方”になっているはず。まずは一歩、身近なユースケースから始めてみてください。
参考(主要ソース)
• JPYC株式会社「【国内初】日本円建ステーブルコイン発行へ-資金移動業者の登録を取得」2025/8/18(登録番号:関東財務局長 第00099号)。JPYC株式会社
• Reuters「Japan startup to issue first yen-pegged stablecoin」2025/8/19(裏付け資産・ローンチ方針等)。Reuters
• 金融庁「Regulatory Framework for Crypto-assets and Stablecoins/Weekly Review」— 安定的な払戻し・発行主体(銀行/資金移動業者/信託)など制度の骨格。金融庁+1
• JPYC Prepaidの取り扱い変更(新規発行終了・継続利用の範囲)。プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMESJPYC
• Progmatや他社事例(相互運用・実証)。ledgerinsights.com
• 海外の円建て(GYEN)などとの位置づけ。stellar.org
著者名/ 鈴木林太郎 経済ライター
テックと経済の“交差点”を主戦場に、フィンテック、Web3、決済、越境EC、地域通貨などの実務に効くテーマをやさしく解説。企業・自治体の取材とデータ検証を重ね、現場の課題を言語化する記事づくりが得意。難解な制度や技術を、比喩と事例で“今日使える知識”に翻訳します。















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE















