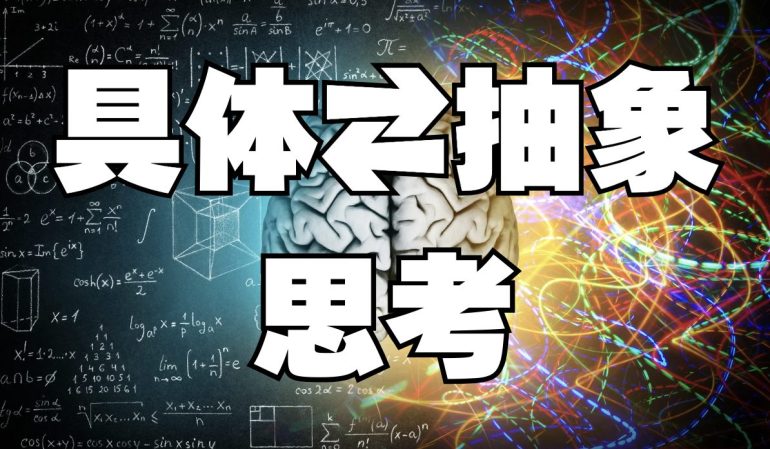
頭の良い人は頭の中にピラミッドがあり、階層ごとに情報が格納されていると言うのがキーメッセージ代表取締役で、元デトロイトコンサルタントの権藤悠さん。逆に仕事がデキない人は頭の中が平面で情報があちこちに散らばっている状態らしい。
今回は権藤さんの最新刊「頭のいい人になる 具体⇄抽象ドリル」(SBクリエイティブ刊、定価1900円+税)で紹介された、頭のいい人になるための思考訓練のドリルを紹介しながら、できる人の思考を身に着ける手法について解説していく。
「ちゃんと考えてる?」と言われ続けた日々
権藤さんは社会人になってから上司に「ちゃんと考えてる?」と言われ続け、役員面談が行われた。そこで役員から「年齢とか役職とか関係なく、周りの人ができていることを観察して、冷静にアドバイスをもらって勉強してごらん。それをやり続けたら成長するよ」と忠告されたのである。
そこで権藤さんはプライドを捨てて、周りの優秀な人を観察して、優秀な人にアタックして質問し続け、たくさんのメモを取ったが、その内容が記憶に定着しない。相手からも「そのメモって、量が多いから読み返せないよね?結局忘れちゃうんじゃない?」と言われる始末だった。
権藤さんは優秀な人が情報をどう頭の中で整理し、記憶しているのかを探ったところ、成果を出している人はみんな具体・抽象力があるということだった。具体・抽象力とは頭の中でピラミッドがイメージできることで、そのピラミッドには引き出しの様な階層がいくつもある。どの情報をどの階層に収納するかを考えながら、頭の中を整理整頓していた。
オフィスのデスクと同じで、資料をただ置いておくだけだと、後でどこにあるかがわからなくなる。分類してファイルや引き出しに整理して保管すれば、すぐに必要な物が取り出せるようになる。この点に気づいた権藤さんも、頭の中にピラミッドをイメージしながら仕事をするようになった結果、社内でも1%しか取れないS評価をもらうほど、成長したのである。
具体⇄抽象がうまくいけばどんな相手も動かすことができる
権藤さんは具体・抽象思考の「・」を「⇄」の矢印に変えて、どちらからも自由に行き来できる点を表現している。「解決したい状況や、伝える相手に応じて、何が大切なのかを見極めて具体と抽象を行き来しながらピントを合わせていく」と言う。
例えば部屋を散らかしっぱなしの子供に母親が「部屋を片付けなさい」と怒るシーンを思い浮かべて欲しい。何度言っても、子供はもう片付けたと言う。そこで母親は「人形は上から二段目の引き出しに入れて、ブロックは三段目の引き出しに入れてごらん」と指示すれば、子どもはきちんと片付けることができるのである。
「部屋を片付ける」という言葉は抽象的である。さらに、子供自身は部屋が片付いているという認識をもっている。でも、母親の目から見れば、床には人形やブロックが落ちていて、片付いている状態ではない。ここでは子どもと親の認識がズレているのである。
このズレを解消し、相手との解像度を揃えながらコミュニケーションをとることができるようになる人こそ、頭のいい人だと言うのが権藤さんの主張である。
あいまいなビジネスの世界を生き抜く思考法
権藤さんは新刊書でこう述べている。「今はAIの発展や、変化の多い世界情勢などによって、未来が見えにくい時代です。ひと昔前であれば、『この流れだったらこんな風にしたらいいよね』というように、正解が見えやすかったのに対し、現在は何が課題か、正解か分からない中、自分で課題を見つけ出し解決していかなくてはなりません。
ところが私たちは学校で、そんなことは習っていません。最近の子供たちは探究学習などを通じて、思考力を磨く機会があるようですが、私の時代はそんな授業はありませんでした。
私たち世代の学校教育で受けてきたのは、1+1=2という世界です。問題を与えられ、そこには必ず一つの答えがあり、それを導き出すという訓練です。これは確かに論理的思考力を鍛えるという意味では有効ですけれども、私自身は論理的思考力だけでは、ビジネスシーンで壁にぶち当たってしまいました。
ビジネスの現場では数字や論理では解決できないあいまいさを、おおいにはらんでいたからです。ここに論理的思考力を絶対視することの落とし穴があると、感じています」と権藤さんは新刊書で具体⇄抽象の必要性について解説している。
ビジネスに必要な具体化思考とは何か
では具体化思考と抽象化思考とは何かを、もう少し詳しく解説してもらおう。権藤さんによると、抽象的な言葉や事柄の構成要素を分解することが、具体化思考であると言う。「頭のいい人は曖昧な状態を放置しません。ふんわりした言葉や、わかるようでわからない概念などを、自分なりに具体化します。そうやって解像度を上げない限り、適切に対応できないことを知っているからです」と教えてくれた。
新刊書では具体化思考を鍛えるために、1)分解思考、2)相違思考、3)分析思考、4)推定思考の4つに分けて、それぞれの思考力を鍛えていくことで、具体化思考が身に付くと語っている。
1) 分解思考
分析思考とは言葉や物事を細かく分けて行く思考法。ざっくりとした抽象的なものごとを細かく分けていく感覚を身につけよう。例えばビジネスシーンにおいては抽象的な課題に頻繁に出くわすことがある。「環境に優しい新製品の企画書を出して」と言われたら、優しいとは何か分解することで、解決の糸口になる。再生可能な素材を使うのか、設計が長持ちするなど、いろいろなアプローチに分解することができる。
2) 相違思考
相違思考とは違いを探す思考法である。単体だと特徴が見えにくいものを、あえて他のものと比べて違いを見つけることで、特徴を浮き彫りにすることができる。自分の強みを見つけられたり、自社の製品の良さがわかって、差別化が可能になる。この相違思考ができないと行動や表現がありきたりになってしまうので、抜きん出ることが難しくなる。
3) 分析思考
分析思考は分解思考と相違思考の両方を使って、物事の構成要素や関係性特性を明快に理解する思考法のことである。例えば営業成績がふるわない時、課題を分解したり、優秀な人との比較によりどうしてどうすれば成績を伸ばせるのか、という道筋を描くようなイメージである。分析思考は課題解決のためのスキルであり、これが身に付いてないと壁に当たった時に、どうしたらいいかわからず、挫折しやすくなる。
4) 推定思考
不確実な問いに、仮説を立てて答えを導くのが、推定思考である。推定思考は抽象的な問いや材料の少ない問題に対して、自分なりの推察仮説をもとに、具体的な状況を明示して課題を解決する思考法である。外資系のコンサルティングファーム企業や金融会社、ITや総合商社などの採用試験で問われることが多い思考法のひとつで、フェルミ推定とも呼ばれている。
見えないものが見えるようになる抽象化思考
一方、抽象化思考とは何かについても、押さえておく必要がある。抽象化思考も具体化思考と同じように4つに分類される。
1) 共通点思考
隠れた共通点を見つけるのが共通点思考である。ものとものの間に隠れている共通点を抽出する考え方で、具体化思考で紹介した分析思考の真逆となる頭の使い方である。
2) 分類思考
分類思考は、グループにして整理整頓する思考法である。これが身につくと、理解力が上がる。「これとこれは同じように分類できる」と頭の中を整理することができるので、仕事のスピードが上がる。逆に分類思考ができていないと、頭の中はすべて箇条書きになっていて、ミスが発生しやすくなってしまう。
3) 要点思考
具体的な情報を基に、物事の芯となる部分を抽出する思考法が、要点思考である。「つまり〇〇だ」ができるようになると、コミュニケーション力が上がる。例えばプレゼンテーションなどで、結論を先に言えば、聞き手にはその後の説明が頭に入りやすくなる。人から説明が分かりにくいと言われる人は、伝え方の勉強する前に、自分の中で「つまり〇〇だ」を抽出する要点思考を磨くことが欠かせない。
4) 法則思考
成功する法則を導き出すことができるのが、法則思考である。例えば営業成績が悪い人が良い人の真似をしようと思った時、法則思考がないと「ナンバーワンの人の服装や髪型を真似しよう」という発想になってしまう。外見の真似だけで、表層的で役に立たない。一方、法則思考を使えば、「うまくいっているトップ5人の人の共通点を探そう」など、成功のための法則を見出して、優秀な人たちの行動や考え方など肝になる部分を見つけることができる。この法則思考は応用が効くので、ビジネスパーソンにとって重要な思考の一つである。
こうした抽象化志向ができる人には、鋭い洞察力がある。雑多に散らばった情報や、一見無関係に見える事柄同士からも共通点を見つけ、物事の本質を見抜くことができる。さらに細部の違いに目を奪われることなく、共通する要素を見極めることが可能になる。つまり世の中の多くの人が見えないものが見えるようになり、多くの人が見落としていることに気づくということにつながる。
権藤さんは新刊書で「具体⇄抽象力」を鍛える思考力クイズを、ドリル形式で62問掲載している。日常生活や仕事の場で具体的に実践し、使いこなすことができるようにするための思考力トレーニングで、解き進めると思考力が身に着いていく。単に思考力が鍛えられるだけでなく、仕事上の気づきも与えてくれるトレーニングで、例えばメタ思考で考える「自分の仕事が評価されない時」の解説は、参考になる。
キーメッセージ 代表取締役社長/ベンチャー三田会幹事
権藤 悠(ごんどう ゆたか)さん
1989年生まれ、広島県出身。慶應義塾大学理工学部情報工学科卒業後、ITベンチャー企業にて人事、オープンデータSaaS事業開発、エンジニア業務に従事。株式会社ZUUに人事企画マネージャーとして参画し、東証マザーズ(現・東証グロース)市場上場前の採用・組織開発に従事。その後、デロイトトーマツコンサルティング合同会社に経営コンサルタントとして入社。大手企業へのDX・組織人事高度化コンサルティング業務に従事し、合計社員数20万人以上の各業界企業を支援。世界最大規模のDXプロジェクト実行実績からデロイト トーマツ コンサルティングの中でも上位1%の人材しか認定されない、”Deloitte Global Talent Standard”にて高度コンサルティング人材としてS評価認定を受ける。
2022年、株式会社キーメッセージを創業。大手企業からスタートアップへ経営コンサルティング、AIやデータ分析を活用したデジタルHR(人事新規事業開発や組織人事DX支援)サービスやM&Aサービスを提供する。サービス提供を通じてGDP1%向上に貢献することを目指す。
2024年2月出版『「解像度が高い人」がすべてを手に入れる 「仕事ができる人」になる思考力クイズ51問』(SBクリエイティブ)、2025年5月出版『頭のいい人になる 具体⇄抽象ドリル』(SBクリエイティブ)。
文/柿川鮎子















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE

















