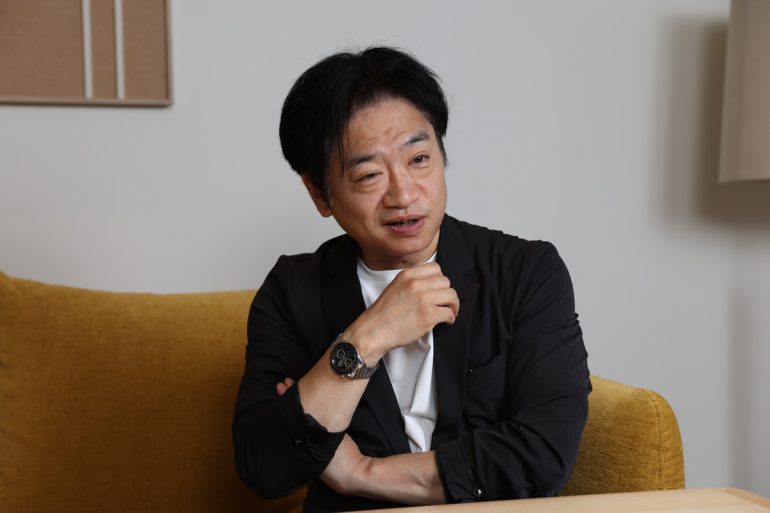2005年の創業の医療グループ・桜十字が業績を伸ばしている。初年度の売上げは約38億円だったが、創業14年目の2019年には約10倍の338億円までに成長。コロナ禍以降、経営にウェルビーイングの思想を導入してから、売り上げをさらに伸ばし、2024年には20倍の約808億円をマーク。桜十字グループの那須一欽さんは、「働く人、施設を利用してくださる方の心や環境をいい状態に保つと、『ハッピースパイラル』ができ、グループはもちろん地域全体が成長していくのです」という。そのウェルビーイング経営の背景を伺った。
桜十字グループCMO(Chief Marketing Officer:最高マーケティング責任者)
那須一欽さん
青山学院大学卒業後、ソニーマーケティングに入社。その後、ソニーに転籍し商品企画に携わる。2011年に桜十字病院経営企画室に入社、桜十字病院経営企画部長を経て、2022年、生活と医療の融合を目指した医・食・住のヘルスケアテーマパーク『メディメッセ桜十字』を手掛け、現職に至る。https://medimesse-kumamoto.jp/
桜十字グループ
熊本県を拠点に展開する医療グループ。桜十字病院を中心に医療、介護、予防医療など、幅広くヘルスケア事業を全国に展開する。
https://www.sakurajyuji.jp/
目指すのは「三方よし」の「ハッピースパイラル」
――那須さんは新卒で世界展開する企業・ソニーに入社しました。そして、36歳の時に熊本を拠点とする桜十字グループに転職。当時、創業6年、売上高は約107億円でした。大企業から一つの病院に転職するという決断をします。
那須一欽さん(以下・那須):私は小学生の頃から「ソニーでスピーカーを作りたい」という夢がありました。2009年に商品企画部に配属され、ある意味で夢が叶ったことに気づいたのです。年齢を考えると、次の挑戦をするなら今がラストチャンスだと思う気持ちが強くなっていったのです。
入社約15年で業界も大きく変わりました。海外メーカーの追随もあり、製品の差別化が難しくなっていました。どの会社が作っても似たような機能や性能でコモディティ化が進み、選ぶ人にとっては、「どれを買っても同じだ」となり、価格競争が激化する一方でした。
そんなとき、早期退職制度もありソニーを辞めることにしたのですが、その直後に東日本大震災が起こり、価値観も大きく変わりました。
それまで、私の人生の中心は会社でした。家族との時間をあまり持てなかったので、退職後は妻と子供と世界を旅したのです。そこで見たのは、安全や生活インフラ、医療など日本では当たり前の環境がない場所で、懸命に生きる人々です。そこで私は「社会に役立つことをしたい」と強く思うようになったのです。
――当時、ヘルスケア業界は、少子高齢化もあり成長産業でした。桜十字グループに入職し、予想と戦略が立てやすい「モノと数字」から、不確定要素が多い「人と心」を扱うキャリアが始まります。
那須:桜十字グループの経営層から、ソニーで培ったマーケティングの知見に可能性を感じていただき、縁をいただきました。経営企画として入職しましたが、入職者研修では現場に入りました。最初に配属されたのは介護現場で、そこで高齢の患者さまの介助もしました。そのとき、忘れられないのはおむつ交換です。臭いが脳裏に焼き付き、それは今でも思い出せるほどの衝撃でした。
ベテランの職員がついてくださったのですが、平然としている。体が動かない方にとって、排泄のたびにおむつの交換をされなければ健康を維持できない。介護は命に深く関わる尊い仕事なのだと、心に響くものがありました。
それなのに、介護職の方々の社会的地位や待遇は低い。私は経営に参画する者として、介護現場で働く人とって、職場も社会もいい環境になるように。そして、医療・介護業界を良くしていくことへの強い使命感を持ったのです。
――那須さんは、医療業界にマーケットイン(顧客のニーズや市場の動向を読み製品やサービスを展開すること)の発想を持ち込み、サービスを大きく変えました。それは、2014年以降、桜十字グループが業績を伸ばし続けることに貢献します。
那須:医療業界は、厚生労働省の方針に則り、決められた保険診療を提供する「プロダクトアウト」的アプローチが常識でした。それには法規制が多いことが背景にありますが、保険診療が中心では高収益が見込めません。加えて、患者さんが求めていたり、医療側が提供したいと思うサービスが保険外の場合、応えられていないという現状もあります。
桜十字グループの経営層は、元コンサルタントや銀行員、シンクタンク出身者など、収益化を徹底的に分析し、実際に行動することができる合理的な方が多い。
マーケットインの思想の広がりも決断も早いので、結果が出たのだと感じています。
それと同時に、10年後の医療サービスについて考えるようになりました。そして行き着いたのは、ウェルビーイングの思想です。そこに軸足を置き、事業計画を考えていきました。
――2025年の今は、那須さんが予想した約10年後の未来ですが、その予想は当たっています。桜十字グループはいち早くリハビリに注力しました。多くの人の「自分で動きたい」という思いを叶える医療を提供しています。
那須:脳梗塞ほか脳の疾患は麻痺が残ります。また、がんなど入院が長期間になり、体力も筋力も奪われるような病気が治ったら、その先の人生が始まるのです。どの患者さんも「元通りの自立した生活に近づけたい」と望んでいました。そこで、リハビリテーション機能を強化したのです。
理学療法士 (立つ、座るなど基本動作の回復をサポート)、作業療法士 (着替え、食事など日常動作の回復をサポート)、言語聴覚士 (コミュニケーションや飲み込みの回復をサポート)ほか、セラピストや歯科衛生士の採用にも力を入れ、数年で九州地方トップクラスのリハビリ体制を整えました。
これには、現場のスタッフの協力がありました。医師や看護師はとても柔軟な発想で、経営層の提案を受け入れてくれた。病棟の師長さんほか、現場のキーマンが並走したので、いい協働体制が確立できました。
加えて、“病院”という施設のリソースを見直し、収益が見込めるよう病床運営の改革を行いました。それまでは慢性期病棟が中心でしたが、亜急性期、回復期、慢性期を含め8つのステージに分類。それぞれに専門のスタッフを配置し、大規模多機能な病院へと変えていったのです。
運営面では、病院や施設でのイベントを増やしました。患者さんや利用者さんも参加する運動会や発表会、季節の行事などイベントを月1回以上行うのです。これは、患者さんの入院生活での楽しみだけでなく、日常の利害関係を超えた部署間の人間関係を構築し、その後の連携促進に寄与したり、地域とのつながりを深めるなど、日常の運営では得難いつながりや様々な効果をもたらします。
――イベントはWHO(世界保健機関)の健康の定義(1948年)である「健康とは、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあること」にある“包括的なウェルビーイング”にもつながっています。
那須:主業務と異なり非日常となるイベントは、いわば“祭り”のように人と人をつなげます。人との交流を個人で始めるのは難しい時代なので、施設が進んで提案することの大切さを感じます。医療や介護施設というコミュニティから、地域社会全体の緩やかなつながりを広げていけば、本人、家族はもちろん、社会全体に良い循環を生むものと感じています。
私たちが目指すのは、患者、地域、職員の三者がハッピーになることで、会社も健全になるという「三方よし」の「ハッピースパイラル」です。この言葉が、2014年に始まり、今や広く評価を得ている「口から食べるプロジェクト」へと繋がっていきます。
――後編では、このプロジェクトについても詳述していきます。「常に念頭にあるのは、時代に合わせたウェルビーイングです」という那須さんに、これからの時代に求められる幸福のあり方について伺います。
構成/前川亜紀 撮影/杉原賢紀(小学館)















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE