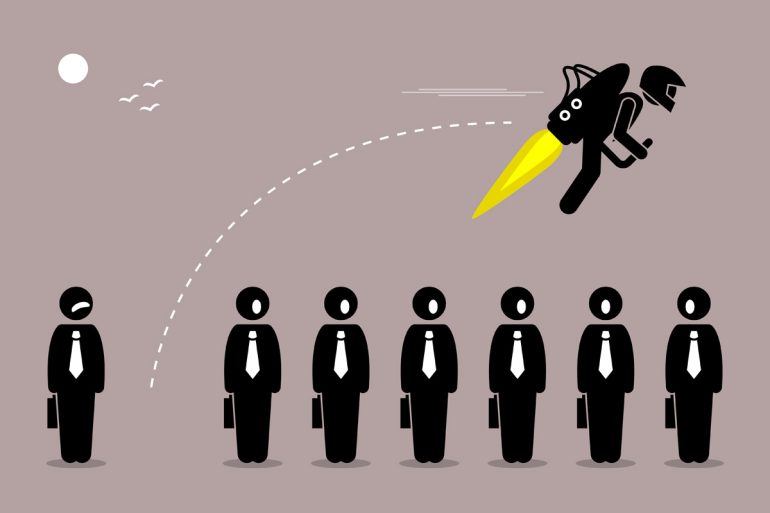
なぜ今「リープフロッグ現象」に注目するのか
固定電話を飛ばし一気に携帯へ、現金を飛ばしてQR決済へ――。後発国やスタートアップが段差飛ばしで先行勢を追い抜く現象を、経済学はリープフロッグと呼びます。近年は生成AIや再生エネルギーでも「抵抗が小さい地域ほど先に導入が進む」という逆説が鮮明になりました。
そこで今回は、(1)海外の跳躍事例、(2)日本企業・自治体の挑戦、(3)跳躍を駆動する三つのドライバー、(4)次に跳ぶテクノロジー潮流を解説し、「レガシーを負債でなく跳躍台に変える具体例」を解説していきます。
1:海外で進む巨大な跳躍

【インド──政府製フィンテック UPI が描く官民エコシステム】
インド政府と中央銀行(RBI)が主導する即時決済インフラシステム UPI(Unified Payments Interface) は、API を無償開放し、決済手数料をほぼゼロに抑えた大胆な制度設計で 2016 年に稼働しました。2025 年 5 月の取引統計では、月間件数が 186 億 7,746 万件、取引額が 25 兆 1,429 億ルピー(約 4.6 兆円)に達し、参加銀行は 673 行に上ります。決済データは零細商店の与信スコアリングや医療保険の料率算定にも使われ、政府の「DPI(Digital Public Infrastructure:デジタル公共インフラ)」戦略は世界の政策担当者を驚かせています。
【インド・レバノン──Starlink が通信空白を一気に埋める】
SpaceX のStarlink は 2025 年 6 月にインドで GMPCS ライセンス(人工衛星の電波を使って、国内で公式に“衛星インターネット・衛星電話”を売るための営業許可)を取得し、農村部7億人を潜在市場に見据えています。月額 15 ドル前後で 25Mbps を超えるブロードバンドを提供できるため、遠隔教育やテレメディシンの導入障壁が一挙に解消される見通しです。レバノンでも経済危機で崩壊した通信網の代替として政府が導入を検討中で、紛争・災害地域向けの通信インフラとして注目されています。
【中国──モバイル決済を飛び越えデジタル人民元へ】
QR 決済でキャッシュレス化を先行させた中国は、次なる跳躍として e-CNY(デジタル人民元) を国家規模で試行中です。2025 年 6 月時点でデジタルウォレットは 2 億 6,000 万件、累計取引額は 7 兆元(約 96 兆円)に到達しました。特徴的なのは「オフライン IC カード」とスマホを併用し、地下鉄や山岳地でも“デジタル現金”を利用できる点です。商業銀行のシステムを経由しない直接決済は、手数料を大幅に引き下げ、災害時のバックアップ通貨としても期待されています。
【ケニア──M-Pesa が築いた「銀行口座不要」の経済圏】
2007 年に Safaricom がリリースしたモバイルマネー M-Pesa は、フィーチャーフォンの SMS を介して送金・貯蓄・マイクロローンまで完結させました。2025 年度の Safaricom 決算によれば、M-Pesa は売上高 KSh 1611 億(約 1,200 億円)を計上し、30 日アクティブ利用者は 3,600 万人を突破しています。取引総額は年間 20 兆ケニアシリングを超え、ケニア GDP の約半分をデジタルで流通させる存在になりました。農村部の家計を対象にした調査では、M-Pesa 導入村の極度貧困率が 2 ポイント低下したとの結果も報告されています。
【ルワンダ・ガーナ──Zipline が創る“空飛ぶ物流”インフラ】
医療用ドローン専門企業 Zipline は、アフリカを中心に自律飛行距離 8,000 万マイル、累計 130 万回超の医薬品配送を実現しました。平均 30 分で血液やワクチンを届ける体制は、農村病院の在庫を 67%削減し、遠隔地の救命率向上にも直結しています。政府は道路網整備よりコスト効率が高いと判断し、2025 年から国策として物流網に組み込む方針を表明しました。
2:国内で進む“段差スキップ”のうねり

【民間セクターの跳躍】
日本でもレガシーに縛られないプレーヤーが次々と段差を飛び越えています。
- PayPay は 2018 年のサービス開始から5年で決済回数 74.6 億回、連結取扱高 12.5 兆円に到達し、キャッシュレス決済全体の約5回に1回を占めるまでに成長しました。加盟店手数料ゼロと 20%還元キャンペーンで臨界質量を獲得し、現金依存度の高かった小規模店舗を一気に取り込む戦略が奏功しました。
- 楽天モバイル は基地局設備をソフトウェア化する Open RAN を全国規模で展開した世界初の通信事業者です。MWC 2025 で発表した AI 制御による省エネ技術は、従来網比で最大 20%の電力削減を見込み、更新投資を一気に圧縮する事例として国際的に評価されています。
【地方自治体が跳躍台になる四つの挑戦】
人口減少で財政制約が強まる地方自治体こそ、レガシー設備から「一足飛び」に踏み切りやすい立場にあります。
- 石川県加賀市 は市街地全域を高精度 3D マップ化し、AI 管制のドローンプラットフォームを構築。医薬品や模擬血液の配送実証を経て、2025 年 6 月には国と共同で「近未来技術実証ワンストップセンター」を開設し、規制相談や飛行ルート許可を一括支援する体制を整えました。
- 福島県会津若松市 は環境省の脱炭素先行地域に選定され、自営線マイクログリッドとデジタル地域通貨〈会津コイン〉を組み合わせました。AI が再エネ発電量と需要を予測し、蓄電池を自動制御することで 2030 年までに3エリアで再エネ 100%を達成するロードマップを公表しています。
- 石川県小松市 ではセイノーホールディングスとエアロネクストが連携し、ドローンと軽バンを組み合わせた買い物代行サービス「SkyHub®」を運営。配送料 300 円で生鮮品を自宅まで届け、高齢化率 50%超の集落でも採算が取れるモデルを実証しました。
- 兵庫県淡路島 では農業ベンチャー〈農社〉が Starlink を常設し、スマートビレッジで AI 潅水や施肥を自動化。農作業時間を 30%削減し、災害時には臨時通信拠点となる二重のレジリエンスを実現しました。 これらの地域に共通するのは「既存インフラを守るより、次世代インフラを新築したほうが安い」という冷静なコスト計算です。人口減少という“逆境”がむしろ決断を後押ししています。
3:リープフロッグを駆動する三つのドライバー
第一にコスト逆転があります。リチウムイオン電池は 10 年で 80%近く値下がりし、太陽光+蓄電がディーゼル発電より安価になる地域が広がりました。コンゴ民主共和国の Nuru が示したように、安価な再エネが治安リスクを跳ね返す例も出ています。
第二は規制ホワイトスペースです。UPI が API を完全無料で公開し、手数料をゼロに近づけられたのは、旧来のカードネットワークが強固に根付いていなかったからです。規制が空白だからこそ、政府が“官製フィンテック”を一気に立ち上げられました。
第三はネットワーク効果とモバイル普及です。PayPay や M-Pesa が短期間で臨界質量を超えられた背景には、スマホ普及率の急上昇とポイント還元による強烈なインセンティブ設計があります。一度「みんなが使っている」状態になれば、後発参入者は切り替えコストの壁に直面します。
4:次に跳ぶのはどこか──3つの新潮流を徹底解剖

【生成AIの“APIネイティブ”導入】
2024年以降、クラウド経由で利用できる生成AIのコストは劇的に下落しました。
たとえば OpenAI が 2024 年7 月に投入した GPT-4o mini は、入力トークン100万件あたり0.15 ドル、出力トークン同60 セント――為替 rate 155 円/ドル換算でも 1 トークンあたり約0.00002~0.00009 円 という水準で、従来「1トークン=0.003 円」と言われた相場を一気に更新しています。
こうした低価格を背景に、南アフリカの大手リテール銀行 カピテック銀行 は Microsoft 365 Copilot と Azure OpenAI Service を 約1万6,000人の社員に展開。メールやレポートを「AI が下書きを生成 → 人がチェック → 送信」という新しいフローに置き換えた結果、社員の8割が「週1時間以上の業務時間を削減できた」と報告しています。
ポイントは 「GPU を自前で抱えない」ことです。Azure OpenAI Service は前払い不要の従量課金モデルで、サイト上にも “no upfront financial commitment” と明記されています。高額なハード投資が不要なため、資本支出に制約のある金融機関でも導入しやすく、実際に シンガポールの UOB 銀行やフィリピンの Security Bank など東南アジア勢も Microsoft 365 Copilot の早期導入プログラムに参加しています。
生成AIを「呼び出すだけ」で使える環境が整ったことで、今後は GPU の確保ではなく 業務プロセスをいかに再設計するか が競争軸となり、アフリカや東南アジアの銀行が先行するのは必然と言えるでしょう。
【分散型エネルギー+蓄電池の標準化】
リチウムイオン電池のパック価格は2024年に115ドル/kWhまで下がり、大口調達では実質100ドル割れも報告されています。LFP(リン酸鉄)セルは平均60ドル/kWhに迫り、再エネ比率100%を目指す島嶼部や山間部で「ディーゼル発電より安い」現象が一般化しました。
日本でも鹿児島・徳之島、長崎・五島列島などがメガソーラー+蓄電ミニグリッドを選択し、「系統を延ばすより安い」を証明しつつあります。蓄電池が“太陽光の定価”を決める新インフラになる日は近いでしょう。
【衛星ブロードバンド×IoTの直結化】
2025年前半、Starlink は農業・災害向け小型端末 Starlink Mini を発表しました。幅20cm弱のアンテナを圃場に置くだけで110Mbpsの上り下りが安定し、センシングデータをクラウドへ即送信できます。
さらに国内では今年4月に開始した「スマホ直接接続サービス」では、衛星テキスト通信を無料開放する計画が公表されました。山岳地や離島の“圏外”が消えることで、ドローン管制・災害時バックアップ通信・スマート農業の3領域が同時にジャンプします。
5:おわりに──「未来のベータ版」が世界を動かす
リープフロッグ現象は、遅れを取り戻すための苦肉の策ではありません。むしろ、レガシーを背負わない側が未来のベータ版をいち早く実装し、既存インフラに縛られる側が後を追うという力学が働いています。生成 AI、宇宙インフラ、分散型エネルギー──跳躍の余地はまだ無数にあり、日本国内でも地方自治体が実証の先頭に立つ事例が続々と現れています。
「成功体験」をいったん脇へ置き、“先に行って戻ってくる” 視点を持てるかどうか。レガシーを負債ではなく跳躍台へ変える意思決定こそが、次の 10 年の競争地図を塗り替える鍵となるでしょう。
「Legacy is a tax; Leapfrog is a discount.」
今、差し出された“割引価格の未来”を選ぶかどうかは、私たち自身にかかっているのです。
【参考文献】
reuters.com
openai.com
microsoft.com
azure.microsoft.com
fintechnews.sg
文/鈴木林太郎















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE













