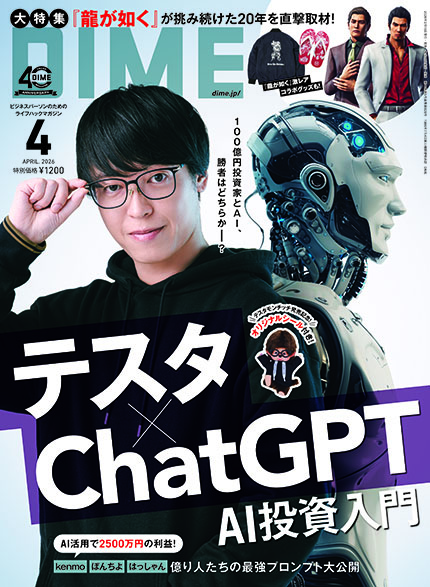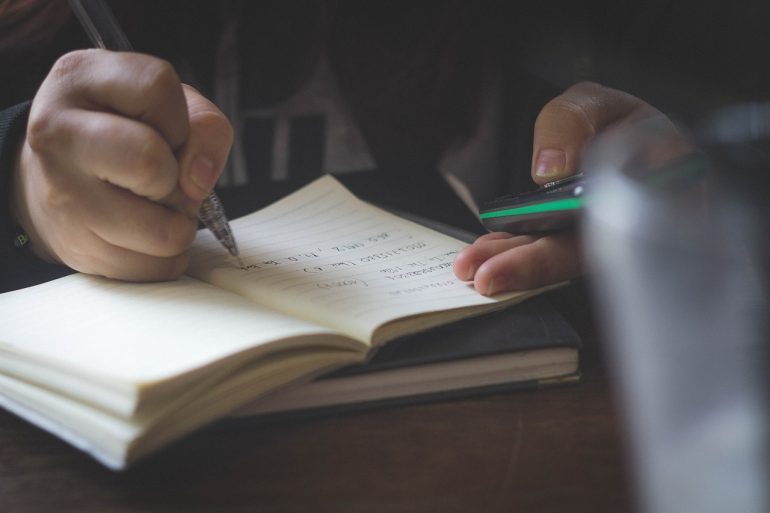
今回は、「丁々発止」という言葉の意味や語源、ビジネスでの使い方をわかりやすく解説する。
目次
会議で「丁々発止の議論を期待する」と上司に言われて、思わず戸惑ってしまった経験はないだろうか。「激しい議論のことかな…?」と雰囲気では理解できても、正確な意味や由来を説明できる人は意外に少ない。今回は、この「丁々発止」という言葉の意味や語源、ビジネスでの使い方をわかりやすく解説する。社会人として知っておいて損はない表現だ。
丁々発止(ちょうちょうはっし)とは

まずは丁々発止の意味や語源から理解していこう。
■丁々発止の意味
丁々発止とは、互いに負けじと熱く議論を戦わせる様子を意味する四字熟語である。また、副詞的に用いられ、「丁々発止と議論を交わす」などの形で使われる。
■丁々発止の由来・語源
もともと刀と刀が激しくぶつかり合う場面で生まれた表現である。『丁々(ちょうちょう)』は物を続けて打ち合わせる音、『発止(はっし)』は堅い物同士がぶつかる音を表す擬音語であり、この音を当て字で四字熟語にしたのが「丁々発止」なのだ。
つまり金属音高く刀が斬り結ぶ激しい戦いの様子を表現したのが始まりであり、その迫力ある様子が転じて、現在では議論の激しさを形容する意味で使われているのである。なお、「丁々発矢」や「打々発止」といった表記揺れもあり、いずれも読みは「ちょうちょうはっし」で意味は同じだ。
■丁々発止の類語・関連用語
侃々諤々(かんかんがくがく):遠慮せず盛んに議論すること。正しいと思うことを堂々と主張し合う様子。
喧々囂々(けんけんごうごう):多くの人が口々に勝手な主張をして騒がしくやかましい様子。(侃々諤々とは異なり、意見がまとまらない状態を指す)
談論風発(だんろんふうはつ):活発に談話や議論を行うこと。勢いよく意見が飛び交うさま。
議論百出(ぎろんひゃくしゅつ):多くの意見が次々と出て、活発に議論すること。
ビジネスシーンにおける丁々発止

丁々発止は、成果を左右する重要局面でこそ真価を発揮する表現だ。たとえば新規事業のロードマップを決める経営会議、利害が鋭く対立する価格交渉、あるいは企業買収のデューデリジェンスなど、論点が複雑で一歩も譲れない場面で用いられる。逆に、和気あいあいとした雑談や単なる説教調の口論にはふさわしくない。ビジネスでの典型例を挙げる。
- 予算会議で営業部と経理部が 丁々発止 の議論を繰り広げ、最終的に双方が譲歩案を引き出した。
- 上司が取引先と 丁々発止 の価格交渉を行い、条件面の譲歩を勝ち取った。
- プロダクト開発チームと法務部が 丁々発止 でリスクと開発スピードをすり合わせ、最適なリリーススケジュールを決定した。
- IT企業でエンジニアと営業が丁々発止 に機能要件を詰め、顧客満足度を最大化する仕様を策定した。
丁々発止の議論は、単に声高に意見をぶつけ合う行為ではない。
- 論点を事実とロジックで裏付ける
- 相手の立場を尊重しつつ迅速に応酬する
- 議論のゴールを明確にする
この三原則を守ってこそ価値が生まれる。白熱しすぎて収拾がつかなくなったり、感情論にすり替わったりすると、決定が遅れ生産性が落ちる。ファシリテーターを置いて論点を可視化し、途中で小休止を挟むなど、議論の温度管理も欠かせない。
オンライン会議では音声遅延や画面共有のタイムラグが誤解を招きやすい。丁々発止を健全に機能させるには、チャットで要点を整理しながら発言を重ねる、発言ルールを事前に合意するなどの工夫が重要だ。互いに敬意を払い切磋琢磨し合う姿勢、それこそが「丁々発止」を成果に結びつける鍵となる。
まとめ
言葉で遠慮なく斬り結ぶ、そんな「丁々発止」の議論から新しい価値が生まれることもある。議論を恐れていては斬新な発想は生まれない。互いに言葉の剣を交えて切磋琢磨する丁々発止の精神を大切にしたいものだ。
文/諏訪 光(すわ ひかる)
大手ネット系企業にて10数年に渡りプログラマーからプロダクトマネージャーまでを幅広く経験。新規事業から企業再生に至るまで様々な案件の開発に携わる。DX推進者や起業経験を経て現在は大手信託銀行でDX推進を行いながら、フリーランスの新規事業、DX、デジタルマーケティングのコンサルティングも行う。















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE