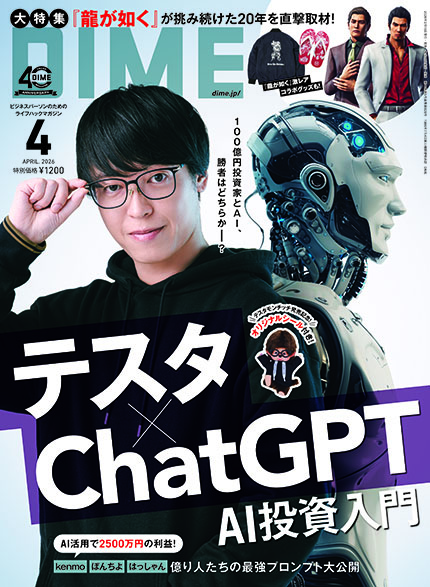本記事では、サバティカル休暇に焦点を当て、その基本知識から導入するメリット・デメリット、導入事例までを紹介していく。
目次
近年、「サバティカル休暇」という制度が、働き方改革などの観点から注目を集めている。これは企業が長期勤続者に与える数ヶ月から数年におよぶ長期休暇のことだ。欧米では古くから導入されているもので、日本でも徐々に導入例が増えつつある。たとえばLINEヤフーやソニーなどが有名だ。本記事では、サバティカル休暇に焦点を当て、その基本知識から導入するメリット・デメリット、導入事例までを紹介していく。
サバティカル休暇とは
■サバティカル休暇の意味
まず、サバティカル休暇の基本的な意味や関連事項について解説していく。
サバティカル休暇とは、企業が一定の勤続年数に達した従業員に対して与える長期休暇のことだ。有給休暇のように法律で定められた制度ではなく、各企業が任意で導入する制度である。休暇期間は、企業によってさまざまであるが、1ヵ月以上にわたるのが一般的で、1年や2年といった長期間におよぶケースもある。
一般的に、取得理由については問われないことが多く、大学院進学や留学、長期旅行、ボランティア活動、資格取得、趣味、育児、介護など、さまざまな目的に利用されている。休暇期間中における給与の支給有無やその金額についても企業によってさまざまである。無給のケースが多いが、基本給の一部を支給するケースや、数十万円程度の支援金を支給するケースもある。
このサバティカル休暇、もともとは19世紀のアメリカの大学で生まれた制度だ。その目的は、大学教員が日常業務から一時的に離れ、自身の研究や教育スキルの向上に専念する時間を確保することである。現在でも、多くのアメリカの大学では、7年ごとに半年から1年程度の休暇を与える制度が運用されている。
■ヨーロッパのサバティカル休暇
現在、サバティカル休暇は主にヨーロッパで広く普及している。スウェーデンやフィンランド、フランス、ドイツなど、ワークライフバランスを重視する国々では、政府レベルで長期のサバティカル休暇の取得が奨励されており、数年レベルの休暇が珍しくない。
■日本におけるサバティカル休暇の現状
日本のサバティカル休暇の普及率は、ヨーロッパと比べるとまだ低いものの、大企業を中心に徐々に広がりつつある。たとえば、LINEヤフー、ソニー、ANA、リクルートなどの企業で、サバティカル休暇、もしくはそれに相当する制度が導入されている。
サバティカル休暇のメリット
企業がサバティカル休暇を導入することには、次のようなメリットがある。
[従業員のメリット]
■やりたかったことに挑戦できる
■心身をリフレッシュできる
■キャリアの方向性が明確になる
[企業のメリット]
■従業員に今まで以上の活躍を期待できる
■企業イメージが向上する
以下、それぞれについて詳しく解説していく。
■従業員のメリット1:やりたかったことに挑戦できる
サバティカル休暇は、「これまでやりたくてもできなかったこと」に挑戦できる機会を与えてくれる。これまでの日本企業では、理由のいかんを問わず、1か月以上の長期休暇を取得するのは現実的にほぼ不可能であった。そのため、たとえば海外での語学学習や、自転車による日本一周旅行など、自分の人生にとって意味のある挑戦を望んでも、多くの人が断念せざるを得なかった。しかし、サバティカル休暇を活用できれば、会社を退職することなく、やりたかったことに思い切って挑戦できるようになる。
■従業員のメリット2:心身をリフレッシュできる
サバティカル休暇は、心身のリフレッシュに非常に効果的である。日常業務から一定期間完全に離れることで、それまで蓄積した疲労やストレスを解放できる。もちろん、通常の休日や有給休暇でもリフレッシュはできるが、サバティカル休暇はそれらでは得られないレベルのリフレッシュを可能にする。燃え尽き症候群やうつ病などのリスクも低減できるであろう。そして復職後は、より高いモチベーションとパフォーマンスで仕事に臨めるようになる。
■従業員のメリット3:キャリアの方向性が明確になる
サバティカル休暇は、自分自身のキャリアを見つめ直すために立ち止まる機会を与えてくれる。十分な時間があるため、「何のために働くのか」「自分にとって本当に価値のあることは何か」「どこへ向かうべきか」など、普段は後回しにされがちな根源的な問いと向き合うことができる。また、休暇を利用して情報収集したり新しくスキルを習得したりすることも可能だ。復職後は、明確なビジョンをもって、より主体的かつ戦略的に仕事に取り組めるようになる。
■企業のメリット1:従業員に今まで以上の活躍を期待できる
企業側からすると、サバティカル休暇を取得した人材には、それまで以上の活躍を期待できる。もちろん、休暇中に何に取り組んでいたかにもよるが、大学院進学や留学、ボランティア活動などは、視野を大きく広げるし、人間的成長や新たなスキル習得につながるケースが多い。そのような人材が自社に戻ってくることで、組織全体の知見や技術力が底上げされ、従来になかったアイデアや革新的な取り組みが生まれる可能性も高まる。
■企業のメリット2:企業イメージが向上する
企業側からすると、サバティカル休暇の導入により企業イメージの向上が期待できる。現代の労働市場では、柔軟で先進的な人事制度を持つ企業が高く評価される傾向にあり、サバティカル休暇を導入することでクライアントや取引先、従業員からの支持を得やすくなるのだ。これは採用活動においても大きなアドバンテージとなる。「魅力的な職場」として映りやすくなるため、優秀な人材や意欲的な人材を確保しやすくなる効果を見込める。
サバティカル休暇のデメリット

企業がサバティカル休暇を導入することには、多くのメリットがある一方で、次のようなデメリットもある。
[従業員のデメリット]
・休暇中の収入が減少する
・復職後に業務のキャッチアップで負担がかかる
・出世に影響する場合がある
[企業のデメリット]
・業務の調整が必要となる
・従業員が離職してしまうリスクがある
以下、それぞれについて詳しく解説していく。
■従業員のデメリット1:休暇中の収入が減少する
サバティカル休暇を取得すると、基本的には休暇中の収入が減少することになる。前述の通り、休暇中の給与の支給有無やその金額については企業によってさまざまで、基本給の一部を支給する企業や数十万円程度の支援金を支給する企業もあるが、全体的な収入としては通常と比べて少なくなるケースが多い。そのため従業員は、休暇中の生活費をあらかじめ工面しておく必要がある。
■従業員のデメリット2:復職後に業務のキャッチアップで負担がかかる
サバティカル休暇を取得した従業員は、復職後に業務のキャッチアップで負担がかかる場合がある。特に業務プロセスやチーム編成が休暇中に変わっていた場合のキャッチアップには相応の時間と労力を要することになるだろう。さらに、メンバーが大きく変わっていた場合、イチから関係性を築き上げていく必要があり、それがさらなる負担となることもある。
■従業員のデメリット3:出世に影響する場合がある
サバティカル休暇の取得は、出世に影響する場合もある。もちろん休暇期間にもよるものだが、数年レベルで休暇を取得していれば昇進や昇給のタイミングが後ろ倒しになることも考えられる。また、長期休暇の文化が根付いていない企業では、「長期休暇を取る=責任感が低い」といったネガティブな印象を持たれることも少なくない。たとえサバティカル休暇の導入を推進した部署・人物からは評価されても、他の部署・人物からは評価されないということも十分に考えられる。
■企業のデメリット1:業務の調整が必要となる
企業側からすると、従業員が実際にサバティカル休暇を取得するとなると、業務の調整が必要となる。業務の調整とは、具体的には引継ぎや人員補充、クライアントや関係部署への説明などのことだ。一般的にサバティカル休暇は、勤続年数の長い従業員を対象とするケースが多い。そうした人材は、豊富な経験を有し、しばしば重要な業務を担っているため、長期間の不在によって、メンバーに大きな負担がかかることが予想される。特に担当業務が属人的または専門的な性質を持っている場合、その引継ぎや人員補充は容易ではない。
しかし、これは業務改革を進めるチャンスとしてみることもできる。たとえば次のような対応を行うことで、それ以降、業務が進めやすくなる上に、休暇取得に対する対応力も向上すると期待できる。
■業務プロセスの標準化やマニュアル整備を進め、誰でも一定の仕事がこなせる体制を作る
■従業員に複数の業務スキルを身につけさせる「多能工化」を進めることで、組織としての柔軟性を高める
■企業のデメリット2:従業員が離職してしまうリスクがある
企業側からすると、サバティカル休暇は、従業員の離職リスクを高めてしまう懸念がある。従業員は休暇中、日常業務から離れ、新しい環境や価値観、人間関係に触れる機会が増えるため、従来とは異なる分野に関心を持ったり、新たな目標を見つけたりすることがある。その結果、従来の仕事に対する意欲が薄れ、退職を考えるようになるケースも少なくない。さらに、休暇により職場とのつながりが希薄になることで、復帰後に居場所のなさや疎外感を覚える場合もあり、これが退職の決断を後押しすることもある。
サバティカル休暇が注目される背景
近年、サバティカル休暇が注目を集めているが、その背景には何があるのだろうか。主に働き方改革やワークライフバランスへの関心の高まりがある。
かつての日本では、仕事に多くの時間を費やすことが美徳とされていた。しかし、近年では、「自分らしい生き方」や「仕事とプライベートの両立」といった視点が重視されるようになってきており、それにともなって休暇に対する考え方も見直されつつある。
また、サバティカル休暇は「リカレント教育」の促進にもつながると考えられている。リカレント教育とは、「学び直し」や「生涯学習」を意味する言葉で、学校教育を終えた社会人が、必要なタイミングで、必要な学びを得ていく取り組みのことだ。変化の激しい現代社会においては、このリカレント教育が、個人の成長だけでなく、組織全体の競争力強化にもつながると期待されている。
加えて、経済産業省が発表する各種資料においても、サバティカル休暇がたびたび取り上げられており、これも注目を集める一因と考えられる。















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE