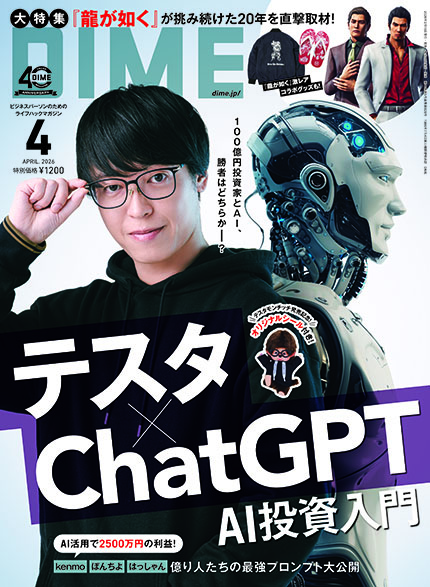「フェロー」とは、高度な専門知識と経験を持つ技術者や研究者に与えられる役職・称号だ。本記事では、フェローの意味や、フェロー制度の導入事例を紹介する。
目次
「フェロー」とは、高度な専門知識と経験を持つ技術者や研究者に与えられる役職・称号だ。ビジネスやアカデミック、医療分野で幅広く活用され、近年は企業の技術的競争力向上を目的としたフェロー制度の導入が進んでいる。
フェローの意味や、フェロー制度の導入事例を詳しく見ていこう。
フェローの意味

まずは「フェロー」という言葉の意味から確認しよう。
■フェローとは
「フェロー」(Fellow)とは、英語で「仲間」「同僚」「研究員」を意味する言葉だ。日本のビジネスや学術分野では、特定の専門性や経験を持つ人材を指す役職名や称号として使われるケースが一般的だ。
実務上、フェローは研究開発や技術革新を牽引する役割を担う。業界に関係なく、専門的な知見を活かして活躍している。
■様々なフェローの使われ方
・ビジネスシーンにおけるフェロー
企業におけるフェローは、高度な専門知識と豊富な経験を持つ技術者や研究者に与えられる最高位の技術職だ。通常の管理職とは異なり、技術的なリーダーシップを発揮する役割を担っている。
特定分野の第一人者として社内外で認められており、実務上は新技術の研究開発や技術戦略の策定を主導する。若手や将来のフェロー候補者への指導やメンタリングも行っており、重要な責務を担う存在だ。
実際に、大企業の中には「フェロー」という役職を設けて、技術者のキャリアパスの頂点として位置づけているところもある。
・アカデミックシーンにおけるフェロー
アカデミック(学術)分野では、フェローは研究機関や大学における研究職の一種だ。博士号取得後のポストドクトラル・フェロー(ポスドク)が最も一般的で、独立した研究者になるための準備期間として位置づけられている。
研究助成を受けて、特定のプロジェクトに従事する「研究フェロー」もある。研究フェローは、特定の研究分野で優れた業績を上げた研究者に対して与えられる称号で、大学や研究機関などで研究活動を推進する役割を担う。
大学によっては、講義内容でわからないところの質問を受け付けたり、答案やレポートの書き方を個別に指導したりする「フェロー」が存在する。
・医療業界におけるフェロー
医療分野におけるフェローは、専門医資格取得後、さらに高度な専門性を身につけるための研修制度だ。レジデント(後期研修医)を修了した医師が、特定の専門分野でより深い知識と技術を習得するために行う研修期間を指す。
「心臓外科フェロー」「腫瘍内科フェロー」「感染症フェロー」など、細分化された専門領域ごとに設けられている。通常1〜2年間の研修期間で、指導医のもとで高度な症例を経験し、各専門分野のエキスパートを育成している。
フェロー制度とメリット・デメリット
企業によっては、専門家を採用・育成するための「フェロー制度」を設けている。特徴やメリット、デメリットを確認しよう。
■フェロー制度の概要
企業におけるフェロー制度とは、高度な専門性を持つ技術者や研究者を、組織内で適切に処遇し、その能力を最大限活用するための人事制度だ。「技術職専門コース」としてキャリアパスが設計されており、純粋に技術的な専門性を追究できる。
先端技術の研究開発をリードする役割が期待されており、一般的には技術的な業績・社内外での評価・将来性などが評価の対象となる。社内の技術者に対する指導・育成も重要な責務で、技術的な相談役として若手の成長をサポートする。学会発表や論文執筆、特許出願など、社外に向けた技術発信を行うこともある。
なお、フェローには役員クラスに相当する高い地位と待遇が与えられる。給与水準は管理職と同等以上に設定され、技術的な意思決定において強い発言権を持ち、研究環境や設備についても優遇措置があるのが一般的だ。
■フェロー制度のメリット
フェロー制度を導入する企業側のメリットとして、技術的競争力の向上が挙げられる。高度な専門知識を持つ人材が技術開発に専念できるため、イノベーション創出や技術的ブレークスルーが期待できる。
また、優秀な技術者の流出防止にも効果的で、管理職への昇進を望まない専門志向の人材にも魅力的なキャリアパスを提供できるだろう。フェローが若手技術者を指導することで、企業固有の技術ノウハウや暗黙知を次世代に受け継ぐことが可能だ。
技術分野を追求し続けることができるだけでなく、高い待遇と社会的地位が保証されているため、専門性を深めることに集中できる環境が整っている。
さらに自分の研究成果を社外にも発信できるため、技術者としての個人的な評価や知名度も高まるだろう。学会での発表や論文執筆などを通じて、業界全体での影響力を持つことも可能だ。
■フェロー制度のデメリット
フェロー制度を導入すると、企業側に高いコストが発生する。フェローには役員クラスの待遇を提供する必要があり、人件費負担が重くなりやすい。また、フェローの研究が必ずしも短期的な収益に結びつかない場合もあり、投資対効果の測定が困難だ。
従業員側のデメリットとしては、キャリアの選択肢が限定される面が挙げられる。また、フェローになれるのは限られた人数のため、多くの技術者にとっては狭き門といえる。
技術分野に特化しすぎることで、ビジネス全体を俯瞰する能力や、組織マネジメントスキルが身につきにくくなる可能性もある。人によっては「常に最先端の技術に触れ続けなければならない」「研究成果を上げなければならない」プレッシャーを感じる可能性がある。
ビジネスにおけるフェロー制度の導入事例

日本の大企業でも、フェロー制度が導入されている。具体的な導入事例を見ていこう。
■導入事例1:住友生命
住友生命は、2023年4月1日から「エグゼクティブ・フェロー制度」を導入した。社内外を問わず高度専門人財を登用し、執行役員と同等の権限を付与する制度だ。
住友生命のプレゼンスを一層向上させていくため、専門的な知見を持つ人財による全社的見地からの業務執行の必要性が高まったことが、導入の背景だ。執行役員と同等の権限を付与することで、意志決定や業務執行といった面において、経営のスピードを飛躍的に向上させていくことを目指している。
■導入事例2:NTT
NTTグループのフェロー制度は、以下の3つの階層で構成されている。
- フェロー(NTTフェロー):世界的に認められる卓越した研究業績をあげている社員の中で、象徴的な研究者に与えられる特別な役職
- 上席特別研究員:世界から優秀な研究者として認められている革新研究者である「特別研究員」の中でも、極めて優秀かつ長期的に活躍が期待できる研究者に与えられる役職
- 特別研究員:世界から優秀な研究者として認められている革新研究者に与えられる役職
NTTグループにおけるフェローは、研究職の中で最も位の高い役職となっており、研究裁量権が与えられる。また、フェローになるまでのキャリアパスとして「特別研究員」や「上席特別研究員」が用意されており、優秀な若手研究者をサポートする仕組みが構築されている。
特に通信・ICT分野において、長期的な視点から重要な技術領域での研究開発をリードする人材を育成・確保することで、同社の技術的優位性の維持・向上に貢献している。
■導入事例3:トヨタ自動車
トヨタ自動車では、技術系人材に対して複数の制度を設けており、その中でフェロー制度も重要な位置を占めている。自動車業界が大きな変革期を迎える中で、高度な専門性を持つ人材が現場により近い位置で判断を下し、イノベーションを推進するために導入された。
領域長を「統括部長」と「フェロー」に見直し、執行役員以上のトップ経営陣と実務を担当する現場との間の階層をさらに減らすことで、実行力のさらなる強化とスピードアップを推し進める体制とした。また、同時にトップによるそれぞれの現場での指導・育成を通じ、組織全体の力の一層の底上げを図っている。
まとめ
フェロー制度は、企業が高度な専門性を持つ人材を適切に処遇し、技術的優位性を確保するための重要な仕組みだ。
技術者に対しては、管理業務に追われることなく専門分野を追求できる理想的なキャリアパスを提供できる。一方で、企業にとってはイノベーション創出と優秀な人材の流出防止が期待できる。
今後、技術革新がますます重要となる中で、フェロー制度は企業の競争力を左右する重要な人事戦略として注目されるだろう。
文/柴田充輝
厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に、これまで1,200記事以上の執筆実績あり。保有資格は1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、社会保険労務士、行政書士、宅地建物取引主任士など。















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE