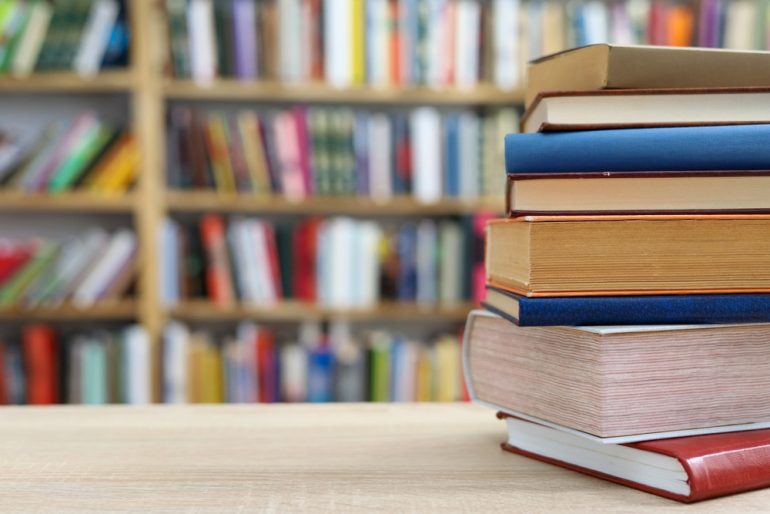
瓦解の意味や具体的な瓦解事例を紹介する。組織を根底から崩壊する最悪の事態から守るためにも、瓦解を防ぐ方法も知っておこう。
目次
組織や制度が一瞬にして崩れ去ったり、長年築き上げた信頼や堅固に見えた経営基盤が連鎖的に崩壊していく様子を、「瓦解」と呼ぶ。
瓦解とは、元々は屋根瓦が一枚落ちると、次々と他の瓦も崩れ落ちる様子が語源となっている。現代のビジネス環境では、些細なトラブルが企業全体を飲み込む破滅的な事態へと発展することがあるため、注意が必要だ。
今回は、瓦解の意味や具体的な瓦解事例を紹介する。組織を根底から崩壊する最悪の事態から守るためにも、瓦解を防ぐ方法も知っておこう。
瓦解(がかい)とは

物事が根本から覆ったり、何らかのトラブルで組織の運営が難しくなったとき、「瓦解」という言葉を用いることがある。
まずは、瓦解の意味や語源などを確認していこう。
■瓦解の意味と読み方
「瓦解(がかい)」とは、組織や体制、秩序などが完全に崩れ落ちる様子を意味する。一部が壊れるのではなく、「基盤から根本的に崩壊する」という強いニュアンスがある点が特徴だ。
たとえば、不祥事が発覚した企業で経営陣が総退陣したとき、「組織が瓦解した」と言われることがある。
なお、具体的な使用例は以下の通りだ。
- 「政権が瓦解した」
- 「社会秩序の瓦解」
- 「経済システムが瓦解する」
- 「会社の経営体制が瓦解」
- 「チームワークが瓦解した」
- 「信頼関係の瓦解」
- 「人生設計が瓦解した」
- 「長年の努力が瓦解する」
何らかのミスやトラブルが原因となり、これまで築き上げてきたものが水泡に帰してしまう状況を、「瓦解」という。
■瓦解の語源
瓦解という言葉は、中国の古典が語源となっている。「瓦」は屋根瓦が崩れ落ちる様子、「解」はばらばらになる様子を示しており、ある一部の乱れ・破れ目が広がって全体が壊れてしまったことが語源だ。
屋根瓦が一枚崩れると、連鎖的に他の瓦も次々と落ちて、最終的に屋根全体が崩壊してしまう。この様子を比喩して「組織や制度の完全な崩壊」を表すようになった。
なお、類語や関連表現として以下が挙げられる。
- 崩壊
- 破綻
- 決壊
- 壊滅
- 土台から崩れる
- 根底から覆る
「瓦解」は「崩壊」よりもさらに深刻で、回復困難な状態を表現する際に使われる。ただし、現実的に細かく使い分けられているわけではなく、物事や組織が崩れていく様子を総じて「瓦解」という。
ビジネスシーンにおける瓦解(がかい)
「瓦解」は日常生活でもビジネスシーンでも用いることがある。以下で、ビジネスシーンにおける具体的な使用例などを見ていこう。
■経営陣の不祥事による組織瓦解
大手食品メーカーで経営陣による粉飾決算が発覚し、同時に品質データの改ざんも明るみに出て、取引先からの契約解除が相次いでしまった。
一連の不祥事により、資金繰りの悪化や主要取引先との契約打ち切り、優秀な社員の大量離職が発生した。また、信頼を失ったことにより銀行からの融資停止や販売網の崩壊につながり、最終的に事業継続が不可能となった。
最終的に事業継続が不可能となっている以上、回復不可能な「瓦解」状態といえる。
■サプライチェーン依存による事業瓦解
自動車部品メーカーが特定の大手自動車メーカーに売上の80%を依存していたが、その顧客が海外生産にシフトしてしまったケースで考えてみよう。
主要顧客からの受注が大幅に減少し、他の顧客開拓がままならないことで、赤字が拡大してしまった。人件費を削減するために従業員の大幅なリストラを実施したものの、技術者の流出で競争力が低下し、残りの顧客からも信頼を失ってしまった。
このように、顧客集中のリスクが顕在化してしまうと、事業モデル全体が瓦解して廃業を余儀なくされてしまうことがある。
ビジネスにおける瓦解の防止例

ビジネスにおいて「瓦解」という言葉を使うときは、総じて悪い状況だ。企業活動が停止したり、倒産・廃業に追い込まれてしまったりする可能性が高いため、瓦解が発生する状況は防がなければならない。
以下で、ビジネスにおける瓦解の防止策を見ていこう。
■ガバナンス・内部統制の強化
組織全体の不正が発生してしまうことを防ぐためには、ガバナンス・内部統制の強化が欠かせない。透明性を確保した事業運営を行い、定期的な内部監査を実施しよう。
また、コンプライアンス体制を維持するために、法令遵守の徹底教育や内部通報制度の整備が効果的だ。定期的な法務チェックを行い、すべての従業員がコンプライアンス意識を持つことが予防につながる。
■リスク分散による基盤強化
収入源が特定の顧客に集中してしまうのは、リスクが大きい。当該顧客との関係に問題が発生すると、事業の継続が一気に困難になってしまう。
そのため、顧客ポートフォリオを多様化させたり、異業種・異地域への顧客開拓を推進したりすることが効果的だ。また、既存の顧客との関係性を維持するために、定期的な顧客満足度調査を実施することも検討しよう。
■財務健全性の維持
十分な自己資金があれば、何らかの事情で事業が不振に陥っても、当面の間は事業を継続できる。その間に事業を好転させれば、企業を存続させ、雇用も守れる。
具体的な対策としては、手元資金を十分に確保したり、複数の金融機関と取引関係を構築したりするとよい。あわせて、融資以外の資金調達手段を用意し、万が一の際に必要な資金を用意できるように備えよう。
そのためにも、日ごろから財務状況をチェックし、十分な流動資金を確保できているかを把握するとよい。
■危機管理・事業継続計画
事業を経営していると、予測不可能な出来事が次々と起こる。状況の変化に柔軟に対応するためにも、危機管理・事業継続計画をしっかりと考えておこう。
具体的には、最悪のケースを想定した対応策を準備したり、事業継続に必要な最低条件を設定しておくとよい。撤退する基準を設けておけば、傷口が拡大して瓦解する前に、事業を立て直すことが可能だ。
リーマンショックやコロナショックのような経済危機や社会の混乱は、いつ起こるかわからない。リスク管理の一環として、最悪のケースが起こったときの対応を策定しておくことは、瓦解を防ぐうえで有効だ。
まとめ
「瓦解」は、組織や制度が根底から崩れ去る、回復困難な破滅的状況を意味する。現代においても、小さな綻びが組織の崩壊へ発展する危険性は常に存在している。
瓦解の発生を未然に防ぐためには、ガバナンスの強化やリスク分散などが効果的だ。また、あらかじめリスクが顕在化したときの対策や危機管理計画を策定し、予防策を講じることも欠かせない。
適切な備えがあれば、危機が発生しても乗り越えることが可能だ。組織の持続的な発展のために、瓦解への対策を真剣に検討すべきだろう。
文/柴田充輝(しばたみつき)
厚生労働省や不動産業界での勤務を通じて社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。 FP1級と社会保険労務士資格を活かして多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。現在はWebライターとして金融・不動産系・ビジネス系の記事を中心に執筆しており、1,200記事以上の執筆実績がある。















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE













