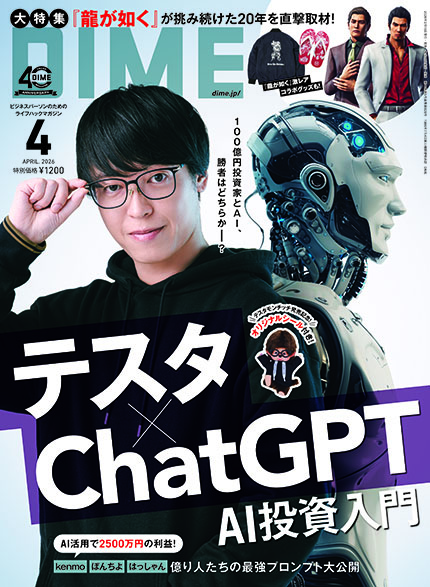人事やマネジメントの世界で出てくる用語のひとつに「ピーターの法則」がある。本記事では、ピーターの法則の基本的な内容から、有能人材が無能化するプロセス、そして組織・個人がそれを回避する方法などを解説する。
目次
人事やマネジメントの世界で出てくる用語のひとつに「ピーターの法則」がある。「〇〇さん、優秀な人だったのに、昇進したら以前のように活躍できなくなった」。このような話を耳にすることはないだろうか。
「有能人材が無能化する」――実はこれ、ピーターの法則で説明できる現象である。本記事では、ピーターの法則の基本的な内容から、有能人材が無能化するプロセス、そして組織・個人がそれを回避する方法などを解説する。
ピーターの法則とは

■ピーターの法則の意味
ピーターの法則(Peter Principle)とは、組織における「昇進」と「能力」の関係を示した法則である。アメリカの教育学者、ローレンス・J・ピーター(Laurence J. Peter)氏が、1969年に提唱した。
その主な内容は次のとおりである。
- 有能な人材であっても、昇進を繰り返すうちに、やがて自分の能力の限界を越えたポジションに就くことになる(=無能化する)
- 能力の限界を越えたポジションに就いた人材は、それ以上昇進することはなく、そのまま活躍できないポジションにとどまることになる
- 組織は、まだ昇進の余地がある人材、すなわち「無能化」していない人材の力によって支えられている。
・書籍「ピーターの法則〈創造的〉無能のすすめ」について
ピーターの法則は、ピーター氏が、レイモンド・ハル(Raymond Hull)氏との共著『THE PETER PRINCIPLE』(1969年)の中で提唱したものだ。この書籍の日本語版は『ピーターの法則〈創造的〉無能のすすめ』というタイトルで、1970年にダイヤモンド社から出版され、さらに2003年には新訳版が出版されている。ピーターの法則を理解する上で、ぜひとも押さえておきたい書籍だ。
■ピーターの法則の関連用語
ピーターの法則と関連する用語として、「階層社会学」と「創造的無能」がある。ここで、それぞれについて簡単に解説する。
・ピーターの法則と階層社会学
ピーター氏は、ピーターの法則に関連する分野を「階層社会学(Hierarchiology)」と名付けた。これは、職業・役割・地位・権力・収入・資産などによって決まる社会的な序列や格差が、どのように作られ、どのように変化していくかを分析する学問分野である。
・ピーターの法則と創造的無能
ピーター氏は、「無能化」を回避する方法として、「創造的無能(Creative Incompetence)」というユニークな方法を提唱している。これは、自分が活躍できる場所にとどまるために、あえて自らを「無能」に見せるというものだ。例えば、「高度な専門スキルを持っていてプレイヤーとして一流だけど、人とのコミュニケーションがちょっと苦手」といった人物を演じることで昇進を回避する、といったアプローチである。
なぜ有能人材が無能化するのか?
ピーターの法則によると、「有能人材が無能化する」とのことだが、具体的にどういった要因があるのだろうか。典型的なものとして、次のようなものがある。
■スキルや適性がないため
前のポジションで活躍していた人材であっても、新しいポジションで求められるスキルや知識、適性を持ちあわせておらず、それで活躍できなくなることがある。一般的に、人員管理や納期管理、顧客折衝など、マネジメントスキルの不足がハードルとなるケースが多い。
■プレッシャーが増加するため
昇進前と昇進後で仕事内容が同じだとしても、昇進後は注目度や期待値が高まりやすい。それだけプレッシャーを感じやすくなり、本来のパフォーマンスを発揮できなくなることがある。
■モチベーションが低下するため
昇進後の仕事内容が自分の興味や方向性とマッチしないことが往々にしてある。それだけモチベーションが低下し、本来のパフォーマンスを発揮できなくなることがある。
ビジネスにおけるピーターの法則

■ビジネスにおけるピーターの法則の具体例
ピーターの法則のイメージが湧くよう、ビジネスの現場における「有能人材が無能化する」現象の具体例を3つ紹介する。
・例①トップ営業マンが営業部の管理職に昇進するケース
トップ営業マンとして抜群の成績を誇っていたAさんが、管理職に昇進。しかし、部下の育成が苦手だったり、パソコンに弱く営業系デジタルツールを使いこなせなかったりして、結局、売上が落ち込んでしまった。
・例②トップデザイナーがチームリーダーに昇進するケース
高度なデザインスキルを持ち、制作現場の最前線で活躍していたデザイナーBさんがチームリーダーに昇進。しかし、リソース管理やスケジュール調整といった業務に苦戦し、たびたび混乱が生じるようになってしまった。また、好きなデザインに取り組む時間が減ったことで、モチベーションも低下してしまった。
・例③プロジェクトマネージャーがより大きな案件を任されるケース
15人規模のITプロジェクトのプロジェクトマネージャーとして成果を上げていたCさんが、規模が50人規模の大型プロジェクトを任されるように。しかし、規模の大きさによるプレッシャーと管理の複雑さからトラブルが頻発し、納期遅延も発生するようになってしまった。
■なぜビジネスでピーターの法則が成立するのか
ビジネスの現場では、「ピーターの法則」が示す「有能人材が無能化する」という現象がしばしば見られるが、その原因は主に組織の文化や人事システムにあると考えられる。
多くの企業では、「成果を出した人材はとにかく昇進させるべき」といった価値観が根強くある。そのため、「今のポジションで成果を出す能力」と「次のポジションで成果を出す能力」は異なるにも関わらず、そこを考慮しないまま昇進人事が決まってしまうことが多い。結果として、昇進後に「無能化」するケースが生じてしまうのだ。
また、多くの企業では、そのポジションで成果を出せなくても、仕組み上、そのポジションにとどまり続けるしかないことが多く、これが問題を深刻化させているケースも多い。
【人事・マネジメント向け】ピーターの法則を回避するための方法
どうすれば「有能人材が無能化する」現象を回避できるのだろうか。特に組織の人事やマネジメントを担当する方は気になるであろう。ピーターの法則を回避する方法として、次のようなものがある。
■昇進前に研修を実施する
まず、昇進前に研修を実施するという方法がある。新たなポジションで求められるスキルや知識を事前に習得できれば、昇進後のギャップを最小限に抑えることができる。また、一定の水準に達した人材のみを昇進させる仕組みにすることも有効な手段である。
■降格制度を適切に運用する
日本では、降格制度が存在しても、形式的なものにとどまり、実際には機能していないケースが多く見られる。そこで求められるのが、成果が出ない場合やトラブルが頻発する場合などに、柔軟かつ現実的に降格を検討できる体制の整備である。
また、「降格=屈辱」といったネガティブな風潮がある場合には、そこへの配慮も欠かせない。降格人事を、特別なこととせず、健全な組織運営を行うための自然なプロセスの一つとして認知されるような文化づくりが求められる。
■昇進しなくても昇給する仕組みを導入する
あえて昇進させない選択肢を用意するのも有効である。しかし、成果を出しても何も報酬がないのであれば、従業員のモチベーションが低下してしまう。そのため、昇格ではなく昇給や特別手当支給といった形で報酬を提供することが手段として考えられる。
■横のキャリアパスを用意する
横のキャリアパスを用意することも有効である。横のキャリアパスとは、昇進ではなく、異なる職種や部署に異動するコースのことをいう。横のキャリアパスには、次のようなメリットがある。
・多様な業務を経験することで、強みや弱みがより明確になる
・多様な業務を経験することで、新たなアイデアやイノベーションが生まれやすくなる
・多様な部署を経験することで、人脈が広がり、全体的な視野を持てるようにもなるため、部署間の調整役として活躍しやすくなる















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE