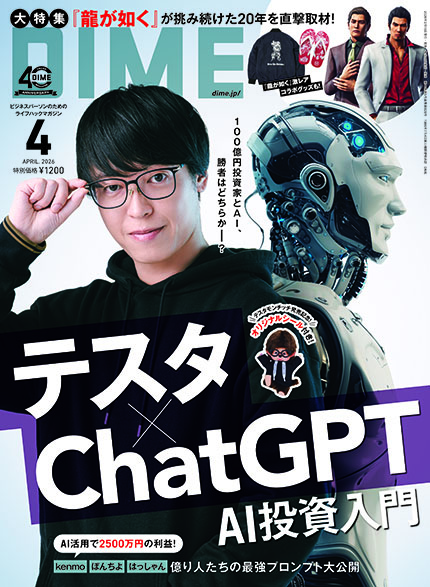ビジネスの場面において、「マトリックス」を用いて、さまざまな分析をする場面がある。今回は、マトリックスの基本的な意味やビジネスにおける活用法を解説する。
目次
ビジネスの場面において、「マトリックス」を用いて、さまざまな分析をする場面がある。複数の情報を多角的に分析し、適切な意思決定をするうえで、マトリックスの作成は有用だ。
事業展開だけでなく、優先的に取り組むべきリスク管理を考える際にも、マトリックスを用いた分析は効果を発揮する。
今回は、マトリックスの基本的な意味やビジネスにおける活用法を解説する。
マトリックスとは

まずは、マトリックスの意味やビジネスの場面で用いる代表的な事例を見ていこう。
■マトリックスの意味
マトリックスにはさまざまな意味があるが、「何かを生み出す土台や枠組み」という概念が根本にある。
数学の世界では「行列」を指し、縦と横に数字を規則的に配列した表や、連立方程式の解法・座標変換などに使われる。ビジネス用語としての「マトリックス」は、数学的概念から派生している。
■ビジネスにおけるマトリックス
ビジネス分野では、「マトリックス」は数学の「行列」概念を応用し、異なる要素同士の関係性を整理・分析するための枠組みとして使われる。縦軸と横軸で構成された表形式のフレームワークであり、情報を整理・分析する際に役立つ。
ビジネスでよく使われるマトリックス事例を、いくつか見てみよう。
- アンゾフマトリックス:縦軸に「製品(既存/新規)」・横軸に「市場(既存/新規)」を設定し、「市場浸透戦略」「新製品開発戦略」「新市場開拓戦略」「多角化戦略」4つの成長戦略を整理する
- BCGマトリックス:「市場成長率」と「市場シェア」で事業ポートフォリオを分析し、各事業を「花形」「金のなる木」「問題児」「負け犬」に分類する
- リスクマトリックス:「発生確率」と「影響度」でリスクを評価し、事業の対応優先度を決める
- アイゼンハワー・マトリックス:縦軸に「重要度」・横軸に「緊急度」を設定し、タスク管理や時間配分の優先順位を決定する
- 競合他社分析マトリックス:縦軸に「品質」・横軸に「価格」を設定し、自社のポジショニングが「高品質・高価格」の高級路線なのか、「標準品質・低価格」のコストリーダーシップなのかを整理する
- 顧客セグメント・マトリックス:縦軸に「購買頻度」・横軸に「単価」を設定し、マーケティング戦略の立案に活用する
これらのマトリックスは、複雑な判断を構造化してチーム内での議論を効率化したり、事業展開を考えたりするうえで有用なツールとなる。
マトリックスを活用するメリット
ビジネスでマトリックスを活用すると、複雑な情報を視覚化し、わかりやすく整理できる。「自社の商品」「顧客」「競合他社の情報」などさまざまな情報がある中で、それぞれの要素を組み合わせてマトリックスを作成すると、自社の強みや今後の事業方針を視覚化できる。
自社の強みや課題などを客観的に視覚化することで、企業内での意思決定がスムーズになるだろう。また、「なんとなく」や「経験則」のような根拠が曖昧な意思決定を防ぎ、分析に基づく論理的な意思決定ができるため、合理的な選択に寄与するはずだ。
これにより、限られた予算や人員をどこに投入すべきかを適切に判断できる。「どの顧客セグメントに営業リソースを集中すべきか」が、明確になるだろう。
さらに、マトリックスを用いて複数の要素を複合的に分析することで、「この点は検討したが、あの点は見落としていた」という事態を防げる。
このように、「意思決定スピードの向上」「リソースに基づく戦略的な意思決定」「勘案すべき要素の漏れを防ぐ」など、ビジネス上のメリットが期待できる。
マトリックスの活用例

ビジネスでのマトリックス活用事例を、3つ紹介する。
■新規事業参入の意思決定
例えば、IT企業が複数の新規事業候補から参入先を決定する場面を想定してみよう。
縦軸に「市場魅力度(市場規模、成長率、収益性)」・横軸に「自社競争力(技術力、資金力、人材)」というマトリックスを作成する。
この場合、市場魅力度と自社競争力がともに「高」に該当する事業が、最優先で参入すべき事業といえる(AI関連事業やIoTプラットフォームなどが代表的だ)。
■顧客管理・営業戦略の最適化
続いて、BtoB商社が取引先に対する営業方針を効率化したいシーンを考えてみよう。
縦軸に「取引金額(年間売上高)」・横軸に「収益性(利益率)」というマトリックスを作成する。「取引金額(年間売上高)」・横軸に「収益性(利益率)」のいずれも「高」の取引先は、戦略的パートナーとして親密な関係を築くべきだ。
「高売上・低利益」の取引先に関しては価格交渉を行う対象となり、「低売上・低利益」の取引先に関しては、関係の継続を判断することになるだろう。
■プロジェクトリスク管理
次に、大型システム開発プロジェクトでリスク要因を管理するシーンを想定してみよう。
縦軸に「発生確率」・横軸に「影響度」というマトリックスを作成して分析する。発生確率・影響度がいずれも「大」のリスクに関しては、早急に対策を打つ必要がある(たとえば、主要メンバーの離脱が挙げられる)。
リスクの顕在化に備えるために、事前の引継ぎ体制を構築したり、複数人でスキルを共有する必要性があるだろう。
優先度に応じた対策を実施することで、適切なリスク管理を行える。プロジェクトが予定通りに完了する可能性を高められ、自社の信頼向上につながるだろう。
まとめ
ビジネス上の問題や将来の展望を整理・分析するときは、マトリックスを用いよう。マトリックスを用いて客観的な分析をすれば、適切な意思決定ができるだけでなく、メンバー間の合意形成を得やすい。
もっとも大きな利益を期待できる経営戦略を実行したり、関係構築を優先すべき取引先を整理したりするとき、マトリックスを用いた分析は役立つ。リスク管理の面でも効果的な分析ができるため、有効活用しよう。
文/柴田充輝(しばたみつき)
厚生労働省や不動産業界での勤務を通じて社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。 FP1級と社会保険労務士資格を活かして多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。現在はWebライターとして金融・不動産系・ビジネス系の記事を中心に執筆しており、1,200記事以上の執筆実績がある。















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE