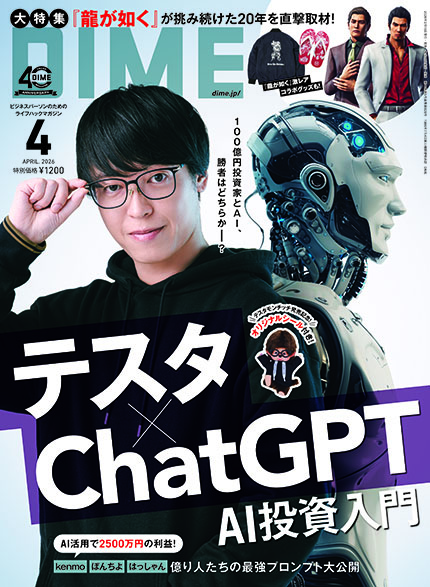ビジネスシーンにおける限界利益の活かし方

ビジネスパーソンであれば、限界利益の定義や活用方法を知っておくとよいだろう。具体的に、限界利益を活用する具体的な場面として、以下が挙げられる。
- 適切な価格戦略の策定
- 値引き販売の採算ラインの設定
- 価格を改定したときの影響の調査
- 複数商品の中で注力すべき高収益商品の特定
- 限界利益率の低い商品の見直しや廃止の検討
- 新商品導入の採算性評価
- 自社生産か外注かの判断
- 仕入れロットを最適化する方法の模索
限界利益を分析し、商品やサービスごとの利益率を把握できたら、限界利益が高い商品の製造と販売に注力しよう。限界利益の高い商品は、少ない販売数でも多くの利益を得られるため、効果的に売るための広告戦略を考えればよい。
もし限界利益が低い場合は、価格設定の見直しや変動費を下げるための工夫が求められる。競合の価格を分析したり、仕入れの方法を見直したりして、状況を改善すべきだ。
このように、限界利益を分析することで、「どの商品に力を入れるべきか」「価格はいくらにすべきか」「原材料費をどう見直すか」など、具体的な経営判断ができるようになる。感覚的な判断ではなく、データに基づいた合理的な経営判断をするためにも、分析方法を知っておくことは有益だ。
まとめ
限界利益は、商品1つ売るごとに増える利益を示す重要な指標だ。自社が販売している商品やサービスが利益に貢献できているかを判断するうえで、欠かせない情報といえる。
限界利益率が高い商品ほど効率よく利益を生み出すため、販売に注力するとよいだろう。もし限界利益率が低い場合は、価格戦略や仕入れ方法の見直しで限界利益率を高めたり、採算が合わない場合は販売を中止したりすることが選択肢となる。
感覚ではなくデータに基づいた合理的な経営判断をするためにも、限界利益や限界利益率、損益分岐点などの考え方を正しく理解しよう。
文/柴田 充輝(しばた みつき)
厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。 FP1級と社会保険労務士資格を活かして多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE