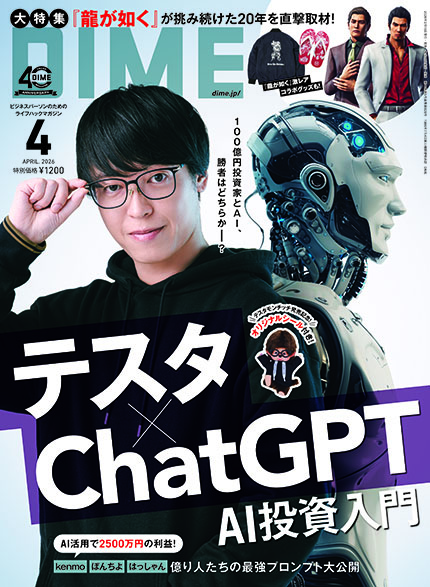「自分のビジネスは本当に儲かっているのか」を分析する際には、限界利益を活用しよう。ビジネスパーソンとして知っておくべき、限界利益や限界利益率などを解説する。
目次
「自分のビジネスは本当に儲かっているのか」を分析する際には、限界利益を活用しよう。感覚ではなく、客観的なデータに基づいて経営判断をすることで、事業を成功させる確率を高められる。
商品やサービスごとの儲けを見える化すれば、販売に注力すべき商品や適切な価格を決められる。
わずか数分の分析で、ビジネスの効率は劇的に向上するかもしれない。ビジネスパーソンとして知っておくべき、限界利益や限界利益率などを解説する。
限界利益とは

事業の経営者として、収益性を判断するうえで重要な数字が「限界利益」だ。収益性の高さを判断したり、事業の継続性を判断する際に役立つ。
まずは、限界利益の基本的な意味合いや、計算方法などを解説する。
■限界利益とは
限界利益とは、売上から変動費を差し引いた金額を指す。1単位の商品やサービスを販売することで得られる利益、簡単にいうと「商品を1つ売ったときに増える利益」を表す。
限界利益が高いほど、追加の売上が会社の利益に大きく貢献する。また、後で解説する「限界利益率」が高い商品・サービスを増やすことで、効率的に利益を向上させることが可能だ。
つまり、限界利益を把握することは、自社の商品やサービスが利益を生み出す力を測るうえで重要な指標となる。
■限界利益の計算方法
限界利益の計算方法は「売上高-変動費」となる。事業運営にあたって発生する「変動費」と「固定費」の違いは以下のとおりだ。
| 変動費 | 生産量や販売量に応じて変動する費用(原材料費、変動人件費など) |
| 固定費 | 生産量や販売量に関係なく発生する費用(家賃、固定給与など) |
ケーキ屋で1個500円のケーキを販売する場合で考えてみよう。ケーキを1つ作るために必要な変動費が200円とすると、限界利益は「500円-200円=300円」だ。
つまり、ケーキを1つ売るごとに300円の利益が生まれる。得られた変動費は利益の増加だけでなく、固定費の回収にも貢献する。
例えば、毎月ケーキ屋の運営に際して発生する固定費が30万円の場合で考えてみよう。この場合、毎月1,000個のケーキを販売すれば固定費を回収でき、黒字経営が可能だ。なお、限界利益は「どの商品の販売に注力すべきか」の意思決定にも役立つ。
先ほどのケーキ屋の例だと、ケーキごと(チョコレートケーキやモンブランなど)に変動費や価格は異なるはずだ。つまり、商品ごとに限界利益は異なる。
効率よく利益を上げるためには、限界利益が高い商品作りに注力し、できるだけ多く販売できるような経営努力が求められる。
■限界利益率とは
限界利益率とは、売上高に対する限界利益の割合を示す指標だ。「売上1単位あたり、いくら利益が残るか」というイメージを持つとわかりやすい。
限界利益率は「限界利益÷売上高×100(%)」という計算式で求められる。先ほどのケーキ屋の例で見てみると、1個あたりの変動費が200円のケーキを500円で販売した場合、限界利益は300円だった。
限界利益率は「300円÷500円×100=60%」となる。つまり、「ケーキを1個売ると、売上の60%が利益として残る」という意味だ。限界利益率が高いほど、少ない売上でも多くの利益を得られるため、効率よく経営できていることを意味する。
また、限界利益率が高いと固定費をより早く回収できるため、黒字転換が早くなるメリットがある。黒字転換後は追加の売上に対して多くの利益を生み出せるため、多くの利益を残すことができ、従業員への給与アップなどの対応が可能だ。
限界利益と損益分岐点

限界利益と並んで重要な経営指標の一つが、損益分岐点だ。限界利益と損益分岐点は経営分析において密接に関連しているため、きちんと両者について理解しておこう。
損益分岐点は「赤字でも黒字でもない、ちょうどゼロになる販売数量」を指す。簡単にいえば、変動費と固定費をちょうど回収でき、収支がトントンになる基準だ。
| 計算式 | 特徴 | 使用する場面 | |
| 限界利益 | 売上高-変動費 | 商品を1つ売ったときに増える利益 | ・商品の収益性評価・価格戦略の決定 |
| 損益分岐点 | ・固定費÷限界利益率・固定費 × (売上高 ÷ 限界利益) | 収支がちょうどゼロになる売上高(ビジネスが黒字化する最低限の売上高) | ・経営の安全性評価・目標設定の基準 |
先ほどのケーキ屋では、ケーキの限界利益率は60%、店舗の固定費が30万円だった。この場合、損益分岐点売上高は「30万円÷0.6=50万円」となる。
つまり、月間売上が50万円あれば収支はちょうどゼロとなり、それ以上の売上があれば利益が出始めることを意味する。
原材料費の上昇があり、限界利益率が30%になってしまったケースはどうなるだろうか(価格は据え置いた場合)。この場合、損益分岐点売上高は「30万円÷0.3=100万円」となり、利益が出始めるまでのハードルが高くなったことがわかる。
「限界利益が大きい商品は、少ない販売数でも利益が出やすい」「限界利益が小さい商品は、たくさん売らないと利益が出ない」ということだ。
このように、限界利益と損益分岐点を活用することで、目標利益を達成するための必要売上高を計算できる。また、値上げや値下げの影響予測や、固定費を削減できたときの効果測定として用いることも可能だ。
事業者の方であれば、販売している商品やサービスの限界利益・限界利益率・損益分岐点は必ず押さえておくべきだろう。限界利益率を高めるために、「どのように変動費・固定費を削減するか」「適切な販売価格はいくらか」を考えることが大切だ。
※出典:独立行政法人中小企業基盤整備機構「損益分岐点を使った目標売上高」
限界利益と他の利益との違い

限界利益の他にも、「〇〇利益」という経営指標は複数ある。それぞれがどのような意味を持ち、どのような場面で用いればよいのかを確認しよう。
■限界利益と売上総利益(粗利)
売上総利益(粗利)とは、売上から売上原価を引いた利益を指す。つまり、商品を作るのにかかった直接のコストを引いた後に残る利益だ。
| 計算式 | 特徴 | 使用する場面 | |
| 限界利益 | 売上高-変動費 | 商品を1つ売ったときに増える利益 | ・商品の収益性評価・価格戦略の決定 |
| 売上総利益(粗利) | 売上高-売上原価 | 「お店全体」の利益 | 「お店の全体的な儲け」を調査する |
限界利益は費用を「変動費」と「固定費」に分けたうえで変動費のみを差し引くのに対し、売上総利益は費用を「売上原価」と「販売費・一般管理費」に分類し、仕入れ費用や製造にかかるコストである売上原価を差し引いて計算する。
両方とも経営判断をする際に重要な数字だが、売上総利益はお店の全体の儲けを見るのに対して、限界利益は「この商品をもう1個売ったらいくら儲かるか」という視点で見るものだ。
分析の対象が異なるため、混同しないように気を付けよう。
■限界利益と営業利益
営業利益とは、「本業での儲け」を表す指標だ。売上高から、売上原価と販売費及び一般管理費を差し引くため、「売上から全部のコストを引いた儲け」を知る際に役立つ。
営業利益が多いほど効率よく利益を出せていることを意味するため、経営者として重視すべき指標といえるだろう。
| 計算式 | 特徴 | 使用する場面 | |
| 限界利益 | 売上高-変動費 | 商品を1つ売ったときに増える利益 | ・商品の収益性評価・価格戦略の決定 |
| 営業利益 | 売上高-売上原価-販売費・一般管理費 | 事業活動に関するすべての費用を、売上高から控除 | ・事業全体の収益力を調査する・会社全体の「本業での最終的な利益を調査する |
営業利益は、売上原価だけでなく人件費・家賃・広告宣伝費・減価償却費など、事業運営に関連する一連のコストを加味している点が特徴だ。過去と比較して本業の収益力が強まっているか、競合他社と比較して自社は課題があるかを調査するうえで役立つ。
営業利益は事業全体の収益性を評価し、中長期的な経営判断を行う際の重要な指標となる。「事業全体は健全か」「前年比でどう改善したか」を数字上で把握することで、営業利益が高い商品やサービスへ集中的に投資したり、営業利益を圧迫している要因(高すぎるコストや低すぎる価格など)を特定し、改善策を考えられるだろう。
営業利益とあわせて確認したい指標が、営業利益率だ。営業利益率は、営業利益と同様に本業での効率性を示す重要な指標であり、「売上の何%が本当の儲けになっているか」を表す。
計算方法は「営業利益÷売上高×100%」だ。例えば、売上高が1,000万円で営業利益が150万円の場合、営業利益率は「150万円÷1,000万円×100%=15%」となる。
営業利益率が高ければ、効率よく利益を生み出せていることを意味する。規模の違う会社同士を比較する際にも、営業利益率であれば効率性をフェアに判断できるため、競合分析との比較にも役立つだろう。
■限界利益と経常利益
経常利益とは、本業での儲けと他の財務活動からの儲けを合わせた利益を指す。本業以外にも、投資で得られた儲けや損失があるとき、経常利益に反映される。
つまり、経常利益は「普段の活動全体でどれだけ儲かっているか」を表す数字といえる。具体的には、本業以外の収入(受取利息、配当金など)や営業外費用(支払利息など)を加味した最終的な利益だ。
| 計算式 | 特徴 | 使用する場面 | |
| 限界利益 | 売上高-変動費 | 商品を1つ売ったときに増える利益 | ・商品の収益性評価・価格戦略の決定 |
| 経常利益 | 営業利益+営業外収益-営業外費用 | 会社が普段の活動全体で、どれだけ安定して利益を出せているかを示す | 会社の通常活動全体でどれだけ儲かっているかを調査する |
経常利益は「会社の通常活動全体でどれだけ儲かっているか」を知るための指標であるため、限界利益とは異なる。限界利益は「個別の商品」に注目しているのに対し、経常利益は「会社全体」に注目するものと理解するとよい。
経常利益では、固定資産の売却益や災害による損失など、一時的な特別損益は含まない。そのため、企業全体の収益力を評価したり、持続可能性を判断したりするときに用いられる。
さらに、経常利益が安定して成長していれば、事業基盤が堅固であることを示す。これにより、新規事業や設備投資の原資として活用できる余力を数字上で把握できるだろう。
■限界利益と当期純利益
当期純利益とは、「会社が1年間で最終的に手元に残った利益」を指す。簡単にいうと、「全部の収入から全部の支出と税金を引いた利益」であり、株主への配当や将来の投資に充てられる。
経常利益は通常の事業活動での儲けであり、当期純利益はさらに特別利益(工場や土地を売って得た利益など)や特別損失(災害での被害や不要になった設備の廃棄など)、法人税などを加味する。
| 計算式 | 特徴 | 使用する場面 | |
| 限界利益 | 売上高-変動費 | 商品を1つ売ったときに増える利益 | ・商品の収益性評価・価格戦略の決定 |
| 当期純利益 | 経常利益+特別利益-特別損失-法人税 | 全ての収入・支出と税金を考慮した最終的な利益 | 会社の1年間の最終的な成績を調査する |
当期純利益がプラスなら会社は健全と判断でき、一方でマイナス(赤字)が続くと会社の存続が危うくなる。そのため、当期純利益は企業の最終的な成績表として、とても重要な数字といえるだろう。















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE