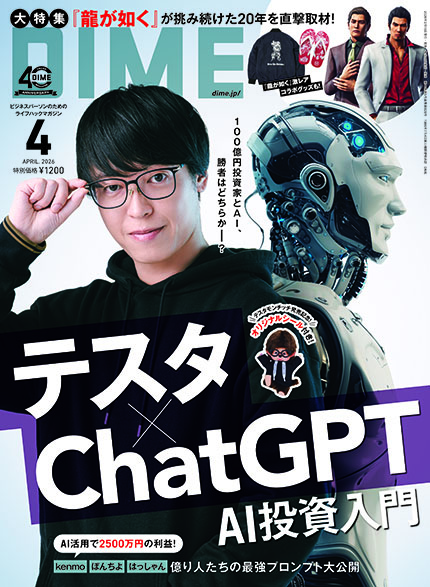本記事では「位相」について、基礎知識を解説した上で、各分野における意味を解説していく。
目次
「位相」という言葉を聞いたことはあるだろうか。あまり馴染みのない方も多いだろう。あるいは「聞いたことはあるが、意味はよくわかっていない」という方も少なくないだろう。位相は、日常的な会話ではほとんど登場することはないが、数学や物理学、言語学、歴史学といった学問領域に加え、ビジネスシーンで登場することがある。本記事では、この位相について、基礎知識を解説した上で、各分野における意味を解説していく。
位相(いそう)とは

■位相の意味と語源
見ての通り、位相という言葉は「位」と「相」から成り立っている。「位」は位置や配置などを示す漢字で、「相」は状態や姿などを示す漢字だ。この位相は、「対象が、どのような位置・配置であるか、どのような状態・姿であるか」を示す概念である。
あまりに抽象的であるため、掴みにくいだろうが、これから説明する各分野における意味を知ることで、きっとイメージが湧くようになるだろう。
位相という言葉の由来は中国語や古典漢語で、日本では明治時代あたりから使われ始めた。当初は数学や物理学などの分野で使われていたが、のちに言語学や歴史学、ビジネスシーンなど、さまざまな分野で使われるようになってきた。
■数学における位相
ではここから各分野における位相について解説していく。まずは数学における位相からだ。
数学において位相は、図形や物体の構造的性質を捉える際の枠組みの一つである。主に「連続変形しても変わらない性質」に着目する。
”連続変形”とは、数学用語で、対象を切ったり貼り合わせたりはせずに、引っ張ったり歪めたりして連続的に別の形に変えていく操作のことだ。
もちろん、この説明では理解しにくいであろう。数学における位相は難解な部分もあるため、かみ砕いて解説していく。
イメージしてみて欲しい。目の前に一枚のゴムシートがある。非常に柔らかいゴムシートである。その上に丸や線などの図形を描いたとしよう。このゴムシートを引っ張ったり歪めたりした場合、その描いた図形の性質はどうなるであろう。切ったり貼り合わせたりしないのであれば、本質的には同じ構造的性質を保っていると考えられる。
このように、形そのものよりも、連続変形によって変わらない構造的性質に着目するのが、数学における位相である。
ここで、理解が深まるよう、2つの例を挙げる。
例①:地図と鉄道路線図の位相的関係
地図と鉄道路線図は、いずれも場所に関する情報を示しているが、フォーカスする情報の種類は異なる。地図は地形や建物の正確な位置を示すのに対し、鉄道路線図は駅同士のつながりを重視しており、位置や距離、角度などは実際とは異なる。それでも、鉄道路線図を使用して目的地にたどり着けるのは、駅同士のつながりという構造が正しく保たれているからだ。つまり、地図と鉄道路線図は、連続変形によって互いに変形可能であり、位相的には同じものと見なせるというわけだ。
例②:Tシャツと靴下の位相的関係
Tシャツと靴下はどちらも布でできた衣類である。Tシャツにも靴下にも穴が空いてるが、靴下は穴が1つであるのに対して、Tシャツには首、両腕、胴体と、合計4つの穴がある。この穴の数は連続変形させても変わらない。どんなに引っ張ったり歪めたりしても、切ったり貼り合わせたりしない限り、Tシャツを靴下に変えることはできない。もちろん、靴下をTシャツに変えることもできない。つまり、Tシャツと靴下は、位相的には別物というわけだ。
■物理学における位相
物理学において位相とは、波が周期内のどの位置にいるかを示す概念である。
そもそも波とは何か。波とは、エネルギーが空間や物質中を伝わる現象のことで、代表的なものに音波や光波、電波、水面の波などがある。
ここで、波の形をイメージしてみてほしい。
- ある規則的なパターンを持って空間や物質中を進んでいく
- 山の頂上(時計でいえば0時)にいるときもあれば、谷の底(時計でいえば6時)にいるときもある
- 周期性があり、一周する時間が決まっている
誰もが、このようなイメージを描けるであろう。
このような波において、現在どの位置にいるか(山の頂上か、谷の底かなど)を示すのが、位相である。
■言語学における位相
言語学において位相は、話し手の属性(性別、年齢、職業など)や状況(場面、雰囲気、フォーマル・インフォーマルの度合いなど)によって使い分けられる言葉のスタイルや表現のことを指す。
[言語学における位相の使い方の例]
- 男性は「行こう」といい、女性は「行くわよ」という(性別による位相)
- 関東人は「本当に」といい、関西人は「ほんまに」という(地域による位相)
- 同じ人物でも、同僚といるときは自分を「私」と呼び、友達といるときは自分を「俺」と呼ぶ(場面による位相)
■歴史学における位相
歴史において位相は、厳密な学術用語ではないが、ある時代における中心的な価値観や社会的な雰囲気のことを指す言葉として使用されることがある。
[歴史学における位相の使い方の例]
- 戦国時代(15世紀後半〜16世紀末):各地の大名が領土を巡って争いをする「武力が中心」の位相
- 明治時代(19世紀後半から20世紀初頭):西洋の価値観や文化、技術を取り入れていた「西洋化」「文明開化」の位相
- 高度経済成長期(1950年代後半〜1970年代前半):物質的豊かさや生活水準の向上を追求した「経済成長」の位相
ビジネスにおける位相(いそう)とは

■ビジネスにおける位相
近年、ビジネスシーンにおいても、位相という言葉が使われるようになってきた。実際、職場で上司や同僚が使っているのを聞いたことのある方もいるだろう。
ビジネスシーンにおける位相は、「段階」「局面」「区切り」などを意味する言葉「フェーズ」に近い。位相とフェーズ、どちらも企画やプロジェクトの状況がどの段階にあるかを示す際に使われる。
しかし、位相とフェーズは、厳密には少しニュアンスが異なる。フェーズは、企画やプロジェクトの進行度や成長ステージを示すことに重点があるが、位相はそれに加えて、関係者間の認識や考え方、方向性、足並み、温度感といった要素が含まれることもある。
■ビジネスシーンでの使用例
では、実際の使用例を見ていこう。
- 「新製品Aは、まだコンセプト検証の位相にあるため、マーケティング施策の策定については時期尚早である」
- 「新規事業の立ち上げについてだが、今はまだリサーチの位相であるため、投資家との交渉は控えている」
- 「本企画をぜひとも実施したいが、各部署の理解度や温度感がまるでちぐはぐだ。できれば、社内全体の位相をそろえてから実施したい」
- 「かつては、マーケティング部門と開発部門で、サービスAに対する戦略の位相が食い違っていたが、ここ最近になってようやく位相があってきた」
まとめ
位相という言葉、最初はとっつきにくかったのではないだろうか。確かに、位相は難解で専門的な響きもある。しかし、記事を読み進める中で、実はこの言葉が、私たちの日常にある身近な物事や現象にも関係していると、気づいたのではないだろうか。
位相は、「今、どこにいるか」「何とどう関係しているか」「どんな流れの中にあるか」「どれだけ変化したか」といった、目には見えにくいものを捉える際や説明する際に便利な言葉である。今後、位相という言葉を見かけたら、どういう文脈・意味で使われているのか、意識してみたらどうだろうか。きっと、理解が深まるであろう。
文/松下一輝(まつしたいっき)
千葉大学大学院修了後、大手システムインテグレータに入社。通信キャリアを担当する部署にて、業務システムやWebアプリケーションの設計・開発に携わる。次第にプレゼン能力が評価されるようになり、製品説明や事業戦略紹介などのプレゼンも任されるように。やがて「伝える」ことへの関心が高まり、フリーのライター/ジャーナリストに転身。現在、ITやサイエンス、ビジネス、言語などの分野を中心に記事を執筆している。















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE