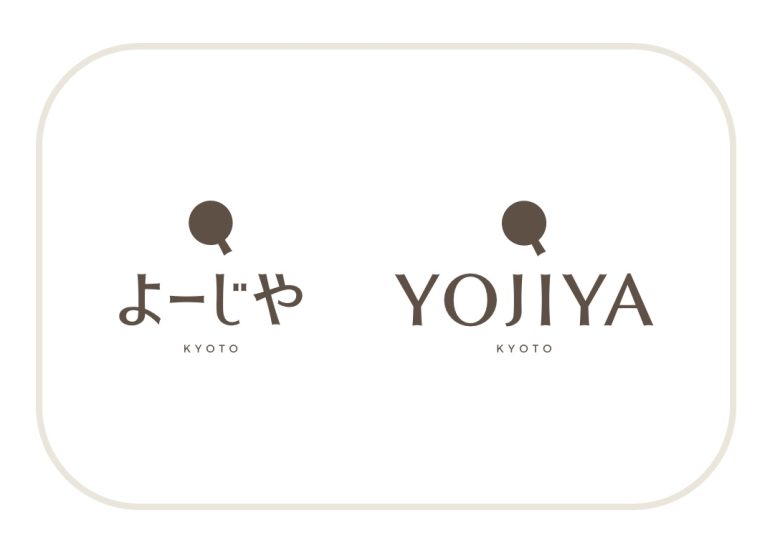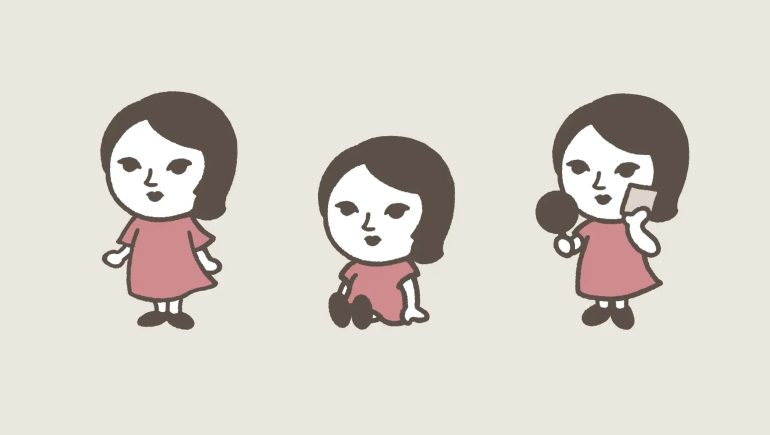彼女と初めて出会ったのはたしか京都への修学旅行の時だった。同級生の女子たちが彼女を囲んで大層盛り上がっていたのを覚えている。
年齢性別問わず、幅広い世代に知られる「よーじや」のあぶらとり紙。そのパッケージを彩るのは「手鏡に映る京美人」のイラストだ。
ちなみにこの京美人、昔から何度も見かけてきたが、誕生したのは1965年だという。
今からちょうど60年前に誕生し、その後ロゴマークに採用された。
以来、あぶらとり紙といえば京美人のイラストが瞬時に頭に浮かぶほど、「よーじや」を象徴するデザインとして広く親しまれてきたわけだが…今年3月、「よーじや」はブランドロゴを変更した。
京美人はその姿を消し、「よーじや」という文字とシンプルな手鏡イラストだけのデザインになった。下には小さく「KYOTO」の文字が添えられている。
まさか、ここまで変わってしまうとは。
それよりも、京都を代表するイラストだったはずのあの女性が“卒業”してしまうとは信じられなかった。
「よーじや」の顔とも言えるロゴの刷新。定着したロゴを捨てるタイミングはなぜ今だったのか?そのメリットとはなんなのか?
今回、企業ロゴから見える経営戦略を探るべく、よーじやグループ広報室の東さんに話を聞いた。
――ブランドロゴ変更の理由を教えてください
「弊社は2020年頃から観光業のみに依存しない経営として日常的に愛されるブランドを目指して取り組んできました。ですが、元々あった京都のお土産屋さんのイメージからなかなか脱却しきれなかったことが大きなきっかけとなります」
――脱却しきれなかったとは?
「いわば、これまでの「おみやげの店」というイメージから、弊社が本当に目指している『おなじみの店』への転換が難しいと感じたということです」
「おみやげの店」から「おなじみの店」へ。
そのために下した決断には、長い歴史を築いてきた老舗としての誇りがあった。
「そもそも弊社は1904年に「國枝商店」として創業し、当時は舞台化粧道具や現在の屋号の由来となる楊枝(歯ブラシ)の販売から始まりました。その後、バッグや化粧品、日用品など取扱い商品を広げ、地元の人にとっての『おなじみの店』として商売をしておりました」
「大きく変わったのが1990年代。とあるドラマで「よーじや」のあぶらとり紙を使っているシーンが放送されたことを機に“あぶらとり紙ブーム”が起こり、国内外問わず多くのお客さまに『あぶらとり紙のよーじや』として知られ、ロゴマークも親しまれてきたわけですが、、、」
「京都みやげのあぶらとり紙屋さんを想起されるロゴマークを使用し続けることは、コーポレート、ブランドともに多くの方々に認識していただけるという強みがある一方、「おみやげの店」ではなく、創業時からの誇りでもあった『おなじみの店』への回帰が難しいと判断し、ロゴマークの変更を決めた次第です」
知られざる老舗の思い。だからこそ、定着を捨てた。「なじみ」のブランドとして定着させるために。60年目の大改革だ。
新たなロゴは極めてシンプル。企業グループのスローガンも「みんなが喜ぶ京都にする」に変更した。60年目のリブランディングに込めた思いとは?
「よーじやがこれまで使用してきた『手鏡に映る女性の像』は、非常に印象的でよーじやの認知度に大きく貢献してきたものですが、今回ブランドイメージを刷新するためにその顔を外し、シルエット化しました。王道感と現代的な雰囲気を兼ね備えるデザインで、よーじやの歴史を大切にしながら、新たな挑戦に取り組む姿勢を表現しています」
「また、シルエットとして抽象化することで、お土産屋の人気商品というよりも品質の良さで商品を選んで欲しいと思いも込められております」
よーじやの思いは新ロゴにたしかに息づいている。
しかし、なぜその発表が60年目となる今年だったのか?そして、年明け早々3月のタイミングだったのか?
「3月というタイミングには大きな意味はなく、現代表就任後に始めた「脱・観光依存」を掲げた経営が4年ほど経過したあたりで、固定化されたイメージをより踏み込んで変えていきたいと考えました。そこからしっかりと議論を重ね、みなさまに発表できるタイミングが今年3月だった、という経緯です」
見慣れた当たり前を変えることは大きな挑戦でもあり、相当な勇気も必要なはず。
ロゴを変えることのメリット、デメリットについてはどう考えているのか?
「メリットについては、“あぶらとり紙のよーじや”というブランドイメージを刷新できる。そして、「おみやげの店」から「おなじみの店」への変化を目指し、京都に貢献したいという本気の想いをみなさまに伝えることができることだと思っています」
「一方デメリットですが、旧ロゴマークに愛着を持つ人からの反発が予想され、おみやげとしての需要に影響をおよぼす懸念があることでしょうか。しかし、現在のロゴマークに愛着を持っている人の多くは日常的によーじやブランドを使っている人ではなく、京都観光のおみやげとしてご購入される方であると考えられます。そのため、あぶらとり紙にはこれまでのマークを残すことで、そこのニーズには一定数応えられると思っております」
それだけではない。ロゴの刷新にはこんな理由も。
「上記の懸念以上に“あぶらとり紙のよーじや”以外のブランドイメージをしっかりと築いていくことが、新規顧客獲得など長い目で見て会社として重要だと考えました」
「20年前をピークに売上が減少し続けており、お土産としての需要も低下している中、ロゴマークを残してほしいとの声と需要が連動していないことは事実としてあるため、新たなイメージを持っていただくことの必要性を強く感じていることも理由としてあります」
時代に合わせた変化で「みんなが喜ぶ京都にする」
新ロゴの誕生に加えて、コーポレートキャラクターとしてお目見えしたのが、「よじこ」さんだ。
実は手鏡に映る京美人も、昨年創業120周年を迎えたことを機に「よじこ」と正式に命名され、社内外問わず多くの方に愛されていた。
そんな彼女が親しみやすいキャラクターとなり、世に羽ばたいたのだ。
「ここまでよーじやを育ててくれた「よじこ」を無くしてしまうのではなく、新しい形で活用していきたいという思いがありました。ロゴマークよりもキャラクターとして存在する方がより自由度も生まれ、よーじやという会社に愛着を持ってもらうための役割をいろんな場面で担っていけるのではないかと考えています」
「これまでの「手鏡よじこ」は、あぶらとり紙を始め、商品パッケージや店頭サインとして引き続き使用してまいります。そして新しい「よじこ」は今後、よーじやグループが目指す『みんなが喜ぶ京都にする』ために、親しみやすく身近な存在になって欲しいと願っております」
大々的なブランドイメージ刷新は、そのインパクトとともに新たな事業展開や新商品の誕生も期待させる。これから「よーじや」が仕掛けていく秘策も聞きたいところ。
「あぶらとり紙などニーズのある商品は残しながら、スキンケアアイテムを取り扱う「よーじや」、飲食事業の「よーじやカフェ」など別々の業態であったものを、これからは京都発のライフスタイルブランド「よーじや」として1つのブランドに集約し、展開していきます」
「それとまだお伝えできる段階ではございませんが、今回発表した「みんなが喜ぶ京都にする」というスローガンをもとに京都の魅力を発信し、京都経済の活性化に繋がる新事業を検討しております。2026年以降に発表できるよう進めております」
100年以上も愛されてきた老舗企業が見せた新たなチャレンジ。そこには計り知れないプレッシャーも付きまとう。
今後も成長していくため、「よーじや」にとって必要なことはなんなのか?
「時代に合わせた変化(チャレンジ)をすることが必要だと思います。洋物が珍しかった時代に他社に先駆け輸入品を販売するなど、よーじやは創業当初よりその時代に合ったチャレンジをする会社でした」
「時代が変わればチャレンジする内容が変わるのは当然で、京都における社会課題に合ったチャレンジをおこなっていきたいと考えています。また、企業としては育ててもらった京都に貢献し、暮らす人も、創る人も、働く人も、訪れる人も「みんなが喜ぶ京都にする」ことを目指したいと思っています」
取材協力
よーじやグループ
よーじや公式X @yojiya1904
文/太田ポーシャ















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE