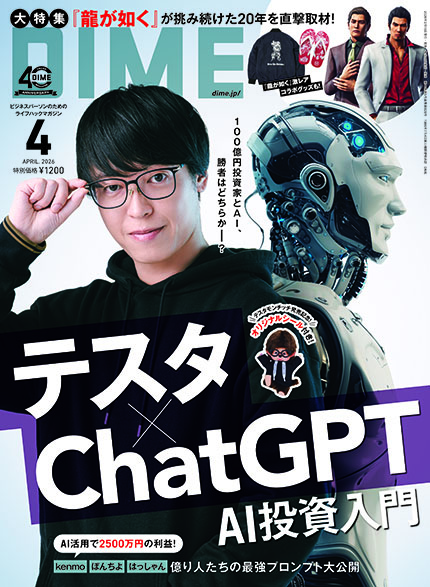営業利益とは、事業で得た利益を表す言葉のひとつ。この記事では、営業利益の意味や、計算方法、経常利益など似た言葉との違いをわかりやすく解説する。
目次
営業利益とは、損益計算書に記載される事業で得た利益のひとつ。事業に関わっていればなんとなく耳にする機会がある人もいるだろう。しかし、営業利益には何の費用が含まれているのか、いまいち理解していない人も多いのではないだろうか。
本記事では、営業利益とは何を表すのか、そして経常利益や粗利益(売上総利益)など似た言葉との違いは何なのかを詳しく解説する。各利益の計算方法も紹介しているので、気になる人はぜひ参考にしよう。
営業利益の概要|似た言葉との違いも紹介
事業の利益を表す言葉には、いくつかの種類が存在する。ここでは「営業利益」の概要と共に、「粗利益」「経常利益」「純利益」との違いもあわせて解説しよう。
■営業利益の意味
営業利益とは、法人が本業で得た利益のこと。法人が本業で得たすべての儲けの金額(売上高)から、売上原価と販売費及び一般管理費を差し引くことで算出できる。
売上原価とは、商品やサービスを販売するために直接かかった費用のことで、例えば仕入れた原材料の原価や、製造ラインでの人件費、工場内の電気代などの例がわかりやすいだろう。
販売費及び一般管理費には、売上原価に含まれない人件費や、コピー用紙などの消耗品費、事務所の家賃や光熱費などが含まれる。
■粗利益との違い
粗利益は「売上総利益」とも呼ばれる利益のひとつ。売上高から売上原価のみを差し引いた金額となる。
ここまでの解説だけでもわかる通り、粗利益と営業利益の違いは、販売費及び一般管理費を差し引くか否かということ。
■経常利益との違い
経常利益とは、営業利益に「営業外収益」を加えた上で、「営業外費用」を差し引いた利益のこと。
営業外収益とは、本業以外での儲けを指し、例えば受取利息や配当金、補助金や助成金、法人税の還付などが挙げられる。一方で、営業外費用は本業以外の活動によって定期的に発生する費用のことで、支払利息や振込手数料、社債利息などがそれにあたる。
経常利益と営業利益の違いは、本業での利益に焦点を当てているのか(営業利益)、財務など本業以外の利益も含めて計算するのか(経常利益)ということだ。
経常利益を見ることにより、本業を含めた企業全体の利益が確認できる。
■純利益との違い
純利益とは、法人のその期の売上高から営業利益などの費用を全て差し引き、最終的に残った利益を指す。「当期純利益」や「最終利益」などと呼ばれることもある。
当期純利益を求めるには、まず経常利益に「特別利益」を加えた上で、「特別損益」を差し引いた「税引前当期純利益」の算出が必要だ。そして、税引前当期純利益から法人税等の税金を全て差し引いたものが純利益となる。
特別利益とは、業務内容に関係なく臨時的に発生した利益のこと。例えば保険金の支払いを受けた時や、固定資産を売却した時などに得たお金が挙げられる。また、特別損失とは、業務とは関係なく臨時的に発生した損失を指す。例えば、盗難や、災害、固定資産を売却した時などに発生するような損失額だ。
営業利益と純利益の違いは一目瞭然だが、差し引かれる項目が大きくことなることが挙げられる。
営業利益やその他利益の計算方法
ここまでは主に言葉を使って解説したが、計算式を使ってもう少し簡単に営業利益を求めてみる。営業利益以外の利益の計算方法も紹介するので、損益計算書を手元に用意したうえで繰り返し計算をすると、より理解が深まるだろう。
■営業利益の計算方法
営業利益の計算方法は次の通り。
営業利益=売上総利益―販売費及び一般管理費
(売上総利益=売上高―売上原価)
例えば売上高が7,000万円、販売費及び一般管理費が3,000万円だった場合を計算してみよう。
7,000万円―3,000万円=4,000万円
営業利益は4,000万円となる。
なお、「販売費及び一般管理費」は「販売費」や「販管費」などと呼ばれることもあるので覚えておこう。
■粗利益の計算方法
粗利益(売上総利益)の計算方法は次の通り。
粗利益(売上総利益)=売上高―売上原価
売上高が1億円、売上原価が3,500万円だった場合の計算は以下の通りだ。
1億円―3,500万円=6,500万円
粗利益は6,500万円となる。
■経常利益の計算方法
経常利益の計算方法は次の通り。
経常利益=(営業利益+営業外収益)―営業外費用
営業利益が4,000万円、営業外収益が1,000万円、営業外費用が3,000万円だった場合の例を計算してみよう。
(4,000万円+1,000万円)―3,000万円=2,000万円
経常利益は2,000万円となる計算だ。
■純利益の計算方法
純利益(当期純利益)の計算方法は次の通り。
当期純利益=税引前当期純利益―法人税等
(税引前当期純利益=経常利益+(特別利益―特別損失))
税引前当期純利益が5,000万円、法人税等が1,000万円だった場合の計算例を見てみよう。
5,000万円―1,000万円=4,000万円
当期純利益は4,000万円となる。
なお、「法人税等」の項目には、法人住民税や法人事業税などが含まれる。
営業利益に関するQ&A

営業利益について、まだまだわからないことがある人も多いだろう。ここでは営業利益に関してよくある疑問と回答をいくつかまとめたので、気になる項目があれば参考にしてほしい。
■営業利益を上げるには?
営業利益を上げる方法は、大きく分けて以下の3パターンがある。
・売上を増やす
→客単価を上げる、客数を増やすなど
・原価を下げる
→仕入れ先との交渉や仕入れ先の見直し、製造工程の見直しなど
・販管費(販売費及び一般管理費)を下げる
→広告費や人件費の削減など
一概に「人件費を削れば良い」「客単価を上げれば良い」などというわけではない。事業ごとの状況を分析し、最適なバランスで各手段を取り入れることが重要だ。
■営業利益はどこで見られる?
営業利益は「損益計算書」と呼ばれる書類に記載される。損益計算書は企業によって記載される項目の順番が異なることがあるが、「販売費及び一般管理費」の項目周辺で見つけられることが多い。
■個人事業主の営業利益はどこでわかる?
個人事業主においては、「所得金額」が法人でいうところの営業利益にあたる。一般的には、「確定申告書B」第一表の「所得金額等」の合計欄で把握が可能だ。所得金額は、売上金額から必要経費を差し引くことで算出できる。
■飲食店や製造業の営業利益とは?
営業利益の算出には、「販管費(販売費及び一般管理費)」と「売上原価」を把握する必要があるが、販管費と売上原価の違いを理解すると、各業種の営業利益が求めやすくなる。
販管費:商品や製品・サービスを販売するために間接的にかかる費用のこと
売上原価:商品や製品・サービスを生み出すために直接的にかかる費用のこと
例えば、飲食店における販管費には、人件費のほか、リース料、通信費、宣伝広告費などがある。一方で、製造業における販管費は、販売活動にかかる人件費や、事務所の賃料、経理担当者への給与などだ。
飲食店における売上原価としては、食材や調味料の仕入れ費用、調理部門の人件費、水道光熱費などがそれにあたる。製造業では、製造ラインの人件費や、製造工場の光熱費などが売上原価といえる。
これらの項目を理解した上で、営業利益を算出してみよう。なお、営業利益の計算方法自体は、どの業種でも変わらない。
■営業利益を英語で表すには?
一般的に、営業利益は英語で「Operating profit」と表記する。例文は以下の通り。
Operating profit increased 13% in the quarter.
(今四半期の営業利益は13%増加しました。)
※情報は万全を期していますが、正確性を保証するものではありません。
文/編集部















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE