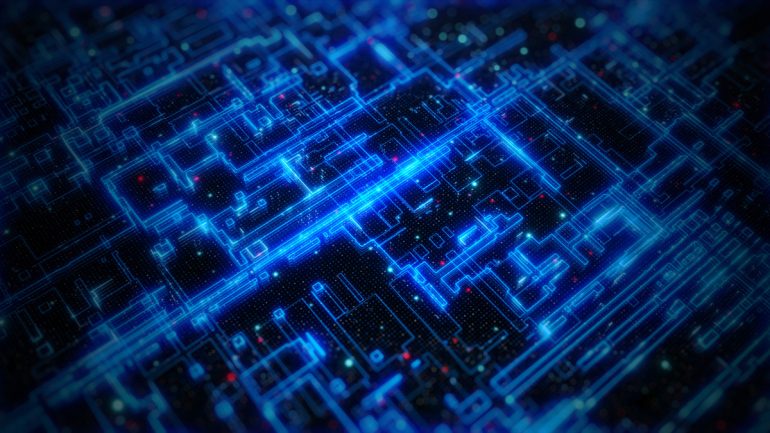企業が今から備えるには
1. 情報収集と啓蒙
経営者や管理職から技術担当者まで、量子コンピュータの基本的な仕組みや潜在的なインパクトを理解する機会を設けることが重要です。
2. ユースケースの探索
自社の業務課題のうち、組合せ最適化やシミュレーションがカギとなる領域がないかをチェックします。物流管理、金融リスク、医薬品開発などは特に候補となりやすいでしょう。
3. プロトタイプ・PoCの実施
クラウド上で量子計算を試せるサービス(IBM QuantumやAWSのAmazon Braketなど)を活用して、小規模でも実証実験に取り組むことが有効です。早めに社内でノウハウを蓄積しておくと、将来の本格導入時にアドバンテージを得られます。
4. パートナーシップの構築
単独の企業で量子技術を深く研究し、実用化まで進めるのは容易ではありません。大学や研究機関、スタートアップ企業と連携し、最新情報や人材を共有する仕組みづくりが大切です。
5. セキュリティの再検討
量子コンピュータによる暗号解読リスクを念頭に、将来的なシステムアップデート計画(ポスト量子暗号への移行など)を視野に入れておく必要があります。
これからの展望
量子コンピュータはまだ発展途上ですが、研究開発と投資が加速している今後5~10年は、技術が大きく飛躍する「勝負の時期」になると考えられます。特定の課題では古典コンピュータを凌ぐ性能を示す例が増えれば、企業の競争力や産業界の勢力図も変わるでしょう。
一方で、「全ての問題を一瞬で解ける万能マシン」にはならないかもしれません。それでも、従来の計算技術では到底手が届かなかった複雑な問題を解く手段として、量子コンピュータが不可欠な存在になる可能性は十分にあります。現時点ではまだ実験や研究の側面が強いものの、将来的にはクラウドサービスを通じて多くの人が手軽に利用する場面が出てくるでしょう。
おわりに
量子コンピュータは、「0」と「1」が同時に存在できる量子ビットの力を使うことで、非常に複雑な問題を高速に解く可能性を秘めています。2023年には量子誤り訂正技術を中心に大きな進歩が見られ、IBMが1,000ビット級の量子プロセッサを発表するなど、実用化に向けた足取りが急速に進んでいる段階です。
従来の実験中心だった科学技術を大きく変え、新素材や新薬の開発、物流・金融・AIなどの分野で革新的な成果を生み出すと期待される量子コンピュータ。実用化にはまだ課題が残りますが、近い将来、ビジネスのあり方を根本から変える大きな波になるかもしれません。
ビジネスパーソンとしては、過度な期待だけでなく冷静な視点を持ちつつ、しかし決して軽視しないことが重要です。次の「産業革命」とも評される量子技術がどのように発展していくのか、今から正しく学び、将来に備えることが、競争力の源泉になるでしょう。
【参考資料】
・https://www.ibm.com/jp-ja/quantum
・https://www.nttdata.com/jp/ja/services/quantum/
・量子コンピュータの頭の中(技術評論社)
・量子コンピュータが変える未来(オーム社)
文/鈴木林太郎















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE