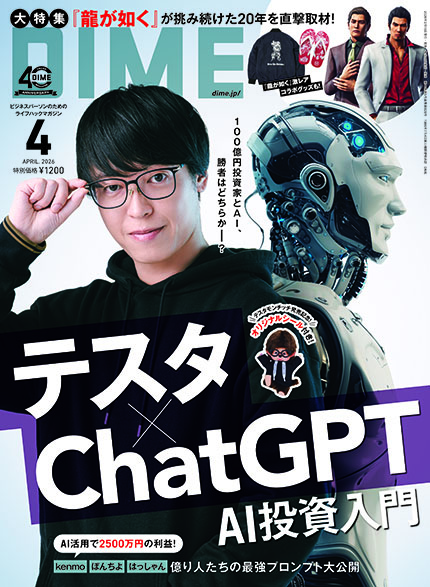臍帯(へその緒)による細胞治療で難病治療の地域格差にアプローチ
難病治療の地域格差問題に貢献しうる、もう一つのスタートアップがある。ヒューマンライフコード株式会社だ。
同社は臍帯(へその緒)に含まれる間葉系細胞を活用した製薬事業を展開する。
これまで、東京科学大学との共同研究を通して臍帯由来間葉系細胞(UC-MSC)の治療効果を検討した末に、新たな治療の可能性を見出した。
そこで2024年7月より同大学に「生涯免疫医療実装講座」を設置し、UC-MSCを用いた細胞治療の研究から開発までシームレスな「難治性自己免疫疾患」の早期診断と最適治療の医療実装を目指している。
同社の代表取締役社長 原田雅充氏は、米国の外資系製薬企業に在籍中、細胞治療で治癒に至った小児患者との出会いをきっかけに、「残りの職業人生の全てをかけてでも、この細胞治療を普及させたい」との強い衝動にかられ、2017年4月に同社を創業した。
難病治療の地域格差問題へ焦点を当てた背景とは? 原田氏は次のように話す。
「難治性自己免疫疾患は、早期診断と適切な治療がその後の患者さんのQOLに大きく影響します。しかしながら、地域によっては専門医へのアクセスが困難な現状があります。
そこで講座の設置を行い、共同研究より得た知見を難治性自己免疫疾患の患者さんやご家族の皆様に届けることを目的とし、同大学を通じて利用可能となることが期待される自己免疫疾患レジストリや診療データ、バイオバンクを活用して各疾患の特徴となるバイオマーカーを探索します」(原田氏)
講座の設置を通じて、UC-MSCによる難病治療がより前に進むことで、地域医療格差にどのように貢献するか。
「当社は、増える、備蓄できる、必要な時に必要とする患者さんに届けられるUC-MSCの作用機序を究明し、難治性自己免疫疾患の病態進行に関わるバイオマーカーとの接点を解明することで、早期診断、早期治療の実現を目指しています。
このような先進技術の普及には、産学連携、医療従事者同志の連携、情報産業や製薬メーカーといった事業者同士の積極的で柔軟な連携が、地域医療格差のない難病治療の普及につながると期待しています。また、研究成果を適時開示し共有を進めることで、全国で標準的な診断と治療が行える体制づくりに協力してまいります」(原田氏)
地域格差を埋めるデジタルとオンラインは、単なる技術ではない。その根底には、人と人、企業と企業、企業と大学などを柔軟につなぐ役割もあることがわかる。今後も、医療とデジタル双方の先端技術の発展に期待したい。
取材・文/石原亜香利















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE