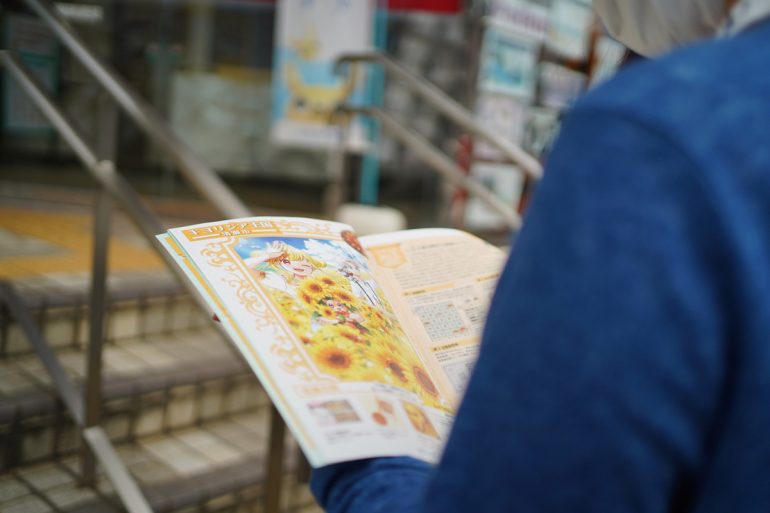制限時間内に、指定の範囲の中を実際に歩き回り、暗号を解いたり、宝を探したりする謎解きゲーム。じわじわと人気と知名度を上げ、今では定番化している屋内外ゲームだ。
謎を解いて服を買う!?話題の謎解きアパレル「トキキル」って何?
今や身近なエンタメとなっている謎解きイベント。リアル脱出ゲームや宝探し、物語仕立ての推理ゲームなどさまざまな趣向が凝らされ、知的好奇心旺盛な大人たちの人気を集め...
大掛かりなイベントとなれば、謎の数も増え、企画・運営する側も手の掛かる作業となりそうだ。今回は、謎解きゲームの裏側を探ってみた。
謎解きゲームの「謎」はどのように作られる?
今回、話を聞いたのは、「リアル宝探し」や謎解きイベントを手がける、謎解き会社の株式会社タカラッシュ。2001年の創業以来、20年以上にもわたって宝探し事業を続けている。「リアル宝探し」とは、その名の通り、宝探しをリアルの場で行う体験型コンテンツだ。「困難に立ち向かい、自らの手で宝を見つけ出す」という非日常的な感動が味わえるのがコンセプトだ。
同社は40万人を超える会員を保有しており、これまでに企業や地域、施設とのコラボイベントなども行ってきた。
その企画や謎は通常、どのように考案されているのか?「タカラッシュ!」ディレクターの東 内記氏は次のように回答する。
「タカラッシュ!のメンバー1人1人が宝探しや謎解きの専門家として、日々あらゆるイベントの制作を請け負っており、どんな企画でもテーマからストーリー、謎、宝物の見た目に至るまで、複数人でディスカッションをしながら決めていきます。
創業から約25年の歴史の中、多種多様なイベント制作の実績を作ってまいりましたので、宝探しを作る上でのある程度の“枠組み”はありますが、あくまで企画ごとに開催地域の特色やクライアントの要望を考慮し、『この場所でどんなテーマで宝探しをしたら盛り上がるか』『どんなストーリーや目標を設定したら没入してもらえるか』を、いい大人たちが童心に返りながら真剣に話し合っています」
特定の枠組みに当てはめるというよりは、一つ一つのイベントに合った企画に創り上げているようだ。
解きにくい謎を作るコツは?
ところで、謎解きゲームのメインとなるのは、やはり「解くのがむずかしい謎」である。簡単に解けてしまったら謎解きにならない。作るコツとは?
「基本的に、参加者が“ちょっと頑張ったら解けるレベル”の謎を作ることを意識しています。むずかしすぎると途中であきらめて帰ってしまうかもしれないですし、簡単すぎると達成感を感じてもらえません。
そのため、最初の時点で大切なのは、メインターゲットの設定。次にそのターゲットに合った難易度設定を行います。我々の経験則で仮設定をした後、社内外の第三者にテストとして謎を解いてもらっては修正を繰り返し、最も良いレベルに調整していきます」
「ちょっと頑張ったら解けるレベル」に調整してくれているからこそ、謎解きのワクワク感が生まれるようだ。
「謎作りは正解のない作業であるため、経験則と検証のバランスをとりながら作っていくことが大事だと考えています。
とはいえターゲットの中でも解ける具合は人それぞれなので、保険としてヒントを用意したり、初級・中級・上級など複数のレベルの謎を作ったりなどして、より幅広い参加者に満足いただく工夫をしています」
謎解きゲームを考えるときに外せないポイント
続いて、謎解きイベントを企画したり、謎そのものの考案するときに気をつけている点やこだわりについても聞いてみた。
「謎解きがエンタメとして定着して久しく、世にたくさんの謎解きコンテンツがあふれる今、まったく新しく誰も体験したことがない謎解きを生み出すのは、至難の業になってきつつあります。そんな中、参加者に目新しさと『そのイベントならでは感』を感じてもらう工夫として、開催地特有の素材をできる限り活かすということにこだわっています。
まったく同じ立地、地名、景色、文化、歴史などを持つ場所は世界に2つとないはずなので、ただ暗号を解けば、目指すべき場所が答えとして導かれる『点的な謎』ではなく、現地のあらゆる情報と謎を見比べながら、街を歩いて少しずつ目指すべき場所に導く『線的な謎』を意識しています。
そうすることで謎解き以外にも、その地域についてたくさんの発見を生み、参加者がその地域のことを好きになるチャンスが生まれると考えています」
参加者にとって、ただ一心不乱に謎を解くだけでなく、地域の魅力を発見できることは、より有意義な体験価値となりそうだ。















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE