
2024年8月にIntelligent.comが行なった調査結果が、米国のビジネス媒体で話題になった。自社で採用決定に関わる966人のビジネスリーダーを対象に、Z世代の大学卒業生の採用に対する考え方を調査したもので、「75%の企業が、今年採用した新卒の一部または全員が不適格だと報告」「10社中6社が、今年採用した大学卒業生を解雇」「採用担当者の6人に1人が、Z世代の採用にためらいがあると回答」など、Z世代を雇用することへの抵抗が数字として表われた。
世代へのレッテルを増幅させる新卒採用のミスマッチ問題
その理由として、最近の新卒が「準備不足」な傾向にあり、プロフェッショナルさに欠けていることが挙げられた。コミュニケーション能力、批判的思考力、時間管理能力の不足など、スキルギャップを主な懸念事項として指摘する声も多い。この認識は「非現実的な職場への期待」を持っているというレッテルを世代に貼りつけるステレオタイプによっても、増幅されているだろう。具体的には、Z世代はテクノロジーに過度に依存し、長期的なコミットメントが苦手で、柔軟性や昇進を要求しすぎるといった考え方だ。さらに、職場での価値観にもジェネレーションギャップがある。コロナ禍のロックダウンで経験したリモート授業やリモートワークの経験、それによる対面環境への不慣れ、ワークライフバランスへの関心の高まりなどによって形成された新たな価値観に共鳴できない上の世代の雇用主も多い。このミスマッチが、労働市場の逼迫や年々応募者に高度なスキルを要求するといった競争の激化と相まって、新卒者が初任者レベルのポジションを確保しにくくなってしまう結果となっている。
上記の数字を見ると、いったん採用されたとしても、多くのZ世代の従業員はわずか数か月で解雇されるという問題も発生している。Forbesの記事では、Z世代のモチベーション不足、コミュニケーション方法のズレ、そして「全てを犠牲にしてでも仕事を優先する」メンタリティの減少が、この問題の原因とされている。いくら頑張って身を粉にして働いても仕事上で必ずしも報われるわけではないこと、不安定な雇用状況の中で頑張るモチベーションが見つかりづらいこと、堅苦しいビジネス的なコミュニケーションに意味を見出しにくいことなど、単に「怠惰な世代だから」だと言い切れない理由がたくさん考えられる。
加えて、リモートワークやハイブリッドワークのモデルが普及していることも、Z世代が職場環境や仕事に慣れない、適応できないひとつの理由としてよく挙げられる。先輩や同僚と親密な関係を築いたり、指導を受けたり、職場の規範に合わせたりすることは、リモートワークに慣れてしまった人にとっては難しい。しっかりとしたサポートシステムがなければZ世代は疎外感やプレッシャーを感じ、それがパフォーマンスの低下にもつながってしまうだろう。一方で、教育やトレーニングへの投資不足を指摘する声もある。Z世代の早期解雇は、非具体的な期待や不十分なコミュニケーションなど、世代ギャップを彷彿とさせる、職場における構造的な問題を浮き彫りにしている。また、適切なサポートがあれば成長できる若い労働者を、企業が早急に見限っているのではないかという疑問も生じさせている。
採用をためらうことと早期解雇という問題の解決策のひとつは、若い従業員が職業環境をうまく乗り切れるようメンターシップを育成することだ。しかし同時に、競争が激化する市場の中で、使い捨てのように「より良い社員をまた採用すればいい」という考え方を持つ企業も米国では増えているように感じる。雇用主と労働者、相互の信頼関係が不安定である限り、この問題は続いてしまうだろう。
文/竹田ダニエル
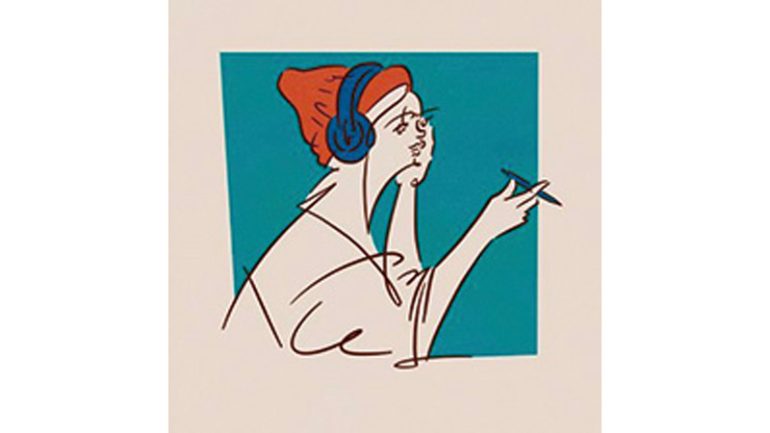 ●竹田ダニエル|1997年生まれ、カリフォルニア出身、在住。「音楽と社会」を結びつける活動を行ない、日本と海外のアーティストをつなげるエージェントとしても活躍する。2022年11月には、文芸誌『群像』での連載をまとめた初の著書『世界と私のA to Z』(講談社)を上梓。そのほか、多くのメディアで執筆している。
●竹田ダニエル|1997年生まれ、カリフォルニア出身、在住。「音楽と社会」を結びつける活動を行ない、日本と海外のアーティストをつなげるエージェントとしても活躍する。2022年11月には、文芸誌『群像』での連載をまとめた初の著書『世界と私のA to Z』(講談社)を上梓。そのほか、多くのメディアで執筆している。















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE













