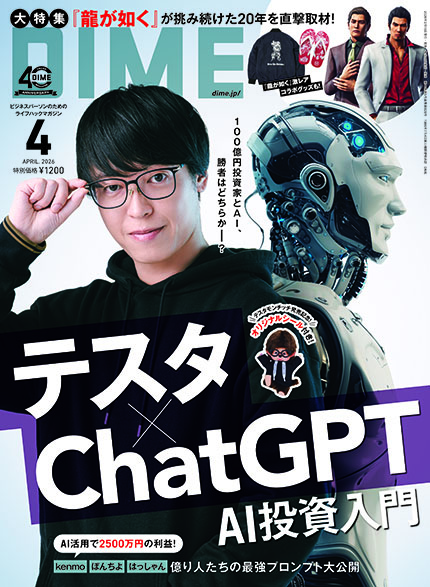向上心とは「目標に向けて努力する気持ち」で、その有無によって仕事や日常生活における影響が大きいものです。実際の向上心の高さによる違いや高め方などを疑問に思うこともあるでしょう。この記事では、言葉の意味やモチベーション・上昇志向との違い、向上心が高い人の特徴、仕事に与える影響を解説します。さらに、向上心を高める方法や就職・転職活動での自己PRのポイントもご紹介するため、あわせて確認しましょう。
目次
向上心があるかどうかは、日常生活だけではなくビジネスシーンでも影響の大きい重要なポイントです。企業では向上心が高い人がいい評価をされるなど、ポジティブな印象が強い言葉だといえるでしょう。言葉の意味を理解して、正しく使っていきましょう。
向上心とはどういう意味?基礎知識を簡単に解説

はじめに、そもそも向上心とはどういう意味を持つ言葉なのか、またモチベーションや上昇志向との違いを確認しておきましょう。
■意味は「目標に向けて努力する気持ち」
向上心とは、「高いところを目指して努力すること」「目標に向けて努力する気持ち」を意味します。また「向上」とは、「よりよい方向に向かうこと」などを意味します。
つまり向上心は、現状に満足せずにさらなる高みを目指して、自分を成長させようと意識し、努力することを指す言葉です。
「向上心が高い」とは、以下2つのポイントのどちらにもあてはまる状態を指します。
- 成長しようという意欲がある
- 実際に行動がともなっている
高みを目指すだけではなく、実際に努力もできるような人が、「向上心が高い人」です。
■向上心とモチベーションとの違い
一方、「モチベーション(motivation)」とは「動機づけ」「やる気」「意欲」などを意味します。向上心とモチベーションとの違いは、「その時々の外的要因や内的要因が影響するかどうか」です。
向上心は「目標に向かう恒常的な心」のため、外的要因や内的要因はあまり影響しません。しかし、モチベーションは外的要因や内的要因による影響が大きく、簡単に上がったり下がったりするものです。
なお、モチベーションの上下に関係しそうな外的要因や内的要因には、たとえば以下のようなものがあります。
- 外的要因の例……これを達成できたら彼女ができるかもしれない
- 内的要因の例……成長した自分になりたい
■向上心と上昇志向との違い
上昇志向とは、「現状に満足せず、社会的な地位や能力などを向上させようとする考え方・姿勢」のことです。つねに高みを目指すという点では、向上心は上昇志向や「野心家」などとも意味が近いといえそうです。
向上心と上昇志向との違いは、「その目的が社会からの評価を上げるためかどうか」だといえるでしょう。
上昇志向を使う場合は、基本的には社会からの評価を上げることを目的としている場合が多いです。一方、向上心は社会からの評価だけではなく人間性を高めるようなときにも用います。
向上心が高い人とは?4つの特徴

向上心が高い人が持つ4つの特徴は、以下のとおりです。
- 積極的で行動力がある
- 目標や夢を持っている
- コツコツと努力できる
- 素直にアドバイスを受け止められる
また、「ポジティブ思考であること」「好奇心や学びを大切にできること」なども、向上心が高い人が持つ特徴だといえます。
一方、向上心がない・低い人は、「具体的な目標や夢がない」「無気力になりやすい」「消極的になりやすい」ことなどが特徴です。
それでは、向上心が高い人が持つ4つの特徴を、さらに詳しく確認していきましょう。
■1.積極的で行動力がある
向上心が高い人は、成長のために積極的に行動へと移せます。そもそも、向上心が高いとは実際に行動がともなっている場合にあてはまる言葉です。
そのため、向上心が高い人はリスクや失敗を恐れて尻込みせず、実際に行動を起こします。自分なりの挑戦を重ねて、失敗しつつも新しい発見を得るような人で、思ったことを実行するまでのハードルが低いことも特徴です。
■2.目標や夢を持っている
向上心が高い人は、自分なりの目標や夢がある場合が多いです。その目標は、長期的なものから短期的なものまでさまざまなものがあります。
向上心が高い人は、現状に甘んじることなく、目標や夢をかなえるために行動できます。自分のやりたいことが明確で、チャレンジ意欲も旺盛であることが特徴です。また、目標を達成できたあとも、新しい目標を見つけて目的に向かって努力していけます。
■3.コツコツと努力できる
コツコツと努力を続けられることも、向上心が高い人の特徴のひとつです。
目標に向かって行動しても、すぐに成果が出るとは限りません。しかし、向上心が高い人は、すぐには達成が難しいことでも日々努力を重ねていけます。
なかなかうまくいかなくても、失敗を重ねて粘り強く地道に改善を続けていければ、目標を達成できる可能性は高まるでしょう。また、努力をし続けられたことで、長期的に見たときに周りと差がつくこともあります。
■4.素直にアドバイスを受け止められる
素直にアドバイスを受け止められることも、向上心が高い人の特徴です。基本的に素直でポジティブなことが多く、自己改善の意欲も高いため、周囲の意見を素直に聞き入れられます。誰かに批判された場合でも、周囲の言葉によって影響され過ぎず、それも糧にして前に進もうとできる傾向にあります。
また、失敗したときには自ら内省できることも特徴です。向上心が高い人は、あまり人のせいにしません。問題から逃げずに自らを振り返って分析し、次につながる行動がとれます。
向上心が職場・仕事に与える影響

向上心は、高くても低くても職場・仕事に与える影響があります。向上心が職場・仕事に与える影響は、以下のとおりです。
<向上心が高い場合の影響>
- 自己成長やスキルアップの促進になる
- 人間関係を構築しやすい
- 生産性が向上する
- 目標達成など、成果や評価につながりやすい
- スムーズに人材を育成しやすい
- 周囲の人が触発されてポジティブな影響を与える
- 職場の雰囲気を改善する
<向上心が低い場合の影響>
- 言われたことをやるだけになる
- 変化に対応できない
- 仕事の生産性が上がらない
- 新しいチャレンジがしにくい環境になる恐れがある
- 周りの従業員もやる気を失う可能性がある
向上心が高い場合と低い場合の職場・仕事に与える影響を、それぞれ確認しましょう。
■向上心の高い人が職場・仕事に与える影響
先述のとおり、向上心が高い人の特徴はなんらかの目標を持ち、達成に向けて努力し続けられることです。これによって、生産性の向上や目標達成などにも貢献します。また、積極的に新しい知識やスキルを得ようと行動するため、自己成長やスキルアップの促進につながりやすいです。
前向きな発言や行動をしやすい向上心が高い人は、周りから好印象を抱かれやすいでしょう。とくに職場の上司から信頼されやすいです。他者からの意見を素直に受け入れて改善につなげるため、チーム内でのコミュニケーションも円滑になりやすいでしょう。
上司から見ればスムーズに育成しやすい人材だといえます。積極的に努力し続ける姿勢に周囲の人が触発されたり、職場の雰囲気を改善したりと、ポジティブな影響を与えやすいでしょう。
■向上心の低い人が職場・仕事に与える影響
一方、向上心の低い人・ない人が仕事をしていると、言われたことをやるだけになります。主体的に行動できず最低限の仕事をこなすだけになりやすいため、仕事の生産性が上がりません。また、前向きになれずになるべく現状を維持しようとするため、変化に対応できないことも特徴です。
そのような様子を見ていると、周りの従業員もつられてやる気を失う可能性があります。職場内に向上心の低い人・ない人が多い場合、向上心の高い人が周りから浮いてしまったり、仕事を回され過ぎたりする可能性があるでしょう。
また、向上心の低い人・ない人が多いと、新しいチャレンジがしにくい環境になる恐れがあります。前向きな提案をしてもポジティブには受け止められず、従来通りの方法から改善しにくくなるかもしれません。
自分・周りの人の向上心を高める方法とは?

向上心を高めたい場合には、その対象が自分なのか周りなのかによって取るべき方法が異なります。また、向上心が自ら目標に向かう心とはいっても、周りの人の言動に影響を受ける場合があるものです。相手の向上心を高めたい場合でも、自分の向上心を高める方法も試してみるといいかもしれません。
なお、向上心が低くなる原因・特徴として、無気力感や劣等感、目標がないこと、物事への関心のなさなどが挙げられます。向上心を高められれば、このような状態から脱却して前向きになれる可能性があるでしょう。
■自分の向上心を高める方法
まずは自分の向上心を高める方法をご紹介します。
- 自分を客観的に分析する
- 10年後の自分を想像する
- 目指すべき目標を明確にする
- 簡単な目標で成功体験を増やす
- すぐに行動に移すよう心がける
- 自分に対して前向きな質問をしてみる
自分を客観的に分析したり、10年後の自分を想像したりすると、自分の伸び代や課題、やるべきことなどがはっきりしてきます。目指すべき目標を決めれば、具体的になにをすればいいのかが明確化するでしょう。
目標は簡単なものでも、成功体験を増やすことで自信がつけられます。また、何度も失敗や成功をしつつ学んでいける姿勢を身につければ、向上心を高められるでしょう。
■周りの人の向上心を高める方法
続いて、自分ではなく周りの人の向上心を高めるものとして、とくにビジネスシーンで考えられる方法を解説します。
- 社内の心理的安全性を確保する
- 目標や業務において、本人が選択できる機会を設ける
- 勉強会・研修をおこなう
- 定期的にフィードバックを実施する
- 相手の努力を褒めるように意識する
心理的安全性とは、「他者の反応におびえるなどせず、自然体の自分を出せる状態」のことです。心理的安全性が確保されている企業とは、従業員が安心して発言し働ける雰囲気・環境であるといえます。
向上心があるといえるような行動をすると、社内で注目を浴びることがあります。他者の反応におびえたり恥ずかしがったりすることなく、自然に受け入れてもらえるような雰囲気を作ることが大切です。















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE