
急がばまわれは、「急いでいるときこそ安全な道を選ぼう」という意味で使われている言葉です。比較的使われることの多いことわざですが、使い方に迷うこともあるでしょう。 この記事では、急がばまわれの意味や語源となった琵琶湖のこと、使い方・例文などを解説します。さらに、言い換えたいときに使える類語表現もあわせて確認しましょう。
目次
「急がばまわれ」の基礎知識を解説

急がばまわれの読み方は、「いそがばまわれ」です。また、急がば回れと漢字表記する場合もあります。たとえば、「焦っていても仕方がない。急がばまわれだよ」などと使います。
はじめに、急がばまわれの意味や語源・由来、「瀬田の唐橋」とはどのようなところか、使い方・例文などを確認しましょう。
■急いでいるときほど遠くても確実な道がいいこと
急がばまわれとは、「急いでいるときほど、遠くても確実な道を選ぶといい」という意味を持つ言葉です。早く着きたいとき、焦って危険な近道を選んでしまいがちです。
しかし、危険な近道を選べばうまくいった場合に早く到着できる可能性があるものの、そのぶん、想定通りに進めない可能性も高まるでしょう。
そのため、遠回りになってでも確実な道を選んだほうが、より目的を達成しやすいだろうというたとえです。
■急がばまわれの語源・由来
急がばまわれは、琵琶湖を渡る交通手段が由来となったことわざです。室町時代の連歌師(れんがし)である「宗長(そうちょう)」は、琵琶湖のことを以下のように詠んでいます。
「もののふの 矢橋(やばせ)の船は速けれど 急がば回れ 瀬田の長橋」
この歌は、「急がば回れ」ということわざの始まりだとされています。また、別の説では平安時代の歌人である源俊頼の歌だともいわれているようです。
この歌は、「武士(もののふ)が京都へ向かう際に、矢橋の港から出る船でいけば速い。しかし、急いでいるならば遠回りでも瀬田という場所に架かる橋を渡ったほうが安全でいい」ことを詠んでいます。
■語源となった「瀬田の唐橋」とは?
語源となった歌で詠まれた「瀬田の長橋」は、現在は「瀬田(せた)の唐橋(からはし)」と呼ばれ、今でも現役で活用されている橋です。瀬田の長橋は、琵琶湖から自然流出する唯一の河川である瀬田川に架かる橋で、日本三大名橋のひとつにあげられています。
この場所は、日本書紀にも登場する交通の要衝です。戦乱の時代には、「唐橋を制する者は天下を制す」という言葉があったほどに重要視されました。
東海道の草津宿から大津までのルートは、矢橋から出る船に乗ればほぼ一直線で移動できます。しかし、比叡山から吹き下ろす突風で船が押し戻され、最悪の場合は転覆することがあり大変危険です。
そのため、「急いでいるときはリスクを取るよりも安全で確実なルートを選んだほうがいい」といわれるようになったようです。
■急がばまわれの使い方・例文
急がばまわれの使い方を、例文で確認していきましょう。
- 焦って仕事をこなそうとしたら、あとからミスが発覚して結局手間が増えた。急がばまわれ、このようなときほど慎重にやらなければならないな。
- この道を使ったら近道にならないかな。いや、急がばまわれでいつもの確実な道を使おう。
「急がばまわれは」私生活だけではなく、ビジネスシーンでも大切になることを伝える戒めのことわざです。
仕事や勉強などで焦っている相手に伝える場合や、自分が時間短縮を狙うあまりにリスクの高いことをしようとしたときに思い出すなど、うまく活用しましょう。
急がばまわれの関連語
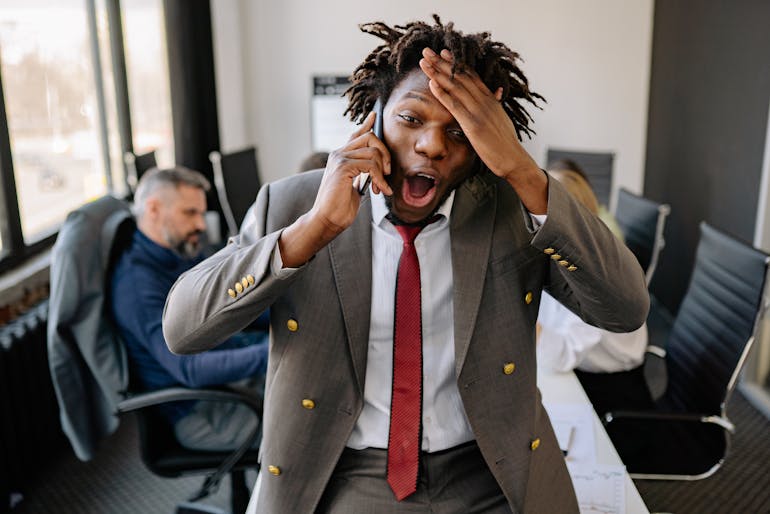
急がばまわれの関連語は、以下のようなものがあります。
<類語・言い換え表現>
- 急いてはことを仕損じる……焦るとやり損ねてしまいやすくなる
- 短気は損気……短気を起こすと、結局は自分の損になる
<対義語表現>
- 先んずれば人を制す……人より先におこなえば有利な立場に立てる
- 鉄は熱いうちに打て……物事は関係者の熱意がある間にことを運ぼう
- 好機逸すべからず……よい機会にめぐりあったならば逃してはいけない
■急がばまわれの類語・言い換え表現2つ
それでは実際に、急がばまわれの2つの類語・言い換え表現の意味や使い方などを確認していきましょう。
なお、ここでご紹介する類語・言い換え表現以外にも、「あわてる乞食はもらいが少ない」「急がば高火」「急ぎの文は静かに書け」なども、言い換えが可能な表現だといえます。
1.急いてはことを仕損じる
急いてはことを仕損じるとは、「焦るとやり損ねてしまいやすくなるため、何事も急ぐときほど冷静に行動するといい」という意味の言葉です。
焦りすぎると、いつもできるようなことでも失敗してしまい、急いでした行動が無駄になってしまうことがあるものです。あわてているときほど、このような言葉を思い浮かべるといいでしょう。
たとえば、「急いてはことを仕損じるというから、焦らずいつものように落ち着いて進めていこう」などと使います。
2.短気は損気
短気は損気とは、「短気を起こすと、結局は自分の損になる」ことを指す言葉です。損になることを、「短気」に語呂をあわせて「損気」と表現しています。
たとえば、「そんなに車線変更を繰り返しても、危険が増えるばかりで到着時間はそれほど変わらないでしょう。短気は損気だよ、ドライブを楽しもう」などと使います。
■急がばまわれの対義語表現
急がばまわれの対義語表現は、以下のとおりです。
- 先んずれば人を制す
先におこなえば、人より有利な立場に立てる。スピード感を重視することわざ。 - 鉄は熱いうちに打て
物事は関係者の熱意がある間にことを運ぶといい。関係者の熱意が冷めたころにやっても、問題にされなくなる。 - 好機逸すべからず(こうきいっすべからず)
よい機会にめぐりあったならば、逃してはいけない。着実性よりもタイミングを重んじたことわざ。
鉄は熱いうちに打ては、このほかに「精神が柔軟で吸収する力のある若いうちに鍛えるべき」という意味もあります。
急がばまわれを正しく理解しよう
 急がばまわれは、急いでいるときほど確実で安全な道を選んだほうがいいという意味のことわざです。
急がばまわれは、急いでいるときほど確実で安全な道を選んだほうがいいという意味のことわざです。
ビジネスシーンでも、焦ったあまりにミスをしてしまい、結局いつものようにやった場合よりも時間がかかってしまうことがあります。スピード感を求めるあまり失敗してしまわないように、急がばまわれという戒めのことわざを忘れないようにしましょう。
一方で、先んずれば人を制すのように、スピード感を重視することわざもあります。
さまざまな言葉を正しく理解し、適切に活用できるようになりましょう。
構成/chihaya















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE













