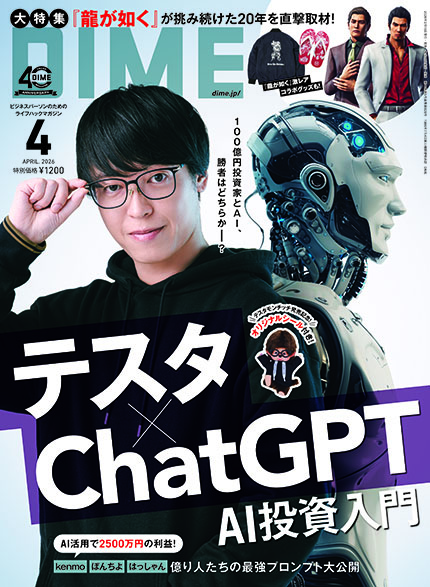企業経営において、重要な決断や専門的な助言が必要な場面は多いものです。顧問は、社内のリソースだけでは対応しきれない場合に起用されます。主な役割と、企業にもたらすメリットを解説します。
目次
顧問の意味
一部の企業では、第三者の専門的なアドバイスを得るために顧問を起用しています。法律で定められた役職ではないため、職務内容は企業の判断に委ねられています。まずは、顧問の位置付けや他の役職との違いを理解しましょう。
■企業経営における位置付け
顧問には、『相談を受けて意見を述べる役』『意見を問うこと』という意味があります。
企業経営においては、専門的な知識・経験を生かし、経営層に助言を提供する重要な存在として位置付けられています。会社法で定められたポジションではないため、設置するかどうかは会社の任意です。
顧問には、企業経営・事業運営のかじ取りをする権限はありません。顧問の存在により、企業は外部の専門知識・経験を効果的に活用でき、新たな視点で事業展開を図れるのです。
■他の役職との違い
顧問と混同されやすい役職には、役員・相談役・参与などが挙げられます。どのポジションも会社経営と深く関わりますが、役割や権限が異なります。
『役員』は、会社法で定められた役職です。株式会社における『取締役』『会計参与』『監査役』を指し、経営上の意思決定権を持ちます。
『相談役』は、経営全般について相談に応じる役職で、元代表取締役が就くケースが大半です。顧問は、外部の専門家や社内の専門知識を持つ者が就くことが多く、専門的な観点からアドバイスを行います。
『参与』は、取締役に準じた限定的な意思決定権を持ちます。顧問はあくまでも専門性を生かした助言を提供する役割であり、経営の意思決定権は持たない点が特徴です。
顧問の種類
顧問の種類は、『外部顧問』と『内部顧問』に大別されます。企業の現状やニーズに応じて、複数の顧問が起用されるケースもあります。ここでは、2つの顧問の特徴や役割を見ていきましょう。
■外部顧問
外部顧問とは、企業が社外から迎え入れる専門家のことです。弁護士・税理士・公認会計士などの士業専門家や、コンサルタントが就任するケースが多いでしょう。
外部顧問の主な役割は、専門知識に基づく助言と第三者の立場からの意見提供です。社内だけでは対応できない問題に直面した際は、外部顧問の専門性を活用できます。客観的な視点からのアドバイスにより、偏った判断を避けられるのも大きなメリットです。
働き方の形態は、業務やプロジェクトごとに契約を締結する『非常勤顧問』が多い傾向がありますが、常勤もゼロではありません。
■内部顧問
内部顧問は、社内事情に精通した人材が担う役職です。多くの場合、退任した取締役や監査役が就任しますが、経営に関わる役員が兼任するケースもあります。
主な役割は、経営全般に関する助言や専門分野での知見提供です。社内の実情を熟知している者であれば、現実的で実効性の高いアドバイスができます。長年培った人脈や社内の人間関係を生かし、円滑な問題解決・調整を図れる点もメリットです。
選任する際は、専門知識や経験、相談のしやすさなどを考慮することが大切です。適切な人材は、企業の持続的な成長を支える強力なサポーターとなるでしょう。
役割と職務内容の一例
顧問の役割と職務内容は、どの領域を担当するかによって変わります。経営顧問・技術顧問・顧問弁護士を例に挙げ、企業にどのような価値をもたらしているのかを解説します。
■経営顧問の場合
経営顧問は、企業の経営課題に対して、専門的な助言を提供するポジションです。経営者と近い立場で客観的な意見を述べ、意思決定をサポートすることで、企業の成長や問題解決に貢献します。
主な職務内容には、経営戦略の立案支援や資金調達のアドバイス、組織改革の提案などが含まれます。幹部育成や社内ノウハウの蓄積にも寄与するため、組織力の底上げが期待できるでしょう。
特に、スタートアップ企業やベンチャー企業では、経験が豊富な経営顧問の力を借りることで、安定した経営が実現します。
■技術顧問の場合
技術顧問は、企業の技術的課題を見極め、解決策を提示する専門家です。企業の技術力を客観的に評価し、トレンドや将来のニーズを踏まえた助言を行います。
主な役割には、技術戦略の策定・プロダクトの品質向上・エンジニア組織の編成に関するアドバイスなどが挙げられます。社員教育やプロジェクト管理に携わり、技術面でのサポートをするケースも少なくありません。
技術顧問の導入により、企業は専門知識を効率的に獲得し、競争力を高められます。技術顧問の持つネットワークを活用することで、新たなビジネスチャンスの創出も期待できます。
■顧問弁護士の場合
顧問弁護士は、企業の法務面を支える重要な存在です。法的リスクを予防するとともに、企業の日常的な法律相談に応じ、法令順守の体制構築をサポートします。顧問弁護士の存在により、トラブルに強い会社を目指せるでしょう。
業務内容は幅広く、労務問題への対応・知的財産権の保護・社内規程の整備・法律文書作成なども含まれます。トラブルが起きたときは優先して対応してもらえるため、問題が大きくなるのを未然に防げます。
一定の顧問料がかかりますが、法務部を設置するよりも安価に済むケースが多いようです。
顧問を起用するメリット
企業が、顧問を活用することで得られるメリットは少なくありません。専門的な知見が得られるのはもとより、信用力の向上や人脈拡大にもつながる可能性があります。以下で、代表的なメリットを確認しましょう。
■客観的で高度な助言を獲得できる
経営・技術・法務など、各分野のエキスパートが顧問として起用されることで、企業は客観的で高度な助言を得られます。
例えば、経営顧問は、戦略立案や組織改革に関する助言を提供します。過去の経験・ノウハウに基づいた顧問の客観的な視点は、社内では気付きにくい課題の発見や、客観的な解決策の提案につながるでしょう。
経営層は、本来の業務に集中でき、質の高い意思決定ができるようになります。顧問の活用は、企業の成長と競争力強化の鍵となるのです。
■企業の信用力向上と人脈拡大が見込める
顧問の起用は、企業の信用力向上と人脈拡大にも大きく貢献します。例えば、業界で名高い人物を顧問に迎えることで、企業の社会的評価が高まり、取引先や顧客からの信頼感が増します。
特に、顧問弁護士・顧問税理士といった専門家との契約は、法務やコンプライアンスへの取り組みを印象付け、企業のガバナンス強化として好意的に捉えられるでしょう。
顧問の持つ幅広い人脈は、新規顧客の獲得やビジネスパートナーとの提携など、事業拡大の機会をもたらします。経済界で活躍してきた顧問を通じて、新たな市場への参入や、異業種との連携が実現することもあります。
顧問を起用するデメリット
顧問の起用には多くのメリットがありますが、同時にデメリットも存在します。企業が顧問を雇う際には、デメリットを十分に理解し、適切に対処することが重要です。
■顧問料がかさむ場合がある
高額な顧問料は、企業にとって大きな負担となります。資金力の乏しい中小企業や個人事業主の場合、毎月の顧問料によって経営が圧迫されてしまう可能性があります。顧問契約を結ぶ際は、自社のニーズと予算に合った報酬体系かをしっかり確認することが重要です。
顧問料は、顧問契約の内容や専門家の経験によって変動します。安価な顧問料を掲げる場合、サポート範囲が狭かったり、追加料金が発生したりするケースがあります。また、長期契約が一般的で、短期間で契約解除がしにくいのもデメリットの一つです。
■依存度が高くなるリスクがある
顧問への過度な依存は、企業の自立性を損なうリスクがあります。経営上の問題に直面するたびに顧問に頼り、その助言をそのまま実行するだけでは、社員が主体的に考え行動する力が失われかねません。
顧問の豊富な専門知識・経験は貴重ですが、それはあくまで外部からの視点です。企業の成長には、顧問の意見を参考にしつつも、自社の状況に合わせて取捨選択し、独自の解決策を見いだす力が不可欠です。
顧問はサポート役であり、最終的な責任は経営者にあることを忘れてはいけません。顧問の力を借りながらも、社員それぞれが主体的に考え、行動できる組織作りが重要です。
顧問は企業の成長を支えるパートナー
顧問の主な役割は、専門的な知識・経験を生かし、企業に助言・支援を提供することです。外部顧問と内部顧問があり、経営・技術・販路開拓などのさまざまな分野に分かれます。
企業は、顧問を雇うことで、専門知識の獲得や客観的な視点の導入などのメリットを得られます。しかし、コストの増大や自立性の低下といったデメリットも、考慮しなければなりません。
顧問の活用は、企業の成長や課題解決に大きく寄与する可能性がある一方で、慎重な選択と適切な運用が求められます。
構成/編集部















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE