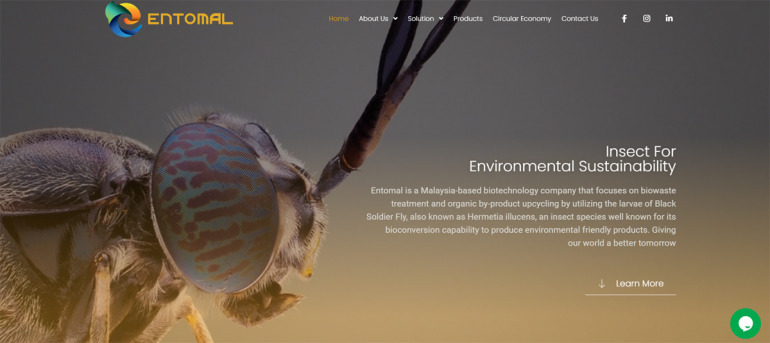プロレスラーのアントニオ猪木がこの世を去ってから早2年。「燃える闘魂」は、今でも人々に勇気を与えている。
少年期にブラジルへ移住し、コーヒー農園での地獄のような生活を経て雄大な体躯を獲得した猪木は、ブラジルにやって来た力道山にスカウトされてそのまま帰国。力道山のシゴキに耐えつつ、プロレスラーとしての実力を発揮していく。
そんな猪木のファイトスタイルは「ストロングスタイル」と称され、プロレスの在り方を大きく変えた。そして、猪木はその闘魂をリング外のビジネスにも向けていた。
その代表格が「アントン・ハイセル」である。当時は批判もあった事業だが、実はこのアントン・ハイセル、現代の目で見れば極めて先進的な部分もある会社だったのだ。
バイオテクノロジー事業の先駆け
猪木がブラジルでアントンハイセルという会社を設立したのは、1980年のことである。
これは、今で言えばバイオテクノロジー企業だ。
この時代のブラジルでは、石油の代わりにサトウキビから抽出したアルコールを使うエネルギー転換が推奨されていた。しかし、アルコール抽出後はどうしても搾りカス(バカス)が出てしまう。これを投棄すると、土壌が悪化して農作物に悪影響を与える。かといって家畜の飼料にもできなかった。それを食べた家畜は下痢をしてしまうからだ。
しかし、そんな搾りカスを発酵処理して飼料化する技術が生み出された。さらに、飼料化した搾りカスを食べた家畜の糞を堆肥として利用し、サトウキビやその他農産物の増産につなげよう……というのがアントン・ハイセルの企業コンセプトである。
これは計画だけを見れば、明らかに「持続可能な農業」を目指す内容である。しかし、時は1980年。この時代、まだバイオテクノロジー事業自体が先鋭的過ぎる存在で、まさに「雲を掴むような事業内容」だったのだ。
猪木、収益を生み出せず
が、猪木はそんな壮大な事業に本気で傾倒していく。
バイオテクノロジー事業は、そのプロセスが確立して一定数の顧客がつくまではほぼ無収益を余儀なくされる。現代では役員がピッチコンテストに参加して事業の実現性をプレゼンし、ベンチャーキャピタルに投資を呼びかけて収益化までの間を持たせるということができる。しかし、ブラジル政府の後援があったとはいえアントン・ハイセルにそのようなことはできなかった。
当時、名だたるスターを揃えて人気絶頂期を迎えていた新日本プロレスの利益からアントン・ハイセルの運転資金を工面していたことはよく知られている。実際にどれほどのカネが新日本プロレスからアントン・ハイセルに渡ったのかは不明な部分も多いが、所属選手にアントン・ハイセルへの投資を半ば強要していたという話もある。
そして、このアントン・ハイセルは膨大な借金だけを生み出してバイオテクノロジー事業から撤退した。
猪木本人は日本原子力学会誌への寄稿で、当時のことをこう振り返っている。
「アントン・ハイセルの事業は、バカスと廃液に酵素菌を加えて発酵させ、安全な家畜飼料を作る。さらに、このバカス飼料を食べた家畜の糞を有機肥料として、農作物と家畜の増産を促す。このように、世界の食料問題を一挙に解決しようという魂胆でした。
(中略)
ところが、日本とブラジルの気候の違いから、現地での発酵処理に行き詰まりました。ブラジルのインフレの影響もあり、事業は頓挫し撤退を余儀なくされました。あのときもマスコミにはいろいろ叩かれました。あれから四半世紀、やれ環境にやさしいだの持続性だのと騒ぐ時代がまた巡ってきました。そして、サトウキビからのエタノールもバカスの利用も事業化の目処が立ってきた。ついに金の卵になったのです」
(日本原子力学会誌 Vol.50 No.12)
「猪木の振り返り」は的外れではない!
アントン・ハイセルが、絶好調の新日本プロレスを頼っても返し切れないほどの借金を作ったのは事実である。
また、当時のブラジルは政治の民政移管を巡って国民と政府が対立していた時期。ブラジルの国民的詩人として知られるアルジール・ブランキが軍事政権を痛烈批判する『O Bêbado e a Equilibrista(酔っぱらいと綱渡り芸人)』という曲の作詞を手掛け、発表したのが1979年だ。こうした政治上の不安要素を考慮して的確な経営判断ができなかった点は、批判されてもやむを得ないだろう。
が、上記の寄稿の最後の一文、「そして、サトウキビからのエタノールもバカスの利用も事業化の目処が立ってきた。ついに金の卵になったのです」は決して的外れな見解ではないのではないか。
コンセプトが先鋭的過ぎたアントン・ハイセル
2024年の今、何かしらの生産・商業活動の過程で「余ったもの」を処理し、さらにそこから発生した副産物を有効活用しようというバイオテクノロジー事業が隆盛を迎えている。
一例を挙げよう。マレーシアの企業Entomal Biotechは、大型商業施設から出た廃棄食料を受け取り、ブラックソルジャーフライというハエの幼虫(いわゆるウジ虫)に食べさせようという方向性の事業を展開している。大量の幼虫の中に魚を1尾入れると、たったの30分足らずで骨まで食べ尽くしてくれる。それをショッピングモールやスーパーマーケットから日々大量に廃棄される食料に対して実施するというのがEntomal Biotechの事業内容。
さらに、幼虫が出した糞は堆肥に使うことができる。土壌の質を改善するオーガニック肥料は、今や世界中の農家が欲しがる商品だ。なお、幼虫は乾燥させて食用にすることも可能。
そして、この事業自体がかつてのアントン・ハイセルのそれと非常によく似ていることに注目する必要がある。「余剰物を酵素菌もしくは虫に処理させる」「そこからオーガニック肥料を生産して食糧増産につなげる」という点は、アントン・ハイセルとまったく同じである。
それは言い換えれば、アントン・ハイセルという企業がそのコンセプトだけは驚異的な先進性を有していたということだ。
【参考】
日本原子力学会誌 Vol.50 No.12(PDF)
Entomal Biotech
文/澤田真一















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE