金融経済アルキ帖「オスマン帝国」
オスマン帝国は1299年に成立し、1922年まで存続したトルコ人のイスラム教帝国です。オスマン帝国は、現在のトルコ、バルカン半島、中東、北アフリカにまたがる広大な領域を支配していました。そこで今回の金融経済アルキ帖は、東西の文化と経済を繋いだオスマン帝国がどのように繁栄したのか、その歴史に迫っていきます。
オスマン帝国の台頭と成長
13~14世紀頃、ヨーロッパとアジアをつなぐアナトリア半島が緩衝地帯となり、モンゴル帝国、マムルーク朝、ビザンツ帝国が勢力争いを繰り広げていました。そして3勢力の緩衝地帯であったはずのアナトリアから台頭して、1299年に建国されたのがオスマン帝国です。
オスマン帝国はブルサと呼ばれるコンスタンティノーブル対岸を拠点に、エーゲ海や黒海を通じて、遠くジェノヴァやヴェネツィアとも交易を行うようになります。
このようにヨーロッパにとって、オスマン帝国はイスラム諸国における窓口としての役割を担うようになるのです。
またオスマン帝国の勢いが増す中で、ビザンツ帝国が衰退していきます。それを好機とみなしたオスマン帝国はバルカン半島へと進出します。そして現在のトルコの最西端の位置にあるアドリアノープルを占拠し、エディルネと改名して本拠地をまるごと移転させます。このエディルネはコンスタンティノーブルの背後に位置する軍事的にも重要な拠点となり、1453年にはオスマン帝国は遂にビザンツ帝国を滅ぼしたのです。これは千年の歴史を持つ大国がなくなる歴史的な出来事でした。こうしてオスマン帝国はコンスタンティノーブルをイスタンブルと改称し、この地を首都と定めたのです。
拡大と黄金時代を支えた3つの海洋ルート
ビザンツ帝国の首都コンスタンティノープルを征服したことで、オスマン帝国は東地中海の支配権を確立することになりました。
16世紀になるとオスマン帝国は最盛期を迎えますが、なぜ他のイスラム国家を圧倒するほどの巨大な力を手にすることができたのか、そこには地政学的な理由があります。
当時、欧州からアジアへ向かうルートは主に3本に限られていました。それがコンスタンティノーブル(ビザンツ帝国の首都)、アンティオキア(現在のトルコ)、アレクサンドリア(エジプト)でした。
各ルートは以下の通りです。
・コンスタンティノーブルのルートは「黒海ークリミア半島ー中央アジア」へと繋がります。
・アンティオキアのルートは「アレッポーユーフラテス川ーペルシャ湾(海路)イラン(陸路)ーシルクロード」へと繋がります。
・アレキサンドリアのルートは「カイロー紅海ーインド洋」へと繋がります。
この3つのルートは東西を繋ぐ経済的な動脈であり、軍事上の要塞でもあり、古代から争いがあった土地です。例えば、かつてシルクロードの覇権を握ったモンゴル帝国は紅海ーインド洋ルートを掌握しようと攻め込むものの、エジプトのマムルーク朝を破ることはできませんでした。実際、13世紀に全盛を極めたモンゴル帝国は3本のルートをひとつも獲得することが出来ず、さらなる拡大を果たすことができませんでした。
こうしてオスマン帝国はコンスタンティノーブルを掌握したことで、東西をつなぐ要所として大きな繁栄をもたらすこととなったのです。
オスマン帝国とヨーロッパ
オスマン帝国が隆盛する中で、ヴェネツィアやジェノヴァは脅威を感じながらも、オスマン帝国と通商条約を結んでいます。これはヴェネチアやジェノヴァからオスマン帝国にエーゲ海や黒海の支配権を認め、貢納金をする形で優先的にオスマン帝国と取引ができるように働きかけたもので、いかにオスマン帝国が巨大な存在であったかを物語るものです。
その後、何度か大きな海戦はあったものの、オスマン帝国とヨーロッパの商取引は互いに密接に関わり続けていくことになるのです。
















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE











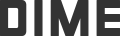 最新号
最新号






