目次
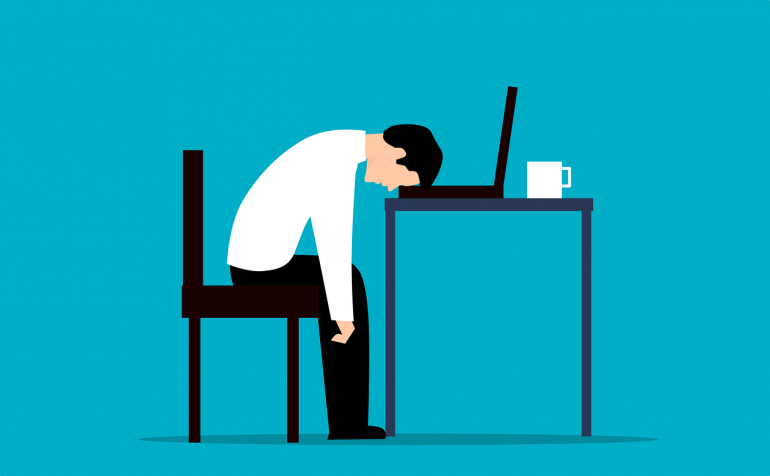
従業員が重大な犯罪を犯し、会社に「懲戒解雇」された。こんなニュースを見聞きしたことがある方も、多いのではないだろうか。「懲戒解雇」は、会社が社員に科す懲戒処分のひとつだが、懲戒処分には、「諭旨退職(ゆしたいしょく)」というものもある。
この記事では、諭旨退職とは何か、退職金の有無から気になる再就職への影響についても、わかりやすく解説する。
諭旨退職とは
まずは、諭旨退職の定義から確認していこう。
■諭旨退職の定義
諭旨退職とは、懲戒解雇に相当する理由があるが、本人の会社への貢献度や反省の程度などを考慮して、退職届を提出させて解雇する懲戒処分のことだ。ちなみに「諭旨」とは、「趣旨や理由をさとし告げること」という意味を指す。
法律上の規定ではなく、会社独自の規定だ。懲戒処分は以下のようにいくつか種類があり、下になるほど処分は重くなる。
|
戒告 |
口頭または書面での注意 |
|
けん責 |
始末書や顛末書などを提出させる |
|
減給 |
給料の一部減額 |
|
出勤停止 |
一定期間の出勤停止。その間の給料は支給なし |
|
降格 |
役職・職位などの解任や引き下げ |
|
諭旨退職 |
退職届を提出させたうえで退職させる(実質解雇) |
|
懲戒解雇 |
制裁としての解雇 |
■諭旨退職・諭旨解雇・懲戒解雇の意味と違い
諭旨退職は、会社によっては「諭旨解雇」ということもあるが、ほぼ同じ意味になる。
対して「懲戒解雇」は、社員の重大な違反行為や犯罪、問題行動などを理由として、会社が強制的に雇用契約を解除するもので、懲戒処分で最も重いものだ。
何をしたら諭旨退職になるの?

それでは、どんなことをしたら、諭旨退職になるのだろうか。以下はその代表例だ。
- 痴漢や傷害など、社外で犯した重大な刑事犯罪
- 横領や背任・詐欺など、会社での職務や地位を利用した重大な違法行為
- セクハラ・パワハラなど、悪質なハラスメント行為
- 無断欠勤や遅刻を繰り返し、指導や勧告、ほかの懲戒処分を科しても改善しない場合
- 情報漏えい
確かな「ライン」があるわけではないが、企業や社会に大きな損害や悪影響を与える行為ほど、諭旨退職となる可能性が高まるという認識で大きな間違いはないだろう。
■諭旨退職に関連する要件
とはいうものの、上記の行為があったからといって、自動的に諭旨退職になるのではない。次の3つの要件を満たすことが必要だ。
1.就業規則に規定があること
2.就業規則が社員に周知されていること
3.「懲戒権の濫用」と「解雇権の濫用」に当たらないこと
※違反行為に対して重すぎる懲戒処分を科したり、懲戒解雇に当たらないレベルなのに懲戒解雇にしたりすること。
■諭旨退職の手続きの流れ
このように会社は、該当する理由があるといっても、社員を簡単に諭旨退職とすることはできない。それは手続きにおいても同じだ。就業規則の規定を確認したあと、次のような手続きを経て、処分が決定される。
1.具体的な証拠集め
直属の上司や同僚へのヒアリング、業務日報、メール、タイムカードなどを集める。確実な証拠がないのに処分した場合は「解雇権の濫用」にあたり、トラブルに発展することもあるからだ。
2.「弁明の機会の付与」
対象社員に対して、諭旨退職を検討している旨と処分理由を伝え、本人に申開きや処分理由が偽りである証拠を提出させる機会を設ける。これを「弁明の機会の付与」という。処分対象者は、諭旨退職に納得がいかない場合は、この場で主張することができる。
3.諭旨退職にするかどうかの決定
集めた証拠と対象社員の弁明の内容も検討したうえで、決定する。
4.諭旨退職の通知、手続き
処分が決定すると、対象社員に「懲戒処分通知書」を渡す。記載内容は、諭旨退職処分と理由、退職届の提出期限、期限までに退職届を提出しない時は懲戒解雇になるならその旨など。
その後は、期限内までに退職届を提出し退職という流れになる。そこで気になるのは、退職金など今後の待遇面だ。
■諭旨退職は退職金はもらえるの?
会社の退職金規程にどのように定められているかによるので、正確には、自社の退職金規程を確認する必要がある。もっとも、一般的には「懲戒解雇は全額支給なし。諭旨退職は一部減額で支給」のように懲戒解雇と差を設けているケースが多い。
|
懲戒解雇 |
諭旨退職 |
普通解雇 |
整理解雇 |
|
|---|---|---|---|---|
|
退職金 |
不支給 |
減額支給 |
支給/減額/不支給 ※1 |
支給※2 |
|
有給休暇 |
消化できる |
消化できる |
消化できる |
消化できる |
|
失業手当 |
自己都合退職扱い ※3 |
自己都合退職扱い ※3 |
会社都合退職 ※4 |
会社都合退職 ※4 |
※1:解雇理由によって変わる可能性あり
※2:会社の経営が厳しい場合は、支払いが不可能なこともあり
※3:7日間の待期+原則2か月(懲戒解雇は3か月)のの給付制限、給付日数は基本的に会社都合退職に比べ少ない
※4:7日間の待期後、給付制限期間なし。給付日数は基本的に自己都合退職に比べ多い
「普通解雇」は懲戒処分によらない解雇のことで、理由は能力不足や素行不良であることが多い。また、「整理解雇」はリストラであり、会社の業績不振など労働者の責任ではない理由での解雇となる。
他の退職と比べると、諭旨退職は待遇面でも不利になることがうかがえる。できるだけ回避したいところだ。参考までに、ニュースにもなった過去の事例を紹介する。
- 学生・教員に対するパワハラ
- 女子学生に対するセクハラ
- 第三者に利用者の個人情報を恣意的に漏えいした
- 業務用ノートパソコンなどの備品を持ち出して売却した
諭旨退職になると再就職は難しい?
諭旨退職になると、再就職は難しいのだろうか。一般的には履歴書には「一身上の都合により退職」と記載でき、面接であっても自分から言う義務はないので、応募段階では再就職には影響しないだろう。
ただ、次のようなケースでは注意が必要だ。
・転職先の会社に、離職票を提出するよう言われた。
離職票には一般的に「自己都合(諭旨退職)」と記載されるので、事実が明らかになる。
・転職活動の面接で、退職理由を聞かれた。
この場合は、諭旨退職の事実を言わなければならない。諭旨退職だったことを隠して入社し、入社後発覚すると、経歴詐称として懲戒処分を受けることがあるからだ。
・刑事罰を受けて諭旨退職になった。
この場合は、履歴書の賞罰欄にその旨の記載が必要。記載しないと告知義務違反を問われる。ちなみに、履歴書に賞罰欄がない場合は、書かなくてもよい。
まとめ
ここまで諭旨退職の定義や退職金の支給の有無、再就職は難しいかなど、具体的な事例も含めて見てきた。
会社員にとって諭旨退職はやはりハイリスクだ。通常の範囲内で勤務していれば諭旨退職となるケースは少ないものの、注意していこう。また、万が一、諭旨退職になってしまったら、再就職に向けて、早めに考えをシフトしたほうがよいだろう。
文/木戸史(きどふみ)
立命館大学文学部卒業後、営業、事務職、編集アシスタントなどを経て、社会保険労務士事務所で社労士として勤務。現在はライターとして活動しており、社労士として多くの中小企業に携わった経験を生かし、ビジネスマンに役立つ法律知識をできるだけわかりやすく発信している。















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE













