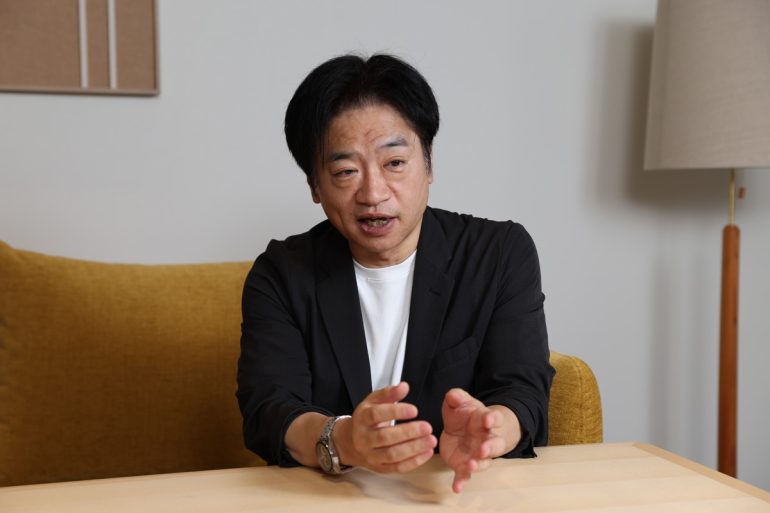2005年の創業の医療グループ・桜十字が業績を伸ばしている。初年度の売上げは約38億円だったが、創業14年目の2019年には約10倍の338億円までに成長。コロナ禍以降、ウェルビーイングの思想を導入してから、売り上げをさらに伸ばし、2024年には20倍の約808億円をマーク。桜十字グループの那須一欽さんは、「働く人、施設を利用してくださる方の心や環境をいい状態に保つと、『ハッピースパイラル』ができ、グループはもちろん地域全体が成長していくのです」という。そのウェルビーイング経営の背景を伺った。
創業20年で売上は20倍!桜十字グループのCMOが語るウェルビーイングな経営学
2005年の創業の医療グループ・桜十字が業績を伸ばしている。初年度の売上げは約38億円だったが、創業14年目の2019年には約10倍の338億円までに成長。コロ…
桜十字グループCMO(Chief Marketing Officer:最高マーケティング責任者)
那須一欽さん
青山学院大学卒業後、ソニーマーケティングに入社。その後、ソニーに転籍し商品企画に携わる。11年に桜十字病院に入社、経営企画室、桜十字病院経営企画部長を経て、2022年、生活と医療の融合を目指した医・食・住のヘルスケアテーマパーク『メディメッセ桜十字』を手掛け、現職に至る。https://medimesse-kumamoto.jp/
桜十字グループ
熊本県を拠点に展開する医療グループ。桜十字病院を中心に医療、介護、予防医療など、幅広くヘルスケア事業を全国に展開する。
https://www.sakurajyuji.jp/
新たなビジョンは「ウェルビーイング・フロンティア」
――前編で桜十字グループは、2014年からリハビリテーション機能の強化にも注力したことを伺いました。経営判断の背景をお聞かせください。
那須一欽さん(以下・那須):それには、深刻な日本の少子高齢化があります。55年前の1970年、65歳以上の人口比率はわずか約7%で、約10人が1人の高齢者を支える社会でした。それが、2024年は29.3%で、約3人で1人を支えるという状況に陥っています。これが、25年後の2050年になると約37%に達すると予測され、約1.4人で1人を支える社会になるのです。
現役世代も高齢者も幸せな生活を送るには、各人が心身の機能を健全に保ち、社会とのつながりを持てる状態を整えておくことが大切です。
もちろん、この状態に政府も対策を打っており、2014年に厚生労働省は地域全体で高齢者のケアを行える社会づくりと、高齢者の在宅復帰や自立支援を目的に含む「地域包括ケアシステム」の構築を提唱。さらに翌2015年に『保健医療2035』の提言書を発表します。このとき「治す医療から支える医療」(キュアからケアへ)という新たな方針が示されました。
そんな社会全体の動きもありますが、実際に現場にいると、患者さんやご家族から「家に帰りたい。帰らせてあげたい」という声をよく聞くんです。もちろん、スタッフはそれを叶えたいと思っています。でも、身体が思い通りに動かず介助が必要だったり、点滴や経管栄養など“医療行為”が必要なことも多く、入院を余儀なくされる患者さんも多いのです。
――ウェルビーイングを実現するには、身体機能の維持が大切なことがよくわかりました。そこで桜十字グループが打ち立てたのは、「口から食べるプロジェクト」(2014年)。これは在宅復帰支援の軸として、医療や介護業界から注目されています。
那須:家で生活するための必要条件は、「食べる」「歩く」「排泄」の3要素です。その最初のとっかかりとなり、身体の回復の鍵を握るのは、「食べる」です。この判断の背景には、桜十字グループのNST(Nutrition Support Team /栄養サポートチーム)研究会で、「臨床的に口から食べると患者が良くなる」と医師たちが実感していたことがあります。そこでこれを本格的なプロジェクトとして推進しました。
――たとえ、寝たきりであっても、口から食べることをきっかけに、全身状態が改善していく可能性はあります。内臓機能を回復させ、リハビリができるまで体力を取り戻し、そこから身体機能を取り戻していけば、退院の可能性が見えてくる。また「食べる」ことは結果が見えやすく、本人のモチベーション向上にも繋がります。
那須:はい。また、口から食べていればADL(日常生活動作)やQOL(生活の質)の維持向上もできます。食べる喜びは生きる幸せ……すなわち、私たちのスローガンである「生きるを満たす。」につながっていきます。
そのため、桜十字グループの医療従事者は、知識と技術と経験を磨き、あきらめない姿勢を持ちながら、食べられる可能性を探り続けます。長く食事をしなかった患者さんにとって、口に食べ物を入れることは恐怖そのものであるケースも多いです。なぜなら、誤嚥や内臓への負担など、リスクと紙一重だからです。
ですから、経験豊富なスタッフがダメな理由を見つけるのではなく、食形態を見極め、食事介助の技術(姿勢や環境など)のほか、どうすれば食べられるかを探すために、あきらめることなく多角的にアプローチをしています。また、口腔ケアの専門チームも作り、歯や口腔環境のケアなどにも努めてきました。
これは、近い将来、高齢化社会になると予想されている台湾の医療関係者に大きな影響を与え、関連書籍も台湾で翻訳され出版されました。私たちも、台湾の医療機関の招待を受け、ワークショップや勉強会を行うなどの活動も行なっています。
日本は世界における超高齢社会のトップランナーです。桜十字グループは、世界に向けて持続可能な医療や介護のモデルを構築し、これを広めていくことも使命の一つとして育てていきます。
――WHO(世界保健機関)の健康の定義(1948年)にもある「社会的ウェルビーイング」については、2019年から放送作家・小山薫堂さんと『まってる。プロジェクト』を行なっています。
那須:ベースとなったのは薫堂さんが翻訳した、フランスの絵本作品『まってる。』(千倉書房)でした。これは、命の誕生、愛する人が戦場から帰ること、新しい家族など「あなたのことを誰かが、そして、あなたも誰かをまってる」という、まってる時間の尊さを描いた静かで心打つ物語です。
薫堂さんは「奇しくもひとは、身体をわるくしたときに初めて気づくことがあります。」と語りだし、健康のことはもちろん、家族や友人の存在、一日の時間の長さ、子供のころ叶えたかった夢や、これからの未来のことなど、「病院は大切なものに気づける場所」でもあるんじゃないでしょうかと、私たちが働く病院という場の尊さに気づかせてくれました。
そこで、『まってる。』の絵本をモチーフに、桜十字病院の1階をカフェ併設の『まってるラウンジ』にリニューアルしたのです。
ここでは、大切な人や退院する自分への手紙を書けるレタールーム、桜の木でできたポスト、明日が楽しみになる本をテーマにしたライブラリーなどを設けました。選書を担当したのは、著名なブックディレクター・幅允孝さんです。『まってるラウンジ』は、どなたも自由に入れますので、是非いらしてください。
――自分の人生を生きるために、自分を認め、向き合い、懸命に生きる……これをサポートするのも医療であり、ウェルビーイングだと感じました。
那須:その通りですね。病気の予防のために、運動習慣を身につけたり、栄養の知識を得るには、プロのアドバイスを参考にしたほうがより有効であることが多いです。ですから私たちは、予防医療事業、フィットネス事業、在宅サービス事業、医療メディア事業なども展開しています。
最も暮らしに近いのは、2022年に開業した、『メディメッセ桜十字』(熊本県熊本市)です。ショッピングセンターの中にあり、従来の人間ドック・健診センターのほか、カフェラウンジ、キッチンスタジオ、レンタルスペースなどを兼ね備えています。イベントも頻繁に開催されており、ヘルスケアテーマパークとして、多くの人に活用いただいております。
ここで、2025年5月から『こどもウェルネスジムUGOKKO』をスタートしました。これは、予防医療を主軸にした、運動・栄養・睡眠を、親子で学べるウェルネスジムです。
桜十字グループを振り返ると、2005年の創業からの10年を「医療グループ」として、2015年からの10年を「ヘルスケアグループ」として展開してきました。
20周年を迎える2025年からは、「ウェルビーイング・フロンティア」を新たなビジョンとして展開していきます。一人ひとりのウェルビーイングが実現すれば、QOLが向上し、豊かな日常がそこにあり、健康寿命も伸びていきます。その先に、社会全体が元気になると確信しているのです。日本がウェルビーイング先進国となり、人生100年時代における世界のリファレンスモデルになれるように、私たちはウェルビーイングな未来を切り拓く最前線で、どこまでも人びとの「生きるを満たす。」を追求していきます。
医療の進化とともに、人生は長くなっています。できる限り、充実した人生を楽しむには、体の知識とメンテナンスが必要です。今、そのために何をすべきか、少し未来の自分の幸せのために、できることを行うこともまた、ウェルビーイングにつながっていくのではないでしょうか。
構成/前川亜紀 撮影/杉原賢紀(小学館)















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE