
Photo:Etsuo Hara/Getty Images
日本サッカー界にとって平成の31年間は飛躍的な進化を遂げた時代だった。というのも、31年前の日本はワールドカップ(W杯)に出たこともなければ、アジアでも最終予選までたどり着けない弱小国だったからだ。
最終予選にさえ進めなかった平成元年
平成が幕を開けた1989年。横山謙三監督(元浦和レッズ監督)率いる日本は90年イタリアW杯アジア予選に挑んでいた。Jリーグ初期のスターだった長谷川健太(現FC東京監督)や井原正巳(柏コーチ)らを擁するフレッシュなチームは香港、インドネシア、北朝鮮からなる1次リーグを戦うも、最終予選に進めなかった。ホームでは辛うじてインドネシアに5-0、北朝鮮にも2-1と勝利したものの、香港にはドロー。アウェーでは1勝もできず、グループ2位に甘んじ、敗退を強いられた。当時の選手たちは世界がどれだけ遠い存在かを痛感したことだろう。
流れが変わり始めたのはJリーグ発足を翌年に控えた92年。日本サッカー協会の川淵三郎強化委員長(現相談役)がヤマハ発動機(現ジュビロ磐田)やマツダ(現サンフレッチェ広島)で監督を歴任したオランダ人のハンス・オフト監督を招聘。A代表に年間5億円、年代別代表にも1~2億円を投じて「全カテゴリーで韓国に勝て」と力強く鼓舞するなど、抜本的な代表強化に乗り出したのだ。
その試みはすぐさま92年アジアカップ(広島)優勝という成果に表れる。ラモス瑠偉(現ビーチサッカー代表監督)やカズ(三浦知良=横浜FC)といったスターと森保一(現日本代表監督)ら黒子の選手を巧みに組み合わせたチームは自信をつけ、94年アメリカW杯アジア最終予選へ進出。夢の本大会へあと一歩まで迫った。けれども、ご存知の通り、93年10月28日の最終戦・イラク戦のロスタイムに2-2に追いつかれ、つかみかけた切符が手からこぼれ落ちてしまう。
「『頭が真っ白になる』という状態。試合が終わって何をやっていたのか、どうやってホテルに帰ってきたのかも覚えてない」と森保監督も述懐する衝撃の大きさだった。
フランスW杯に向けた強化は順調ではなかった
98年フランスW杯までは4年。筆者が初めて代表練習取材に赴いた94年4月にはパウロ・ロベルト・ファルカン監督が就任したが、わずか8ヵ月で更迭され、加茂周監督(現解説者)が後を引き継いだ。しかし、96年アジアカップ(UAE)で8強止まりに終わるなど、正直言って当時の日本代表強化はそこまで順調には進んでいなかった。
その閉塞感を打ち破ったのが、川淵氏がもう1つ強化に乗り出した年代別代表だ。自国開催の93年U-17世界選手権(現W杯)に宮本恒靖(現G大阪監督)、中田英寿、松田直樹らが出場したのを皮切りに、日本の若年層が世界舞台を経験するようになっていく。中田と松田は95年U-20W杯を経て、96年アトランタ五輪にも出場。彼らのような「外国コンプレックス」を持たない若手が急激に台頭したのは大きかった。
その数人を加茂監督がA代表に抜擢。98年フランスW杯アジア最終予選に間に合わせたのは特筆すべき点だ。川口能活(現U-17日本代表GKコーチ)と中田、城彰二(解説者)は主力として活躍。97年11月16日にイランに3-2で勝った「ジョホールバルの歓喜」の時には揃ってピッチに立ち、城が値千金の同点弾を叩き出している。「ドーハ組の人たちはそのことに囚われていたけど、僕ら世代は『アジアは勝って当たり前と思っていた」と城も強気の発言をしていたが、いわゆる「新人類」の成長が初のW杯出場に大きく寄与したのは間違いない。
長年、代表を支えたカズが途中で代えられたのもこの日が初めてだった。当時アトランタ世代を強く推していた有名ライターが「ついにカズが下がった」と筆者の隣でガッツポーズした姿が今も脳裏に焼き付いているが、カズの存在はそれほどまでに絶大だった。中村俊輔(磐田)らアラフォー世代の選手の多くが「カズの勝負強さはすごい。一番厳しいところで必ず点を取って日本を勝たせる」と口々に語っていたように、全てのサッカー関係者の憧れだったのは確かだ。
そのキングを、最終予選途中から指揮官となった当時41歳の岡田武史監督(現FC今治代表)がフランスW杯本大会直前に外したことは、衝撃以外の何物でもなかった。98年6月2日にスイス・ニヨンで昼過ぎから開かれた青空会見には筆者もいたのだが、「外れるのはカズ」という言葉が出た瞬間、数人の新聞記者がカズを探しそうと走り出したのをよく覚えている。すでにホテルはもぬけの殻。駅にも空港にもおらず、数日後にイタリア・ミラノで見つかった時にはメディアが押し寄せた。そこで語った「魂は置いてきた」という発言は人々の心を打った。残されたメンバーも気持ちをしっかり受け取ったが、日本は3戦全敗。「エース失格」の烙印を押された城は帰国した成田空港で水をかけられた。
黄金世代の台頭とドイツW杯の挫折
それでも、この惨敗から日本はW杯常連国への道をひた走ることになる。2002年日韓W杯まではエキセントリックなフランス人のフィリップ・トルシエ監督が就任。U-20、五輪、A代表の3世代を一貫指導した。その時に寵愛を受けたのが、小野伸二(札幌)、遠藤保仁(G大阪)ら79年生まれの黄金世代だ。99年U-20W杯(ナイジェリア)2位の偉業を達成した若きタレントたちと一緒にトルシエはW杯まで突き進んだ。史上初の16強入りした2002年大会のメンバーを見ても、小野と稲本潤一(相模原)、中田浩二(鹿島CRO)はナイジェリア組。高原直泰(沖縄SV代表)も直前の病気がなければスタメンでピッチに立っていた。この時代の日本サッカーの快進撃は、彼ら黄金世代とともにあったと言っても過言ではないかもしれない。
 Photo:Bob Thomas/Getty Images
Photo:Bob Thomas/Getty Images
小野らが円熟期を迎える2006年ドイツW杯は8強超えへの期待も高まった。が、指揮官となったジーコ(現鹿島TD)は指導経験が乏しく、明確な戦術や方向性を示すことができなかった。さらに、この時代になると中田、中村、小野、稲本ら主力の多くが海外へ移籍。代表戦のたびに欧州から戻るというハードスケジュールを強いられるようになり、国内合宿で強化を図ることができなくなった。こうした環境の変化も重なり、ドイツでの日本はまさかの1次リーグ最下位。クロアチアに勝ち点1を取っただけで、なすすべもなく敗れ去った。中田英寿も現役引退し、1つの時代が終わった印象だった。
ドイツ惨敗ショックは日本サッカー界にマイナス影響を及ぼし、2006年夏から就任したイビチャ・オシム監督時代も苦しみは続いた。2000年代半ばは年代別代表も足踏み状態に陥り、U-17世代が世界切符を逃し、U-20世代も16強進出が精一杯。五輪世代も2004年アテネ、2008年北京ともに1次リーグ敗退と振るわなかった。オシム監督が急病で倒れ、2008年から岡田監督が再登板してからもトルシエ時代のような躍進は見られず、南ア行きも危ぶまれたが、スコットランドで飛躍した中村俊輔がエースとして存在感を発揮。岡崎慎司(レスター)や長友佑都(ガラタサライ)、内田篤人(鹿島)ら若手も伸びてきて、何とか最終予選突破にこぎつけた。
南アフリカW杯組が主力へと成長
その陣容で南アに行くと見られたが、チームは本大会直前に想像以上の停滞に陥った。それを打破すべく、岡田監督は中村俊輔や楢崎正剛(名古屋CSF)らベテランを外し、本田圭佑(メルボルン)や川島永嗣(ストラスブール)ら若手を抜擢。その本田が大会2ゴールを奪ってスターダムに上り詰めたのだから、指揮官の決断力と大胆さには驚かされた。「自分の夢は代表の攻撃を仕切ることでも、日本の看板選手になることでも何でもない」と言い切る強心臓の持ち主である本田圭佑という新たなスターが登場し、日本代表はさらに新時代へと歩みを進めた。
そこから8年間は南ア組が君臨し続けることになった。内田はケガ、遠藤保仁(G大阪)は年齢面を考慮されて2015年以降は代表を離れたものの、本田、岡崎、長友、川島、長谷部誠(フランクフルト)、香川真司(ベシクタシュ)、吉田麻也(サウサンプトン)といった岡田監督が若いうちにピックアップした面々がトップを走り続け、日本は昨夏の2018年ロシア大会で3度目の16強入りを果たした。その間、アルベルト・ザッケローニ、ハビエル・アギーレ、ヴァイッド・ハリルホジッチ(現ナント)、西野朗という4人が指揮を執ったが、主力の顔ぶれは大きく変わらなかった。現在の森保体制移行後も長友が左サイドバック一番手に君臨し、長谷部復帰待望論も浮上している通り、彼らの残してきたインパクトがいかに大きかったかがよく分かるだろう。
本田がACミラン、香川がマンチェスターU、長友がインテル、内田がシャルケというように欧州ビッグクラブに日本人選手がズラリと並んだのも、この8年間だった。黄金世代も傑出したタレント集団ではあったが、日本人の海外移籍環境が整っていなかった分、世界的知名度は南ア世代の方が高いと言っていい。筆者も2000年頃から欧州に頻繁に出向くようになったが、2014年ブラジルW杯前後が日本人選手と日本代表の評価が最も高かった印象がある。それを超える人材がいつ出てくるのか。そこが森保体制の課題だろう。
とはいえ、日本代表が6度のW杯出場と3度の16強入りを果たし、これだけ多くの選手が欧州でプレーするようになるなど、30年前には想像だにしなかった。筆者が初めて記者席で見た代表戦である97年5月21日の日韓戦の頃から考えても隔世の感がある。そうやって急成長を遂げた平成を経て、令和の時代の日本サッカーはどうなるのか。1月のアジアカップ(UAE)を見ても日本代表を取り巻く環境は厳しくなる一方だが、「8強超え」の悲願を達成する日がいち早く訪れることを切に祈りたい。
 Photo:藤岡雅樹(小学館)
Photo:藤岡雅樹(小学館)
取材・文/元川悦子
長野県松本深志高等学校、千葉大学法経学部卒業後、日本海事新聞を経て1994年からフリー・ライターとなる。日本代表に関しては特に精力的な取材を行っており、アウェー戦も全て現地取材している。ワールドカップは1994年アメリカ大会から2014年ブラジル大会まで6大会連続で現地へ赴いている。著作は『U−22フィリップトルシエとプラチナエイジの419日』(小学館)、『蹴音』(主婦の友)『僕らがサッカーボーイズだった頃2 プロサッカー選手のジュニア時代」(カンゼン)『勝利の街に響け凱歌 松本山雅という奇跡のクラブ』(汐文社)ほか多数。
















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE










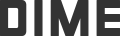 最新号
最新号






