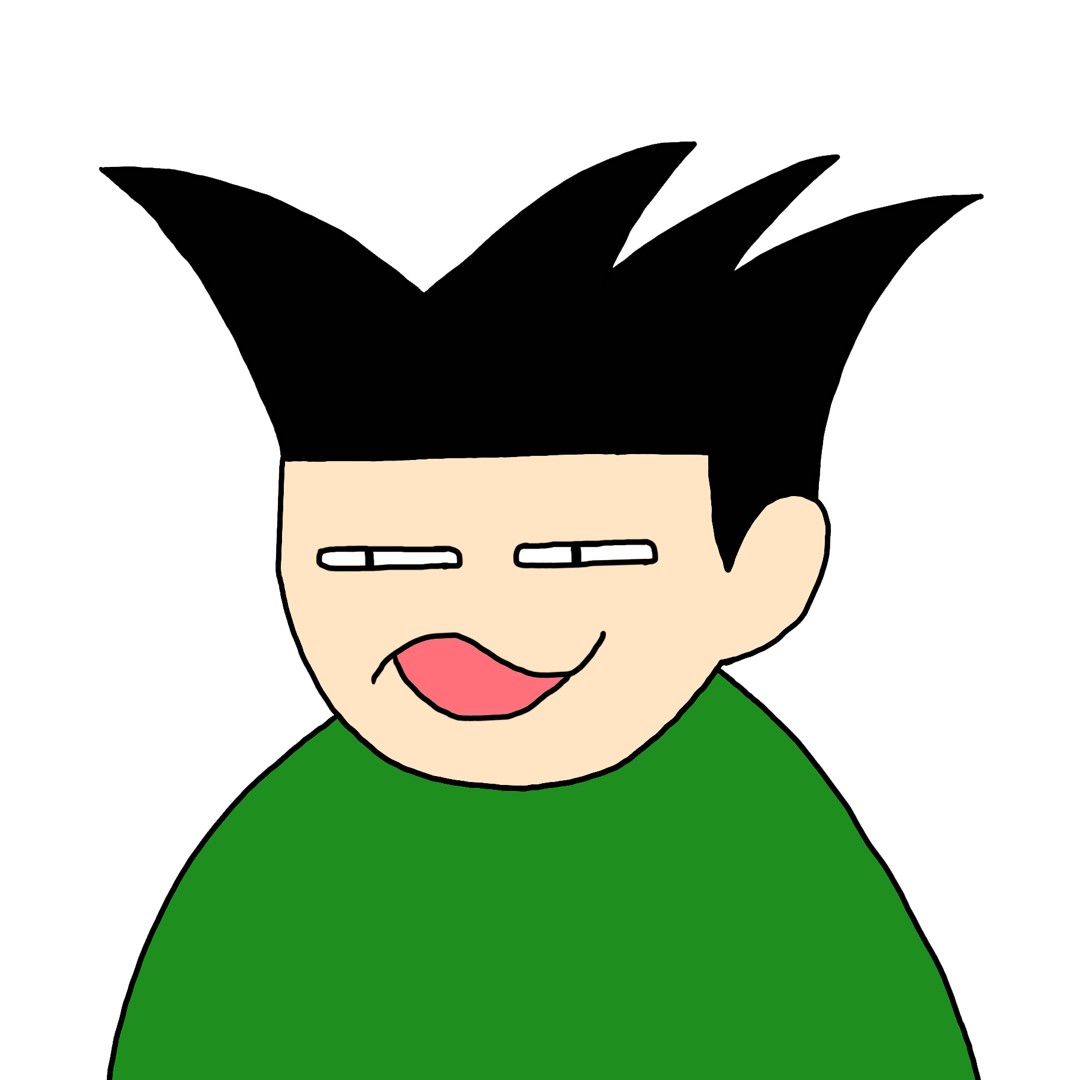週末はどこに行こうか?
そう考えた時、多くの人は「映画館」とか「ショッピングモール」とか「アミューズメント施設」とか、そのような場所を連想するはずだ。しかし、ここは「寄席」という選択肢を考えてみるのはいかがだろうか?
寄席ほどコストパフォーマンスに優れたエンターテイメント施設はないだろう。今日びの映画館は映画が終わったら全席入れ替えで、昔のように1日中席に着きっぱなしということはできない。しかし、寄席で入れ替わるのは芸人である。落語家、漫才師、奇術師等々が日中から夜になるまで持ち芸を披露してくれる。客はたまに居眠りをしつつ、小屋じまいの時刻まで同じ席を温め続けることができるのだ。
観たい映画もないし、ボーリングもゲームセンターも飽きた。そんなことを言いながら溜め息をつく首都圏在住の人たちは、この記事に騙されたと思って寄席に行ってみるのもいいのではないか。
落語家と最先端テクノロジー
落語は日本の伝統芸能だが、同時に時代毎の最先端テクノロジーを上手く取り込んできた歴史を抱えている。
日本初のラジオ放送は1925年、大正14年の出来事である。社団法人東京放送局(今のNHK)が行った試験放送では、五代目柳亭左楽が電波に噺を乗せた。実はこの時代、寄席の経営者や一部の落語家からは「ラジオで落語家がしゃべったら寄席に客が来なくなる」と言われ、ラジオ局に対する反発もあった。しかし蓋を開けてみれば、ラジオを聴いた人が「あの落語家の顔を拝んでやろう」ということでむしろ寄席が賑わうようになったのだ。
戦後、テレビ受像機という文明の利器が一般向けに販売されるようになると、大衆の目を新メディアに集めるためのキラーコンテンツがいくつも企画された。その筆頭格はプロレスである。テレビ画面が白黒で中継車やVTRというものがなかった時代、低予算で年中いつでもできるスポーツ中継といえばプロレスしかなかった。
しかし、日本の場合は落語家という優秀なエンターテイナーが存在する国でもある。大正期のラジオ放送のように、昭和中期のテレビ放送が落語家を番組に出演させるのは自然の流れであった。これには五社協定という名のカルテルを構築していた映画業界が、テレビ局に対して監督や俳優を貸そうとしなかったからという事情も多分にあるだろう。日本におけるテレビの歴史とは、テレビ局が自前のタレントを発掘し続けた歴史でもある。が、落語家がテレビの登場とその普及の波に乗ることができたのは、やはり彼らの掌に「魅せるための魔力」が宿っていたからに他ならない。
「新技術による職業淘汰の可能性」を毎回のように退けてきたのが、落語家と呼ばれる人たちなのだ。
日本の落語家は、道具をあまり使わない。彼らの持ち物といえば扇子と手拭いくらいである。が、それらを巧みに使ってあらゆる場面をリアルに再現し、客を特定の世界観に引きずり込んでしまう。シンプル故の技巧さと表現するべきか。どのようなフォーマットにも収まってしまう「融通の利き」が落語にはあり、だからこそ時代毎の最先端テクノロジーを味方につけることができたのだ。
我々は、落語から多くのことを学ぶことができる。
若手と老齢の真打が同じ高座に
そんな落語で生計を立てている落語家にとって、寄席は活動のベースとなる場所だ。
20代の前座から80代の高齢の真打まで、全く同じ高座に上がって噺をする。もちろん、出てくる順番はそれぞれ異なる。前座は通常、正午頃から始まる昼の部の一番最初の合間を埋める役割に徹する。そこから二ツ目が場を温め、ここぞという節目で真打が高座に上がる。その間、前座は座布団を整えたり、機材を運んだり、師匠のお茶を淹れたりという仕事で容赦なく揉まれていく。
寄席は若手にとっての「修行の場」、そして老齢の真打にとっては収入のベースとなる大事な職場である。
新宿末廣亭の場合は、特別興行を除いて昼の部は正午~16時15分、夜の部は16時45分~20時30分まで。その間は先に述べた通り、客の入れ替えは行われない。大人1人3,500円の木戸銭を払えば、最大8時間30分そこにいられる計算だ。途中退場した場合の再入場は認められないが、寄席の中には飲食物の販売もあり、近くのコンビニへ寄る必要がないようにできている。
その雰囲気は、映画館よりも「気楽」と表現してもいいかもしれない。

「笑えない」落語家の実力
寄席の楽しみ方は、人それぞれである。
『笑点』に出てくる有名な落語家の噺を聴きに行くという目的でもいいし、まだあまり名が知られていない二ツ目を応援する目的でもいい。しかし、覚悟するべきは「噺の上手さ・面白さ」はよほどの例外を除いて身分の順番通りという点だ。
前座は通常であればプログラム(番組)に名前が載ることはない。「前座」という肩書通り、一番最初に登場して『寿限無』や『子ほめ』といった最も基本的な噺を繰り出す。誰もが内容を知っている噺のため、これで笑う客はまずいない。
二ツ目はこの業界のジャーニーマンだが、笑える落語家と笑えない落語家が混在している。ここで言う「笑えない」とは、必ずしも「つまらない」という意味ではない。笑える噺よりも怪談やシリアスな内容の語りのほうがあまりにも向いているため、結果として客の顔が真剣そのものになってしまうという現象も時折見受けられるのだ。
もちろん、それもまた「才能」である。
寄席小屋とは、様々な形の才能を低料金で堪能できる場所と言えるだろう。
文/澤田真一
AIとガチ恋?AIとマッチングする話題のアプリ「LOVERSE」を試してみたら想像以上に沼だった
恋愛は大変な仕事である。費用も時間も体力も費やす一大事業と言ってもいいだろう。 その上で、恋愛は「失敗の可能性」が小さくないという点も考慮しなければならない。も…















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE