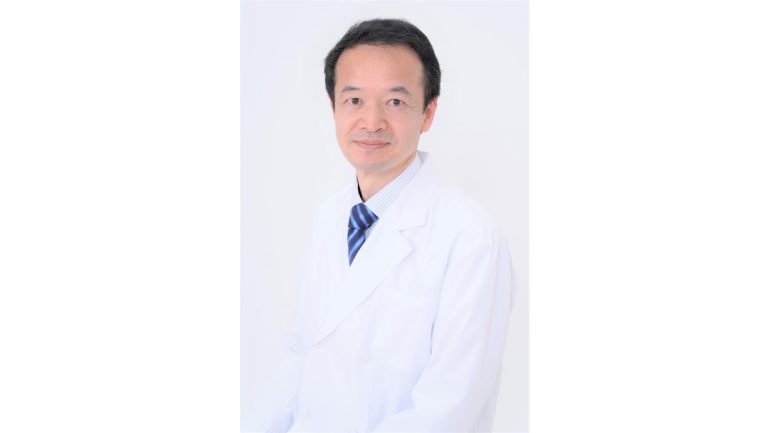温泉がますます恋しくなる季節が到来。湯けむりを満喫する旅のプランを立てている人も多いのではないだろうか。
旅立つ前にぜひ知っておきたいのが、温泉・入浴の健康効果と目からウロコの正しい温泉の入り方。温泉療法研究の第一人者であり、星野リゾートの温泉旅館「界」の温泉の監修を務める早坂信哉先生に教えていただいた。
地域医療をきっかけに、入浴に関する調査研究を開始
――早坂先生が温泉や入浴の研究を始めたきっかけを教えてください。
早坂先生 今から30年ほど前、宮城県の医療機関で内科医を務めていた際、多くのお年寄りを診察しているなかで、彼らにとって訪問入浴サービスがとても重宝しているのを日々実感するようになりました。入浴に健康効果があることはみなさんもなんとなくご存じかとは思いますが、いざ調べてみると、当時は例えば安全な入浴法などを医学的に研究している人はほとんどいなかったんです。これはちゃんと研究したほうがいいなと感じて、1998年に入浴に関する調査研究をスタートしました。
――ズバリ、温泉・入浴はなぜ健康によいのでしょうか。
早坂先生 まず、入浴には以下の7大健康作用があります。
(1) 温熱作用
・血流がよくなるので栄養や酸素が行き渡り、老廃物が血液中に排出。デトックス効果が高まり疲れが取れる
・いったん上がった体温が入浴後に急に下がり、質の高い睡眠につながる
・身体が温まると神経の過敏性が抑えられて痛みが取れ、また身体の柔軟性がアップすることで、身体活動の低下による症状を改善
・副交感神経が優位になり、緊張やストレスをリリースできる
(2) 浮力作用
・お湯に肩までつかると体重が約10分の1になり、凝り固まった筋肉が休まる
(3) 水圧作用
・座りっぱなしで下肢にたまった血液やリンパ液を心臓へ押し戻す
・むくみの改善につながる
(4) 清浄作用
・湯にしっかりつかることで角層が柔らかくなり、かなりの汚れが落ちる
・石鹸やボディソープを使う量が減り、タオルでゴシゴシこすらなくてもよくなる
(5) 蒸気・香り作用
・鼻や気管が潤い、線毛運動が改善される
・好きな香りの入浴剤を投入すると、自律神経が整いやすくなる
(6) 粘性・抵抗性作用
・水から受ける抵抗を利用し、アクアビクスやリハビリに応用できる
(7) 開放・密室作用
・衣服を身につけずに裸になるという非日常に、心身ともにリラックスできる
早坂先生 これらの7つの作用に加え、温泉には特有の作用があります。それが以下のとおりです。
(1) 温熱作用がより強い
(2) 保湿効果
(3) 殺菌作用
(4) 温泉成分の吸収(皮膚・呼吸)
(5) 転地作用(場所が変わることによるリフレッシュ作用)
温泉の効果をさらに高める2つのコツ
――こんなにたくさんの作用が医学的に証明されているとは! 日本には古くから湯治という文化がありますが、理にかなっているということですね。
早坂先生 実は環境省が2018年から実施している「全国『新・湯治』効果測定調査プロジェクト」というものがあるんです。現代版の湯治を「新・湯治」と銘打ち、その効果を把握したうえで全国に広めていこうという温泉地活性化プロジェクトで、私は効果測定を担当しました。6年をかけて2万人近くにアンケート調査を行ったところ、ほとんどの人が温泉地訪問後に「癒やされた」「リフレッシュできた」などのポジティブな変化が起きたと回答。さらに、興味深いエビデンスを2つ取ることができました。
――ふむふむ、気になります。
早坂先生 ひとつは、ただ単に温泉に浸かって過ごすだけでなく、ゴルフや登山などの運動、温泉地での観光や食べ歩き、マッサージやエステなどのアクティビティを行った人ほど、「ストレスが減った」「肌の調子がよくなった」などの心身の変化を感じていたということでした。
――温泉宿にこもってひたすらのんびり過ごすよりも、プラスアルファの体験をしたほうがお湯の効果をより感じる、ということですね。
早坂先生 はい。そしてもうひとつが、一度に長く滞在するよりも、年間を通して何度も温泉を訪れるほうが心身へのよい影響が見受けられたことです。















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE