
2025年の年末調整から、税制改正により給与所得控除が引き上げられます。年末調整から対応が変わるため、内容の確認と早めの準備が大切です。
目次
2025年の年末調整から給与所得控除の変更について、よくわからないという方も多いのではないでしょうか。税制改正により、給与所得控除額の最低保障額の引き上げが行われます。
本記事では、給与所得控除の変更をはじめとする2025年の年末調整の改正点や源泉徴収事務での留意点などをご紹介します。
給与所得控除とは

給与所得控除とは、給与を受け取る人の所得から一定額を差し引き、課税対象となる所得を軽減するための控除です。
ここでは、給与所得控除の概要を簡単にみていきましょう。
■給与収入から差し引かれる
給与所得控除は、給与や賞与などの収入から一定額を必要経費とみなして差し引き、課税対象となる所得を軽減する制度です。正社員や契約社員、パート・アルバイトなど給与所得者が対象で、収入に応じて控除額が定められています。
これにより、実際の生活費や仕事にかかる経費を考慮した課税が可能になり、所得税や住民税の負担を軽減できます。控除は、年末調整や確定申告で自動的に反映されるのが特徴です。
■所得控除との違い
給与所得控除と同じく、一定の金額を差し引いて節税できる控除に「所得控除」があります。
所得控除は、納税者それぞれの事情に応じて所得から一定の金額を差し引く制度のことです。給与所得控除などで算出された課税所得から、扶養控除や基礎控除、社会保険料控除などの各種控除額を差し引いて、最終的な課税所得を算出します。
一方、給与所得控除は、給与や賞与などの収入から必要経費とみなして一定額を差し引き、課税対象となる所得を減らすものです。
給与所得控除が収入段階での経費控除であるのに対し、所得控除は課税所得段階での控除という点が異なります。
2025年(令和7年)税制改正による変更

2025年(令和7年)の税制改正で、給与所得控除の見直しが行われました。
ここでは、改正の具体的な内容と、その背景にある目的について詳しく解説します。
■最低保障額を65万円に引き上げ
2025年の改正では、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。これにより、給与収入が190万円以下である給与所得者の控除額が最大10万円増加します。なお、給与収入190万円超の控除額に変更はありません。
控除額の引き上げにより低所得者層の課税所得が減少し、所得税の負担が軽くなります。この改正は所得税では2025年分から、住民税では2026年度分(2025年分所得)から適用される予定です。
■改正の目的
給与所得控除が引き上げられる改正の目的は、給与所得者の実質的な負担軽減と税制の公平性確保です。最低保障額の引き上げにより、低所得者層でも一定の控除が確保され、課税所得が減ることで所得税負担が軽減されます。
また、高所得者に対しては控除額の逓減が行われることで、所得格差に応じた公平な課税が実現されます。給与所得控除の見直しにより、働く世代の税負担を適正化し、より公正な所得税制度が期待できるでしょう。
■改正前の給与所得控除制度の概要
改正前の給与所得控除制度では、給与所得者の必要経費を概算で控除する仕組みが設けられていました。控除額は給与収入に応じて段階的に決まり、収入が増えるほど控除額も増加する仕組みであり、この点では改正後も変わりません。
また、控除上限が設定され、所得が高い給与所得者は控除額が頭打ちとなるなど、収入格差に応じた税負担の調整も行われていました。
ただし、改正前の最低保障額は55万円で、一定の低所得者層には控除の恩恵が限定的といえる状況でした。
■改正後の控除額
改正後の給与所得控除制度では、給与所得者の実際の必要経費をより適切に反映させるため、控除額の最低保障が引き上げられています。
最低控除額は従来の55万円から65万円となり、給与収入が190万円までの低所得者にも控除の恩恵が広がります。
一方で、高所得者向けの控除上限や段階的控除の仕組みも見直され、所得に応じた適正な税負担が確保されるようになりました。
2025年の年末調整と2026年分以降の給与の源泉徴収事務での留意点
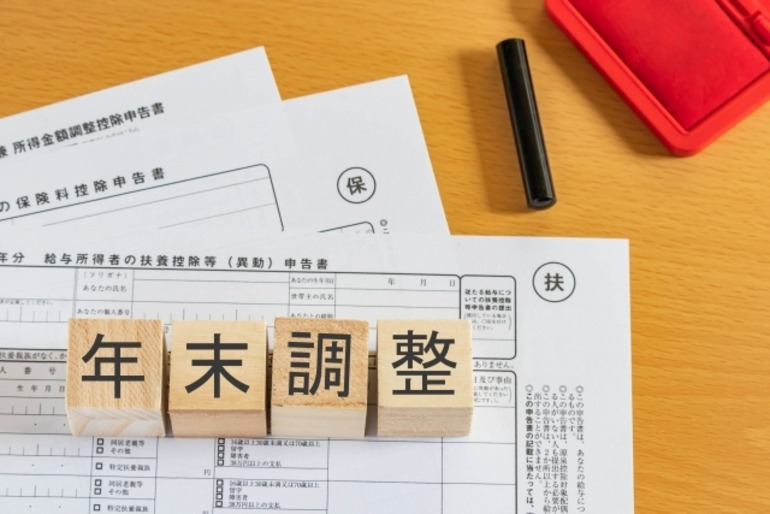
給与所得控除の見直しをはじめとする改正は原則として2025年(令和7年)12月1日から施行されます。2025年(令和7年)以降の所得税に適用され、その時期以降の年末調整やその他の源泉徴収事務では変更が生じます。
なお、令和7年11月までの給与については現行制度による源泉徴収処理となり、源泉徴収業務に影響はありません。
2025年の年末調整事務や、2026年(令和8年)分以降の給与支払いにおける源泉徴収事務では、以下の点に留意しましょう。
■源泉控除対象親族の記載が正しいか確認する
2025年分の年末調整では、改正内容を踏まえ、新たに扶養控除等の対象となる親族がいないかを従業員に確認しましょう。もし該当する親族がいる場合は、その旨を記載した「扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいます。
さらに、2026年以降についても、従業員が提出する扶養控除等申告書の内容を精査し、源泉控除の対象となる親族が正しく記載されているかを確認することが大切です。
■新たな源泉徴収税額表に基づいて計算する
2025年の年末調整では、改正後の基礎控除額や給与所得控除額など、新しい税制内容を反映した源泉徴収表に基づいて計算を行います。従来の控除額や課税範囲と異なる結果となる場合があるため、担当者は早めに改正内容を確認し、システム設定や計算方法を見直しておくことが大切です。
また、2026年以降は、毎月(または毎日の)給与支給時に行う源泉徴収についても、新しい源泉徴収税額表に基づいて正しく処理しなければなりません。最新の資料を確認し、運用開始前に社内で周知しておくことが求められます。
2025年(令和7年)税制改正によるその他の改正

今回の税制改正では、給与所得控除のほかにも基礎控除の改定や扶養控除・配偶者控除の所得基準の変更など、複数の制度が見直されました。
さらに、新たな制度として「特定親族特別控除」が導入されるなど、大きな変更が行われています。
それぞれの改正内容について、みていきましょう。
■基礎控除の見直し
今回の改正では、すべての納税者が対象となる「基礎控除」の内容も見直されました。基礎控除とは、所得金額にかかわらず一律に差し引ける控除で、所得税や住民税の課税対象となる所得を減らす役割があります。
従来の48万円から原則58万円へと10万円引き上げられ、合計所得金額が132万円以下の低所得者については、時限的な措置として最大95万円の基礎控除が適用されます。この時限的な加算額は、所得が132万円を超えると段階的に減少する仕組みです。
これにより、より多くの所得を得ている人は控除額が少なくなりますが、合計所得金額が2,350万円を超える場合の基礎控除額については、従来どおり変更はありません。
■扶養控除・配偶者控除などの所得要件の緩和
基礎控除や給与所得控除の変更に伴い、扶養控除や配偶者控除などの適用条件となる所得の上限も以下のように緩和されます。
| 対象 | 変更内容 |
| 扶養親族同⼀⽣計配偶者ひとり親の⽣計を⼀にする⼦ | 48万円以下→58万円以下に変更 |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 48万円超133万円以下→58万円超133万円以下に変更 |
| 勤労学生 | 75万円以下→85万円以下に変更 |
今回の改正により、これまで扶養控除の対象外だった「年収103万円を超え130万円未満の家族(配偶者・子ども・親など)」が、新たに控除対象となるケースが出てきます。
さらに、勤労学生は、合計所得金額の上限が従来の75万円から85万円へと引き上げられ、アルバイトなどで一定の収入がある学生でも、より幅広く控除を受けられるようになっています。
■特定親族特別控除の創設
今回の改正では、「特定親族特別控除」が創設されました。納税者と生計を一にする所定の親族がいる場合に、その親族1人につき定められた金額を所得から控除できる制度です。
特定親族特別控除の控除の対象となる「特定親族」とは、以下の条件を満たす人を指します。
- 年齢が19歳以上23歳未満であること
- 配偶者や青色・白色事業専従者ではないこと
- 合計所得金額が58万円を超え123万円以下であること
- 児童福祉法に基づき養育を委託された「里子」も対象に含まれること
この制度により、該当する親族を扶養する従業員は課税所得が減り、税負担の軽減が期待できます。















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE













