2025年の年末調整用チェックリスト

2025年の年末に行う年末調整では、従業員から提出される書類と担当者が作成する書類の種類は多く、漏れのないよう注意が必要です。
ここでは、それぞれのチェックリストを紹介しますので、自社の業務に合わせてカスタマイズしてご活用ください。
■従業員から提出される書類
年末調整で従業員に提出してもらう書類は、以下のとおりです。
| 書類 | 内容・ポイント | チェック |
| 扶養控除等(異動)申告書 | 扶養親族の氏名・生年月日・続柄・所得状況が正しく記載されているか確認する | ⬜︎ |
| 給与所得者の基礎控除申告書 | 所得金額が2,350万円を超えると金額が減少するいう制限が設けられるため、申告書に所得金額の記載が必要になる | ⬜︎ |
| 給与所得者の配偶者控除等申告書 | 配偶者の所得に基づき、配偶者控除・配偶者特別控除の適用ができるかを確認する | ⬜︎ |
| 給与所得者の特定親族特別控除申告書 | ・令和7年分以後に新設された特定親族特別控除の適用を希望する場合に提出する ・親族の年齢や所得が要件に合うか確認する | ⬜︎ |
| 所得金額調整控除申告書 | 所得金額調整控除を受けるための要件が記載されているか確認する | ⬜︎ |
| 保険料控除申告書 | 生命保険料・地震保険料・個人年金保険料などの控除対象額が記入されているか確認する | ⬜︎ |
さらに、控除の内容によって、以下のような証明書類の回収も必要です。
- 生命保険料控除の証明書
- 地震保険料控除の証明書
- 小規模企業共済等の掛金支払証明書 (iDeCoの掛金がある場合も含む)
- 国民年金などの社会保険料控除を証明する書類
- 住宅ローン控除で必要となる、年末時点の借入残高証明書
国民健康保険の保険料控除に関する証明書は、自治体によって発行の有無が異なります。
■給与担当者が作成する書類
担当者が年末調整事務で作成する書類は、以下のとおりです。
| 書類 | 内容・ポイント | チェック |
| 年末調整計算表 | 基礎控除・給与所得控除・扶養控除・特定親族特別控除などを反映して計算する | ⬜︎ |
| 源泉徴収票 | 年末調整の結果を反映して作成し、従業員へ交付する | ⬜︎ |
| 社会保険料・所得税控除額確認表 | 提出書類と控除計算の整合性をチェックする | ⬜︎ |
| 過不足税額確認表 | 年間の源泉徴収額と確定控除額を比較し、過不足の精算を確認する | ⬜︎ |
| 保存用書類一式 | 提出書類・計算書・源泉徴収票控えなどを法定保存期間に従って保存する | ⬜︎ |
年末調整を行い計算が完了すると、従業員ごとの所得や源泉徴収額が確定します。会社はこれを源泉徴収票として従業員に通知すると同時に、翌年1月31日までに税務署や市区町村へ必要な書類を提出する義務があります。
税務署に提出する書類
| 書類 | 内容・ポイント | チェック |
| 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 | ・源泉徴収票や支払調書などの法定調書を税務署に提出する際に添える書類 ・法定調書一式の表紙のようにして添付する | ⬜︎ |
| 給与所得の源泉徴収票 | 年末調整をした従業員で、その年中の給与等の支払金額が500万円(役員については150万円)を超えるもののみを提出する | ⬜︎ |
| 退職所得の源泉徴収票 | その年に退職金の支払いのあったときに、退職金や退職所得控除などの情報を記載する | ⬜︎ |
| 社会保険料・所得税控除額確認表 | 提出書類と控除計算の整合性をチェックする | ⬜︎ |
| 過不足税額確認表 | 年間の源泉徴収額と確定控除額を比較し、過不足の精算を確認する | ⬜︎ |
| 保存用書類一式 | 提出書類・計算書・源泉徴収票控えなどを法定保存期間に従って保存する | ⬜︎ |
市区町村に提出する書類
| 書類 | 内容・ポイント | チェック |
| 給与支払報告書(総括表) | ・給与支払報告書の表紙のようなもの ・会社名や所在地、全従業員のうち何人がその市区町村に住んでいるかなどの情報を記載する | ⬜︎ |
| 給与支払報告書(個人別明細書) | ・一般的に記載内容は源泉徴収票と同じ ・原則として全員分を提出する | ⬜︎ |
年末調整の流れ

年末調整の事務をスムーズに進めるためには、基本的な流れを押さえておくことが大切です。
全体のスケジュールをまとめると、以下のようなスケジュールになります。
| 6〜8月 | スケジュールを立てる |
| 9月〜11月 | ・従業員への案内と申告書の配布 ・法改正についての説明 ・記載方法・提出期限・添付書類を案内 ・回収後に内容を確認 |
| 12月 | ・各従業員の税額を計算 ・従業員配布用・税務署提出用の源泉徴収票を作成 |
| 1月 | ・法定調書の作成 ・税務署へ源泉徴収票・法定調書合計表・支払調書を提出 ・市区町村へ給与支払報告書を提出 |
ここでは、9月からの年末調整の手続きについて、順を追って解説します。
■申告書の配布・回収(9月〜11月)
年末調整の準備は、毎年9月〜11月頃に従業員への申告書の配布・回収から始まります。この期間に、会社は「扶養控除等(異動)申告書」や「生命保険料控除申告書」など、年末調整に必要な書類を従業員に配布します。
従業員は自分や家族の情報、支払った保険料や掛金などを記入し、期限内に会社へ提出するという流れです。
11月中旬から下旬頃までには書類を回収できるよう、対象となる従業員には早めに案内しておくようにしましょう。法改正についての周知も重要です。
さらに、記入方法や提出手順について質問が寄せられる可能性もあるため、事前に対応体制を整えておくことも大切です。
会社は提出内容を確認し、不明点や誤記があれば従業員に照会して修正を依頼します。この準備段階を丁寧に行うことで、年末調整の計算や源泉徴収票の作成をスムーズに進めることができるでしょう。
■年税額の計算・源泉徴収票の発行(12月)
12月に入り、その年の給与やボーナスの合計額が確定した段階で、年末調整に基づく従業員の年間所得や税額の計算を行います。
給与担当者は、従業員から提出された扶養控除等申告書や各種控除証明書に基づき、基礎控除・給与所得控除・社会保険料控除・生命保険料控除などを反映して所得税額を算出する仕組みです。
所得税の計算後、従業員の給与から差し引くべき税額を確定させ、過不足があれば調整を行います。また、調整後の情報をもとに、従業員に「源泉徴収票」を作成・発行するという流れです。
源泉徴収票には年間の給与総額や控除額、源泉徴収税額などが記載され、従業員が確定申告を行う場合や住宅ローン控除の申請などに使用されます。作成した源泉徴収票は、従業員本人への交付に加え、翌年1月31日までに税務署へ提出しなければなりません。
これらの作業により、従業員の税額が正確に反映され、会社としての法的義務も果たされます。事前に書類の不備がないか確認し、円滑に作業を進めることがポイントです。
■法定調書・給与支払報告書の作成・提出(1月)
年末調整の処理が完了して従業員ごとの所得や控除の内容が確定したら、翌年1月には法定調書や給与支払報告書の作成・提出が必要です。
法定調書は、給与や賞与、退職金などの支払状況を税務署に報告するための書類で、源泉徴収税額や控除額も記載されます。
給与支払報告書は、市区町村に対して従業員の所得や税額を通知する書類で、住民税の計算に使用されます。
これらの書類は、作成にあたり従業員の扶養控除等申告書や年末調整結果をもとに正確な情報を反映させなければなりません。税務署や市区町村への提出は期限を守ることが義務付けられており、電子申告(e-Tax)や電子提出に対応している場合は、これを活用することで作業の効率化が図れます。
また、提出後は控えを保存し、必要に応じて従業員や税務署からの問い合わせに対応できる体制を整えておくことが大切です。
2025年の法改正を把握しよう
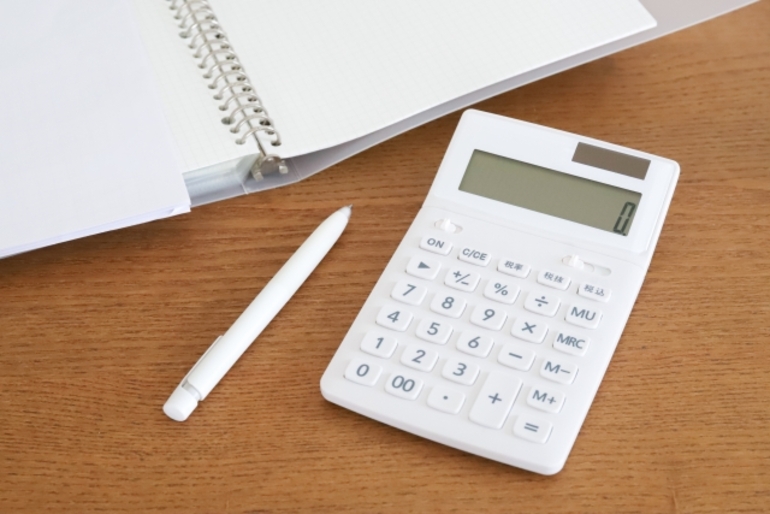
年末調整は、税制改正によって内容が大きく見直されます。2025年(令和7年)分の年末調整では、所得税の基礎控除や給与所得控除の変更に加え、新たに「特定親族特別控除」が創設されます。
基礎控除は48万円から最大95万円に引き上げられ、給与所得控除は上限が引き下げられるなど、年末調整事務に大きな影響があるため、担当者は早めに確認しておきましょう。
従業員は、従来の扶養控除等申告書に加え、要件に該当する場合は特定親族特別控除申告書も提出する必要があり、これまでとは対応が異なります。改正の内容について、早めに周知しておくことが必要です。
年末調整の計算や源泉徴収額の設定に変更が生じるため、給与担当者は記載内容の確認や新しい控除への対応と、正確な処理が求められます。また、適切な書類管理も忘れずに行いましょう。
構成/須田 望















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE













