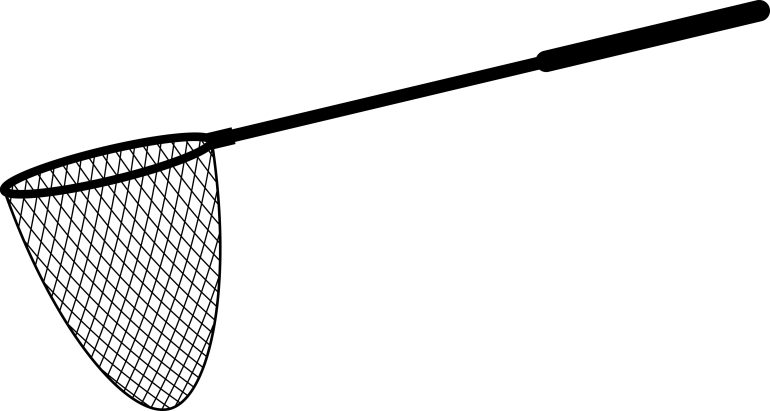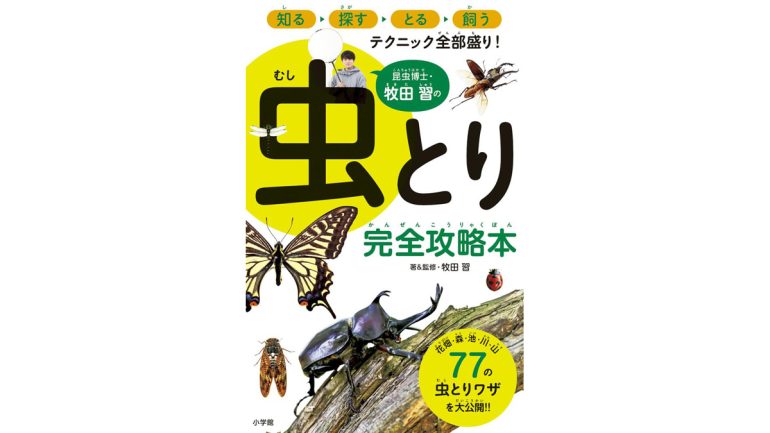今年は遅くやってきた秋。草むらなどから虫たちの鳴き声が聞こえてくる機会も多くなってきたのではないでしょうか?しかしながら、鳴き声はよく聞くけど、どんな姿の昆虫が鳴いているかを知らないという方も多いはず。そこで、今回は代表的な鳴く虫たちの生息地とその採集方法について解説いたします。
身近な場所でも見ることのできる鳴く虫たち
そもそも、鳴く虫とは文字通り、鳴き声を出す虫のことですが、昆虫好きの間では一般的に、直翅目のコオロギ科やキリギリス科などに属する鳴き声を出す仲間のことを意味します。一部にはメスも鳴く種類がいますが、オスのみが鳴き声を出す種類がほとんどです。まずは身近な場所でこれからの時期にも見ることのできる種類を中心に鳴く虫5種類を紹介させていただきます。
(1) エンマコオロギ
コオロギ科コオロギ亜科に属する一種で、閻魔大王のような顔を持つことからその名前がつけられました。オスが「コロコロリー」と鳴き声を出し、日本で最大かつ最も普通なコオロギで、北海道から九州まで広く分布しています。
(2) アオマツムシ
コオロギ科マツムシモドキ亜科に属する種類で、オスは「リーリーリー」と大きな鳴き声で鳴きます。動きがゴキブリに似ていることから「アオゴキブリ」と呼ばれることもあります。また、現在は東北地方中部~九州までの広い地域で見られますが、元々は日本にいなかった種類で、明治時代に中国から人間によって持ち込まれたと考えられています。
(3) カンタン
コオロギ科カンタン亜科に属する種類で、オスは「ルルルルルルル」と鳴きます。オスの翅のつけ根から出る甘い物質をメスが舐めている間に交尾するという一風変わった生態を持っています。北海道から九州までの広い地域で秋遅くまで見ることができます。
(4) ササキリ
キリギリス科ササキリ亜科に属する種類で、オスは「シリシリシリシリシリシリ」と鳴きます。名前はササに住むキリギリスの仲間であることに由来します。東北地方南部~沖縄までの地域に広く分布しています。
(5) カネタタキ
カネタタキ科に属する種類で、オスは「チンチンチン」というまさに鐘を叩くような鳴き声で鳴きます。8月頃から12月頃までというかなり長い期間見ることができ、夏は夜にしか鳴かないのに対して、秋になると昼夜問わず鳴くようになります。東北地方中部から沖縄まで広く分布しています。
鳴く虫を探すのに適した場所
次は鳴く虫が好む環境について解説いたします。鳴く虫は都市部から自然豊かな森までいろいろな場所に生息していますが、今回は都市部の公園、河川敷、森の近くで見られる鳴く虫それぞれについて解説いたします。
(1) 都市部の公園
東京や大阪などの都市部の公園であっても、エンマコオロギやアオマツムシ、カネタタキなど多くの鳴く虫たちが生息しています。特にエンマコオロギは市街地でも鳴き声をよく聞きますし、アオマツムシは樹上性のため、街路樹の上にいることがよくあります。同じく樹上性のカネタタキは住宅地にも多く生息しています。
(2) 河川敷
河川敷の草むらにも多くの鳴く虫が生息しています。(1)で紹介した市街地で見られるような種類はもちろん、マツムシやカンタン、キリギリスの仲間なども見つけやすいです。また、自然度の高い場所のススキの原っぱなどでは9月頃までであれば、野生では比較的珍しいスズムシが見つかることもあります。
(3) 森の近くの草むら
森の周りには数の多くの鳴く虫が生息しており、特に林縁部などでは様々な音色が聞こえてきます。上記で紹介してきた種類と共に、10月以降でもササキリやクツワムシなどを観察することができます。
採集方法について
鳴く虫の生息地で実際に採集するための方法を紹介します。まず、鳴く虫を探しに行くのにおすすめの時間は多くの種類が活発に鳴く夜間帯です。とはいえ、いきなり夜の森に行くのは危険も伴うため、明るい時間に下見をして、夜にどのあたりを探索するかの目星をつけておきましょう。鳴く虫の探索は両手を使うことが多いため、頭につけるヘッドライトを持参することをおすすめします。
採集方法は仲間によって異なります。まず、草むらの葉っぱの上などにいることの多いキリギリスの仲間などを捕まえるには前もって網を2つ用意しておくことをおすすめします。鳴き声を頼りに探して姿を確認したら、彼らが逃げて飛びそうな方向や下側に1つの網を構えておいて、もう1つの網で捕まえようとするとゲットできる確率が高まります。
次に地面の近くにいるコオロギの仲間などは草むらをかき分けていき、姿を見つけたら、小さな網やプラスチックコップなどを使って追い込んで捕まえることをおすすめします。
一方、カネタタキやアオマツムシなどの樹上性の種類は枝や葉の下に傘を逆さにして構え、上から叩くと、びっくりして傘の方向に落ちてきてくれます。鳴き声が聞こえる木があれば、積極的に試してみましょう。

さて、今回は秋の風物詩である鳴く虫の生息地や採集方法について解説してきましたが、飼育も簡単な種類が多く、市販の餌や野菜などを与えることで飼育することができます。鳴き声を楽しむ のもいいですが、採集して観察してみると、彼らの魅力をより知ることができるはずです。
昆虫ハンター・牧田習
博士(農学)。1996年、兵庫県宝塚市出身。2020年に北海道大学理学部を卒業。同年、東京大学大学院農学生命科学研究科に入学し、2025年3月に同大学院博士課程を修了。昆虫採集のために14ヵ国を訪れ、9種の新種を発見している。「ダーウィンが来た!」(NHK)「アナザースカイ」(NTV)などに出演。現在は「趣味の園芸 やさいの時間 里山菜園 有機のチカラ」(NHK)、「猫のひたいほどワイド」(テレビ神奈川)にレギュラー出演中。昆虫をテーマにしたイベントにも多数出演している。
著書:「昆虫博士・牧田習の虫とり完全攻略本」(小学館)、「昆虫ハンター・牧田習のオドロキ!!昆虫雑学99」(KADOKAWA)、「昆虫ハンター・牧田習と親子で見つけるにほんの昆虫たち」(日東書院本社)、「春夏秋冬いつでも楽しめる昆虫探し」(PARCO出版)好評発売中。Instagram・Xともに@shu1014my
昆虫博士・牧田習さんが解説!日本で絶滅が危惧される意外な昆虫たち
昆虫は環境の変化を受けやすい生き物であり、私たち人間が気づかないうちに、多くの種類が絶滅の危機に瀕しています。その中には「この昆虫、昔はたくさん見たのに!?」と…















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE