
近年の登山ブーム以来、山で遭難する人の数は右肩上がりに増えている。昨年は微減したものの、それでも3千人以上が遭難し、死者・行方不明者は300人に上った。
なかでも最近の傾向として挙げられるのが、「入山前遭難」の増加。まったくの準備不足で登って、救助を要するトラブルに遭うことから、登山前に遭難が確定しているような状況をこう呼ぶ。
実際にどのような「入山前遭難」が起きているのか、また未然に防ぐためのアドバイスを、『あなたはもう遭難している』(山と溪谷社)の著者、羽根田治さんにうかがった。
観光地化された山でも遭難事故はある
――標高約600メートルの高尾山のような低山でも、入山前遭難があるそうですね。
観光地化した山ですと、転んで怪我したといった軽微な遭難事故が多いと思います。登山者というより観光客が遭難しているようです。やはり、準備や装備が足りなすぎるのが原因です。極端な話、ペットボトル1本だけしか持たずに登り、痛い目に遭う人が後を絶ちません。
『あなたはもう遭難している』の中でも、車窓から見えた富士山がきれいだったからと、何の準備もせずに登って遭難という事例を載せています。毎年夏になるとテレビでは、老若男女が列をなして富士山を登る映像が流されます。それを見て、誰でも気軽に登れる山というイメージが根付いたというのもありますね。もっとも富士登山は、昨年から規制がかけられ、遭難者は大幅に減少しました。
低山ブームですが、低くても何かしらのリスクが伴うものです。相応の準備は必要と心得るべきです。
絶対に持っておくべき意外なアイテム
――低い山であっても、最低限持つべき装備として、どんなものがありますか?
意外かもしれませんが、ヘッドランプです。これがないと、アクシデントが起きて日没までに下山できなくなった場合、行動不可能となります。持っていないがために、救助を要請してくるケースは多いです。
スマホのライトで大丈夫と思う人もいますが、光量は乏しいですし、バッテリーもそう持ちません。それなりの光量があるヘッドランプは、必需品と考えましょう。
服装に関しては、涼しい時期でも行動していると汗はかきます。それで休憩すると、汗が冷えていきなり寒くなります。そのため、体温を保てる適切な服装を携行しましょう。低山でも薄手のフリース素材のウェアや、風を防げるウインドジャケットは持つべきです。必要なウェアは、山や季節によって変わってきますが、登山用のものを選ぶのが肝心。アウトドア専門店の店員に聞いて、アドバイスを受けるのが確実です。
登山用の雨具は必携品
――秋が深まる今の季節、うっかり忘れやすい装備はありますか?
雨具ですね。100円ショップで売っているようなペラペラのレインコートではダメです。登山用の雨具は必ず持って行ってください。
今年から富士山では、登山者の装備をチェックして、「装備不足の人は登れません」という指導が始まりました。そこで、登山用の雨具を持っていない人は、「入山ゲートにある登山ショップで購入しなさい」と言われました。
山の天気は変わりやすいし、通常の天気予報は下界の話なのであまりあてになりません。低山でも、雨具は絶対に持つことを心掛けてください。
予備の1食と行動食は忘れずに
――さほど高くない山で日帰りする場合、持参する飲食物の中身・分量の目安はありますか?
みなさん、お昼御飯は持っていくと思いますが、念のためもう1食分は用意してください。プラスして行動食も持つといいでしょう。これは、火を通さずに食べ歩きできるチョコレート、ビススケット、エナジーバーといった軽食をいいます。
飲み物として水も忘れないでください。分量は、汗っかきであるとか人によって異なりますが、目安として夏場だと1人2リットル、夏でなくても、最低1リットルは持ったほうがいいでしょう。詳しく言えば、登山時の脱水量は、体重(kg)×行動時間(時間)×5 mlで求められ、その70?80%を補給するのが目安です。
どんな山でも登山届を出す
――ご著書を読んで意外と思ったのは、登山届です。危険な山についてだけ、提出が義務付けられているものと勘違いしていましたが、そうではないのですね。
どんな山であっても登山届は提出しておいたほうがいいです。トラブルに見舞われて下山できなくなった時に、すぐ探してもらえるというメリットは大きいです。
多くの自治体では、フォームに入力してインターネットで提出できるようになっています。これは便利なので、ぜひ活用してください。
実はあぶない大人数での登山
――1人の登山の危険性は承知していても、それなら多人数なら安心かと思ったら、そうでもないのですね。
実は、人数が多ければ多いほど、リスクは高まるものと考えたほうがいいです。
大人数のパーティーだと、各人の体力レベルが異なってくるものです。すると、どうしても登るのが早い人と遅くなる人が出てきて、バラバラになりやすいのです。「自分は遅いから先に行ってて」と言った人が、全然追いついてこなくて、探したら遭難していたという事例は結構あります。小さな子供がいる家族連れは、特に注意が必要です。
また、危険箇所を通過する場合などは、大人数だとそのぶん時間がかかるので、リスクにさらされる時間も長くなってしまいます。
主観の多いネット上の情報には要注意
――最近は、インターネット上の登山情報が充実している印象があります。こうした情報源を活用するとよいでしょうか?
山小屋や自治体、山岳救助隊などの公的なサイトは役立ちます。一方、個人が発信している情報を100%参考にするのは、おすすめしていません。一個人の主観にもとづいた情報が多いからです。例えば動画のなかで、実際には難しいルートをいかにも簡単そうに登っていたり……。それを鵜呑みにして、遭難につながるリスクはあると思います。もちろんネットでは最新情報が入手できるし、個人が発信する情報にも正確なものもるので、そこはきちんと取捨選択できればいいでしょう。
書籍や山岳雑誌などは、情報の裏付けをしっかりとっているはずなので、信頼していいと思います。ただし掲載されている情報が古くなっていることもあるので、確認が必要です。
ちょっとの不調で救助要請する人が多い
――万全の体制で登山に臨んでも、アクシデントが起こる可能性は常にあると思います。救助を頼む、頼まないの判断の目安はありますか?
自分で対処できるかどうかが、目安となります。怪我をしても応急手当をして行動できるのなら、救助要請する必要はありません。しかし、自力で下山できないと判断したなら、救助を頼むべきです。
ただ、最近は、疲労、体調不良、足がつったといった理由で救助要請する人が少なくありません。そのような場合は、休憩をとって様子を見て、回復しそうかどうかを見極めてから、要請すべきでしょう。そのあたりの判断は、常識にも照らして行うようにしたいですね。
お話を伺った方:羽根田治さん
1961年、埼玉県出身、那須塩原市在住。フリーライター。長野県の山岳遭難防止アドバイザー、日本山岳会会員。山岳遭難や登山技術に関する記事を、雑誌・書籍などで発表する一方、沖縄、自然、人物などをテーマに執筆を続けている。著書に『ロープワーク・ハンドブック』『野外毒本』『パイヌカジ 小さな鳩間島の豊かな暮らし』などあり、最新の著書は『あなたはもう遭難している 本当にあったびっくり遭難に学ぶ登山の超基本』(いずれも山と溪谷社)
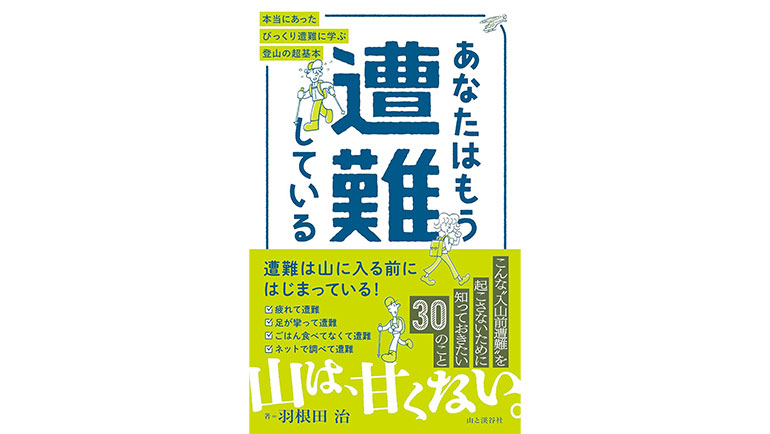
取材・文/鈴木拓也
1位は横浜みなとみらいの「コスモクロック」 絶景が満喫できる観覧車TOP10
観覧車は、実はとっておきの絶景が味わえるスポットでもある。空に浮かぶような気分で、海や山、きらめく街の夜景まで一望できる特等席。さらに空調が効いている観覧車も多…
しながわ水族館のイルカショーが終了するって本当?30年以上の歴史に幕を閉じる背景
1991年10月19日に開館した「しながわ水族館」。 首都圏(都内)で初めてイルカショーが観られる水族館として話題となり、開館当時はイルカショー人気もあり、年間…















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE
















