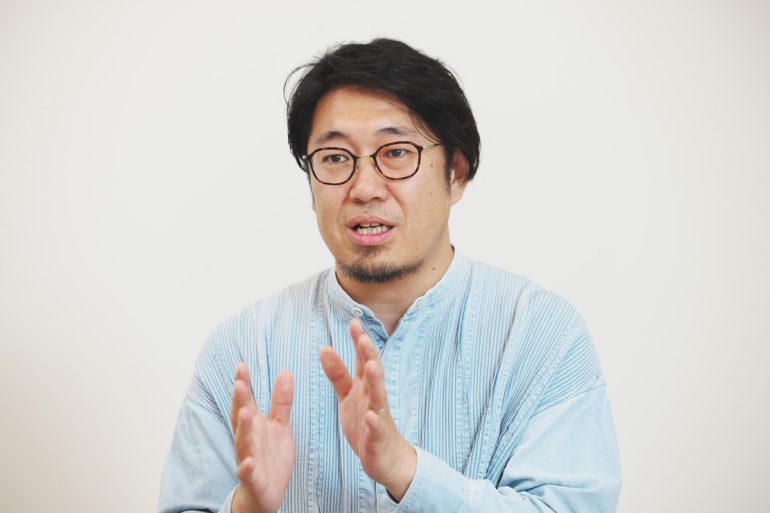ビューティーディレクター MICHIRUさんとおくる、連載「Wellbeing beauty by MICHIRU」。
連載第6回はビューティーの世界を飛び出し、食の領域へ。2025年7月に本格オープンした、会員制オンラインスーパーマーケット「Table to Farm(テーブルトゥファーム)」。ディレクター・発起人の相馬夕輝さんに、食の世界の課題と新しい取り組みについて伺った。
美味しいものが減っている。でも、できることはある
MICHIRUさん(以下、MICHIRU):この連載では、これまで化粧品やビューティー関係のブランドや会社に取材に行っていました。そこでみなさんのお話を聞くと、多くのブランドが「口に入れても安全であること」を大切にされていました。健康も美容も行き着く先は“食”。安全で、心から信頼できて、体が喜んで受け入れるもの。でもそういう食べ物がどんどん減っている気がしていて……。
相馬さん(以下、相馬):現実問題、美味しいものがなくなっていっていると僕も感じています。たとえば魚も昔に比べたら味も質も変わってきているし、野菜にしても調味料にしてもつくり方そのものが変わってきています。
MICHIRU:そんななかでTable to Farmさんがオープン前に開催された食事会に伺って、衝撃を受けました。美味しさへの感動はもちろんですが、生産者さんや食の流通について、現代の課題にこんなにちゃんと着目されて、行動している方たちがいるんだって。“美味しいもの”を残すには、さまざまな課題があることにも気がつきました。
相馬:環境の変化や作る人と食べる人との距離感など、さまざまな要因があると感じています。時間をかけなければ改善できない課題も確かにあります。でも、すぐに手を出せることもある。生産者の方々の所を回っていると、決して悲観的なことばかりではなく、できることも見えてきました。
MICHIRU:それをTable to Farmさんで実現されようとしているのですね。
作る人と食べる人。距離の近さをもう一度
相馬:“Farm to Table”という流れが世界中で少しずつ大きくなってきています。僕らはどちらかというと“Table to Farm ”という考え方。食べる人たちの意志や食べるものの選択を、つくる現場に返していくことで、素晴らしい食文化をつづけることができないか、という視点で、新しいフードシステムをつくろうという試みだと思っています。
MICHIRU:昔は地元の人が作って、地元の人が食べる。そんな顔が見える距離感と関係性がありましたよね。
相馬:その距離感や関係性の近さを、“流通”によって新しい形で作れないかと考えました。そのためには作る人と食べる人、両方がいないと成り立ちません。食べる人がいれば価格も適正になり、次世代への継承の可能性も高まります。「いつの間にか美味しいものがなくなっていた」ということを防げるんです。
作る人の価値をなきものにする流通の問題
MICHIRU:私たちが求めている、安全なもの、美味しいものは買える場所を探すのが大変という印象があります。現代の流通の問題について、もう少し教えてもらえますか?
相馬:流通の問題は根深いですが、わかりやすいのは野菜でしょうか。大きさや見栄えなどの流通の規格やルールに合わせるために、今はある意味栽培が機械的になってしまっています。一方で土地に根付いてきた在来種や、季節の必然性が置き去りになってしまっている。流通に乗せるための栽培になっていて、さらには安さを追求され、作った人の価値を感じにくい状況です。
MICHIRU:合理的になりすぎて、本当に美味しいものが作れなくなってしまっているんですね。
相馬:今まで作る人に任せすぎていたんです。だからこそ作り手の視点にも立って、流通の見直しが必要だと感じています。食べる人には作る側に“半歩”踏み込んでもらうことで、作る人が集中して良いものを作れる環境が生まれる。Table to Farmはそんな循環の仕組みの設計を試みています。
Table to Farmが集める「素の味(もとのあじ)」
MICHIRU:ホームページに「0.1%の『素の味』があつまるスーパーマーケット」とあります。「素の味」って伝統的なつくり方をしているもののことだと思ったのですが、どうもそれだけではないようですよね?
相馬:昔ながらの地域の食文化も然りですが、人間のテクノロジーも文化だと思っています。全てを手作業にしたら良いかというと、それは持続可能ではないですよね。自然の力と人間が生み出した文化を織りなして作られたとびっきりに美味しいもの。僕らはそういうものを「素の味」と呼んでいます。とはいえ伝統的なつくり方については、食べ比べていくと納得がいくことも多いのも事実です。天然醸造のお醤油や自然栽培のお米……。厳選していくと結果的にそういうものが残っていきました。
MICHIRU:やっぱり昔ながらのつくり方には意味があるのでしょうね。
相馬:それを実感しています。たとえば納豆。スーパーで販売されている多くは純粋培養した納豆菌によって発酵させたものなのですが、冷蔵庫に置いておくと賞味期限が近づくにしたがって乾燥して少し固くなりますよね。でも菌が生きている稲藁の納豆は、どんどん熟成感が増していくんですよ。一般的に賞味期限は2週間程度とされていますが、正直、稲わらの納豆においては、僕はその頃が一番美味しさのピークではないかと思っています。
MICHIRU:流通のルールは最大公約数のようなものですもんね。そこからこぼれ落ちてしまう0.1%の美味しさが、ここにはあるんですね!
☆ ☆ ☆
次回、中編ではTable to Farmの「素の味」を見つけるプロセスや、消費者への届け方について語ってもらう。
相馬夕輝(あいまゆうき)
郷土料理や食文化をフィールドワークとして学び体験してきた経験を活かし、新たなフードシステムを構築することを目指して「Table to Farm」のプロジェクトを始動。ブランドディレクション、商品選定、ウェブメディアや食事会など、日本各地の生産者をめぐる。またD&DEPARTMENT PROJECT飲食部門「つづくをたべる部」ディレクターとして、その土地の食材や食文化を活かしたメニュー開発や、イベント企画なども手がける。
MICHIRU(みちる)
メイクアップアーティスト・ビューティーディレクター/渡仏、渡米を経て、国内外のファッション誌や広告、ファッションショーやメイクアイテムのディレクション、女優やアーティストのメイクなどを数多く手がける。また体の内側からきれいになれるインナービューティーを提唱するなど幅広く活躍中。本連載ではナビゲーターを務める。
取材・構成/福田真木子
写真/黒石あみ















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE