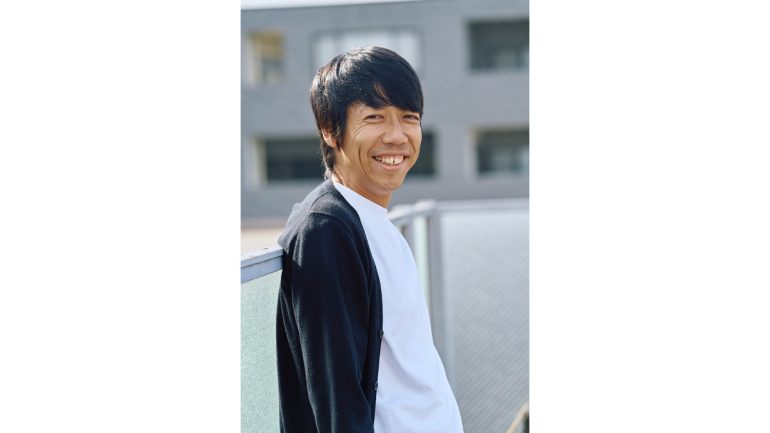アスリートを支える声援という名のエール。アスリートにとってそのエールが大きな原動力となる一方で、残念ながら応援の名のもとに誹謗中傷が起きてしまうこともある。そんな中で今、私たちができるアスリートへの応援とは--。
第3回は、Jリーグ川崎フロンターレや日本代表で活躍し、今なお人格者として一目置かれ続ける元サッカー選手の中村憲剛さんと考える。
中村憲剛(なかむら・けんご)
1980年東京都生まれ。中央大学から2003年に川崎フロンターレに加入。Jリーグ通算546試合出場83得点。MFとして3度のJ1優勝に貢献し、Jリーグベストイレブンに8度選出、2016年にはJリーグ最優秀選手賞を受賞した。日本代表68試合出場6得点。2010年南アフリカワールドカップ出場。2020年現役引退。
川崎フロンターレの応援は、選手の心に〝効く〟んです
18年間プレーした川崎フロンターレの応援を、中村さんは印象的な言葉で振り返った。
「ゴール前のチャンス。でも僕のパスミスで相手にボールが渡ってしまった……。そんな時、川崎のサポーターはブーイングじゃなく『いいぞ次いけ!』って声援をくれるんです。負けた試合の後でさえ、サポーターの方々だって悔しいはずなのに『次また頑張ろうぜ!』って。背中を押されたとかのレベルじゃないですよ。〝効く〟んですよ、実際に」
成功か失敗かという〝結果〟ではなく、プレー中の〝チャレンジする姿〟を観客が讃えてくれる。アスリートにとっての理想とも言える環境は、いかにフロンターレに整っていったのか。その一端を、中村さんは若手時代の思い出とともに紐解いていった。
「僕が加入する以前のフロンターレはJ2からJ1に昇格して、1年でまたJ2に逆戻りしたりと人気クラブとは言い難く、観客も数千人。スタジアムが満員になることはほとんどなかったと思います。そこでクラブとして『強くなることを目指すだけじゃダメだ。地域の人たちとともに歩んでいくんだ』という路線を明確にしたんです。僕はその道を歩み出し始めた2003年に入団しました。
僕たち選手も、地元商店街を回ってチラシを配ったりしていました。ですから僕たちは〝有名なスター選手〟じゃなく、〝地元の顔見知りのお兄ちゃん〟という距離感でまずは地域に受け入れてもらえたのかなと思っています」
やがてフロンターレはJ1に定着し、優勝争いに絡む有力クラブへと成長。その過程で、ホームスタジアムの等々力競技場には2万人を超える観客が常時駆けつけるようになった。個人としても実力をつけていった中村さんは、自分のために、チームメイトのために、そして仲間と呼べるサポーターのために勝利を目指し続けた。
「僕たちはプロなので、プロ選手がサポーターの優しさに甘えてはいけないのは大前提。彼ら彼女らからいただく観戦料が僕らの生活の糧になっているんですから、いつでもベストのパフォーマンスを見せなきゃいけない。しかし、それでもうまくいかない日だってあるのがスポーツだと思うんです。そこまでわかってくれるサポーターのみんなを、僕は同志だと思っていました。この人たちとともに戦い、喜びを分かち合いたいと思っていました」
〝言葉の持つ力〟が自己肯定感を上げてくれた
〝効く〟応援を身に染み渡らせた一方で、中村さんはSNSなどを通じて多様なメッセージを受け取ってきた。
「SNSで特に嬉しかったコメントやメッセージは『ありがとう』。この言葉は自己肯定感が爆上がりします。僕の投稿には賛否両方の意見が返ってくることがありました。そんな時、たとえば賛が98%、否が2%だったとしても、否のほうがめちゃくちゃ(自分の心の中で)刺さるんですよ。
僕らアスリートは多少は心が強いかもしれませんけど、生身の人間ですし、弱い部分もいっぱいある。だから、35歳でSNSを始めた僕もダメージを食らいました。もし僕がもっとずっと若くて、リテラシーも耐性も足りなかったらと思うと、ゾッとします」
日本代表の重圧の中で ――「一言の重み」を学んだ
2006年、中村さんは日本代表に初選出。2010年にはワールドカップ南アフリカ大会に出場した。代表という舞台では、クラブとは違った責任感や言葉の重みを実感していた。
「代表では、自分たちの出す結果が日本サッカーの未来に直結するということを強く意識してやっていました。一つの試合の結果に対するリアクションの大きさは、正直凄まじかったです。
メディアの取り上げ方も全然違いました。なので代表に入ってからは本当に一言一言に最大集中。フロンターレでは顔なじみになった記者さんたちと話すことが多かったのですが、代表では初めて会う方など本当に多くの記者の方たち囲まれて取材を受けますし、そこで自分の発した言葉が翌日のスポーツ新聞などにドーンと載るわけです。
当時と比べて今はネットメディアも多く、言った瞬間にすぐに配信される時代なので、今の現役の選手たちはもっと大変な思いをしてるんじゃないかと思います」
言葉に関する様々な思いを語る中村さんの背景には、アスリートとしてだけでなく、3人のお子さんの父親としても熟考してきた〝言葉の力〟がある。プラスばかりでなく、時にマイナスに働くもの、と。
「SNS上でもリアルでも、僕や妻が他人のことをどう言っているかを子どもたちは結構見てるんです。僕は元々、チームが負けた時は自分に責任を求めるタイプでしたけれど、もし僕が逆のタイプの人間で『負けたのは誰々のせいだ』とか家で言ってたら、きっと子どももきっと同じ発想になってしまうと思うんです。
SNSも同じ。うちの子たちが見てるんですよ。娘は『私が一番にいいね押したよー』なんて言ってくれてますし。
そして、子どもが見るのは〝僕が何を言っているのか〟だけじゃない。〝何を言われているのか〟も、不意に目に飛び込んできてしまう……。
僕たちアスリートにも、家族がいます。応援してくれる人、支えてくれる人がいます。SNSに書き込まれた言葉は、僕だけでなく、僕の妻や子どもたち、そして応援し、支えてくれている人たちにも向いてしまうものなんです。誰かは誰かの大切な人なんです。なので、書き込む時は感情に任せてすぐに打つのではなく、その書き込みによる影響がどこまで及ぶのかをよく考えた上で書き込んで欲しいと切に願います」
投稿する前の一呼吸
「僕自身、現役時代からSNS投稿は徹底して慎重にやってきました。勝ったら何でも言っていいわけではないですし、負けた時はなおさら。勝敗で明暗が分かれるプロスポーツの世界では〝いつ出すか〟も大切です。見る人の気持ちやタイミングを想像して表現することが、結局は自分やクラブを守ることになると思います。
僕は投稿前に何度も書き直すし、何度も読み返します。時には妻に読んでもらうこともあります。そうして送信ボタンをタップする直前に、もう一度立ち止まるようにと心がけています。「最後は自分の親指に聞く」。これは川崎フロンターレのネットリテラシー講習で教わった言葉で、ずっと大切にしている考え方ですね。
相手を傷つけないか。その相手を大切に思う人を傷つけないか。僕のフォロワーや、たまたま読んだ誰かを不快にしないか。投稿を目にする可能性のあるすべての人を想像して、〝このまま送っていいか?〟と、僕は送信ボタンを押す自分の親指に聞くようにしているんです。
先ほども言いましたけれど、うちの子どもたちも僕のSNSを見ています。親がSNSに真剣に向き合うことは、言葉の責任を学ぶ姿を見せることになると思います。子どもたちがいつか発信者になった時、きっと〝言葉を継ぐ〟子になると信じています」
中村さんを勇気づける言葉とは?
「この言葉は大学を出てプロに入る時、父から授けられました。『中村家の家訓だ』と教えられて……本当に家訓ならもっと早く伝えるはずなのでそこは怪しいんですが(笑)、この精神はそれまでの自分を振り返っても大切だったなと思えたし、プロ生活を通じても、現役を終えた今も大切にしています」
中村さんは現在、川崎フロンターレ・リレーションズ・オーガナイザー(FRO)という役職につき、次世代選手の育成や、地域活動・プロモーション活動などで幅広く活躍している。
この記事の冒頭で触れたとおり、川崎の応援スタイルを心に刻み込んだ中村さんは、未来の選手への「エール」にどんな希望を持っているのだろうか。
「選手だけではなくサポーターも世代交代していくわけですけれど、前の世代を見て育った新世代が、川崎フロンターレの応援文化を引き継いでくれることを願っています。そして、選手の心に〝効く〟応援が、他のクラブや他の競技にも広がってくれることを願っています」
最後に4つの一問一答!
最後は一問一答で締めくくりを。
Q1好きな食べ物は?
妻が作るもの
「好きな食べ物……えっと、なんだろう……。シンプルにこれというもの思い浮かばないんですけど、いくつか思い浮かんだものはだいたい妻が作るものでしたので」
Q2好きなアーティストは?
スキマスイッチさん、Mr.Childrenさん
「スキマスイッチの常田さんは初めてリアルにお会いしたアーティストで、それ以来すごく仲良くしています。そして、10代の頃からずっと聴いてきたのはMr.Childrenさん。たぶんミスチルは、僕らの世代はみんな通った道ですよ」
Q3何をしている時が一番しあわせ?
爽やかな朝、妻と散歩しているとき
「選手の頃はやっぱり勝った時が最高でしたけれど、今は朝、妻と散歩する時ですね。爽やかな空気の中で『こうして1日がスタートするのっていいよね』と、今日も妻と話してきました」
Q4 今ハマっているものは?
ピラティス
「引退から4 年半、体重が3kg増えました。70kgが間近になった時『まさか自分がこうなるか』とショックだったので、今は楽しみながら体を動かしています」
その道のりに、賞賛を
日本オリンピック委員会(JOC)と日本パラリンピック委員会(JPC)は、SNSの存在感がこれほどまでに大きくなったことを踏まえ、アスリート等に対する誹謗中傷対策の取り組みとして、アスリートや関係者が安心して競技に集中できる環境を整えるため啓発映像を制作し、各競技団体や関係機関の協力のもと、国内主要大会や各種イベント等で広く展開しています。
DIMEでは、第一線で活躍するアスリートとの対話を通じて、これからの“エールの在りか”を探っていきます。ぜひ今後もご注目ください。

協力/
JOC-日本オリンピック委員会
JPC-日本パラリンピック委員会
協力/JOC-日本オリンピック委員会 JPC-日本パラリンピック委員会
取材・文/江橋よしのり 撮影/高田啓矢 編集/髙栁 惠















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE