ここ数年、私用で夏は沖縄に行く筆者。旅先のスーパーを見るのが大好きなため沖縄でも行くのだが、そこでいつも気になるものがある。
『シーチキン』だ。箱に敷き詰められたシーチキンが山ほどある。本土では見ない光景のため、どういうことなのか気になっていた。
こんなに箱でたくさんの『シーチキン』が売っているということは、もちろん売れるからなのだろう。しかしなぜなのか…。
その謎に迫るべく、『シーチキン』を製造・販売している『はごろもフーズ株式会社』の沖縄営業所 所長の柏田喬士氏に話を聞いた。

シーチキンの沖縄での消費量は本土の約3倍
すばり、沖縄でシーチキンの売り上げは多いのだろうか?(以下、「」内、柏田氏)
「沖縄での1人当たりのシーチキン消費量は、本土での約3倍になります」
特にお中元、お歳暮の時期に贈答用の箱入りシーチキンがよく売れるんだとか。
「沖縄ではお中元、お歳暮は『お米かシーチキンか』と言われるほど、特にこの2品がよく売れます。シーチキンは贈り物のお値段的にもちょうど良いためもともとツナ缶の使用頻度が高い県でまとめ買いする人が多く、お値段的にもちょうど良いため、贈り物の定番として、定着したのだと思います」
お店が包装紙を巻くのも大変になるほど売れるので、包装紙を撒く手間を省くべく、贈答用の箱そのものがシーサーやハイビスカス模様がついた沖縄仕様のオシャレなものになっている
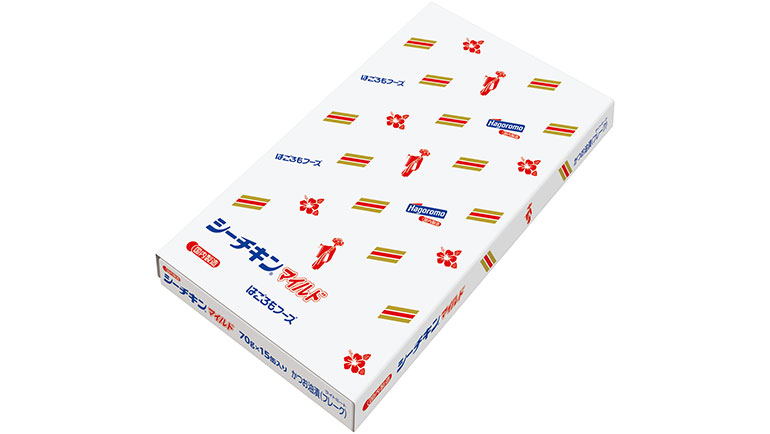
「箱にのしだけ貼ればいいようになっています。このような箱入りの用意があるのは沖縄だけです」
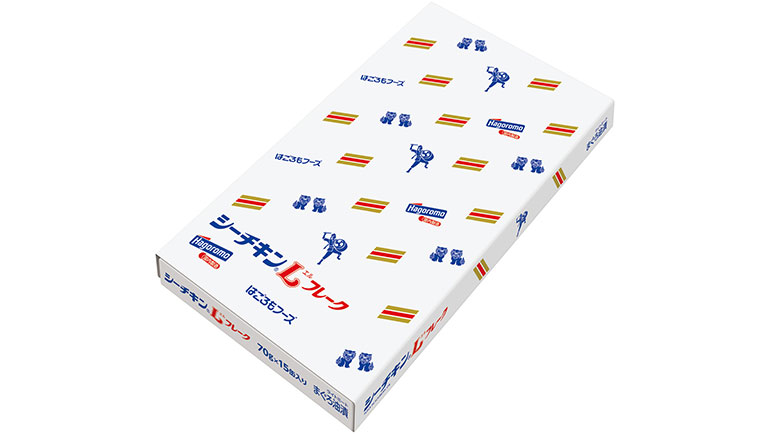
シーチキンは調味料
沖縄では“シーチキンは調味料”という扱いであり、他の調味料と共に常にストックしている状態になのだという。缶の油ごと炒め物などの調理に使うんだとか。
「沖縄でシーチキンがよく食べられることがわかっていたので、1997年に15缶の箱入りの販売を始めました」
そもそも15缶や12缶の箱入り販売を行っているのは沖縄のみだという。

「沖縄のほとんどのスーパーでは、15缶や12缶の箱入りか1缶ずつのものしか販売していません」
よく本土のスーパーで見かける3缶パックや4缶パックのものはほとんど販売されていないのだ。
ちなみに、筆者の沖縄出身の知り合いも「シーチキンは箱で買うのが普通だった」と話している。
なぜ沖縄はシーチキンなのか?
調味料として缶の油ごとゴーヤチャンプルーやソーメンチャンプルー、サラダやその他の沖縄県民食に多用されるシーチキン。
なぜここまでシーチキンなのだろうか?
「沖縄での缶詰文化が根強いというのも、シーチキンが愛される理由のひとつだと思います」
アメリカの影響がありランチョンミートなどの缶詰文化に馴染みがある沖縄。また台風も多いため保存食にもなるシーチキンの缶詰が風土にマッチしたのだろう。
「本土のスーパーでは週に1回くらい、チラシにシーチキンの特売が出でいるくらいかと思いますが、沖縄では色々な種類が代わる代わる登場します」
シーチキンが登場しない日は、他のブランドのツナ缶が載っていたりするという。
売れる種類にも違いが
シーチキンが沖縄で人気の理由に「生マグロ文化」も関係しているのではと柏田氏は話す。
「沖縄では生マグロが流通していて、マグロへの馴染みがより深く、『シーチキン』の中でもキハダマグロが原料である『シーチキンLフレーク』の売り上げが全体の7割に上ります」
ちなみに、はごろもフーズのシーチキンには原料がカツオの『シーチキンマイルド』、びんながまぐろの『シーチキンファンシー』、ぶりの『シーチキンEvery』などがあるが、“どれを食べても『シーチキン』であること”を目指していたため、魚の違いにフィーチャーしていない。
「地域によって多少選ばれる魚種に差がありますが、どの魚種を使ったシーチキンも同じシーチキンとしてお使いいただけるように調味液を工夫しています」

近年の売り上げは伸び悩み
沖縄で大人気なシーチキンだが、近年の売り上げは伸び悩んでいるという。
「売り上げの数量は微減しています。物価高の影響もあってかお手頃感がなくなってしまったのかも知れません」
海外からの安いツナ缶も多く出回っているため、そちらに消費者が流れていることも考えられる。
「日本で1番ツナ缶を作っているメーカーですので、品質、味わい共に自信があります。安いツナ缶と食べ比べてみてくれたら、シーチキンのおいしさがわかっていただけると思います」
製法や味付け、調味液などにもこだわりと自信を持って生産しているという。
シーチキンは調味料として缶の液体ごと使うのが沖縄流。微力ながら筆者も、沖縄流調理でシーチキンを今後も応援したい。
※「シーチキン」は、はごろもフーズ株式会社の登録商標です。
取材協力:はごろもフーズ株式会社
文/まなたろう















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE













